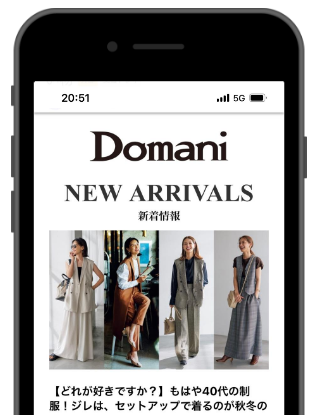〈15〉
【登場人物】
川口圭一 (24) 大手広告代理店・東通勤務。コピーライター。
小林かおり(24) 大手出版社・祥明社のティーンズ誌『プチファスト』編集者。長野出身。
大宮ちか(24) 祥明社の文芸誌『トロイカ』編集者。かおりの同期。
<これまでのあらすじ>
2022年2月14日、東京・佃。銀座にほど近い高級マンションから一人の男が転落した。男の身元は大手広告代理店勤務42才の川口圭一。転落したマンションは、川口が家族4人で住んでいた。他殺か、自殺か、事故か。話は18年前の2004年の冬、圭一と妻のかおりの出会いへさかのぼる。
はじめてのデートの夜、勢いでセックスをしてしまった。そこから、小林かおりと川口圭一は、どこにでもいる恋人たちのように自然と連絡を取るようになった。
夜になれば「いまなにしてる?」と電話をし、時間があれば会い、連絡が遅いと不安になり、会えない時は「会いたい」とメールした。
小林かおりが、大宮ちかに「たぶん付き合いだした」ことを報告すると、自分のことのように喜んでくれた。あの日、すぐにセックスをしてしまったことも言うとあきれていた。しかし続けて、「わたしがキューピッドなわけだから、幸せになってほしい」と言った。
かおりは、母が破いた父親の写真を修復することはしなかった。ちかにもらった写真館のメモと、やぶれた写真を封筒に入れ、引き出しに入れた。
そして一か月が過ぎた。
生理が来ない。祈るように毎日待ったが、予定の日にちを一週間過ぎても二週間過ぎても来ない。体が熱っぽいようなダルさがある。
風邪薬を買うために寄った薬局で、念のために妊娠検査薬も買った。
一人で調べるのは怖くてちかに家へ来てもらった。
ピンクのパッケージを破り、指示通りにした。しばらく時間を置くと、窓に二本、ピンクの線が出た。
トイレから出てちかの顔を見る。
「赤ちゃんいるみたい」
ちかは絶句している。かおりは平然とした顔で続けた。
「やったらホントにできるんだね。いままで生でしたことなかったから甘く考えてた」
「それで……かおりはどうするの?」
「できてたらどうしようってずっと考えてたけどね、産むよ」
「川口圭一が『おろしてほしい』って言ったらどうするの?」
「別れて産む」
「ひとりで育てるってこと?」
「そう。おろしたら、もう付き合えないと思う。ケンカするたびにこの子のことを考えて、責めてしまう。いつまでもふたりの間にこの子がいて……そんな未来はうまくいかないもの」
「……」
「それに、何かあるたびに『あの時、産んでたらいまごろ』って後悔すると思う。わざわざわたしを選んで来てくれた命だから、産む」
「かおりはいいの?」
「わたしはね、川口くんが好き。もし別れたとしても、こんなに好きになれた人の子供が来てくれて嬉しい。こんな予定じゃなかったけど、まあ、いつか子供は産んでみたいと思っていたし、早いか遅いかの違いかなって」
「仕事はどうするの」
「続ける。仕事好きだもん」
「そのほうがいいかもしれないね」
「編集長もあきらめてない」
ちかは目をまんまるくしてかおりを見た。
「本気? 結構厳しいと思うよ」
「わかってる」
「なんか……ここ最近、かおりは違う人みたい」
「川口くんに会って、サキさんにぼろくそ言われて、赤ちゃんできて。たった一か月だけど、強くもなるよ」
ちかは頭の中でかおりと川口圭一の出会いが約一か月前の1月9日だったことを思い出した。
「案外、ぐずぐず迷うより、そのくらいさっさと決めたほうがいいのかもね」
励ましてくれるちかを前に、かおりはうつむいて下唇をかんだ。
「いや、ほんとは、できれば、もう少し時間が欲しかったけどね……」
ちかはかおりの肩を抱き、励ました。
「もしかしたら違うかもしれないから、お医者さん行こう」
後日、クリニックに行った。女医はエコーを見せながら言った。
「赤ちゃんいますね、ほら」
ひらひらする小さなクリオネのようなものが見えた。女医はカルテを確認した。
「えっ……と、産むか産まないかよく話し合って、決まったらまた来てください」
かおりは夜、圭一と会った。
『車で迎えに行く』とメールが来ていた。
BMWの黒い二人乗りオープンカーで圭一は神楽坂に現れた。遠出をして、等々力の寿司屋に行った。
ふたりともお茶で寿司を食べ、いつものように手をつないで車まで戻った。
信号待ちをしているときに、圭一が言った。
「今日はお酒飲まなかったんだね」
かおりはこのチャンスを逃すまいと、意を決して言った。
「あのね、赤ちゃん……できてたみたい。だから……お酒は飲まなかった」
圭一は信号が青になっても発車させることができず、後続車からクラクションを鳴らされた。
大きな音で我に返り、交差点を進み路肩に車を停めた。
「……間違いないの?」
「病院で見てもらったから」
圭一は背もたれに体を預け黙っている。近くの信号が三回ほど変わってから、口を開いた。
「そんなに急がなくてもいいんじゃない」
かおりは表情を変えず、前だけを見ていた。かおりはあの晩から祈るように過ごしていた。生理が遅れていて不安になり、「もしかして、あの時、赤ちゃんできていたらどうする?」という話になった。圭一は「産めばいいよ」と言った。けれど、これが本心だったということだ。圭一の無責任な言動にだまされていた自分の愚かさが悲しい。
「わかった。別れよう」
かおりは圭一の顔を見ずに言った。圭一は息をのむ。
「え…? それでどうするの?」
「産むよ。わたしとあなたは別の人生を行く、それでいい」
「ちょっと待って。ひとりで産むの?」
「そう」
圭一はハンドルにあごを預ける。しばらく思案して言った。
「すこし考えさせてほしい」
かおりと圭一は何も言わず、神楽坂まで帰った。かおりは少し車に酔ったような気がして、これがつわりなのかなとぼんやりと考えていた。
「連絡するから、待っていて」
つまり、かおりのほうから連絡をして来るなということだ。ずいぶんな扱いだとは思ったが、かおりは返事をせずきびすを返し、マンションの階段を登った。
「どうだった?」
大宮ちかから電話が来た。
「うん……『いそがなくてもいいんじゃない』って」
「なにそれ」
「おろせってことじゃないの」
「いや……ちょっと。川口よ、それはないわ」
「それに、『連絡するから待ってて』って。このまま連絡ないかもね」
「そ、っそんなことになったら……わたしと育てよう」
ちかの返事にかおりは笑ってしまった。
まだ会社に入って2年もたっていないのに子供ができてしまった。クビにはならないまでも、キャリアはここで終了し、閑職に行かされるだろう。それに厳しい母親のことを考えると頭が痛い。想像するだけでもめまいがするが、自分の体に現実、宿っている命を思うと強くならざるを得なかった。
圭一から連絡が来たのはそれから数日後の2月14日だった。
かおりの仕事の都合で、会う時間は夜遅くなった。西麻布のブックカフェで夜の22時に待ち合わせた。かおりが到着すると、圭一はすでに席に座っていた。表参道で買った袖と襟が白い水色ストライプのシャツを着ていた。圭一は、かなり早く来たのか、何かを食べた空っぽの皿と、赤ワインを飲んでいた。
かおりはペリエを頼む。後ろの棚にある本を何気なく手に取り読んだ。圭一は何も言わない。太宰治の『斜陽』だった。貴族のお母さまが『ひらりひらりと、まるで小さな翼のようにスプウンをあつかい、スウプを一滴もおこぼしになる事も無い』と優雅にスープを飲んでいる描写のところで、ペリエが届いた。
貴族のお母さまの飲み方が脳裏に浮かんでいたかおりは、精一杯虚勢を張って、いつもより優雅にペリエのふたを開け、ひらりひらりとコップに注いだ。弱いところや媚びる顔をしたら負けだ。わたしは、愛されているわたしは、自分で自分を愛せる。コップの向こう側に思いつめたような圭一の顔があった。
「いつも笑顔でいてほしい」
唐突にそう言って、圭一は机に両肘をつき手を組んだ。
「おれと、結婚する? 大変かもしれないけど」
かおりは圭一をじっと見つめている。圭一も目をそらさない。かおりに選択肢はなかった。祐天寺で出会ったあの夜から、かおりの気持ちは決まっていた。ひらりと小さな翼が動いたようにうなずくと、圭一はほっとした顔をした。圭一が、かおりの方に手を伸ばしたとき、赤ワインのグラスが倒れた。圭一の袖の白に赤ワインが広がった。
後日、結婚指輪を買うために、圭一とかおりはBMWに乗り、銀座へ向かった。途中、ガソリンスタンドに立ち寄った。
「ハイオク、2000円分、現金で」
ハイオクなのに、2000円…。かおりは、圭一のことばをいぶかしんだ。かおりは、自分が圭一という人間をほとんど知らないことに気づき、背筋が寒くなった。その瞬間、猛烈なつわりがかおりを襲った。
作家 松村まつ
東京都内に勤務する会社員。本作がはじめての執筆。趣味は読書と旅行と料理。得意料理はパテ・ド・カンパーニュ。感動した建物はメキシコのトゥラルパンの礼拝堂とイランのナスィーロル・モルク・モスク。好きな町はウィーン。50か国を訪問。