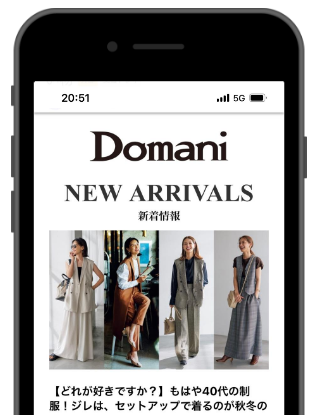【目次】
〈20〉
【登場人物】
川口圭一 (24) 大手広告代理店・東通勤務。コピーライター。借金がある。
小林かおり(24) 大手出版社・祥明社のティーンズ誌『プチファスト』編集者。長野出身。
<これまでのあらすじ>
2022年2月14日、東京・佃。銀座にほど近い高級マンションから一人の男が転落した。男の身元は大手広告代理店勤務42才の川口圭一。転落したマンションは、川口が家族4人で住んでいた。他殺か、自殺か、事故か。話は18年前の2004年3月。圭一と妻のかおりの出会いへさかのぼる。たった一度のセックスで子供ができてしまった圭一とかおり。結婚することを決めたが、お互い知らないことばかりで……。
小林かおりは川口圭一の引っ越しを手伝うため、部屋へ行った。どうしても訪問させてくれなかった部屋。いったいなにがあるのだろうか。生々しい女の痕跡が見つからないことを祈りながら住所を頼りに向かうと、1階で圭一が待っていた。
デザイナーズマンションは、白い壁に赤いアクセントが印象的だった。おしゃれな圭一によく似合うマンションだった。圭一は紺のフィッシャーマンズセーターを着ている。すそに赤いラインが入っていて、このマンションのアクセントカラーと同じだった。首元にちらりと見える白シャツの分量も絶妙で、ブラックジーンズは圭一の長い脚を引き立てていた。
借金のことなど忘れてしまいそうなくらいほれぼれとした。
圭一の部屋は三階だった。
「ここだよ」
そういわれて踏み込んだ部屋は……床の見えないごみ部屋だった。もうだいぶ荷物は運び出したというのに、何層にも物が積み重なっていた。大量の服や本やCDにDVD。
「広告代理店ってのは、流行りのものを押さえておかないとだから」
圭一は恥ずかしそうに言い訳した。高額そうな特装版の画集の金箔が、借金の象徴のように輝いていた。
かおりはテレビで見たことのあるごみ部屋に衝撃を受けていた。ベッドの上は唯一物がなく、ここだけで生活をしているような感じだった。だが、シーツは汚れていて、におってきそうだった。事故物件の遺体があった場所のような汗じみがあった。座るのも嫌だった。
キッチンは、コンビニの弁当ガラや中途半端に飲んだペットボトルがたくさん置いてあった。料理をした形跡はなく、冷蔵庫に入っているのはビールくらいだった。料理をしないため生ものがないからか、虫がわいていないのがせめてもの救いだった。
トイレは洋式便器の水がたまる部分に黒いカビが汚く生え、この家に引っ越しをしてから一度も掃除をしたことがないのではないかと思った。
わたしは……とんでもないはずれを引いた。
かおりは、実感した。この生活力のまったくない男とこれから一生暮らしていくのは厳しい。ただでさえ子供ができるというのに、この男の世話までしなければいけないのだろうか。さらに仕事。しかし、仕事は絶対に手放してはいけない。この男と、いつ離婚をするかわからない。頑張れるところまで頑張って、だめなら離婚しよう。
かおりは腹をくくった。
この男は腐っている。見た目がいいだけで、中身は借金に汚部屋のくず男だ。これだけ物を買っていれば、借金もかさむだろう。なにがあっても連帯保証人にだけはなるまいと決心した。夫の借金の返済義務は妻にあるのだろうか。この男の生活を立て直すには、どこから手を付ければいいのだろうか。妊娠・出産や結婚式についてだけでなく、調べることがまた増えてしまった。
ただ、意外とこだわりがなくて素直なところがあるのと、年齢が24歳と若いことを考えると、もしかしたら変わってくれるかもしれない。一縷の望みをかけて、挑戦することにした。かおりはもう、後に引くことはできない。さめざめと泣いて、だれか責めたところで、だれもかおりを助けてはくれないのだから。
かおりは持ってきた、マスクをつけ、手ぬぐいをかぶり、エプロンをした。あきらかにごみとしか思えない色褪せたパンフレットやチラシを指さした。
「この辺、どうする?」
「とりあえず全部、箱に詰めて」
「なにも捨てないの」
「いまは……考えてる時間ないからぜんぶ持っていく」
私には『全部捨てておいで。新しいの買おう』と言ったのに、自分は『全部、持っていく』。買うお金もないくせに。かおりは、圭一が口先だけで嘘をつく人間であり、自分の生活を変えるつもりはまったくないことを実感している。
無言で片付けや荷造りをしていくかおりに、圭一はばつが悪そうにしていた。かおりの怒りと絶望に気づくくらいは鈍くないのだろう。
かおりだけでなく、引っ越し業者も手伝い、圭一の荷物は積み終わった。
「普通の1Kの量ではなかったので、当初より追加して2トントラックを増やしました」
引っ越し業者が言う。トラックがすべてを運んでいく。からっぽの部屋を見て圭一が言った。
「けっこう広かったんだねえ」
「……」
「かおりさん、怒ってる?」
「あきれてる」
「そうだよね」
「ねえ、圭一。変わろうって気持ちはあるの」
「うん」
「本当だね」
「うん」
「この部屋と、借金と。もう秘密はない?」
「ううん? ……たぶんないと思う」
迷子のように、そっと手をつなごうとする圭一を、かおりは力いっぱい振り払った。
この日、ふたりの力関係は完全に変わった。
作家 松村まつ
東京都内に勤務する会社員。本作がはじめての執筆。趣味は読書と旅行と料理。得意料理はピクルス。感動した建物はメキシコのトゥラルパンの礼拝堂とイランのナスィーロル・モルク・モスク。好きな町はウィーン。50か国を訪問。