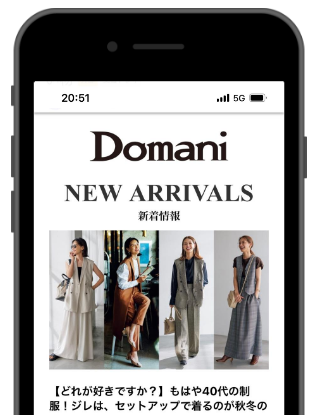〈13〉
【登場人物】
川口圭一 (24) 大手広告代理店・東通勤務。コピーライター。
小林かおり(24) 大手出版社・祥明社のティーンズ誌『プチファスト』編集者。長野出身。
大宮ちか(24) 祥明社の文芸誌『トロイカ』編集者。かおりの同期。
妹尾サキ(24) 高文館のスクープ誌『週刊女性ファイブ』編集者。かおりのことが本能的に嫌い。
<これまでのあらすじ>
2022年2月14日、東京・佃。銀座にほど近い高級マンションから一人の男が転落した。男の身元は大手広告代理店勤務42才の川口圭一。転落したマンションは、川口が家族4人で住んでいた。他殺か、自殺か、事故か。話は18年前の2004年1月。圭一と妻のかおりの出会いへさかのぼる。
神楽坂の住宅街を、雨の中、かおりは走る。
角を曲がって息を整える。後ろを見てもだれも追いかけてこない。
だれも、追いかけてはいなかった。
「なあんだ。っていうかなんで逃げたんだろう」
自分が、はしたなくて、大それたことを言ったような気がして恥ずかしくなってしまったが、よく考えれば、「仕事も家庭もぜんぶほしい」なんてたいしたことではない。だいたい、川口圭一のからかうような態度もそれに拍車をかけた。
いや。違う。その前に、不意打ちでされたキスのせいだ。かおりだって中学生ではないのだから、キスのひとつやふたつしたことはある。いままで彼氏もいた。中には濃厚でとろけるようなものも、なくはなかった。
しかし、なんだろう。圭一のあの引力は。圭一の香水が鼻の奥をかすめる。圭一の手のあたたかさや、耳元で聞いた声を、こわれたゼンマイ仕掛けのおもちゃのようになん度もなん度も反すうし、味わってしまう。走って逃げたと言うのに、いますぐもう一度会いたい。もしかして連絡が来ているかもしれない。携帯を開いたが、だれからも連絡はなかった。
そんなことを考えていると、家に着いた。頭のかたすみに追いやって考えないようにしていた母の顔が浮かぶ。
「いつだって私のことをばかにして!!」
とかおりを突き飛ばした母の様子は鬼気迫る物があった。かおりがだれかを好きになると「はしたない」「汚らしい」といやがる母は、圭一のことをどう思うのだろうか。人を思うことはそんなにもいけないことなのだろうか。
母へ、土産に買った肉まんがずしりと重い。楽しかった気持ちが一気にしぼんで、ゆううつだった。
家のドアの前で一度立ち止まり大きく息を吸う。からだのすみずみまで酸素を行き渡らせ、力を満たしていく。そして、母に気づかれないよう、そっとドアを開けた。ひんやりした空気が流れてくる。部屋は暗く、だれもいない。
電気をつける。母の荷物はなくなっていた。
「帰ったんだ」
ほっとすると同時に、圭一の買ってくれた肉まんがおいしそうに思えた。たくさんあることが嬉しい。買いすぎてしまったので、冷凍しなくては……と考えていたら携帯が鳴った。圭一かもしれない。急いで電話に出る。
「あんねえ、いまから家に行っていいかなあ。いいとも~!!」
脳天気な声が、一方的にまくしたてて切れた。
10分後、「うおおい、帰ったぞお!!」と、大宮ちかがひとりで来た。
「ちょっとさあ、さっき店で別れたばっかりなのに。それに、神楽坂で飲むたびにうちに来るの止めてくれる?」
「いいやないかあ。そんな心の狭いことを言わんとお」
出身地である関西の方のことばになりつつある。これは、相当飲んでいる。
「お酒、買ってきた。飲もら」
「はいはい」
そう言いながら、ちかのコップには水をつぐ。一口飲んでいやな顔をした。
「これ水やんな」
「そう」
「なんでやら」
「もう飲むのはやめなさい」
「えええ。飲むら」
「だめら」
かおりがちかの方言をまねした。
「それ変ら」
「でもお酒はもうだめら」
「わかったよっ」
ちかは、口をとがらせて水を飲む。
「今日さ、変な感じになってごめんね」
「……あの後すぐに解散したんだね」
「そう。サキが危ないレベルに酔っ払ってたし。あと、かおりと川口圭一がお互い会いたそうだし、川口も呼んだけど来ないから解散した」
「川口圭一……」
「まあ、川口は飲み会とか来ない人だからさ。今日も、だめもとで誘ってみたら『来る』ってメールもらってびっくりしたんだよね」
「そうなんだ」
「そう。結局は来なかったけど」
「……わたし、会った」
「いつ?」
「店を出るときにいた」
「来てたんだ」
「そう。雨が降ってたから、うちまで送ってくれたの」
「川口が?」
「うん」
「それは珍しい。あんまりそういうことしないと思ってた」
「雨が降ってたから…じゃないのかな」
「いやいやいや! かおり、わかってるよね? サキが暴れてたのはそういうとこだよ。もうちょっと本音で行こうか」
ちかの冗談っぽい言い方で、気持ちが楽になった。そうだ。もっと正直になろう。我慢したときに出るじっとりとした空気がみんなを不愉快にさせているのかもしれない。思うことをはっきり口にできるようになれば、もっと人はわたしをこころよく思ってくれる。
「そうだよね。なんか、ちょっと、好きでいてくれてる気がした」
「川口、だいぶ気になってるね。手とかつないだ?」
「手はつないでない」
「手は……と言うことはほかになにかしたのかな?」
手だれの刑事のように、ちかがぐっとせまってくる。ほんのすこし前の圭一の唇を思い出し、心臓がはやく打った。
「キス…された。いや、してくれた? していただいた?」
そこで、いったん言葉を切って、かおりは正直な気持ちを打ち明ける。
「嬉しかった」
照れくさそうなかおりを見て、ちかはまぶしそうに目を細めている。
「ふええええええ。酔いが完全にさめた。川口から? いやあ、生々しいな。ずっと川口と友達だから、ちょっと想像つかないや」
「彼はどんな人なの?」
「ううん……まあ、感じはいいんだけど、付き合いが良い方ではないかも。飲み会とか騒がしい席はあんまり来ない」
「彼女とか、いままではどうなの」
「川口はさ、体育会系でバレーボールやってて、大学時代にバレーボール部のきれいな先輩とつきあってたね。学部も同じだったかな。先輩は商社かテレビか、大きいとこ入ったと思う。もう別れたのかはよくわかんない。でも、キスしてきたなら別れてるのかな」
「きれいな先輩と……」
「そう。川口は優しそうだし、背も高いし、見た目も良いし、早稲田だし。しかも東通でしょう? 調子に乗るレベルで、まあもてるとは思うよ」
「そっか」
かおりが目を空中に泳がせる。
「かおり、いま『わたしなんか』って思ったでしょう」
「え?」
「サキが言ってたけど、たしかにかおりは『わたしなんか』って口ぐせだね」
「よくないね」
「うん。よくないよ。サキもあの言いかたはよくないけど」
「嫌われちゃった」
「大丈夫。サキはね、お酒弱いから、たぶんかおりが来たことすら覚えてないと思う」
「そんなにお酒弱いんだ」
「そうだよ。意外とかわいいやつなんだよ。本音で生きてるし」
「思ったこと言ってて、気持ちよさそう」
「かおりもそうしなよ」
「うん……。なんか今日からちょっとだけ生まれ変われるかも」
「その調子。川口と連絡先交換した?」
「教えてもらった」
―――わたしはできる。わたしは強い。わたしは愛されている。心の中で圭一に教えてもらったおまじないを唱えると、今朝のみじめな自分とはちがうような気持ちになった。サキの横暴とも言える、しかしはっきりとした物言いがかおりの心を明るくした。卑屈になって、気持ちを隠す必要なんてひとつもない。
そのとき、携帯がだれかからの着信を告げていた。ちかが携帯を指さした。
「圭一じゃないの?」
かおりは携帯を見る。知らない番号からだ。いったいだれだろう。かおりは、おそるおそる電話に出た。
「もしもし」
作家 松村まつ
東京都内に勤務する会社員。本作がはじめての執筆。趣味は読書と旅行と料理。得意料理はパテ・ド・カンパーニュ。感動した建物はメキシコのトゥラルパンの礼拝堂とイランのナスィーロル・モルク・モスク。好きな町はウィーン。50か国を訪問。