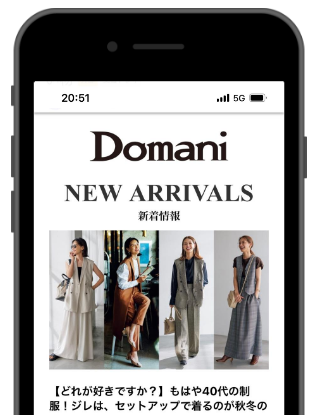〈17〉
【登場人物】
川口圭一 (24) 大手広告代理店・東通勤務。コピーライター。
小林かおり(24) 大手出版社・祥明社のティーンズ誌『プチファスト』編集者。長野出身。
<これまでのあらすじ>
2022年2月14日、東京・佃。銀座にほど近い高級マンションから一人の男が転落した。男の身元は大手広告代理店勤務42才の川口圭一。転落したマンションは、川口が家族4人で住んでいた。他殺か、自殺か、事故か。話は18年前の2004年2月。圭一と妻のかおりの出会いへさかのぼる。たった一度のセックスで子供ができてしまった圭一とかおり。結婚することを決めたが、お互い知らないことばかりで……。
「きみは、仕事を辞めないほうがいい」
川口圭一と小林かおりは飛行機のタラップを下りる。昼近いとは言え、2月だというのに太陽が照りつける。ここは高知龍馬空港。川口圭一の両親に挨拶をするために、小林かおりはここに来た。かおりは、『子育てしながら編集の仕事を続けるのは難しい』と編集長に言われたことを圭一に相談していた。圭一は、タラップの最後の一段で冒頭の言葉を言った。かおりのキャリアを応援したいと言うことだ。
「辞めないで子育てもできるかな」
「うちの母親も上京して育ててくれるんじゃない」
「そんなことしてくれるの」
予想外の言葉に驚くかおりをよそに、圭一は「できるんじゃない?」と楽観的だった。しかし、かおりは、出会って40日しか経っていないこの男に、ところどころ信頼できない言動が見え隠れしていることを感じてもいた。
とまどうかおりを包む高知の空気は、初夏のような能天気さだった。かおりはカシミアのコートと、厚手のセーターを着ている。コートを脱いでも暑い。川口圭一はコートを脱ぎ、薄手の長袖Tシャツになった。
「2月なのにすごく暖かい」
「今日は20度だって」
かおりは首をすこし傾けて圭一に聞く。
「ところで、こんな突然行って大丈夫?」
「うちは平気。喜んでた。でも、本当におれの親を先にして大丈夫? 長野に先行ったほうが……」
「いい。大丈夫。聞いてみてるんだけど、来月まで待ってって」
かおりは圭一の言葉をさえぎった。教師の母親に、結婚前の妊娠を告げられずにいる。だらしないことが大嫌いな母は半狂乱になるだろう。母は妊娠を知っても、かおりの育児を手伝ってくれる可能性はゼロだ。祖母にかおりを丸投げした母が、育児を手伝ってくれるとは思えなかった。それに、かおりの親が離婚したことも、父がこの世にいないことも、圭一にはまだ言えていなかった。親のことを言われるたびに、かおりは胸に重苦しい石を乗せたような気持ちになる。
雪も降らんばかりに冷え切った東京から来たので、温度の差をより感じる。それだけではなく、日差しが強い。
「高知ははじめて?」
圭一はかおりを振り返る。かおりは、気を取り直して圭一に嬉しそうに答える。
「一度、来てみたかった。大学は史学科で幕末が一番好きだった。『龍馬が行く』とか『お~い! 龍馬』とか読んだことある? ないの? 山内容堂公、武市半平太、坂本龍馬、中岡慎太郎、岡田以蔵、岩崎弥太郎……」
かおりが指を折りながら数えていると、圭一は声を出して笑った。
「じゃあ、桂浜の龍馬像を回って行こう」
圭一が手配してくれたレンタカーに乗る。道路に車がない。それどころか、信号もほとんどない。都会的な圭一からは想像もできないくらいのんびりした風景にかおりは拍子抜けした。道路の両脇にはヤシのような木がたくさん生えていて、それは「ヤシの中でもフェニックス」という木だと圭一が教えてくれた。
坂本龍馬像は崖の上のほうにあり、車を降りて少し歩いた。潮の香りが鼻をくすぐる。見上げるような大きな銅像に、青い空と青い海が映える。セーターは暑いが、海風が強く少しはましだ。
「これは……太平洋?」
「そうだよ」
「波打ち際に行ける?」
「遊泳禁止だけど、砂浜は歩ける」
かおりにとって海と言えば、東京都内から行ける湘南や横浜の混雑した景色しか知らなかった。かおりは、海のない長野で育った。小さい頃は海を湖のようなものだと思っていた。だけどこの海はぜんぜん違う。遠くから見ると凪いでいるように見えた。誰もいない浜辺を歩くと、青黒くて波が高くて、海は力強く生きていた。
いまごろ長野は雪に埋もれているだろう。近くの湖は氷が張り、校庭では雪遊びをするこどもたちが大はしゃぎしている。かおりもかつてはその一員だった。
どちらも日本だというのに、同じ一日がこんなにも違うということをかおりは知らなかった。海はどこまでも広く、大きくうねり、小さな白波を立てている。歩くたびに黒っぽい砂が靴につくが、かおりは、そんなことはどうでもよかった。長野の雪深い場所で育ったかおりは、圭一の育った場所が正反対だと思った。それは同時に価値観の違いを生み、ひっそりとふたりの未来に影を落とした。
「よう来たねえ」
川口圭一の母は小林かおりの両手を包み込む。50歳を少し過ぎたころだろうか。ふくよかで穏やかそうな田舎のおばさんという風情の女性。ゆったりとしたロングワンピースを着ている。圭一は、母だと紹介した。
「ずいぶん厚着してきたのね」
「お母さん、玄関で話さないで、早く中へ入ってもらいなさい」
「お父さん……そうね、つい嬉しくて」
かおりを見ながら花のように笑う母親は、圭一と優しそうな目元が似ている。圭一の身長は父親譲りだろうか。家の中から大柄な父が圭一たちに声をかける。圭一の家は立派な門構えで、瓦屋根が目を引く古い屋敷だった。家の近くを路面電車が通っているそうで、風に乗って電車の音が聞こえた。
「お昼はまだでしょう? みんなで食べましょう」
居間に圭一の父方の祖父母、両親が一堂に介した。席が一つ空いている。
「うちは敷地の中に家がふたつあって、片方にはおじいちゃんたちが住んでる。週に1、2回、一緒に食事をするの。で、あっち側が貸しているアパート」
圭一の母がかおりに説明をする。窓からは隣のアパートが見えた。何棟かあり、ベランダには洗濯物がはためいている。
「うちは大家さんなの。生活していくには何とか困らないくらいだから、私たちの心配はしなくて大丈夫よ」
居間の机の上には刺身やてんぷらなど、料理がたくさん並んでいる。昼から日本酒の一升瓶が出てきた。かおりはテレビで見るような大人数の食卓にめんくらった。
「それでは圭一とかおりさんのご縁を祝って、乾杯!!」
「おめでとう」
「おめでとう!」
「かおりさん、ありがとうね」
家族が口々に圭一とかおりをお祝いしてくれた。
「おお、圭一。お帰り」
みんなが食事をはじめてしばらくたってから、気の強そうな女性が部屋に入ってきた。
「久美子、何回呼んでも来ないんだから」
圭一の母に『久美子』、と呼ばれた女性はうるさそうに手をふりながら、空いている席に座った。
「ごめんごめん。かおりさんだっけ? おめでとう。でも、圭一と結婚すると苦労するよお」
新入りのかおりを見つけて、久美子は目を輝かせて言った。
「姉ちゃん、うるさい」
「圭一はねえ、金遣いも荒いし、片付けできないし、だらしないし。夏の自由研究なんて、わたしの前の年のを写して出したんだよ。人間として終わってる」
「うるさいよ、早く嫁に行け」
「余計なお世話だよっ。言われなくてもそのうち行くわ」
久美子は姉で、ふたつ上の26歳だと圭一はかおりに紹介した。仲がよさそうにじゃれあっている。
「かおりさんは、圭一のどこを好きになったの」
圭一の祖父が身を乗り出して聞く。
「おじいちゃん、また、ストレートな質問して。で、どこが好きなの」
圭一の母は祖父の質問を止めるのかと思いきや、加勢する。
「わたしは圭一の笑顔が好きや」
祖母が言う。圭一はえくぼがくっきりと出るくらい笑う。
「ちょっとおばあちゃんには聞いてないよ」
姉の久美子が突っ込みを入れる。圭一の家は、底抜けに明るく、風通しが良くて、かおりのトゲトゲした母親とは大違いだった。
夕方近くまでどんちゃん騒ぎをし、圭一は疲れからか座敷でそのまま眠ってしまった。一番飲んだのは祖母だった。片付けを始めたころ、圭一の父はかおりに言った。そばには圭一の母がいる。
「かおりさん、突然のことに驚いたでしょう。でもね、圭一はあなたを幸せにしたいと言っている。どうか、圭一をよろしくお願いします」
「そうよ。一目ぼれだったって。しっかりした女の子だから、俺にはぴったりだって。かおりさん、仕事も続けるのよね?」
「それは圭一がしっかりしないと」
「体に気を付けてね。うち、土地は貸すくらいたくさんあるからいつでも帰ってきて」
「お母さんは帰ってきてほしいんだろう」
「そりゃあそうよ。さみしいもの」
「わしがおるやないか」
「でも、みんないるともっと楽しいでしょう」
圭一の両親の仲の良い所を見て、かおりは身が縮む思いがした。
かおりの母は、失敗を許さない人だった。かおりがテストでクラス一位を取っても『100点取れてない』。マラソンで2位になると『1位じゃないの』。頑張っても、褒めてもらったことはない。高校まで、まわりからは『小林先生の娘』と言われ、息を抜く場所がなかった。なにか母に相談をしたら『恥ずかしい子』『あなたになんかできるわけがない』『私の時間を奪って迷惑かけないで』と言われ続けていた。
母は、家でもテストの採点や書類作成などで忙しそうだった。夕食もあまり一緒に食べた記憶はない。わたしのことがわずらわしかったのかもしれない。家では、出来のいい生徒の話ばかりをしていた。彼らと比べられるのも辛かった。
「圭一はね、足らないところもあるけどいい子なの」
「お母さん、それは親ばかと言うやつだよ」
「お父さんも、いつも圭一のこと私に自慢してるでしょう」
「圭一も久美子も、わしに似て、天才じゃ」
「ほら、お父さんも親ばか」
「すてきな奥さんだけじゃなくて、孫まで連れて来てくれて」
「産まれるのが楽しみよね」
かおりはここまで戦ってきた。お腹の命を一人で守った。だれも、お腹の子のことを喜んだり、楽しみにしてくれる人はいなかった。かおりは涙が出そうになって、ぐっとこらえようと口をへの字にしていた。
「男の子かな、女の子かな」
「どっちだって、私たちのかわいい初孫よ」
ただただ嬉しそうなふたりの様子に目頭が熱くなる。目に涙がたっぷりたまり、今にも流れ落ちそうになっている。圭一の父と母はそれに気づいて、おろおろしている。
「変なこと言っちゃったかな。ごめんなさいね」
かおりは、とぎれとぎれに言葉を発する。
「いや……結婚前にこんなことになって申し訳ないです。みっともなくて、恥ずかしいです。わたしなんかが来て、ご迷惑おかけしてすみません。それに仕事も子育ても、できるか不安で……」
かおりが震える声で詫びると、圭一の母はかおりの肩を抱いて、かおりの涙をぬぐった。柔らかい風が縁側から居間を通り、路面電車の音を運んできた。かすかに聞こえる規則的な音が心地よい。
「『わたしなんか』なんて二度と言わないこと」
そう言いながら義母は、かおりをぎゅうっと抱きしめた。
「あなたはできる。あなたは強い。あなたは愛されている」
あの雨の夜、神楽坂で圭一がかおりに教えてくれたおまじないだった。
義母の声が子守歌のように優しくて。やわらかで温かい義母のカラダに包まれて。かおりは我慢できず、子供のように声をあげて泣いた。義父母は、かおりのことを自分たちの子供のように抱きしめ、優しく背中をなでてくれた。
一泊というあわただしい日程だったが、翌日、かおりは日曜市やチンチン電車など高知を十分堪能した。空港まで送りたがる家族たちを断り、圭一はレンタカーに乗り込んだ。
「また来てねえ」
「いつでもおいで」
「結婚式楽しみにしてるね」
「わたしも花嫁衣裳着ようかしら」
「おばあちゃんはいいの」
窓の外から、家族の笑い声が聞こえる。この人たちがわたしの家族になる。かおりは嬉しくて胸いっぱい、この町の空気を吸い込んだ。頑張ろう。圭一を育んだ高知。彼のおおらかさの源をもっと知りたいと思った。
空港のレンタカー屋についた。圭一が会計をする。ゴールドカードを渡す。しばらく試していた店員が申し訳なさそうに言った。
「お客様、このクレジットカードは使えないようです」
「あれ? じゃあ、こっちを試してもらっていいですか」
圭一は、レシートでふくらんだ財布から、もう一枚ゴールドカードを渡す。かおりは、ぼんやりと、はじめてデートした表参道のカフェでも磁気がおかしくなっていたなと思い出した。圭一のパンパンに膨らんだ長財布を見て、財布の整頓をすればいいのにと思った。
「こちらも……磁気がおかしいのかもしれないです」
「じゃあ、こっちはどうですか」
出発の時間が迫ってきた。マルイのカードを渡す。しばらくすると、ピーっという音がして、店員の顔は曇る。
「すみません、こちらも……」
手続き時間が迫っていたこともあり、かおりは焦った。
「ここはわたしが払うよ」
圭一は待っていたかのようにすっと身を引いた。
飛行機にはギリギリ間に合ったが、荷物を預ける時間も、土産を買う時間もなかった。
「いまから高知、いっぱい来るから」
窓側に座った圭一はかおりの手を握った。飛行機が離陸する。窓の外は美しい夕焼けで、オレンジとピンクに染まっていた。高知の広い空が圭一の鷹揚さの象徴のようで、かおりは圭一越しに空を見つめた。
「結婚式、楽しみにしてくれてたね」
「うん」
「わたしは結婚式しなくてもいいかって思ってたけど、どうしようか」
「しなくてもいいよ」
「でも、みんな楽しみにしてくれてたし」
圭一は窓の外をしばらくながめていたが、なにかを決心したように口を開く。
「俺ね……が……ある」
「え?」
離陸の雑音が大きく、圭一の声が聞こえづらい。
「おれ借金がある」
「え?」
かおりは聞き間違えたかと思ったが、その瞬間、表参道のカフェでクレジットカードが使えなかったことや、ガソリンスタンドで『ハイオク、現金2000円分』と言ったこと、レンタカー屋でカードが使えなかったことなどが次々と頭の中をめぐった。
「ちょ、ちょっと待って」
「うん」
「借金って本当に」
「うん。だから赤ちゃんできたって聞いた時に『そんなに急がなくてもいいんじゃない』って言ったの。結婚式するお金なんてないよ」
「え、いや、なにそれ」
「プロポーズするときも『大変かもしれないけど』って言ったじゃん」
「借金なんて一言も言ってないよ」
「聞かなかったよね」
「聞かなかったわたしが悪いの?」
「まあ、そうなるね」
圭一の他人事のような物言いに、かおりはあっけにとられる。だけど、これでつじつまが合う。圭一のクレジットカードが使えなかったのは、磁気のせいではなかったのだ。
「……借金っていくらぐらいなの」
「わかんない」
「わかんないってなにそれ」
「最悪、うちの親に助けてもらえばいいよ。お金あるだろうし。きみも仕事やめないでしょ」
圭一の無責任な言動にかおりはつないでいた手を振り払った。そして、自分の貯金を計算した。学生時代に借りた奨学金はもう返し終わって、400万ほど貯金がある。それになんといっても、東通も祥明社も年収は1000万を下らない。かおりは、学生時代と生活を変えていなかった。そう思い当たった瞬間、まわりの空気がなくなって真空状態になったような気がした。
『東通も、年収は1000万を下らない』。それなのに、クレジットカードが何枚も使用不能になっている。借金がある。圭一はいったいなににそれほど金をつかっているのだろうか。
高知空港に降り立った時、圭一は『きみは、仕事を辞めないほうがいい』と言った。あれはかおりのためではなく、自分のために言ったのだということに気づくのに、そう時間はかからなかった。
告白をしてすべて許されたようなつもりなのだろうか。圭一は何事もなかった顔をして窓の外を見ている。夕焼けのピンクやオレンジが締まりのないだらしない空に見えて、かおりは目を閉じた。頭の中には、圭一の姉、久美子の言葉が浮かんだ。
『圭一はねえ、金遣いも荒いし、片付けできないし、だらしないし。人間として終わってる』
冗談かと思ったが、本当なのだろうか。どこまで本当なのだろうか、もしかして、すべて事実なのだろうか……。かおりは上空の窓から忍び寄る冷気に身震いした。
作家 松村まつ
東京都内に勤務する会社員。本作がはじめての執筆。趣味は読書と旅行と料理。得意料理はパテ・ド・カンパーニュ。感動した建物はメキシコのトゥラルパンの礼拝堂とイランのナスィーロル・モルク・モスク。好きな町はウィーン。50か国を訪問。