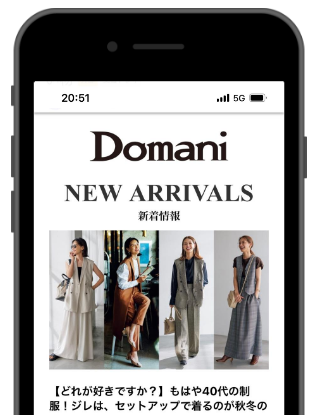〈19〉
【登場人物】
川口圭一 (24) 大手広告代理店・東通勤務。コピーライター。借金がある。
小林かおり(24) 大手出版社・祥明社のティーンズ誌『プチファスト』編集者。長野出身。
<これまでのあらすじ>
2022年2月14日、東京・佃。銀座にほど近い高級マンションから一人の男が転落した。男の身元は大手広告代理店勤務42才の川口圭一。転落したマンションは、川口が家族4人で住んでいた。他殺か、自殺か、事故か。話は18年前の2004年、圭一と妻のかおりの出会いへさかのぼる。たった一度のセックスで子供ができてしまった圭一とかおり。結婚することを決めたが、お互い知らないことばかりで……。
『ちょっと遅れるかも』
小林かおりは川口圭一にメールを打った。圭一との約束は19時だ。いますぐに出ないと遅れてしまう。かおりは渾身の企画案を編集長にメールで送付し、編集部を出た。
中目黒から目黒にかけては雰囲気のいいインテリアショップが軒を連ねている。今日はそこで目をつけていたソファを見に行く予定だ。
時間より5分前に店の前についた。圭一はまだ来ていない。かおりは先にソファを試すことにした。15分遅れて圭一が来た。店内で、ソファに試し座りしているかおりを見つけた。
「そのソファが欲しいやつ? いいね」
「15万って高くない? わたし、お金ないかも」
「欲しいんでしょう。貯めている時間が無駄だよ。ローンかボーナス払いで買っちゃえば」
「……止めておく。新しいソファは、なくても暮らせる」
「うん。でも、俺はこれ、欲しいな」
圭一が指さしたのはル・コルビジェの黒い三人掛けソファだった。100万はゆうに越す。かおりは意味がわからなかった。
「そんなお金、どこにあるの?」
「ボーナス払いにすればいいんじゃない?」
「これからお金かかるのに?」
「なんとかなるよ。親がお祝いに買ってくれるかも」
「あのさ、なんともならないよ。まさか、親からお小遣いとかもらってないよね」
「たまにもらうかもね」
すでにいくらかわからない借金があるというのに、さらに身の丈に合わないものを欲しいと言える感覚。頭を抱えるかおりの横で、圭一はフランクロイドライトの照明・タリアセンを眺めていた。20万。イサム・ノグチのガラステーブルも見ている。30万。
どうして店にあるものの中で、一番高いものを見るのだろう。圭一は1ー1=3とでも思っているのだろうか。奨学金とバイトで爪に火を点すような大学時代を過ごしたかおりには理解ができなかった。
結局その日はなにも買わずに帰った。圭一はクレジットカードが使えないようで、かおりが支払わなければ買い物はできなかった。
おしゃれなレストランに入りたがる圭一を制し、ファストフード店に入った。
注文をする。圭一は一番高いセットに、チキンナゲットも追加した。そういう目で見ると、圭一はなんでも一番高いものを選ぶ。これっぽっちも節約する気はなさそうだった。そもそも、そういう人間だから借金があるのだろうけど。
「あのね、借金があるって言ったでしょう」
「うん」
「なんでそんなにお金がないの」
「東通はお金がかかるの」
「どういうこと」
「後輩と行くとぜんぶおごりだし。まわりはみんな金持ちばっかりだし。俺だけみっともない恰好とか車に乗るとかできない」
「あの……オープンカーのBMW。あれもローン?」
「そう」
圭一は手元にお金がなくても、軽々しくローンやボーナス払いを選ぶ人間だということがわかってきた。家計簿をつけて、アルバイトをして、奨学金を返してきた自分とは考え方が根本的に違う。
「車の維持費は、年どのくらいかかるの」
「わかんない」
「ねえ、子供生まれるのに」
「なんとかなるよ」
「なんともならないよ!」
圭一は足を組んで、肘をつき、顎を手で支え、黙り込んだ。このどうでもいいもめごとから逃げたいという顔をしていた。
「お願いだから、借金の総額を出して。年間にかかる車の維持費や、携帯とかの年間額も計算して」
「はいはい」
「それから、引っ越し先の候補。あと結婚届もいつだす」
「いま3月だから4月までには。冗談みたいな結婚だから4月1日でいいんじゃない」
「嘘でしたって。できるといいね。わたしだってそうしたい」
かおりが望んだわけではないのに、かおりが結婚を迫っているような構図になっているのが腹立たしかった。元はと言えば、圭一が無責任に生でセックスをしたからではないか。喉元まで出かかった言葉を飲み込んだ。借金だけではなく、圭一にはまだ疑惑がある。どうしてたくさん給料をもらっているのに借金があるのかわからなかった。
「婚姻届けはかおりの家で書こうか」
「……そういえば、わたし、家に行ったことないんだけど」
「来なくていいよ」
「そんなに隠されると、心配なんですけど」
「なにも隠してない」
「なにがあっても平気だから見せて」
「ほんと大丈夫」
「大丈夫じゃない」
どうしてこんなに家に入れたがらないのだろうか。もしかして女と住んでいるんだろうか。借金もそうだが、圭一はわからないことが多すぎる。
「そうそう、うちの両親が、かおりのご両親にご挨拶したいって。妊娠中でつらいだろうから、東京でどうかなだって。その前にご両親にもご挨拶行かないとだけど」
「わたしの親……」
圭一にも借金という秘密があったが、かおりも圭一に親が離婚していることを言っていない。そして、できちゃった結婚なんて知ったら、母は、鬼の首を取ったようにかおりをあざ笑うだろう。家族の仲がいい圭一に、自分の家庭環境を伝えることはつらかった。
「長野だから、近いし、いつでもいいよ」
「ううん、そしたら今週末行こうか」
「聞いてみるね……あのさ、私の母、教師ですっごく厳しいの。だから覚悟して」
「お父さんは」
「父も教師だったけど、もう亡くなった」
「いつ亡くなったの」
「小さいころ。だから祖母に育ててもらった。祖母も大学時代に亡くなった」
かおりは噓は言わなかったが、巧妙に親の離婚について避けた。強引に話を変えるように、バッグから物件のちらしを出した。
「あと、引っ越し先の候補。駅から徒歩10分以内、15万円以内の2DKで探してみた」
「小田急線の経堂、京王線の芦花公園、中央線の三鷹……。広尾とか麻布十番とか無理かな」
「お金ないし、無理」
「うん……まあいいか」
翌日、内見をして芦花公園から徒歩12分の2DKを契約した。圭一はリビングに備え付けてあるプロジェクタースクリーンが気に入ったようだった。引っ越し費用はかおりの貯金から出した。
「わたしは3月1日には引っ越せると思う」
「手伝いに行くよ」
「荷物少ないからトラック小さいので大丈夫」
「全部捨てておいで。新しいの買おう」
「だから……そう言うのが積み重なって借金ができるんじゃないかな。この引っ越し費用は折半で、後で請求するから」
かおりが厳しく言うと、圭一は愛想笑いをした。
かおりは一足早く引っ越しを終わらせた。6畳の1Kは物が少なく、4時間ほどで終わった。圭一はあとから引っ越しをしてくることになった。前日の夜、圭一から電話がかかってきた。
「引っ越しの荷物詰めてるんだけど、朝までに終わらないかも」
「手伝おうか」
「いや。大丈夫」
そういって電話は切れた。朝もう一度電話をかけると泣きついてきた。
「どうしても終わらないから手伝って」
そういわれて圭一の恵比寿の部屋へ向かう。そこには、少し感じてはいたけれど、予想を超えた世界が広がっていた。
作家 松村まつ
東京都内に勤務する会社員。本作がはじめての執筆。趣味は読書と旅行と料理。得意料理はコルドンブルー。感動した建物はメキシコのトゥラルパンの礼拝堂とイランのナスィーロル・モルク・モスク。好きな町はウィーン。50か国を訪問。