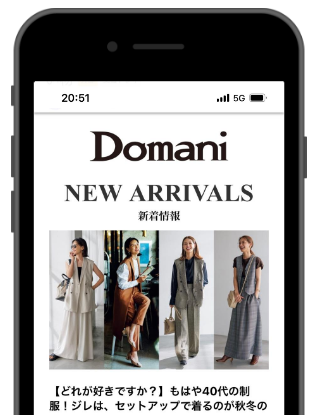【目次】
〈12〉
【登場人物】
川口圭一 (24) 大手広告代理店・東通勤務。コピーライター。
小林かおり(24) 大手出版社・祥明社のティーンズ誌『プチファスト』編集者。長野出身。
大宮ちか(24) 祥明社の文芸誌『トロイカ』編集者。かおりの同期。
妹尾サキ(24) 高文館のスクープ誌『週刊女性ファイブ』編集者。かおりのことが本能的に嫌い。
<これまでのあらすじ>
2022年2月14日、東京・佃。銀座にほど近い高級マンションから一人の男が転落した。男の身元は大手広告代理店勤務42才の川口圭一。転落したマンションは、川口が家族4人で住んでいた。他殺か、自殺か、事故か。話は18年前の2004年1月。圭一と妻のかおりの出会いへさかのぼる。
傘の先からはしずくがしたたり、遠慮がちに傘に入る小林かおりの肩をぬらす。川口圭一は傘をかおりのほうにかたむけながら、かおりの肩を抱き寄せた。圭一のさわやかでいて甘い香水が鼻をくすぐる。
「もっとこっちにきて。おれの肩がぬれちゃうでしょ」
圭一はいたずらっぽく笑う。かおりのカシミヤのコートの肩に乗せられた圭一の手に雨粒があたっている。すこしでもかおりがぬれないように、手で雨を防いでくれているようだった。雨、といっても真冬の雨は雪に近い。圭一の手は冷たさで真っ赤になっている。申し訳なさで、かおりはすこし体をよせた。
ふたりは大通りから、住宅街の細い道へ曲がる。いままでの喧騒がうそのように、人通りがほとんどなくなった。
圭一は肉まんのビニール袋を見ながら、かおりに聞く。
「肉まん好きなの?」
「好きですよ」
「すごく好きなの?」
「すごくってほどでもないけど」
「それなのに、こんなにたくさんの肉まん。ひとりで食べるの?」
ずっしりとたわむ肉まんのビニール袋を見ながら圭一が聞いた。
「ううん、母と食べようと思って」
「いっしょに住んでいるの」
「質問攻めですね」
かおりは、体を引いて圭一の顔を見つめる。圭一は前を見ている。目を合わせて、警戒されるのを避けようとしているのか、不自然な自然さを装ってた。
「うん。それで、いっしょに住んでるの?」
「今日はたまたま田舎から来ていて……」
かおりは、答えながら、携帯に母のメールが来ていないか気になった。バッグから携帯を手に取り、ちらりと確認する。折りたたんだ携帯の窓にはなにも表示されていない。そのままコートのポケットに入れる。
「田舎はどこなの」
「長野です」
「電車で2時間くらい? まあまあ近くだね」
「長野市なら。でも長野の山奥だから、そんな近くもない」
「へえ、どんなところ?」
「湖がすぐそばにあって、山もあって」
「湖に山。長野に、そんなところがあるんだ」
「うん。……冬は体育でスキーをするの。帰りたいなあ」
「ねえ」
呼ばれてかおりは、圭一の顔を見る。かおりを見る目が優しい。
「もっと、こっちによっておいでよ。雨にぬれる」
かおりの肩と圭一の手はずいぶんぬれてしまった。それでも、さほど圭一のほうに体をよせないかおりをからかうように、圭一は肩から手を離し、傘を自分のほうにかたむけた。
「ぜんぜんこっち来ないから。もう知らない」
圭一のこどものような口調に、かおりはつい軽口をたたいた。
「ひどいなあ」
「なん回も言った。こっちおいでって」
「だって、そんなにまだ仲良くないでしょう」
「まだ?」
「そう」
「『まだ』ってことは、これから仲良くなるの?」
「知らない」
「いつ仲良くなるの」
「わかりません」
圭一は、顔をそむけたかおりの体を自分のほうに向ける。かおりの身長に合わせ、かがんでいる。圭一のやわらかくウエーブした前髪が目にかかり、手でかきあげた。
「おれは、もっと知りたい」
圭一の目が切なそうにゆれる。
「なにが大切で、どんな場所が好きで、どんな映画が見たくて。好きな食べ物も、嫌いな食べ物も、黙っているとき、なにを考えているのか。知りたい」
まっすぐな圭一のことばと視線を処理しきれず、かおりは戸惑った。
「そんな……知ったってがっかりするだけだよ」
「がっかりするかどうかは、おれの気持ちでしょう? どうしてわかるの」
「わかるよ」
「おれの気持ちが?」
『あんたみたいな女、だいきらい』妹尾サキに、ほんのさっき言われたことばが、とげのように刺さっている。昨夜、母は『いつだって私のことをばかにして!!!』とかおりの肩を突いた。かおりは、そこにいるだけで、人の気持ちを逆なでしてしまった。
圭一の迷いなき視線を受け止めきれず、かおりは目を伏せる。
「だれもわたしのことなんて知りたくない。わたしなんて……頑張ったってなにしたって、めざわりで……」
かおりが言い終わる前に、圭一は、もうそれ以上ことばを重ねないよう、優しく、キスをした。
固まるかおりを見つめて、もう一度ゆっくりと、いとおしむようなキスをした。圭一の広い胸に、長い両手でかおりを包みこむ。いままでかすかに香っていた圭一の香水が、かおりのすべてをすっかりおおってしまう。静かにかおりを抱き寄せて、圭一は言う。
「ことばには……魂があるって言うでしょう。そういうことばは言ったらだめ」
すぐにとけてしまう初雪を思うほどそっと、大きな手で、かおりの髪をなでた。圭一のすこし鼻にかかったような、低くて、透明で、あたたかい声が心地よい。
「大丈夫、大丈夫」
圭一は体を離し、かおりの瞳をのぞきこむ。そして、指を1本、2本、3本と出す。
「かおりはできる。かおりは強い。かおりは愛されている」
「……なにそれ」
「おまじない。おれはつらい時、いつもこれを言うの。『おれはできる。おれは強い。おれは愛されている』」
圭一がニコッと笑う。目じりにしわが寄る。
「できないかもしれない。でも『できる』って決める。さっき、店で妹尾サキに言ってたよね」
戸惑うかおりに、圭一は続ける。
「全部入りラーメン」
「ちょ、ちょっと……どこから聞いてたの」
かおりの声はうわずっている。
「妹尾サキが『芸能人の泣いてる顔見るとスカッとする』って言ってたあたりかな」
……ということは、そのあとの『全部ほしい』と言ったくだりも、なにもかも聞かれてしまっている。大宮ちかと妹尾サキが酔っぱらっているから思いきって言ったと言うのに。狼狽したかおりのとなりで、圭一は片ほおだけ笑った。
「『わたしは全部ほしい』、それに『自分の人生で証明して見せる』…かっこよかったね」
かおりは力なく笑い、懇願した。
「忘れて」
「忘れない。強烈だった」
圭一は完全に面白がっている。圭一から逃げ出そうとするかおりの腕をつかんで抱きすくめると、かおりのコートのポケットから携帯を取り出し、かおりのことを抱きしめたまま、背中あたりで、いくつかの番号と発信ボタンを押した。圭一の香りにむせかえる。
携帯の着信音が鳴る。音を認めると、圭一はかおりの携帯を持ったまま、器用にズボンのうしろポケットから自分の携帯も取り出した。圭一の片方の手はずっと、逃げないようにかおりを抱きしめている。
「こ、ば、や、し、か、お、り」
片手だけでかおりの番号を携帯に登録すると、やっとかおりを放し、携帯を差し出した。
「この発信履歴、おれの番号。登録して」
かおりは圭一から携帯を奪い取ると、走って家へ向かった。
「忘れ物!」
圭一が呼びかける。
かおりが振り返ると肉まんをかかげている。そのとき、だれかから着信があったのか、圭一の手の中の携帯のランプが点滅していた。圭一はちらっと携帯を見たが、すぐかおりの方を見なおした。
かおりはあせって肉まんを取りに戻る。肉まんのビニール袋をつかむが、圭一は手を放さない。
「なんか言うことあるんじゃないの?」
「か、買ってくれて、ありがとうございましたっ」
圭一の顔は見ずに勢いよく頭を下げ、肉まんを力いっぱいひったくり、こんどこそ、走って逃げた。
圭一はかおりの後ろ姿を見ながら携帯を開いた。
画面には『圭一、なにしてる? 会いたいよ、セックスしよう』とメッセージが書かれていた。圭一は『いいよ』と送信し、夜の街に消えていった。
作家 松村まつ
東京都内に勤務する会社員。本作がはじめての執筆。趣味は読書と旅行と料理。得意料理はパテ・ド・カンパーニュ。感動した建物はメキシコのトゥラルパンの礼拝堂とイランのナスィーロル・モルク・モスク。好きな町はウィーン。50か国を訪問。