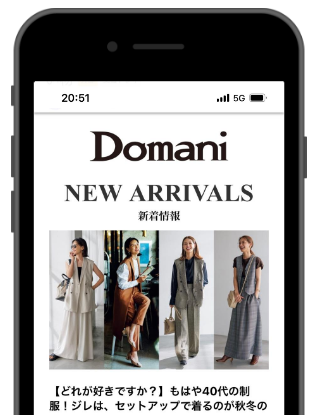【目次】
〈14〉
▶︎各話一覧
【登場人物】
川口圭一 (24) 大手広告代理店・東通勤務。コピーライター。
小林かおり(24) 大手出版社・祥明社のティーンズ誌『プチファスト』編集者。長野出身。
大宮ちか(24) 祥明社の文芸誌『トロイカ』編集者。かおりの同期。
<これまでのあらすじ>
2022年2月14日、東京・佃。銀座にほど近い高級マンションから一人の男が転落した。男の身元は大手広告代理店勤務42才の川口圭一。転落したマンションは、川口が家族4人で住んでいた。他殺か、自殺か、事故か。話は18年前の2004年1月。圭一と妻のかおりの出会いへさかのぼる。
小林かおりが携帯を取ると、電話の向こうでは息を殺している気配がした。
ブツッ。そのまま、何も言わずに切れた。
友人の大宮ちかがかおりに聞く。
「間違い電話?」
「かな。切れちゃった」
ちかは、返事を聞きながら塩ピーナツをつまむ。その塩をふくため取ったティッシュを捨てるごみ箱を探した。
かおりがごみ箱を取ろうとしたとき、中にやぶれた父と母の写真があった。ばらばらになった、ふたりの笑顔がむなしい。ごみ箱をのぞいて動かないかおりをいぶかしく思い、ちかもごみ箱をのぞく。
「写真の男の人、川口圭一にちょっと似てる」
「お父さんなの」
「へえ。……聞いていいかわかんないけど、なんでこの写真破いちゃったの?」
「わたしじゃなくて、昨日、母が怒って破いてしまった」
「昨日、お母さん来てたの?」
「そう。合鍵を持ってて、突然来るの」
「ええっ。それは嫌じゃない?」
「嫌だよ。でもわたしがちゃんとしてないのが悪いからしょうがないの。それに、嫌がると『なんか隠しているんだろう』『お前に正しい判断ができるわけがない』『親を大事にしないと不幸になるぞ』ってすごい言うし……」
ちかは険しい顔をした。そしてピーナツを空中に投げ、口でキャッチした。食べながら言う。
「……かおりが『わたしなんか』って言って、自分に自信がないのは、お母さんが関係してるのかもね」
自分の自信のなさと、母のことが結びつかず、かおりがきょとんとした顔をしている。ちかはぼそぼそと続ける。
「『毒になる親 一生苦しむ子供』って本が出てて、この前、作家さんに資料で送ったとこ。かおりのお母さんみたいに、子供に対して過干渉というかそういう感じ」
「『毒になる親』……読んでみる」
「うん。あと、この写真も直せるかも。写真屋さんに持っていくと、破れたり色あせた写真を修復してくれるサービスがある。ちょっと待ってね」
ちかが自分のバッグから手帳を探して開く。
「1万円くらいかかるけど。小説の取材で聞いたお店、メモに書いとくね」
表参道の写真館の電話番号と住所をメモしてくれた。
もう一度携帯を見ると、川口圭一からショートメッセージが届いていた。
『明日なにしてる? ひまなら昼ごろ、買い物に付き合ってくれませんか』
文字を読むだけで蛍光灯を取り替えたような気持ちになる。
「ちか。川口くんから『明日なにしてる? 昼ごろ買い物付き合って』って連絡来た」
「見せて見せて……ほんとうだ。かおりの明日の予定は?」
「ひとりで映画見て、本も読もうと思ってた」
「かおりらしい過ごし方。行っておいでよ。昼に集合ってのは健全でいいじゃない。深夜に現れる川口らしからぬ誘いだね。けっこう本気なのかも」
「そうであってほしい! なにを着ていこう」
「やはり、ワンピースかスカートでは!?」
「やはり……!!」
川口圭一は『昼前がいい』と言う。11時に表参道のパン屋・アンデルセン前で待ち合わせた。かおりとちかは、しばらくファッションショーをした。白いワンピースほど本気すぎず、ピンクのフリルシャツほど子供すぎず、「ちょうどいい塩梅」と言う理由で、黒のタートルニットにボルドーのスカートに決めた。靴は買い物でたくさん歩くことを考え、黒のバレエシューズにする。シンプルだけど、なかなか好きな組み合わせが決まり、ハンガーにかけた。
「明日が早く来ないかな」
「いつもはしゃがないかおりが嬉しそうなの見ると、嬉しいよ」
かおりは遠足の前の日のように、わくわくしている。ちかは優しく微笑んだが、すぐに厳しい顔になった。
「ただし、川口が独り身かどうかはなんとも言えないから、即エッチはぜったいダメだよ」
「わかってる」
「流されないようにね」
「うん。ちか、ありがとう」
翌朝。かおりは嬉しすぎて早起きをしてしまった。ホットサンドメーカーで肉まんをはさみ、焼いた。それを朝ごはんにして、ちかとふたりで食べた。外はカリっと、中がふっくらと焼けている。ちかが「おいしい」とほめてくれた。かおりの家に来てから水しか飲めなかったちかは、二日酔いにならずにすんだ。
いま考えている企画のこと、今日の天気のこと、最近観て面白かった映画。なんてことない話をたくさんした。そして、写真館にも寄れるよう、早めに家を出た。外は寒いけれど、冬晴れのすばらしくよい天気だった。
東西線から九段下で乗り換えるとき、母から電話がかかってきた。昨日の朝、怒ったまま別れている。きっとこの電話も「なにをやっているのか」という、詮索の電話だろう。せっかくのよい気分を壊したくなかったが、わたしはもう違う。逃げたくなくて電話に出た。
「かおり? なにしてるの」
「今日は友達と買い物」
「金曜も土曜も出かけて。遊び歩いてばかりじゃだめでしょう。今日は早く帰りなさい。わかった? お母さんの言う通りにすれば間違いなんだからね」
かおりの返事を聞かずに、一方的にまくしたてて電話は切れた。
いつも母に愛されたいと思っていたけれど、もしかして母は普通ではないかもしれない。昨日、ちかに指摘されたことで、ずっと抱えていた疑問が、猛烈に細胞分裂をするアメーバのように心に広がっていった。かおりがぼんやり立ち尽くしていると、走ってきた人に当たってしまった。
「ごめんなさい」
反射的に謝り、時計を見ると、11時が近づいてた。これでは写真館どころか、待ち合わせにすら間に合わない。急いで半蔵門線に乗り換えた。
待ち合わせの場所には3分遅れで着いた。このぐらいなら連絡をするより、走ったほうがいい。川口圭一はすでに店の前で待っていた。遠くから見てもバランスのいい体躯が人目を引く。自分だけに会うために、そこにたたずむ圭一。早く来て、陰からこっそり眺めたかったな。かおりは走りながらそんなことを考えた。
かおりを見つけて、圭一は手を振り近寄ってきた。
「走らなくていいよ。まだ遅刻じゃない」
すこし肩で息をするかおりの様子を、圭一は優しい目で見ていた。昼の光で見ると、茶色い目がいっそう透明感を持って迫る。切れ長で、涼しげで、でも笑うと少したれ目で。かおりは圭一から目が離せなかった。
「どうしたの、そんなに見ないでよ」
「いや……つい。ごめんなさい」
うつむいて赤くなるかおりを見て、圭一はえくぼを出して笑った。つねに愛されてきた人間の余裕だろう。謙遜することなく、自分に魅せられた者を面白そうに眺めている。
圭一は流行りのセレクトショップを何件か見てまわった。どの服もよく似合う。特にざっくりと編み上げられた白いセーターは圭一の広い肩幅にそって落ち、いっそう魅力的だった。
昼過ぎに近くのカフェに入った。半地下のテーブルに案内されると、奥にかおりを座らせ、圭一は手前に座った。圭一は一番ボリュームのあるメニューを頼んだ。
「すみません、グラスの赤ワインも」
かおりはパスタと白ワインを飲んだ。かおりが一杯で済ませたのに対して、圭一は二杯飲んだ。会計は圭一がごちそうしてくれた。
「お客さま、クレジットカードの磁気がおかしくなっているのか通らないんですが。ほかのカードはお持ちですか」
と店員に問われ、もう一枚出した。どちらもゴールドカードで、東通の羽振りがいいことを示していた。
店を出て、もう一度、白いセーターのある店に戻ることになった。
「寒いね」
とかおりを振り返った圭一は、かおりに手を差し出し、自分のポケットに手をつないだまま入れた。ポケットの中は暖かかった。圭一の手をぎゅっと握ると、握り返してくれた。
店に入り、手を離した圭一は白いセーターを買った。ほかの店でも襟とカフスだけが白くなった薄い水色ストライプのシャツを買った。
店に入るたびに手を離し、そして出た時に再びつなぐ。何回か繰り返していたら、ふたりで歩き出すとき、手をつなぐのが自然になっていた。圭一はいろんな話をした。
圭一の大学時代のバレーボールのことや、好きな本に、好きな料理。旅行の話やテレビの話。話題は尽きることなく、次から次へとあふれていた。
途中、写真館の近くを通ったが、圭一の話を聞いていたいと思ったかおりは、立ち寄ることを言いださなかった。
そのまま、村上春樹が行きつけだという蕎麦屋で夕食を食べ、日本酒を飲んだ。楽しくて、ふたりでビールと4合瓶2本を飲みほした。ふたりでほろ酔いになった。圭一は、かおりを家まで送っていくと言ってくれた。
「まだ電車はあるから大丈夫」
「でももう少し一緒にいたい」
自分のことを大切にしてくれる圭一の優しさが嬉しい。ふたりでタクシーに乗った。夜の11時を過ぎていた。
タクシーに乗ったとき、携帯が鳴った。母からだ。かおりはため息をつき、電話に出なかった。疲れた様子を見せたかおりに気づいた圭一は、そっと手を握った。
しばらくして、また携帯が鳴った。昨日かかってきた謎の電話番号だった。もしかして、明日、撮影する仕事相手だろうか。何度もかかってくるということは、緊急の電話なのかもしれない。
「もしもし」
かおりが電話に出る。つばを飲み込む音が聞こえた。
「……どうして電話に出ないの」
それは母の声だった。
「あなたがわたしの電話に出ないから、別の携帯からかけたの。なにをしてるの。どこにいるの。だれかといるんじゃないの」
準備をしていなかった突然の母の声に、心がつぶれそうになる。かおりは迷子の子供のように圭一の手をぎゅっと強く握った。
そうだ。わたしは昨日までのわたしじゃない。わたしはできる。わたしは強い。わたしは愛されている。胸の中でそうつぶやき、小さな吐息を吐いた。
「わたしがだれといてもお母さんには関係ない。こんな夜中まで電話をかけてこないで」
電話を無視された上に、いままでにない反抗的な態度を取る娘に、母は一線を越えた。
「なにを言っているの? あなたおかしいんじゃないの。そんな言い方、おかしいでしょう。ここまで育ててあげたのに! 親を大事にしないなんて不幸になるわよ。あんたみたいな恩知らず、生まなければよかった‼︎」
聞くに堪えないことば。かおりは反射的に電源を切った。圭一はだまって手をつないでくれていた。家についた。
「もう少し、一緒にいよう」
冷え切ったかおりの手を握りしめ、圭一が言う。かおりは目が泳いだ。部屋に入れてしまったらどうなるかはわかっているけれど……かおりはひとりになるのが怖かった。
「ごめんなさい」と断ることで、圭一が自分から離れていくのではないかとも思った。圭一はかおりの頭をなでた。部屋の中の人気のない底なしの寒さを思うと、自分の存在価値すらもわからなくなりそうだった。だれにも愛されていない。わたしなんか生まれなければよかった。母の呪いがかおりにのしかかる。その闇がおそろしくて、圭一の手の暖かさを振り払うことができなかった。
部屋に入るとキスをした。昨日、雨の中でした優しいキスとは違い、すべてをむさぼるようなキスだった。圭一と目が合うと何も考えられなくなった。
自分の体に圭一が入ってきたとき、やっと満たされたような気持ちになった。ひとりぼっちじゃない。わたしの体が女でよかったと思った。自分の体で圭一が切ない顔をしているのを見ると、自分が圭一の役に立てていることで「生きていていい」と肯定されたような気持ちになった。その刹那、全身を貫いたように体がそりかえった。そして同時に圭一も果てた。
かおりの体から圭一自身が抜ける。そのとき、圭一が生のままでかおりの中で果てたことに気づいた。
作家 松村まつ
東京都内に勤務する会社員。本作がはじめての執筆。趣味は読書と旅行と料理。得意料理はパテ・ド・カンパーニュ。感動した建物はメキシコのトゥラルパンの礼拝堂とイランのナスィーロル・モルク・モスク。好きな町はウィーン。50か国を訪問。