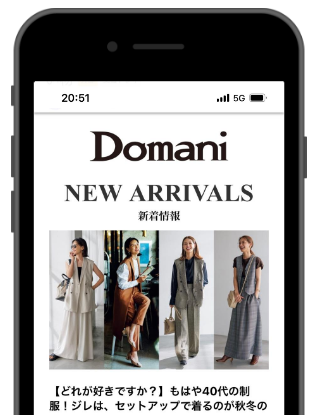〈1〉
▶︎各話一覧
深夜12時を過ぎた。
バレンタインデー特有の華やいだ時間が、日付をまたいでもまだ後をひいている。川口圭一は自宅のリビングで、妻のかおりが会社から持って帰ってきたDEMELのチョコレートボックスをながめた。中身はもうほとんど残っていない。
「これ、食べよう。会社で後輩にもらった」
夜食後にチョコとワインを出してきたのはかおりだった。チリ産の赤ワイン、カッシェロ・デル・ ディアブロは、1000円を少しこえる程度で手ごろだが、チョコレートと相性がよくつい食べ過ぎた。ワインの、カシスやブラックチェリーに似たつややかでさわやかな香りが鼻に抜ける。北京オリンピック2022の開会式のすばらしさや、ドーピングに揺れる15才のフィギアスケート選手ワリエワについてと、話は尽きなかった。しばらくするとアルコールがまわったのか、「眠たくなった」とかおりは寝室のほうへ行った。
結婚して18年。圭一とかおりはうまくやっている。
――「すぐ別れるんじゃないかと思っていた」と学生時代の仲間からは言われていた。
出会ってすぐ結婚をした。まだ24歳。ふたりとも、やっと仕事に慣れたばかりで、結婚は考えたこともなかった。あの時、どうして。圭一はなんども考えたことをまた考えた。思い出すたび、おろしたてのクレリックシャツを思う。ストライプ柄の身ごろに、襟やカフスだけが白いシャツ。よりにもよって、その襟やカフスに墨が飛び散ったような気持ちになる。 あの時、どうして、自分は。
なんど考えても墨に染まってしまったシャツは白くならなかった。
圭一はまだ半分ほど入ったワイングラスを手に、ベランダへ続くガラス戸を開けた。同時に寝室からリビングへかおりが入ってきた。
「まだ起きてた」
「うん」
「外、寒いな」
「うん」
ワインで酔った頭を冷やしたい。圭一は底冷えの寒さを求めてベランダに出た。夕方から降り始めた雪が積もっていた。圭一は低い手すりにあごを乗せ空をながめる。かおりも隣に立った。白い息が重なる。東京の佃にあるこの高層マンションからは夜景がよく見える。真夜中でも、見渡す限りの高層ビル。宝石箱をひっくり返したようにきらめいていた。『幸福な家庭はどれも似たものだが、不幸な家庭はいずれもそれぞれに不幸なものである』と書いたのはトルストイだったか。このひとつひとつの宝石のような光は幸福な家庭だろうか、それとも。
圭一がベランダから転落したのは15分後のことだった。
血とワインが純白の雪を赤黒く染めていった。
作家
松村まつ
東京都内に勤務する会社員。本作がはじめての執筆。趣味は読書と旅行と料理。得意料理はキャロットラペ。感動した建物はメキシコのトゥラルパンの礼拝堂とイランのナスィーロル・モルク・モスク。好きな町はウィーン。50か国を訪問。