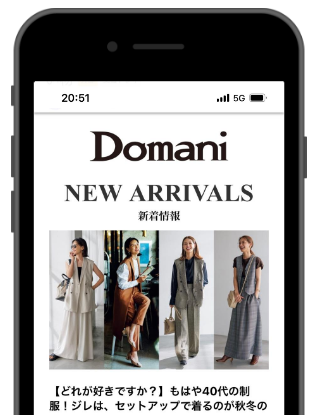〈2〉
「2月14日未明、佃の高層マンションから大手広告代理店勤務の男性(42)が転落」
北京オリンピックの最中ということもあり、川口圭一の転落はすぐに仕事に結び付けて報道された。
「仕事がうまくいかず、東通マン自殺か?」
「東京オリンピックからおろされた東通マン、北京オリンピックが引き金となり自殺」
まだ、事故なのか自殺なのか他殺なのか、なにもわかっていないときに、「東通」という社名が出たことで、圭一は、またたくまにマスコミの餌になった。圭一のいかにも大手広告代理店勤務というような、スマートで遊びなれた見た目が、さらに世間の興味を集めた。
2021年に開催された「東京オリンピック2020」は難題続きだった。部下のことが嫌いでしょうがない上司が、ミクロ単位のほこりを探して突きつけているような執拗さだった。問題が浮上するたびにマスコミやSNSは東京都やオリンピックの運営を引き受ける広告代理店の東通を責めた。そして、コロナウィルスが世界を覆いつくした。
時の首相が「全国民にマスクを配る」と発表する。——どうやら受注企業に東通がからんでいるらしい。「全国民に10万円を給付する」ことになった。——また東通がからんで莫大な金額の中抜きをしているらしい。
裏で糸を引くフィクサーとして、東通は世間にすべてのいらだちと疑惑を押し付けられた。
いらだっていたのは「東通」の方だった。オリンピックの延期が決まるたびに、なん十億という金額を出したスポンサーに、追加のスポンサー料をお願いに行った。
しかも、通常とは異なり、広報活動はほぼ望めないという最悪の状況で、だ。
「スポンサーたちに報えないのに、なんどもなんども金を出せと言わなければいけない」
圭一たち東通マンが、数々の横やりやストレスと戦っているのを、かおりは知っていた。
だけど、かおりは東通という会社が好きではなかった。だから圭一の仕事にはふれなかった。
「いまだけ半額」
「一億総キャンペーン実施中」
クライアントのほうを向き、あまいことばで人をさそいこむ構図がなんとも気にかかっていた。おいしそうなもの、かっこいいもの、おしゃれっぽいもの。
一見すてきな砂糖菓子は甘いだけで体をむしばんでいく。東通にとって大切なのは、クライアントだ。
「なにがリボ払いのリボ太郎かな」
かわいいキャラクターが踊るCMを見るたびに、かおりは高校生の息子・健太に言った。
「健太、リボ払いはぜったいにだめだよ。複利ってのは雪だるま式に増えていくんだから」
かおりの眉間には怒ったオオカミのようなしわが出ていた。
「お母さん、いますごくブスいよ」
健太が笑いながら言うと、かおりも恥ずかしそうな顔をして笑った。
だからかおりは、圭一が東京オリンピックでストレスをためているのを見て見ぬふりをした。
ある日、かおりは夕食の片づけをしていた。圭一は保育園に通う娘、ひなこのパジャマの着替えに手間取っている。ひなこは、圭一とかおりの間にやっとできた2番目の子。長男の健太と年が離れて大人に囲まれているだけに、子ども扱いされるのをいやがるしっかり者だ。
「早く着替えなさい」
「やあーだ」
「着替えよう」
「着替えたくないっ」
「着替えないとだめ」
「もっとYouTube見たあい」
「着替えろっ」
ひなこは圭一の声が大きくなると同時に、泣きべそをかいている。
「早く着替えろっ」
動かないひなこに、圭一は壊れたラジオのように同じ言葉をあびせる。
「ひなちゃん、ぼく着替え持ってきたよ」
見かねた兄の健太が、ひなこのお気に入りのぬいぐるみ、白うさぎメリーにパジャマを持たせる。うそ泣きをしていたひなこは泣き止み、メリーのほうを向いた。
「メリー、持ってきてくれたの?」
「うん」
「ありがと、メリー」
「もしかして……ひなちゃんひとりで着れるのかな」
健太が裏声で話しかけながら、メリーの右耳でひなこの髪をなでた。
「着れるよ! わたし、お姉さんだから」
「すごおいねぇ~」
「メリー、見ててね!!」
ものの1分でひなこはみずから着替えた。
「メリー、わたしと歯磨きしよう。磨いてあげるね」
自慢気な顔でメリーを見つめ、抱きしめて歯磨きをしに洗面所へむかった。
圭一は途中から自分は関係ないといわんばかりに、スマホを見ていた。健太はかおりのほうを向いて、苦笑いした。かおりはため息をついて、皿を置き、洗面所へむかった。
「オリンピックは延期、延期で、圭一くんも大変だねっ」
ひなこが眠った後、かおりはビールを渡しながら冗談めかして言った。圭一の顔がさっとくもった。
「……どうしたの」
圭一はどろんとした沼のような目をしている。
「東京オリンピックは外れた」
「なんで」
「ちょうど配置換えの時期だから」
「そう」
「うん」
こういう時、圭一は決して弱みを見せない。かおりはそれがわかっているので黙っていた。きっと、結果が出せなかったから変えられたのだろう。ひなこのきげんすらとれない圭一が、あの手この手でクライアントをその気にさせる広告代理店の仕事に合っているとは思えなかった。「結果を出し続ける強いおれ」でありたいのはわかるけれど、もう少し圭一らしいところが生かせる仕事につけるといいのに。おしゃれなところとか、新しもの好きだとか。
「東通はずいぶんときらわれた」
ぼそりと圭一がテレビを見ながら言っていたのを、息子の健太は聞いていた。嫌われているのは東通だけじゃないよ。健太は父の圭一を見ながら思った。
見栄っ張りでそとづらばかりいい男。
「健太のパパってかっこいい」
「そうかな」
「おしゃれだよね」
「ううん、そうかもね」
「東通マンってあこがれる」
「そんないいもんでもないよ」
高校の友達が父をほめるたびに、健太は鈍い反応をした。皮肉めいた作り笑いの裏側で、特別扱いされたくすぐったさと、腐った水を飲まされたような嫌悪感と、両極端な気持ちを味わっていた。
父の圭一が見た目を大事にすればするほど、健太はそとづらに気を遣わないようにした。おれはあいつとは違う。あいつみたいに自分のことばかり考えているやつとは違う。なにが「天下の東通マン」だよ。このマンションだって母さんが買ったのに。偉そうにしても、ブラックリストにのっていてローンが組めなかったこと、おれは忘れないからな。
作家
松村まつ
東京都内に勤務する会社員。本作がはじめての執筆。趣味は読書と旅行と料理。得意料理はキャロットラペ。感動した建物はメキシコのトゥラルパンの礼拝堂とイランのナスィーロル・モルク・モスク。好きな町はウィーン。50か国を訪問。