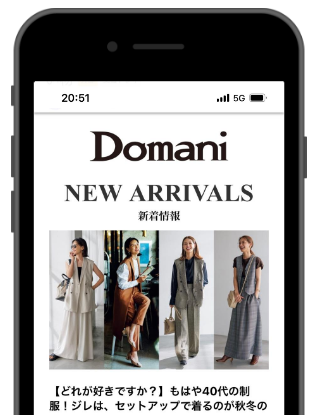〈5〉
【登場人物】
川口圭一 (42) 自宅の佃にあるマンションから転落。大手広告代理店・東通勤務。
川口かおり(42) 圭一の妻。大手出版社・祥明社の美容雑誌『JOLIE』美人編集長。
川口健太 (17) 圭一とかおりの長男。私立光星高校在学中。
川口ひなこ (6) 圭一とかおりの長女。保育園在園中。
妹尾サキ(42) 高文館『週刊女性ファイブ』副編集長。圭一とかおりのスキャンダルを取材中。
<これまでのあらすじ>
2022年2月14日、東京・佃。銀座にほど近い高級マンションから一人の男が転落した。男の身元は大手広告代理店勤務42才の川口圭一。転落したマンションは、川口が家族4人で住んでいた。他殺か、自殺か、事故か。はじめは事故による転落と思われていた事件は、人々の証言により二転三転し、セレブ夫婦の暮らしと愛憎が明らかになっていく―――。
いま、わたしの夫がベランダから落ちた。
雪の上に落ちた。
川口かおりは雪の降る中、ベランダでぼうぜんとしていた。
となりに立つ息子の健太も同じだった。こういう時なにをするのだろう。あそこまでどうすれば行けるのだろうか。わたしも飛び降りるとか。それとも部屋を飛び出して助けに行くのだろうか。ああ、110番に電話をするのか。いや117番かな。117番は時報じゃないか……。
――18年前、2004年。
前年の日経平均は瞬間的に7607円を記録し、恐ろしいほどの低調相場だった。底を打ってから少しずつ上昇し、2004年、初売り5日の終値は1万825円をつけた。初売りだからと言ってご祝儀相場というほどでもなく、静かに一年の幕が開けた。
1月9日金曜の20時。24歳の小林かおりは新入社員で配属をされたティーン誌『プチファスト』編集部にいた。まだまだ新年気分で、まわりは早めに帰ってしまい、編集部は静かだ。手持ちのページは年末進行で去年の年末までにあらかた仕上げていた。急ぐ仕事はなく、のんびりした気持ちで一日が過ぎた。
かおりは、アンケートはがきを読みながら、過去の『プチファスト』や競合誌に目を通す。
「まだ仕事してるの?」
呼びかけられた声に、かおりは顔を上げる。と、同期の大宮ちかが立っていた。きのこのようなボブカットがよく似合う。あまり高くない身長に、好奇心の塊のような目が印象的だ。文芸誌『トロイカ』で先輩と一緒に大御所作家を担当している。
「ちかこそ。作家さんの原稿まだあがってないの」
「あがってないね。でも、今日はこれから大学時代の仲間と新年会なんだ。かおりも行く?」
「そうだね……」
手元の企画書に目を落としたかおりは笑い出した。
「どうしたの」
「わたしは『プチファスト』の読者だった。この手に持ってる昔の『プチファスト』を、買って読んだことあるの。だから。それなのに。自分がここにいて、企画を書いてるのがおかしくなったんだ。なんだかうそみたい」
「地元は長野だっけ」
「そう。山奥だから寒いとこ」
「長野の山奥は寒そうだねえ」
「雑誌の服の組み合わせって、寒さを防げない格好ばっかり。こんな足元ではしもやけになっちゃう。長野で雑誌読んでた時はピンとこなかったけど、東京はぜんぜん寒くないもんね」
かおりは愛おしそうに資料雑誌のページをめくる。
「寒いよ。わたしは和歌山だから東京の冬は寒くて家から出たくない」
「それなのに新年会には行くの」
「もう東京に染まっちゃったの! さあかおりも行こう。企画は土日に一緒に考えてあげるよ」
かおりは、どうしようか迷っている。「ぐう~」とかおりの腹の虫がないた。かおりとちかは大笑いした。
祐天寺駅すぐそばのカフェバーには20人ほどはいただろうか。
「おお、おつかれ」
「もう始まってるよ」
大宮ちかと小林かおりは、みんなが空けてくれた場所に座った。
「とりあえずビールふたつください」
薄暗くて小さな店内は貸し切りのようで、ちかはあちらこちらに手を振っている。
小林かおりは失礼にならない程度の笑顔を保ちながら大宮ちかにくっついていた。
ビールが運ばれてくるとだれかが声をあげた。
「ちか、おつかれ!」
「おつかれ」
「ひさしぶり」
「おつかれさま」
次々とグラスが近づいてきて、ちかとかおりのグラスに当たっていく。
乾杯が終わると、ちかはメニューを引き寄せ、自分の食べたいものを次々と注文していった。
「カマンベールチーズのフライに、しらすのシャキシャキサラダ、ささみ梅ナッツ和えと……おむすび3種盛り。かおりなんかほしいのある?」
「燻玉ポテサラ、トリュフ塩枝豆、いいかな」
「おいしそう」
大宮ちかが注文し終わると、隣の席の人を紹介してくれた。
「かおり、この彼は毎朝新聞に勤めてて…そのとなりは…」
「遠藤です。僕、橋を作ってます」
「遠藤くんはおれが連れてきたの。はじめまして、建築雑誌の編集をしています」
新聞社、出版社、ゲーム会社、音楽会社、建築家にラジオ局、広告代理店……次から次へと華やかな会社名が出てくる。かおりはめんくらっていた。たった10年前は長野の中学生だったのに、こんなところにいることが現実ではないような気がした。
「それでこっちはサキ。サキって苗字なんだっけ?」
「ひどいなあ。せ・の・お! 妹尾サキです。高文館の『週刊女性ファイブ』にいます」
「このまえの政治家×アナウンサー不倫スクープと、俳優さんの不倫スクープも、サキだよね」
「うん。同じ広尾のマンションで不倫がふたつも撮れてしまった」
「スキャンダルにめっぽう強い、すっぽんサキ」
「狂犬サキとも呼ばれている。でもほんとうは小説やりたかった。ちかがうらやましい」
「わたしは美術系やりたかったから、建築雑誌行きたかった」
「おれは建築雑誌やりたかったから、夢がかなった。毎日楽しい」
ぴかぴかのまぶしい笑顔につられてみんなが笑った。
そこに店員さんがやってきた。
「しらすのシャキシャキサラダとささみ梅ナッツ和えです。こちらのお皿おさげしてよろしいですか」
「あ、お願いします」
橋を作っていると言った遠藤が使った皿やグラスをまとめる。
それを手伝いながらとなりの男がかおりのほうを向いた。
「いっぺんに覚えられないと思うから、まあゆっくり。この会はね朝まで続くから」
「その通りだ。もう一度かんぱい!」
大宮ちかのグラスが高らかにかかげられた。
もうすぐ夜中の12時になりそうだ。
終電も近づいているが、だれひとり帰らない。逆に、次から次へと人が増えていた。
かおりは橋を作っているという遠藤と話しこんでいた。
「道路は設計次第で、車のスピードをおさえられる」
「どうやって?」
「下に敷いたオレンジの線の間隔でスピードが出てると錯覚させたり……」
その時、ドアが開き、二人の男が入ってきた。
一人は品よくカジュアルダウンしたいでたちに、鍛えあげられた、すらりとした体つき。低めに見積もっても180センチは超えている。なにかスポーツをやっていたのだろう、肩幅が広い。通った鼻筋に、涼しげでいて、やさしそうな切れ長の目元が印象的だった。急いで来たのか、柔らかくカーブした前髪がひたいに一筋かかっていた。
もう一人も同じような背格好で、おしゃれな二人組だった。
大宮ちかがかおりを呼びよせた。
「かおり、かれは川口くん。遅かったね。彼女はわたしの同期の小林かおり」
「はじめまして、川口圭一です。コピーライターをしています」
向かいに座っていただれかが言う。
「川口は悪名高い大手広告代理店、東通だよ。かおりちゃん、ぜったい相手にしちゃだめだよ」
「ひどい言われようだな」
川口圭一の目元に笑いジワが浮かぶ。
「圭一はこの前、宣伝会議のシルバー賞取って勘違いしてるから」
「勘違いじゃないよ実力」
「でたでたでた」
「いつも自信満々だな」
いままでばらばらに話をしていた人たちが圭一を中心に集まる。
かおりは無表情で聞いていた。横文字の職種も、柔らかそうなクシャっとした茶髪も、おしゃれな外見も、深夜に参加してくるところも、かおりの危険アラームをたっぷりかき鳴らした。なんてうわついた人。いかにも東京だ。見た目はいいけど、こういう人はだめだ。だめだだめだ……。そう言いながらも、つい目で追ってしまっていた。
圭一たちが来てすぐ店は閉店時間になり、2軒目に移動した。かおりはなんとなく、帰るタイミングを逃してしまった。無理をして走れば終電には乗れた。黙って帰れば抜けられなくはなかった。でも。もう少し、ここにいたいと感じていた。
「次行ってみよう!」
千鳥足の大宮ちかが先導して2軒目へ行った。思い思いにビールや水割りを頼む中、圭一だけがチャーハンを頼んだ。小さな声で「お腹が減った」と言った。かおりは離れたところに座っていたが、なぜかその声が聞こえた。
全員で乾杯をしたあと、チャーハンが届いた。
圭一は大量のチャーハンをスプーンですくった。口に入りきらず少しこぼした。
その瞬間、かおりは圭一をもっと知りたいと思った。夜中の1時だった。
チャーハンをこぼした。きっとちょっと間が抜けた人だ。ちっとも計算高くないから大丈夫。男友達と二人で来たのもいい。東通にだって誠実な人はいるはずだ。いろんな言い訳を並べ立てた。
だけど、本当ははじめて見た時から気になっていた。ただ圭一にひかれても許される理由が欲しかった。食べていたのがチャーハンでもカレーでも餃子でも。こぼしてもこぼさなくても。
かおりは、圭一が来た時からそっと圭一のことを見てしまっていた。川口圭一は生き別れた父親に少し似ていた。2歳で親が離婚して生き別れたお父さん。そのあとすぐに亡くなってしまったから、写真でしか見たことがないのだけれど。写真の父と、圭一の優しそうな目元が似ている。
そんなことを考えていたら、なぜかみんなの目線がかおりに集まっていた。
作家 松村まつ
東京都内に勤務する会社員。本作がはじめての執筆。趣味は読書と旅行と料理。得意料理はキャロットラペ。感動した建物はメキシコのトゥラルパンの礼拝堂とイランのナスィーロル・モルク・モスク。好きな町はウィーン。50か国を訪問。