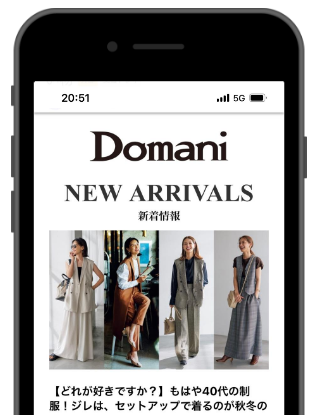〈11〉
【登場人物】
川口圭一 (24) 大手広告代理店・東通勤務。コピーライター。
小林かおり(24) 大手出版社・祥明社のティーンズ誌『プチファスト』編集者。長野出身。
小林きみ子 かおりの母。長野で小学校教師をしていてひどく厳しい。シングルマザーでかおりを育てた。
遠藤敦士(26) 橋の建築家。かおりに気がありそう。
大宮ちか(24) 祥明社の文芸誌『トロイカ』編集者。かおりの同期。
妹尾サキ(24) 高文館のスクープ誌『週刊女性ファイブ』編集者。あだ名はすっぽんサキ。
<これまでのあらすじ>
2022年2月14日、東京・佃。銀座にほど近い高級マンションから一人の男が転落した。男の身元は大手広告代理店勤務42才の川口圭一。転落したマンションは、川口が家族4人で住んでいた。他殺か、自殺か、事故か。話は18年前の2004年1月。圭一と妻のかおりの出会いへさかのぼる。
『サキと合流したよ。お店決まったらメールする』
同期の大宮ちかから小林かおりにメールが来たのは17時過ぎだった。
ちょうど、雑誌の企画を20本書き終えたかおりは会社のPCを閉じた。
「『い、ま、い、く、ね』……っと」
ちかへメールを打ちながら、コートを手に持つ。袖に腕を通そうとしたとき、昨日、かおりの肩にコートをかけてくれた遠藤の穏やかな物腰を思い出した。同時に、遠藤へ、メールの返信を忘れていたことも思い出した。PCを開きなおすと時間がかかってしまう。ちかに「いま行く」と言った手前、返信は週明けにすることにした。
かおりは、借りていた雑誌を社内の資料室へ戻しに行く。他社のものも含めた雑誌を見入ってしまう。
「冬のリッチカラーニット100」「5分おうち鍋ごはんランキング」「ベストコスメ2003!」。どの企画もキラキラしていて胸が弾んだ。恋やお金や見た目や仕事や友達や、たくさんの悩みが載っていて、「みんな同じなんだ」と安心する。
星座占いに目がとまった。8月28日、おとめ座のかおり。「今月のラッキーアイテムは傘」。
こんなに晴れているのに『傘』。もうすこし冬にありがちな『みかん』や『アーガイル柄セーター』のほうがいいかもしれない。
「でも、まあ、占いは気持ちの問題だもんね」
ひとりごとを言いながら携帯を開く。ちかからまた、メールが来ていた。
『近くではごはんが食べられるお店がないから、神楽坂に移動したよ』
ほかに、母からメールがないか確認したが、なにも来ていなかった。かおりは携帯を閉じた。
大宮ちかと妹尾サキは、すでに「神楽坂おでんや」で日本酒をあおっていた。
「でさ、むかつくのがさ、わたし・妹尾サキが出した企画なのに、気づいたらほかの人がやってるの」
「それはなんで」
「『お前じゃ、まだ力不足だ』とかなんとか。でも、その企画、たいしたことないやつに任せるの。気のせいかと思ったけど、二度も三度も続くとさすがに気づく。わたしの出した企画だよ!? そんで、編集長は、そいつらとかお気に入りメンバーで徒党組んで飲みに行ってさ」
「そんなこと…ありうるね。ありうる」
「ちかもある?」
「なんか企画、通らないんだよね。同じような企画を別の人が出すとするっと通ったり。それから、女の担当なんかいやだとか、逆に女の担当がいいとか」
「女の担当がいいだと?」
「おじさん作家でね、そういう人いる。『女』ご所望だから、わたしみたいなきのこ頭が来たらあからさまにがっかりするよ」
「ああ、いる。そういう人って、昨日のあんたの同期みたいな人が来たらどんどん原稿書くでしょう?」
「かおりのこと?」
「そうそう、妙に不幸くさい人」
「ちょっと。ひどい言い方だよ」
「あの感じは男好きするんだよ。守りたくなるというか。いつもひいきされてるのに、『自分の実力です』って顔してんの! 川口とか男たちが全体的に色めき立ってた。わたしはわかっている」
「川口とか……鋭い。さすがスクープ量産型サキ」
「とにかくああ言う女は気に食わん」
「あの。ねえ。……今日、呼んでしまった。仲良くしてよ」
「ええっ。ちょっと! 帰ろうかな」
「まあまあ、そう言わず」
ちかはサキのおちょこに日本酒をなみなみとつぐ。サキは一気にあおった。
かおりは、会社を出て、ちかが指定した「おでんや神楽坂」に向かう。
飯田橋の駅から神楽坂を登り、「神楽坂五十番総本店」を過ぎる。ガラスのドア越しに、なんの気なく店内をのぞいてしまう。店頭のケース内に山盛りに置かれた肉まん、あんまん、五目まん…帰りに母へ、お土産として買って帰ろう。母は、怒りが長続きしない。厳しくかおりを叱責しても、そのあとすごく優しくなる。きっと、今日も機嫌は直っているだろう。ちかとのご飯には、ちょっとだけ顔を出して、早く帰ろうと思った。
ビルの左側にある階段を上り、店に入る。奥の席に大宮ちかと妹尾サキが向かい合って座っていた。
おでんやあんきもなど、すでに料理が運ばれている。ふたりはずいぶんと日本酒を飲んでいた。すっかりできあがっているのか、どちらも軽く、前傾姿勢になっている。
「遅くなりました。あ、日本酒、飲みたい」
ちかの隣に座り、かおりが言うと、すぐにちかがお店の人に声をかけた。
「すみませえん。おちょこひとつくださあい」
そしてかおりのほうへ向くと、サキを紹介した。
「かおりい、サキは、昨日の祐天寺・新年会にもいたけど、ほとんど話してないよねえ?」
「うん、でも覚えてるよ。すっぽんサキさん」
「そう、わたしはね、喰いついたら離さないよっ」
酔っているのか、すっぽんサキの目が座っている。
「『女性ファイブ』ですよね?」
「不倫とか有名人のスキャンダルが大好きな下世話な雑誌ですよお」
「サキはうそつく人とか大嫌いだもんねえ。天職だよ」
「うん。許せないね。すっぱ抜くと気持ちいい。わたしがすっぱ抜いたネタで、芸能人とかが泣いてる会見なんて見ると、すかっとする。ざまあみろだよお」
「……」
「人間なんて、金と愛と名誉が欲しくてしょうがない生き物でしょお。芸能人も政治家も犯罪者も、普通の人も一皮むけば、おおんなじ! 目立ちたいし、いい思いしたいし、ちやほやされたいしい。あたしだってちやほやされたいい」
「ちやほや、いいねえ」
ちかはサキの話に合いの手を入れる。
「ねえ、ちかはさあ、ひとつだけ。ひとつだけ、選ぶならどれがいい?」
サキがちかに問う。
「金とお、愛とお、……名誉…だっけ?」
「そお」
「いまは、名誉。新人作家見つけてえ、100万部売りたいっ。サキは?」
「名誉だよ。ひとつだけえ、だもん。『女性ファイブ』、車内吊り広告の右はじと左はじのスクープを取ってやりたい。わたしの企画で記事作ってるあいつらめえ。妹尾サキを見てろよお」
ふたりは、どんどん日本酒をあおる。それと比例してふたりとも、ふりこのようにぐらぐらしている。
「たしかに車内吊りのスクープ記事って右と左に載ってるねえ。かおりはさ、なあに」
ちかに聞かれてかおりは、言うか言うまいか逡巡した。しかし、酔っているふたりの様子がかおりの背中を押した。この様子なら、きっと明日はあまり覚えていないだろう。
「わたしは……全部ほしい。編集長にもなりたいし、お金もほしいし、結婚してこどももほしい。わたしなんかにできるかどうか、分からないけど……」
――そして母に自分を認めてほしい。いちばんの本音はぐっと飲み込んだ。ちかとサキには言えなかった。母に愛されていない自分がみじめで、あまりに幼い願望で、言うのがはばかられた。母に「私の娘だから当たり前」ではなく、「かおり」自身の努力を認めてほしい。かおりの脳裏には昨日の母の冷たい様子が浮かんでいた。
それを聞いたすっぽんサキは表情を変えた。
「あのさあ、ひとつだけって言ったでしょお。あんたみたいな女、だいきらい。あれもこれもそれも。『わたしなんか』って言ってさあ。自信あるの? ないの? なんなの? 今までだって十分いろいろ手に入れてきたでしょお。全部入りはラーメンだけで十分だよ!」
「ま……まあまあ」
ちかがサキを落ち着かせようとするが、振り切ってサキは続けた。
「あのさあ、1日は24時間しかないのに、そんなにたくさん手に入ると思うのお」
変に突っかかってくるサキにむっとして、かおりは言った。
「手に入るか入らないかじゃなくて、『手に入れる』と決めるかどうかでしょう」
「女がそんなことできるわけない。実際に女でえ、家庭円満でえ、編集長やってて、こどももいる人なんているう? いないでしょう? だいたいは、仕事に人生ささげて結婚しなかったり、子供の熱が出ただの、PTAだので抜け出してえ、使い物にならない厄介者扱いで一線から飛ばされたりさあ。仕事しすぎて浮気されたり。それで結局、離婚するにきまってる。にしたって、編集長はいつも男ばかりだし。無理に決まってる」
かおりは鼻で笑った。
「昨日ダメだったから、明日もダメなんて。ずいぶんと視野が狭……」
かおりが言い終わる前に、サキは手に持っていたおちょこの日本酒をかおりにかけた。その日本酒は的を外し、ちかにかかった。
「ちょっとお!!! サキもかおりも言いすぎ」
幸い、おちょこだったので、かかった日本酒の量は少しだった。ちかは、おしぼりできのこ頭をふく。奥の席だったこともあり、店の人にもめごとは気づかれていない。かおりは、すくっと立ち上がり、サキに向かって言いはなった。
「わたしは自分の人生で証明して見せる。全部手に入れたはじめての編集長になって見せる」
ちかにたたきつけるように一万円を渡し、かおりは席を立った。
「ちか、昨日から途中退席でごめん。もう帰るね」
「全部入りはラーメンだけで十分なんだよ! 帰れ帰れ!」
サキはわずらわしい虫を追い払うように手を振った。
「もうちょっと……」
かおりの腕を引くちかを押しとどめ、かおりは出口へ向かった。柱を曲がったところに、川口圭一が腕を組み、壁にもたれていた。突然の登場にひるんだかおりは固まった。圭一は頭をかたむけ、いたずらっぽい顔で、目だけ動かしてかおりを見たあと、まっすぐ前に視線を戻した。真一文字に口を結ぶとほほのえくぼが目立つ。
「大宮ちかに呼ばれてきたんだけど、入るタイミングがわからなくて」
「……」
「帰るの?」
「帰ります」
圭一はうなずき、先を歩き階段を下りた。
外はいつのまにか雨が降っていた。圭一はかおりのほうを向いて聞いた。
「傘、持ってる?」
首を振るかおりに、圭一はバックから自分の傘を出し、かおりにさしかけた。
「持ってって」
「家は近くだから、傘はなくても大丈夫です」
「おれが貸したいの。でも必ず返して」
「……」
その時、肉まんの五十番が目に入った。手土産を買って帰ろうと思ったのに、ちかに渡した一万円でほとんどすっからかんなことに気がついた。いまは時間外で、お金をおろすと手数料がかかる。でも。母に、仲直りの肉まんを買って帰りたかった。
かおりの視線に気がついた圭一は五十番のドアを開けようとした。
「あの」
かおりはその手を押さえた。
「たぶん……現金がないとおもうから大丈夫」
圭一はかおりの手をやわらかに外し、ドアを開けた。
「昨日のタクシー代、返すよ」
圭一はかおりにどれを買うのかうながし、お金を払って袋を受け取った。
「ありがとうございます」
「うん」
店を出ても、圭一は肉まんを渡そうとはしない。そして、傘をさした。
「送っていくよ。おいで」
圭一は指を右左確認するようにゆらして、どちらに向かうのかかおりに問いかけた。かおりは苦笑いをした。
「やっぱり、強引」
「よく言われる。でも肉まんは、家まで渡さないよ」
それを聞いてため息をつき、目を細めたかおりを、圭一は傘に引き入れた。
―――今月のおとめ座、ラッキーアイテムは傘。
作家 松村まつ
東京都内に勤務する会社員。本作がはじめての執筆。趣味は読書と旅行と料理。得意料理はパテ・ド・カンパーニュ。感動した建物はメキシコのトゥラルパンの礼拝堂とイランのナスィーロル・モルク・モスク。好きな町はウィーン。50か国を訪問。