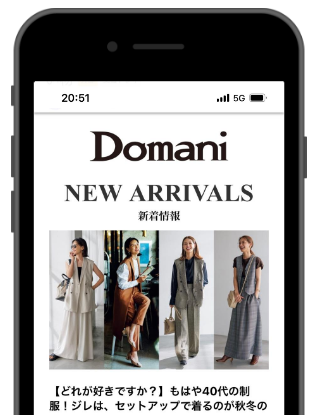「ビッグロックの法則」という有名なたとえ話があります。つぼに、まず大きな岩を入れられるだけ入れます。次に石を入れられるだけ入れます。そして砂利を入れられるだけ入れます。さらに砂を入れられるだけ入れます。最後に水を入れられるだけ入れます。つぼが満杯になりました。
次にそれらを一度ぜんぶ外に出し、さきほどとは逆の順番でつぼに戻していきます。水を入れます。砂を入れます。砂利を入れます。石を入れます。岩を入れます。どうなるでしょう? 岩はつぼに収まりません。ものごとには順番があるというシンプルな教訓が得られます。
子どもの成長も同じです。どんなに世の中の変化が激しくても、子どもの成長・発達のペースは変わりません。生後3カ月の赤ちゃんがいきなり漢字を読んだり、1歳の子どもがいきなり九九を覚えたりはしません。これからの時代は英語やプログラミングも必要だからといくら大人が焦ったって、ほかの成長や発達を差し置いて、それらを先に子どもの頭にインストールすることなどできないのです。そんなことをしたら、なにか大事なものが、あとから入らなくなってしまいます。
子育ての最優先は自己肯定感と非認知能力
時代は変わっても人間が幼い頃に学ばなければいけないことの優先順位はそれほど変わらないのに、それを忘れて子どもに未来の知識やスキルを先取り的にあれもこれも教え込もうとすることは非合理的だということです。ではなにが優先か。私が監修した『究極の子育て 自己肯定感×非認知能力』でも詳しく解説していますが、多くの専門家が口をそろえるのが、「自己肯定感」と「非認知能力」の大切さです。それぞれを家庭で育む方法を専門家に聞きました。
自己肯定感が高い人間というのは、無条件に自分を認めている人間を指します。「僕は○○ができるからすごいんだ」と思っているわけではありません。「自分は自分なんだから、自分のままでいい」と思っているわけです。となると、そのベースにあるのは、いわば「根拠のない自信」といえるでしょう。

一方、一見、自信があるように見えてじつは自己肯定感が低い人間はどうかというと、「僕は○○ができるからすごいんだ」と思っている。つまり、そのベースにあるのは、自己肯定感が高い人間とは対照的に「根拠のある自信」となります。「自己肯定感」と「自信」は似て非なるものなのです。
東京都市大学人間科学部教授の井戸ゆかりさんは、「自己肯定感が高い子どもは、自分に自信がもてるのでどんなことにも積極的に取り組むことができます。それから、自分のいいところも悪いところも含めて『いまの自分でいいんだ』という思いがあるので、気持ちにゆとりがあり、情緒が安定して他人にも優しくできます」といいます。
空気を読もうとするあまりに自分がわからなくなる
自己肯定感を育む方法として、井戸さんは、日常的に「ありがとう」「頑張ったね」と声をかけることを推奨します。また、結果ではなく頑張りのプロセスを見てその子のいい部分に気づかせてあげることで「お母さん、お父さんがちゃんと見ていてくれた」と感じさせてあげることも大事だと訴えます。

一方で、明治大学文学部教授の諸富祥彦さんは、「いい子症候群」に警鐘を鳴らします。「いい子症候群」とは、自分を抑えて周囲の人の期待に過剰に応えようとする、いま風にいえば、空気を読もうとするあまりに、自分というものがわからなくなっている子どものことです。
いい子症候群の子どもがそのまま大人になるといわゆる「アダルトチルドレン」になってしまいます。アダルトチルドレンとは、子どもの頃に自分らしくさせてもらえない体験を重ねることで、大人になってからも、生きづらさを抱えてしまう大人のことです。
親の価値観にそうことをしたときにだけ「えらいね」「いい子だね」とほめていると、子どもは無意識のうちに親の期待に過剰に応えようとする心の癖を身に付けてしまうので要注意です。
AIの時代には、ペーパーテストで測れる偏差値的な学力よりも、「非認知能力」が子どもたちの人生を左右するようになるといわれています。非認知能力とは、テストなどで簡単には測ることのできない能力の総称です。主体性、自己抑制力、思いやり、コミュニケーション能力など多岐にわたります。
玉川大学教育学部教授の大豆生田啓友さんは、「本来、非認知能力とはなにか特別なものなどではなく、昔であれば子どもの普段の遊びや当たり前の子育てのなかで勝手に育っていたものです」としたうえで、親として意識すべきことは「大人からしっかりと受け止められる経験を子どもにさせること、そして、子どもの興味関心を大人が大切にすること」だと訴えます。
未熟な部分をぶつけ合うことが大切な学び
法政大学文学部心理学科教授の渡辺弥生さんも、遊びの大切さを強調します。「例えば、少しはけんかもしないと本当の意味で友だちと仲良くなることはできません。何気なくいったことでも『ここまでいうと相手を傷つけちゃうんだ』とか、よかれと思っていったことでも『ここまでいうとおせっかいになっちゃうんだ』というふうに失敗して学ぶのが人間であり、未熟な部分をぶつけ合うことが子どもにとっては大切な学び」というのです。

わが子の非認知能力を高めたいと思う親に対して、白梅学園大学子ども学部教授の増田修治さんは、「身構えるような必要はありません。大事なのは、『子どもの話をきちんと聞く』ことです」とアドバイスするとともに、「教育に熱心な親ほど、子どものいうことに耳を貸さず、『これが子どものためになるんだ』と勉強や習い事を押しつける傾向にあります。それでは、まったくの逆効果」と警告します。
「非認知能力が鍛えられる」とうたう教育プログラムをむりやり受けさせるよりも、子どもが純粋な興味関心をもって始める遊びを尊重して、親も一緒になって面白がってあげることのほうがよほど大事だということになります。
以上の専門家の意見を煎じ詰めれば、自己肯定感を育むうえでも非認知能力を伸ばすための大原則は、親が先回りして子どもにあれやこれやを与えることよりも、子どもをできるだけ自由に遊ばせて、その様子をつねによく見て子どもが発する興味関心のサインを見逃さないことだと言えます。
アイコンタクトを返すだけでもいい
幼児であれ思春期の子どもであれ、「いま、僕頑張ったよ。見てた?」とか「やった! わたし、すごいでしょ?」という意味で、親をチラッと見ることがありますよね。それがサインです。そのときに「うん、見てたよ」「すごいじゃん!」とアイコンタクトを返すだけでもいいのです。

それだけで子どもは勇気づけられ、励まされます。「お父さん、お母さんはちゃんと自分のことを見ていてくれる」と安心します。
逆に、スマホをのぞき込んで他人のSNSに「いいね!」なんてしていたがために、子どもがせっかく発したサインを見逃すようなことが連続すると、子どもはだんだんとやる気を失っていきます。「どうせ……」が口癖になっていくのです。
親が子どものためにあれこれ手を出したり口を出したりするのは最低限にとどめるべきだと、わたし自身は思っています。でも、子どもに背を向けてなにもしないほうがいいといっているわけではありません。子どものありのままの姿、振る舞いを近くで見守り、子どもが「いま、見てた?」とこちらを見たときにはできるだけそれに気づいてあげて、目の動きひとつでいいので「見てたよ!」というサインを送り返してあげてほしいのです。
それさえできれば、余計な心配などしなくても、子どもは勝手にぐんぐん伸びていくはずです。それが、さまざまな専門家の話を聞き、さまざまな教育の現場を見てきたわたしの、現時点での結論です。

『究極の子育て 自己肯定感×非認知能力』(プレジデント社)
育児・教育ジャーナリスト
おおたとしまさ
「子どもが“パパ〜!”っていつでも抱きついてくれる期間なんてほんの数年。今、子どもと一緒にいられなかったら一生後悔する」と株式会社リクルートを脱サラ。育児・教育をテーマに執筆・講演活動を行う。著書は『名門校とは何か?』『ルポ 塾歴社会』など60冊以上。著書一覧はこちら。
東洋経済オンライン
東洋経済オンラインは、独自に取材した経済関連ニュースを中心とした情報配信プラットフォームです。
写真/Shutterstock.com