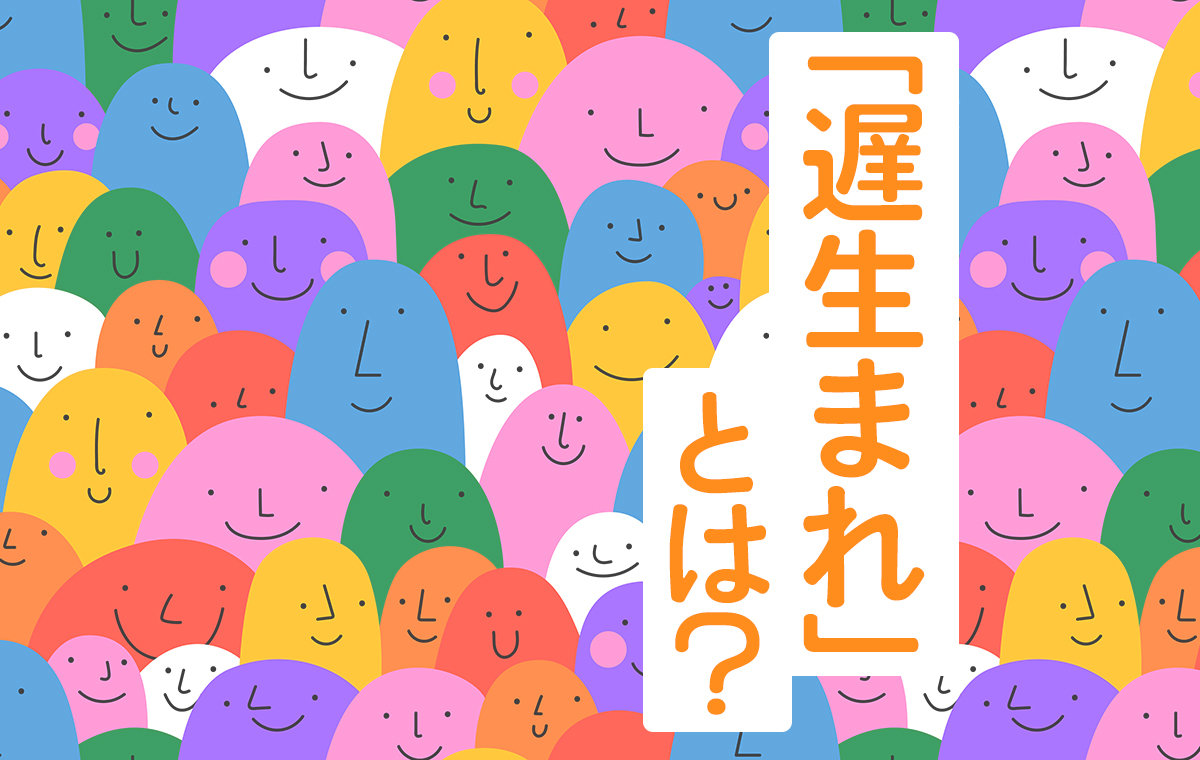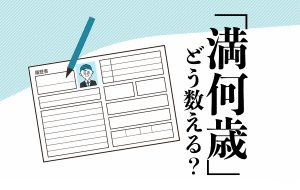遅生まれとは?「遅い」と表現する理由もご紹介
「遅生まれ」とは、4月2日~12月31日に生まれることです。同じ年の1月1日~4月1日に生まれた「早生まれ」よりも1年遅く就学するため、「遅い」と表現します。

(c)AdobeStock
おそ‐うまれ【遅生(ま)れ】
4月2日から12月31日までに生まれたこと。また、その人。同じ年の早生まれの子どもより1年遅く就学するところからいう。はや‐うまれ【早生(ま)れ】
1月1日から4月1日までの間に生まれたこと。また、その人。4月2日から12月31日までに生まれた人が数え年8歳で就学するのに対して、数え年7歳で就学するところからいう。
(引用〈小学館 デジタル大辞泉〉より)
遅生まれと早生まれの学年の違い
たとえば、2020年に生まれた子どもの場合、遅生まれは2027年に小学校に入学しますが、早生まれは2026年に入学します。
中学校・高校・大学においても、留年や浪人、出席日数不足による遅れなどがなければ、常に遅生まれの子どもは早生まれの子どもよりも1年遅く入学することになります。
遅生まれと早生まれの数え年の違い
数え年(かぞえどし)とは、生まれた瞬間を1歳とし、以後、1月1日を迎えるたびに1歳ずつ増える数え方のことです。たとえば、2020年4月1日生まれの場合、2021年1月1日に2歳、2027年1月1日に8歳になります。
遅生まれの子どもは数えで8歳のときに小学校に入学、早生まれの子どもは数えで7歳のときに入学します。なお、七五三や年祝いはかつては数え年で行われていましたが、現在では満年齢で行うこともあるようです。
4月1日と2日で分かれる理由
学校教育法では、「子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから」小学校に通うこと、「小学校の学年は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる」ことが定められています。つまり、4月1日時点で6歳になっている子どもが小学校に入学します。
そもそも満年齢は、誕生日の前日が終了するときに年齢が1歳増えるという考え方です。誕生日が4月1日の人なら、3月31日が終わる瞬間(まだ4月1日になっていないとき)に1歳、年をとります。
そのため、小学校が始まる4月1日に満6歳に達するのは、6年前の1月1日~4月1日に生まれた子ども(早生まれ)と、7年前の4月2日~12月31日に生まれた子ども(遅生まれ)となります。このような事情から、4月1日までが早生まれ、4月2日以降が遅生まれとなって区別されるようになりました。

(c)AdobeStock
遅生まれのメリット
遅生まれには、次のようなメリットがあります。それぞれのメリットについて見ていきましょう。
幼少期は体格的・学力的に有利になることがある
遅生まれは早生まれと比べると、幼稚園や小学校に上がるのが約1年遅くなります。幼少期において1年の違いは大きいものです。体格や学力においても、大きな差がつくと考えられます。
たとえば、6歳男児の平均身長は116.5cmですが、7歳男児の平均身長は122.5cmです。遅生まれの子どもはすぐに7歳になる状態で小学校に入学しますが、早生まれの子どもは6歳になったばかりのタイミングで入学するため、約6cmも身体が小さいと考えられます。
学力においても同様です。個人差もありますが、もうすぐ7歳の子どもができることと、6歳になったばかりの子どもができることには差があって当然といえます。
児童手当の支給額が多い
児童手当は、中学校を卒業するまでの子どもを養育している方に支給される手当です。子どもが3歳未満のとき一人当たり一律月額15,000円、3歳以上小学校修了前は10,000円(第3子以降は一人当たり15,000円)、中学生は一律10,000円が支給されます。
児童手当には所得制限があり、制限額以上の所得を得ている場合は、「特例給付」として子ども一人当たり一律月額5,000円が中学校を卒業するまで支給されます。なお、児童手当と特例給付をあわせて「児童手当等」と呼ぶことが一般的です。
児童手当等において中学校卒業とは、15歳の誕生日以後の最初の3月31日のことです。早生まれの子どもの養育者の場合、子どもが15歳0ヶ月~3ヶ月の時点で児童手当等の受給が終了します。
一方、遅生まれの子どもの養育者なら、15歳4ヶ月~11ヶ月まで児童手当等の受給が可能です。早生まれの子どもと比べると最大11ヶ月間も長く受給でき、総額は最大11万円多くなります。
遅生まれのデメリット
遅生まれのデメリットとしては、次の点が挙げられます。
・生涯収入が減る可能性がある
・幼少期は「何でもできて当然」と思われがち
それぞれについて見ていきましょう。
生涯収入が減る可能性がある
多くの職場では、定年退職を誕生日で決めています。60歳で定年の職場なら、同じ学年の中でも早い時期に誕生日を迎える遅生まれは、早く退職することになります。
たとえば、4月生まれ(遅生まれ)の人が22歳11ヶ月で就職した場合、60歳になるまでに働けるのは37年1ヶ月です。一方、3月生まれの人が22歳0ヶ月で就職した場合、60歳になるまで38年間働けます。働ける期間が短いと、その分、生涯年収も減ってしまうでしょう。
幼少期は「何でもできて当然」と思われがち
幼少期は早生まれと比べると体格的・学力的に優れている傾向にあるため、周囲も「遅生まれだから何でもできて当然」と思われるかもしれません。そのため、かえって褒められる機会が減ったり、かわいがられることが減ったりする可能性もあります。
遅生まれ・早生まれではなく個性に注目しよう
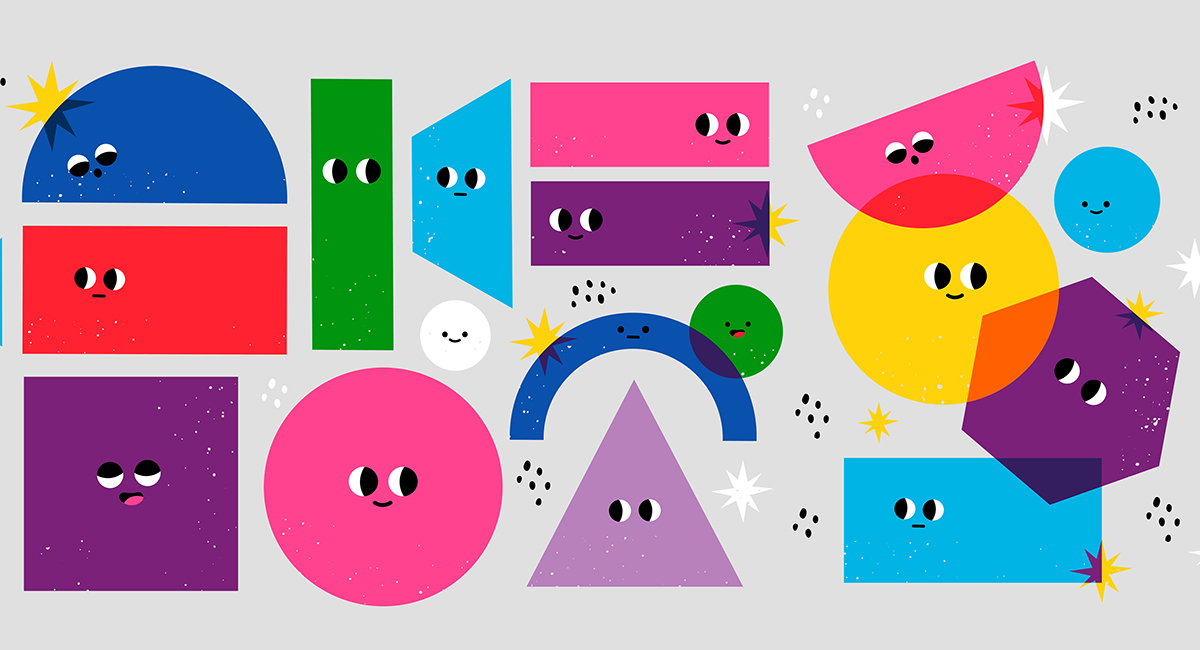
(c)AdobeStock
遅生まれにも早生まれにも「いつ生まれたか」という点だけに注目していると、その子どもが持つ個性を見落としてしまうかもしれません。子どもの誕生日ではなく個性に注目し、できることを褒め、できないことを励まして育てていきたいものです。
メイン・アイキャッチ画像:(c)AdobeStock
あわせて読みたい