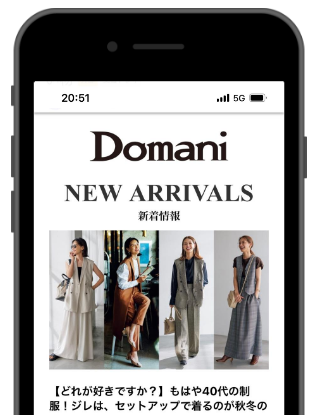〈4〉
護国寺のファミレスの夜はけだるい空気だった。妙に高い天井で、ゆっくりとファンが回っている。店員の動きが鈍い。夜の23時は、シフトの交代直前なのかもしれない。バレンタインがあけた2月15日。外は雪が降り積もっている。
疲れはてた様子で男女が入店してきた。
「なん名様ですか?」
男は指を2本挙げた。話をするのもめんどくさいといった風情だ。
「お煙草はすわれますか」
2本挙げた指をそのまま開き、左右にゆるく振った。
「では禁煙席でご案内しますね」
黙ってふたりは後に続き座った。寒さから抜け出せないのか、メニューを見ている間もコートを着たままだ。
思い思いに好きなものを頼み、女がドリンクバーからコーヒーを2杯入れてきた。
「お疲れ様です」
「おう」
「編集長、話ってなんすか」
「まあ座れよ。しかし校了だというのに、22時過ぎたらビルの暖房が切れるなんて赤字にもほどがあるな」
「ほんとですよ、うち経営ヤバいんですかね」
「まああんまり良くはないな。小説もコミックもない弱小出版社だから」
「だとしても、暖房くらいは24時間つけてほしいですよ」
「今日はたまたまだろうけどな」
「そう願いたいです」
「妹尾、お前、早稲田卒だよな。うちの高文館で働きだして何年目?」
「新卒で入って20年目ですかね」
「てことは42か。これ知り合いじゃねえのか?」
週刊女性ファイブの編集長、須藤は妹尾サキに向けてスマホを見せた。ぱっと見にイケメンと言われるようなこざっぱりとした男の顔写真がうつっている。
「知ってますよ。川口。大学からの知り合いで、広告代理店の東通ですね。編集長、どっかで会ったんですか?」
「川口圭一な。今朝というか夜中、佃の自宅マンションから落ちた」
「ええ!? なんでですか? 生死は?」
「まだ理由はよくわからない。なにしろ本人は意識不明だし、家族は寝ていたと言っているし」
「意識不明ってことは、助かったんですか」
「そうみたいだな。雪の上に落ちたのが幸運だった」
「……」
妹尾は須藤の後ろにある窓を見た。カーテンが閉じていて見えなかったが、先ほどまで見ていた雪景色が頭に広がった。
「お前、どのくらい仲がいいんだ」
「彼はけっこう早く結婚したんですよ。年に一回、仲間内で集まるときにたまに会うくらいですかね」
「相手は?」
「美人編集者で有名です」
スマホをいじって雑誌のウェブサイトを出した。
「祥明社『JOLIE』の編集長、川口かおりか。確かに美人だよな。おれも知ってるわ。妹尾、こっちとは面識は?」
「うちの美容ページやってたときに発表会で少し会ったことはあります。なにしろ向こうは三大出版社の祥明社さまで、売れ行き絶好調の『JOLIE』ですから。いつもプレスとわいのわいの話し込んでて」
「美男美女で、大手広告代理店と大手出版社のエリートの夫婦かよ。掘れば浮気のひとつやふたつ出てきそうだな。出てこなくてもこの事件は『世間好きする』ってやつだ」
「……そうでしょうね。記事にしますか」
「その前提で」
「わかりました」
「美人編集長が旦那殺して、ばらばらにして捨ててくれたらもっと盛り上がったんだけどな」
「ワインボトルで殴り殺した事件、ありましたね」
「そのくらいキツいネタが出てくるといいな」
「まあでも、なんかしらあるかもしれませんよ。なんてったって東通ですし」
妹尾はそういいながら、席を立った。
「もう行くのか」
「調べたいことあるんで」
「おう。うまくいけば、次の異動で編集長に推してやる。がんばれよ」
「はい」
須藤は、全く手を付けられないまま残された妹尾のチキンステーキを無表情でじっとながめていた。
店を出た妹尾サキはタクシーに乗り込んだ。
「要町まで」
そう伝えると、スマホで「川口圭一」と調べ始めた。
――しまった。チキンステーキ、ひとくちも食べずに出てきてしまった。それにしても、川口が。ぜったい自殺はありえない。あんなに自分を好きなやつはいない。
川口圭一と妹尾サキの出会いは大学時代だった。
「となり空いてる?」
ずいぶんさわやかな男だな、そう思いながら妹尾は自分のリュックをどけた。ジャージだから体育会系か。あまり関わらない人種だな。
ところが同じ社会学のゼミ、就職希望がマスコミということもあり、何度か会ううちに、情報交換がてら話をするようになった。圭一はいつもさわやかで、まるで我が世の春のような顔をしていた。大学のマスコミセミナーでもいっしょだった。圭一はアナウンサー試験を受け、いいところまで行ったらしい。結局は東通に決まった。妹尾が高文館に就職が決まってからは、大手広告代理店と弱小出版社ということで、格差もあり疎遠になっていた。
年に一回、マスコミの同期を誘い合って集まる新年会があり、そこで会うくらいの関係だった。川口圭一と小林かおりもこの会で出会った。
18年前の2004年のことだった。あの時は祐天寺のカフェバーに集まった。総勢20人を超えていた。
川口とかおりはあの日がはじめてだったはずだが、もう半年後には結婚していた。まわりがあっけにとられるほど早かった。
あとからわかったのだけれど、先に妊娠していた。
毎年の新年会で出会うたびに名門小学校に入った息子の写真や、出世する妻について自慢気に話していた。
「すぐ別れるんじゃないかと思っていた」今年の新年会で妹尾サキが意地悪な気持ちをかくせずに言うと、川口圭一は一瞬無表情になり、すぐに笑顔を返してきた。
しかしその、川口圭一が転落した。おもしろい。
妹尾は不自然にさわやかな圭一を嫌いだったが、かおりのことはもっと、大嫌いだった。
まるで源氏物語の夕顔のように、何もほしくなさそうな顔をして、すべてを手に入れていく女。できちゃった結婚だって、かおりが圭一をはめたに決まっている。
いつまでたっても独身の自分とは違って、東通でイケメンの夫。名門に通う息子に娘。ご丁寧に子どもは男と女ひとりずつ。「美人編集長」ともてはやされている様子を、野良猫のように遠くからながめていた。クソみたいなわたしの人生。かおりは、妹尾サキの心をざらつかせる存在だった。
いっそ夕顔みたいにかおりも死んでしまえばいいのに。
まずはどこから調べるか。あの二人を会わせたのは、大宮ちかだったかな。妹尾サキは、ひさしぶりにわくわくしていた。目の前に生肉をなげこまれたハイエナのように、肉のにおいを胸いっぱいに吸いこみ、くらいついて振りまわし、かみちぎりたい。食べそびれたチキンステーキで満たされなかった空腹が、いつのまにか消えていた。妹尾サキは、週刊女性ファイブにいることを、心の底から喜んだ。
作家 松村まつ
東京都内に勤務する会社員。本作がはじめての執筆。趣味は読書と旅行と料理。得意料理はキャロットラペ。感動した建物はメキシコのトゥラルパンの礼拝堂とイランのナスィーロル・モルク・モスク。好きな町はウィーン。50か国を訪問。