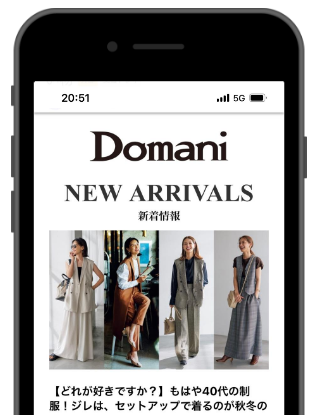〈18〉
【登場人物】
川口圭一 (24) 大手広告代理店・東通勤務。コピーライター。借金がある。
小林かおり(24) 大手出版社・祥明社のティーンズ誌『プチファスト』編集者。長野出身。
大宮ちか(24)大手出版社・祥明社の文芸誌『トロイカ』編集者。かおりの同僚。
遠藤敦士(26)橋の設計をする新進気鋭の建築家。
<これまでのあらすじ>
2022年2月14日、東京・佃。銀座にほど近い高級マンションから一人の男が転落した。男の身元は大手広告代理店勤務42才の川口圭一。転落したマンションは、川口が家族4人で住んでいた。他殺か、自殺か、事故か。話は18年前の2004年。圭一と妻のかおりの出会いへさかのぼる。たった一度のセックスで子供ができてしまった圭一とかおり。結婚することを決めたが、お互い知らないことばかりで……。
「もしもし……」
昼時のため、編集部に人はまばらだ。小林かおりは今日の夜の待ち合わせについて確認をするため、川口圭一へ電話をした。むなしく呼び出し音が鳴り続ける。圭一は、一度もすぐに電話に出た試しがない。かおりはそのまま電話を切った。昨日高知から帰ってきて、かおりは圭一の言動をよく思い出していた。こういう電話に出ないところも不愉快だった。
圭一が電話に出ない間も、赤ちゃんはかおりの体の中で育っている。だけど仕事は、かおりが妊娠する前からやりたくて採用された企画ばかりだ。むしろ子供は後からやってきたのに、いまやかおりのすべてを支配しようとしている。圭一は、なにも手放すものはないというのに。不公平だ。
かおりは、だるさをおして、デスクに戻ろうとした。同期の大宮ちかとすれ違った。ちかがかおりに話しかける。
「お昼食べた?」
「まだ」
「そしたらサクッとメシしよう。略してサク飯」
強引にかおりを引っ張って行く。
「かおり、顔色が悪いね。食べたいものある?」
「無性にエビフライ食べたい」
「じゃあ、七條行こう。ラストオーダーぎりぎりだから、並んでないかも。会社の人、だれも居ないといいんだけど」
地下にある洋食屋の七條は混んでいたが、並ばずに滑り込めた。こってりした味と本格的な洋食が手ごろな値段で味わえるため、いつも人気の店だ。かおりはミックスフライ、ちかはカキフライを頼んだ。これからお金がかかるのだから、お手頃な『日替わり』にしておいたほうがよかっただろうか。かおりは一瞬考えを巡らせた。そんなかおりに気づかずに、お手拭きで手をぬぐいながらちかが言う。
「かおりがミックスフライなんて珍しい」
「おなかがやたら減る」
ちかは顔を近づけ、声をひそめる。
「赤ちゃんいるからかな」
「たぶん。おなかが減ると気持ち悪くなるから、常になんか食べてる」
すぐに、ミックスフライとカキフライが到着した。妊娠すると味覚が変わるというのは本当だった。枝豆や寿司、月見そばのようなさっぱりしたものが好みだったかおりだが、つわりが始まって以降、グラタンやフライ、ハンバーグ、カレーのような洋食を好むようになった。
「それで……川口圭一はなんて?」
ちかはカキフライにかぶりつく。一口では食べきれない大きなカキフライだが、豪快に口に押し込んでいる。
「『おれと、結婚する? 大変かもしれないけど』だって」
「『大変』ってなに!? 忙しいとかそういうこと? 天下の東通さまだから?」
「ううん。その時は細かいことは聞かなかったけど」
「けど?」
「昨日、『借金がある』って。しかもいくらあるかわからないって」
「ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょと待て。いや、わかる。確かに川口圭一は不自然に羽振りがいい。それが借金だったってこと?」
「よく考えたら、わたしって、なあんにも知らないの。これからどうすればいいか。彼がどんな人なのか。わかっているのは10月になると、子供が生まれるってことだけ」
「そんなことって……」
絶句するちかから目をそらして、かおりは遠くをぼんやり見ている。店内は客が帰り始め、空席がぽつぽつ目立っていた。ラストオーダーを過ぎたからか、扉の向こうに行列はない。
「これからなにすればいいか数えてみよう。そしたら見えてくるかも」
ちかはポケットからメモ帳を取り出して書いていく。
「1、かおりの親に報告すること。
2、川口圭一の親に報告すること。
3、両家の顔合わせ。
4、結婚届。でもいつ出すものかな。
5、結婚式……はするかよくわかんないけど、とりあえず。
あ、結納もか、6。
それで、7、新婚旅行。
8、産休。
だめだ、引っ越ししてないわ。9、引っ越し。
そして、10月に出産。
いまは2月だから、あと8カ月。仕事をしながらでしょう」
ちかとかおりはため息をついた。ちかはペンを持ったままかおりのほうを向く。
「いま数えただけで、出産までに9個。でも、結婚式の準備とか家探しとか入ってないから、現実はもっとたくさんあるのかも」
かおりはちかのペンを預かり、『2、川口圭一の親に報告すること』の1項目に二重線をし、3項目に括弧をつけた。
「彼の親には土日に会った。結納は必要かな。結婚式とか新婚旅行はお金ないから無理かも。1、2、3、4、これで5個になる」
「とはいえ、5個か」
普通、プロポーズから出産まで何年もかけることを考えると、たった8か月ですべてを走り抜けることが超人的なことだというのは理解できた。
ただ、どれもこれもはじめてのことで、まわりにも結婚をした人はいない。どのくらい大変なのか、かおりたちには見当がつかなかった。
「でも、やるしかないから。今までできちゃった結婚した人たち、みんなこれやってるわけだし。わたしはできる」
「たしかに。しかし、かおりのお母さん、どう言うかね」
「それは、考えたくない」
「会社には?」
「編集長には報告した」
「はやっ」
「少しでも早く報告しないと、迷惑かける。暗に『子育てしながら編集者なんて無理だ』って言われた」
「ええっ。うちでもそうなの? 業界最大級の大手よ? 新入社員の時、人事のひと『子供産んでもどんどん働いてほしい』って言ってたのに」
ちかはカキフライでテカテカした唇をペーパーナプキンでぬぐう。
「理想と現実は違うらしい」
「かおり、言いにくいんだけど……もう一度よく考えてみたら」
ちかは探るような視線でかおりを見る。かおりがコップを空にすると、タイミングよく店員が水を注いでくれた。
「でも編集長に『産むし、仕事も続ける』ってたんか切った」
「おお」
「編集長の話だと、仕事を続ける限り、いくつになっても結婚して子供を育てるタイミングがないんだよ。サキが言ってた通りだよ」
「サキのこと呼び捨てになってる」
ちかが笑った。
「だからね、結婚のほうもなんだけど、仕事の結果を残したい。産休までに一回でもアンケートの一位取って産休に入りたい」
「産休まであと何回企画出せるの」
「数えたら、夏は合併号だから、たぶん6回」
やれるだけやって、だめなら異動希望を出そう。圭一の借金を考えると、退職はなんとしても避けたかった。かおりは、付け合わせの薄い野菜スープをぐっと飲み干した。
ちかと話をしたことで、頭の中が整理された。かおりはちかが書き出してくれたメモを手帳にはさんだ。バッグの中の携帯が目についた。
圭一はなぜ電話を折り返してこないのだろう。そもそも、なぜいつも電話に出ないのだろう。かおりは不安よりも、自分の都合を優先する圭一の態度に腹が立ち始めていた。
ちかと別れ、席に戻り、PCを立ち上げる。
原稿もラフ書きも、驚くようなスピードですすんだ。ランナーズハイはこんな感じかもしれない。締め切りの近い作業をすべて済ませ、一息つく。気が散るため、立ち上げなかったメールを開いた。昼過ぎに、建築家の遠藤敦士からメールが届いていた。橋の情報をもらってから、時々メールのやりとりをしていた。
『今日の16時頃、近くに行きます。コーヒーに付き合ってくれませんか。会社は出てしまうので、携帯に電話ください』
メッセージには電話番号と携帯のメールアドレスが添えられていた。すでに16時をすこし過ぎている。
かおりは携帯電話を開く。圭一からの連絡はない。遠藤に教えられた電話番号にかける。遠藤は、呼び出し音、一度で出た。
「もしもし」
「もしもし、遠藤です……かおりさん?」
「はい」
「よかった。喫茶店の『さぼうる』ってわかります? 店内の奥のほうで待ってます」
これまで遠慮がちなメールとは打って変わって、有無を言わさない強引な誘いだった。かおりは、会うことをやんわりと避けていた罪悪感もあり、言われた通り『さぼうる』へ向かう。
天井の低い、雑多な店内は満員だった。店員に待ち合わせだと告げると店の奥のほうへ案内された。遠藤が座っていた。はじめて会った時と同じ、カーキのセーターを着ていた。かおりを見つけると、軽く会釈をした。かおりは店員に『彼と同じものを』、と注文した。
「久しぶりです」
「……祐天寺ぶりですね。いちごジュース頼んだんですか?」
「そう。子供みたいかな」
大きないちごジュースを前に、遠藤はストローでぐるりとかき回した。
「僕、建物が好きで。いろいろ見に行くんですけど、撮影によさそうなところがたくさんあったので、リストにしてたんです。持ってきました」
「そのためにわざわざ?」
「いや、神保町は建築系の雑誌や古本を探しに時々来るんです。かおりさんの会社、この辺だったかなって。ついでだしと思って」
「こんなにたくさん」
かおりは遠藤からもらったリストをめくる。
「個人のお家も…」
「それは、東工大で同じ研究室にいた先輩が手掛けた家です。そっち経由で頼めば撮影許可が下りると思います」
かおりのいちごジュースが運ばれてきた。一口飲む。不思議と安心する味だ。子供のころ、祖母が作ってくれた、甘くておいしいいちごの練乳掛けを思い出す。先の割れたスプーンの背で押して食べた。
「東工大なんですか」
「そう、だから普通の人にはないルートもたくさんあると思います」
遠藤がふわりと目を細めた。
「もうすこし時間ありますか? 散歩しませんか」
遠藤はコートを手にし、席を立った。『さぼうる』の深い飴色に色褪せた古い内装が、遠藤の静かなたたずまいとよく馴染む。当然のように遠藤は支払いをし、かおりからお金は受け取らなかった。小さな二つ折りの皮財布は、よく使いこまれていい風合いになっていた。レシートかなにかで膨らんでいる圭一の財布とは対照的に、遠藤の財布は薄かった。レシートを受け取っているところを見ると、毎日、財布からレシートを出しているのかもしれない。セーターは肘あてがついており、実用的で好ましかった。おおよそ、派手なところのない遠藤という男と一緒にいると、時間が丁寧に流れるようでくつろげた。
歩きながら、遠藤が言った。
「僕、もうすぐパリの建築事務所に移るんです」
突然のことにかおりは目を丸くした。
「パリでもいい撮影場所、探しておきます」
遠藤が自分のことを思ってくれているのが伝わる。
「素敵ですね。パリで建築事務所」
「わくわくしますよ」
「本当に」
「初めて会った日、かおりさんがね『編集長になりたいんです』って言ったでしょう。あの凛としたところに勇気をもらったというか。勝手に背中を押されました」
「わたしが……背中を」
「そう。お礼を言いたかったんです」
遠藤の言葉がかおりに突き刺さる。惨めだった。先月、『編集長になりたい』といったことが遠い昔のようだった。
「遠藤さんにそんなこと言ってもらえるような人間じゃないです」
ちかには『仕事で結果を残したい』と威勢のいいことを言ったが、かおりはきっと、どこかのタイミングで異動になるだろう。編集長など、夢のまた夢だ。東通の圭一は、家事も育児も自分のこととは考えていない気がする。かおりひとり、子育てに忙殺されて、仕事がおろそかになる未来図がはっきりと見えている。圭一の家族は優しいが、高知はなにしろ遠すぎる。
それに、自分が圭一を拒めなかったからとはいえ、結婚前に子供ができてしまった。『性欲に負けた、だらしない人間』という烙印は一生消えない。しかも、圭一は借金があり、どうもそれ以上になにかを隠している。始まったばかりの編集者人生は、目の前で閉じようとしている。
問題が山積みしている。妊娠していることもあり、歩くのが辛い。かおりを見た遠藤はうろたえた。
「顔色が真っ白です。気づかなくて申し訳ない。ベンチで休みましょう」
「大丈夫。大丈夫……」
「僕も疲れたから」
かおりと遠藤は、皇居堀のベンチに座る。冬晴れとはいえ、日が傾きはじめている。雪が降りそうな寒い中、ベンチは氷のようだった。それでも立っているよりは楽で、気分がずいぶん落ち着いた。
「かおりさんのことが時々、頭をよぎるんです」
かおりから顔をそらし、すぐそばにある木を眺めながら遠藤が言った。かおりは、自分のトートバッグを膝にのせてクッションのように抱きしめた。
「強い人かと思ったら、自分に自信がなくて。泣き出すかと思えば、『編集長になりたい』と野心を見せて。だけど、今日は妙に頼りなくて。あなたはずいぶんいびつな人だ」
「……」
「パリに行っても、連絡をしてもいいですか」
遠藤はかおりのほうを見ず、堀のほうに目を移した。かおりの返事をじっと待っている。遠藤は圭一のように強引に手を握ったり、キスをしたりしない。かおりの気持ちを優先してくれる。かおりはトートバッグをひざに置きなおした。大きく、そっと、深呼吸をした。
「あの……わたし結婚するんです。子供ができて。だから……もう編集長なんて無理だと思うし、夢なんか見なければよかったと思っています」
遠藤はかおりの方に耳を傾け、肯定するでも否定するでもなく、じっと話を聞いていた。瞳は哲学者のように、静かに光をたたえていた。やわらかな藍色の薄暮がやさしくふたりを包み込む。しばらく黙っていた遠藤は、かおりのほうを向いて、力強く言った。
「それでも。僕たちは友達として、付き合って行けませんか」
「友達として」
「そう。あなたと僕との間にはなにもない。だから友達として」
そのとき、電話が鳴った。圭一からだった。かおりは遠藤に断って電話に出る。
「もしもし。うん。いま外にいる。そうだね……わかった」
電話を切って、かおりは遠藤に向き合う。
「祐天寺で、川口圭一さんっていたでしょう。彼が結婚相手なんです。いまの電話も彼」
「覚えている。東通の。僕、気が付かなくて、ごめん。赤ちゃんがいるなら、こんな冷たいベンチに座ったらだめだね」
遠藤はベンチから立ち上がった。
「同じ時に出会ったのに。悔しいけど、おめでとう」
かおりは、どう返事してよいものか、困ったように笑い、続けて立った。ずいぶん、体調はよくなっていた。もし、お腹の子が流れてしまったら……すべてから解放されるのだろうか。かおりは、身勝手なことを考えている自分に気がつき、頭から振り払った。
「パリ、行ってらっしゃい」
「メールするね。こんどは僕の恋の話も聞いてもらうかな」
遠藤はにこりと笑って、友達の距離を保ちながら神保町まで戻った。
かおりは、圭一の借金と、子供の命と、仕事の重圧に潰されそうになっていた。すべてを投げ出せたら、楽になれるのに。だけど、現実はおとぎ話とは違う。かおりには、そばに頼れる家族はいなかった。自分で道を切り開くしかなかった。
出産まで、あと8カ月。しかも、出産はゴールではなく、これから続く圭一との人生の始まりに過ぎなかった。
作家 松村まつ
東京都内に勤務する会社員。本作がはじめての執筆。趣味は読書と旅行と料理。得意料理はパテ・ド・カンパーニュ。感動した建物はメキシコのトゥラルパンの礼拝堂とイランのナスィーロル・モルク・モスク。好きな町はウィーン。50か国を訪問。