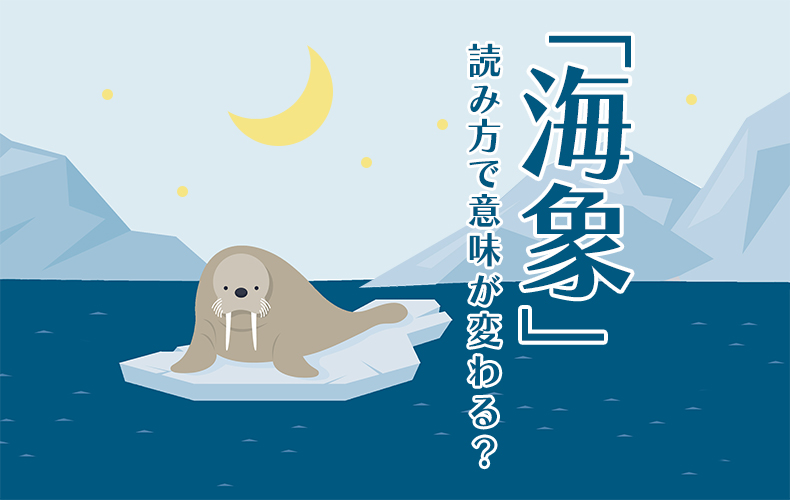「海象」の意味や読み方とは?
では、早速「海象」の読み方と意味を見てみます。

読み方と意味
「海象」は読み方によって、実は意味が異なる言葉なので要注意。ここでは、2通りの読み方「かいしょう」と「かいぞう」とそれぞれの意味を説明します。
まず、「海象」を「かいしょう」と読む場合です。意味を辞書で調べてみると、
海洋の自然現象の総称。(<小学館デジタル大辞泉>より)
次に、「海象」は「かいぞう」と読むこともできます。この意味を辞書で調べてみると、
1 セイウチの別名。2 ゾウアザラシの別名。(<小学館デジタル大辞泉>より)
と、海にすむ哺乳類の「海獣」の名前に! いかがでしょう? 「かいしょう」と「かいぞう」、読み方が変わると、全く違う意味になるのです。正しい意味を理解してくださいね。
また、「海象」のように「海」と生き物を表す漢字を組み合わせた言葉もたくさんあります。例えば「海豚」「海獅」「海獅子」など。こちらはいずれも海獣のこと。「海豚」はイルカ、「海獅」はアシカ、「海獅子」はアザラシです。漢字をよ〜く見て、その言葉からその動物の姿をイメージすると、不思議とぴったりしませんか? 不思議ですね。
「海象」の使い⽅
海の生き物である「海象(かいぞう)」は、動物園やテレビなどを通じて、その姿をイメージできる人も多いと思いますが、「海象(かいしょう)」は、馴染みがないという人も、少なくないのでは。本記事では「海洋の自然現象の総称」を指す「海象(かいしょう)」について見てみましょう。実際には、どのような使い方がされているか、説明します。
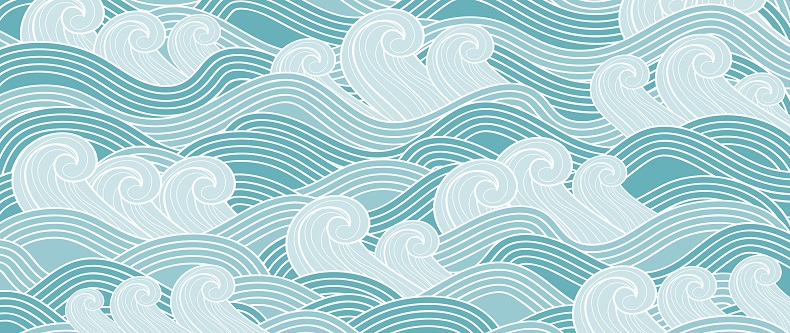
波浪等の状況を観測後直ちに知らせるオンラインの「海象情報」サービスはとても便利だ。
「海象観測」により得られたデータ「海象情報」は、地球環境変動予測や海洋上での安全な活動、海岸保全対策の実施等の資料として利用されます。
「海象観測」の主な観測項目は、「風」「波浪」「潮位」。
国土交通省河川局では、各地の所管観測所で気象・「海象観測」を行っています。海岸の保全にあたっては、海の現象は複雑で未知の部分が多いのが現状。そこで、海岸構造物の設計や災害時の対応などの基礎資料にすべく、国土交通省河川局では、各地の所管観測所で気象・「海象観測」を行っています。
「気象」との違いは?
「気象海象」と並べて使われることが多い「気象」と「海象」。さて、言葉の意味として、どんな違いがあるのでしょう。
「気象」の意味
「気象」は「きしょう」と読みます。その意味を調べてみると
1 大気の状態、および雨・風・雪など大気中で起こる諸現象。2 「気性」に同じ。3 宇宙の根元的なものの作用により生じる形象。
(<小学館デジタル大辞泉>より)
自然現象という点で共通する「気象」は「海象」の類語とも言えそうです。ただし、「海獣」の意味は、ありませんね。
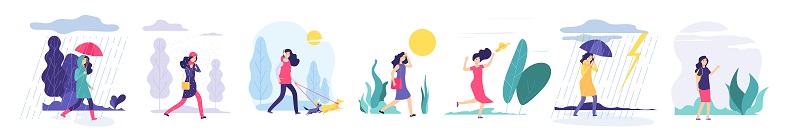
「気象」と「海象」の違い
「海で発生する自然現象」の総称が「海象」。「気象」は海に限らず、「大気の状態」として、雨・風・雪など大気中で起こる諸現象を表しているので、少しニュアンスが違いますね。
「海象」に注意する必要がある時は?
身近なところで、「海象」を気にする必要があります。それは、マリンスポーツのシーン。最近、人気の「SUP」でも、気をつける必要があります。他には水上オートバイや、カヌーも。また、海が好きな人は覚えておくといいでしょう。いざというときに役立ちますよ。ここではそれぞれの注意点について、説明します。