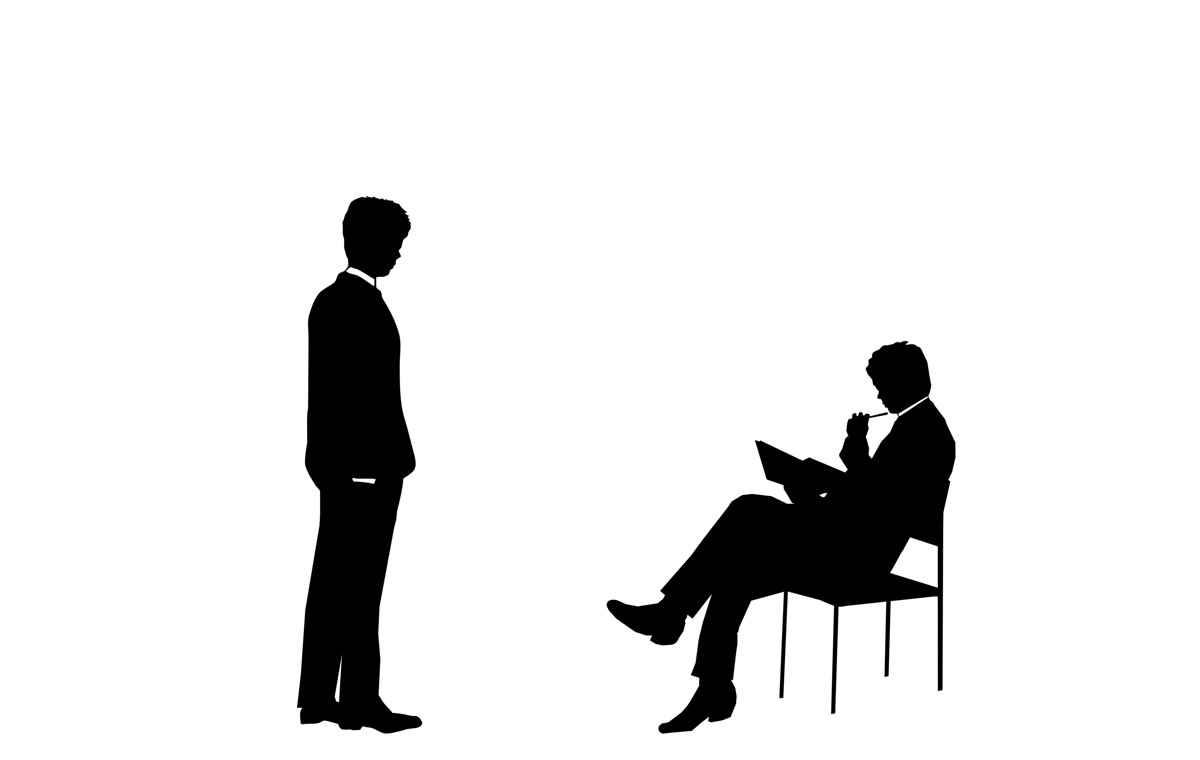指示待ち人間とは?
「あの人は指示待ちだから困る」のようにいわれる「指示待ち人間」。会社などの組織には、少なからず「指示待ち人間」が存在しますよね。周りにそういう人がいる場合、なぜそうなってしまうのだろうと思ったことはありませんか?
“指示待ち”を改善するには、そもそもの定義や行動特性の原因を知ることが欠かせません。まずはその定義から見ていきましょう。

(c) Adobe Stock
自分自身で考えて行動できない人のこと
指示待ち人間とは、やるべきことを誰かから指示・命令されないと、行動できない人を指します。
ビジネスシーンでいうと、「誰かからの指示がないと自発的に動けない」「自分で仕事を見つけることが苦手」などがあてはまるでしょう。指示の有無が行動に影響するため、突発的な案件やトラブルに対応できない、あるいは対応が苦手という傾向もあります。
指示待ち人間になるには理由がある
指示待ち人間になるのは、親や上司の対応が影響するという説があります。
たとえば、本人が何かをする前に親や上司が先回りをする、本人の意向を聞かずに親や上司が管理するなどが頻繁にあると、指示待ちになりやすいかもしれません。また、指示通りに動くことで認められると、それが自分の役割と思ってしまうことも。せっかく主張したり、主体的に行動したりしたのに、周りにそれを否定されてしまい、指示待ちになることもあります。
特に、周りが先回りしてやってくれる状態に慣れてしまうと、それが当たり前と考えてしまいがち。そのときは気がつかなくても、後々問題が顕在化するケースもあり、深刻です。
指示待ち人間になると、責任を負うということをしなくなりがち。何か問題が生じたら、無意識に周りのせいにしてしまいます。また、指示をされて仕事をするわけですから、常に「やらされる側」にいるため、主体性が育ちません。
▼あわせて読みたい
指示待ち人間によくある特徴
指示待ち人間には、行動や態度に特徴があるとされています。自分の部下や子どもがあてはまるかどうか、確認してみましょう。

(c) Adobe Stock
自信がなく、決断することが苦手
指示待ち人間は、自分の行動に自信が持てない傾向にあります。失敗することを恐れているため、行動に移せないのです。
また、自分で決断するのも苦手で、放棄してしまいがち。少し考えたら決められそうなことでも、上司や親に逐一確認をとるなどして、判断を委ねようとするでしょう。そのため、イレギュラー対応は苦手とする人が多いといえます。
自分の意見を言えない、質問できない
指示待ち人間は、自発的に質問する、主張するなどが苦手です。自分から発信したことで周りを怒らせる、批判されるなどを過度に恐れるのです。質問をするのも、誰に何を聞いたらよいかが判断できません。
焦りからなんとか動こうとしますが、意思表示することに慣れていないこともあり、結局何もできずに終わるということも。誰かが決めた内容に従うことになりがちです。