「釈迦に説法」は、知り尽くしている人にそのことを説く愚かさを意味します。
Summary
- 「釈迦に説法」とは、知識や経験が十分な人に教えようとしても無駄なことのたとえ
- 由来は、仏教の教えを説いた釈迦に説法をした人の愚かな行為にある
- 似たことわざには「猿に木登り」や「河童に水練」、対義語に近い表現には「馬の耳に念仏」などがある
Contents
「釈迦に説法」の意味と由来
「釈迦に説法」は、特にビジネスシーンで使われることの多いことわざで、一度は耳にしたことがある人も多いかもしれません。
「釈迦に説法」の意味
読みは「しゃかにせっぽう」で、言葉の意味は次のとおりです。
【釈迦に説法】しゃかにせっぽう
知り尽くしている人にそのことを説く愚かさのたとえ。釈迦に経(きょう)。
『デジタル大辞泉』(小学館)より引用
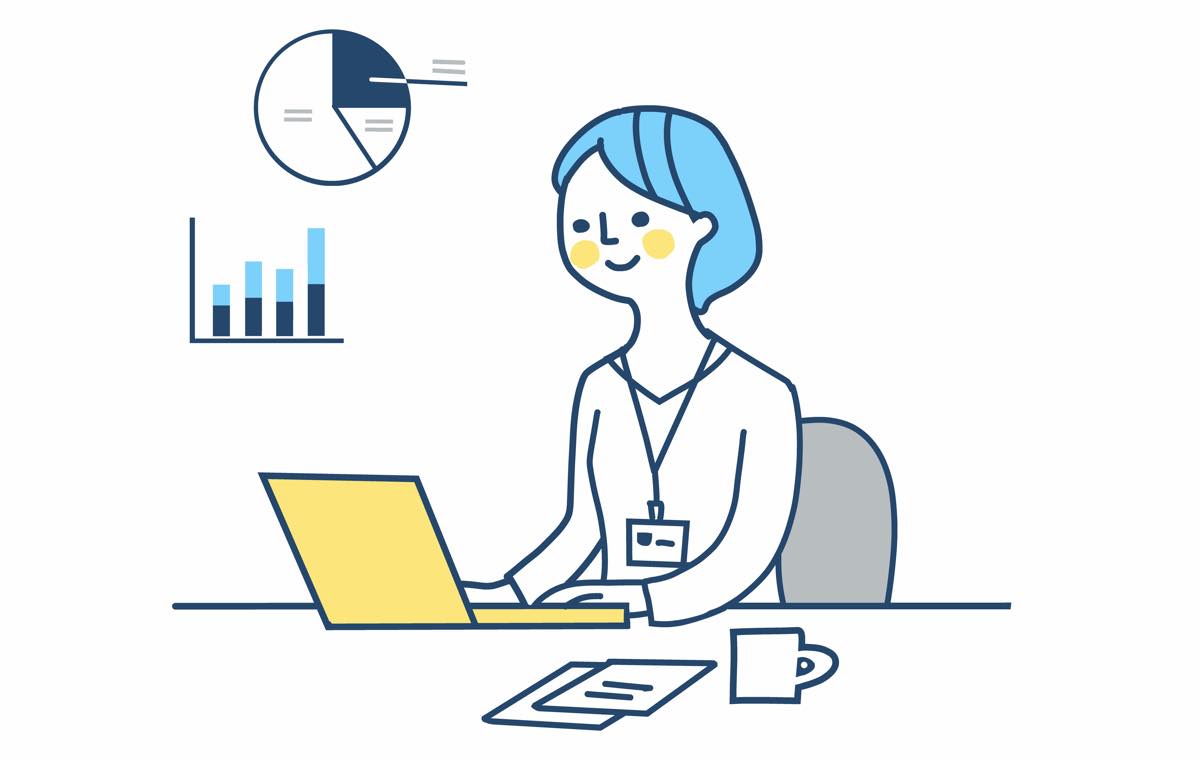
実際に会話の中で使いこなすのが意外と難しい、「釈迦に説法」の詳しい意味と由来を詳しく解説します。
「釈迦に説法」は愚かな行為を表す
「釈迦に説法」とは、自分と比べてより詳しく深い知識を持っている人に、そうとは知らずに自信満々に教えているさまの愚かさを表します。
例えば趣味の釣りで出会った人に、自分がこれまで釣った魚の自慢や、高価な釣り道具の説明を交え指導していたら、全くそんなふうには見えない相手が実は釣りのプロだった、という状態が「釈迦に説法」です。
「能ある鷹は爪を隠す」ということわざにもあるように、人は見かけでは持っている能力を判断できません。
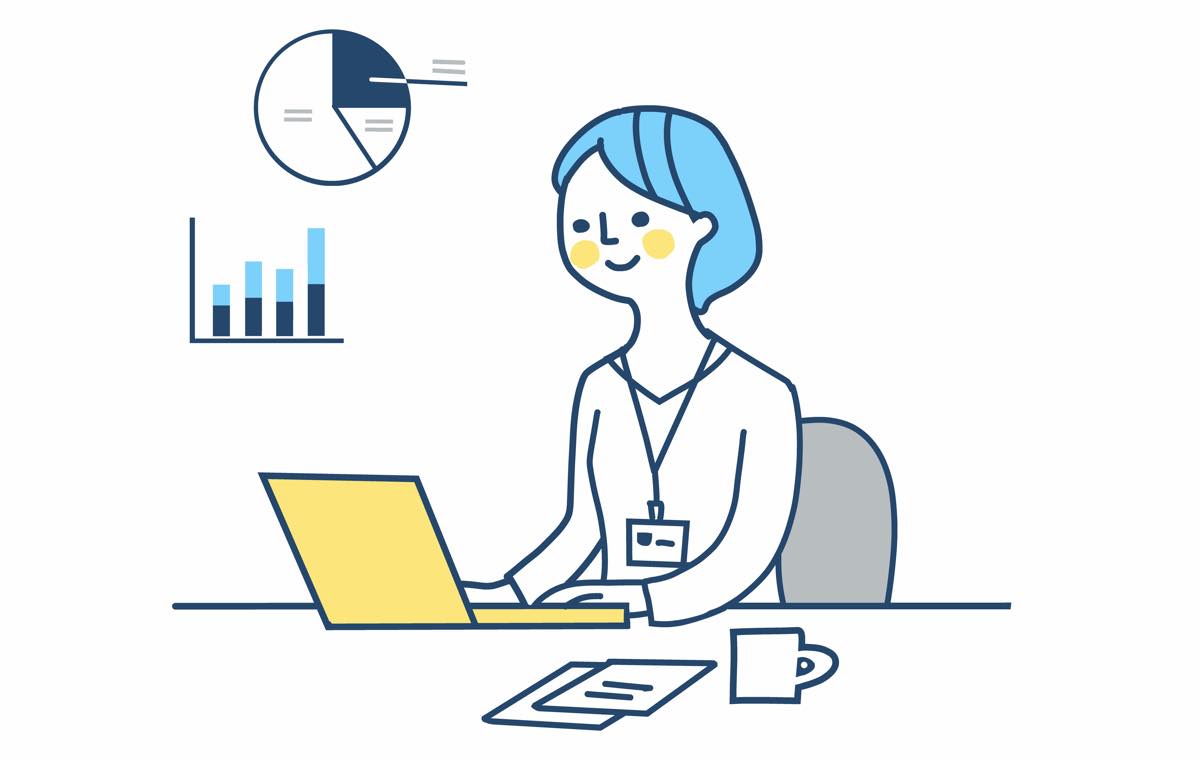
自分が得意であったり、自信があったりすることでも、謙虚な姿勢でいることが大切です。
語源は仏教の開祖に説法をした行為
「釈迦」という言葉で仏教に関する言葉だと予想できた人もいるかもしれませんが、「釈迦に説法」の「釈迦」は仏教の開祖を指します。「釈迦に説法」は、仏教の教えを説いた張本人である釈迦に、説法(仏教の教義を説き聞かせること)をした人の愚かな行為が語源となっているのです。
ここから転じて、ある特定の分野に理解がある人に、そうとは知らずに教えを説く愚かさを表現する言葉となりました。
「釈迦に説法」の使い方ポイント4つ
自分よりはるかに知識を持った人に教えることを意味する「釈迦に説法」ですが、実際の会話で使う際には次の4つのポイントを心得ておきましょう。
誤ったシーンで使ってしまうと、相手に失礼になってしまうことがあります。釈迦に説法の使い方について、各ポイントを詳しく紹介します。

誰かをたしなめる時に使う
「釈迦に説法」は、誰かが自分の立場をわきまえずに、出過ぎた行為をしている所をたしなめるために利用できます。
例えば社外の人達と一緒に進めているプロジェクトで、入社して日の浅い社員が相手企業の責任者に、偉そうに意見をしている場面に出くわしたら、「釈迦に説法」を使って注意する必要があるかもしれません。
しかし実際には、経験の浅い社員の意見で凝り固まった偏見が取り払われ、相手企業もありがたいと思う可能性もあります。
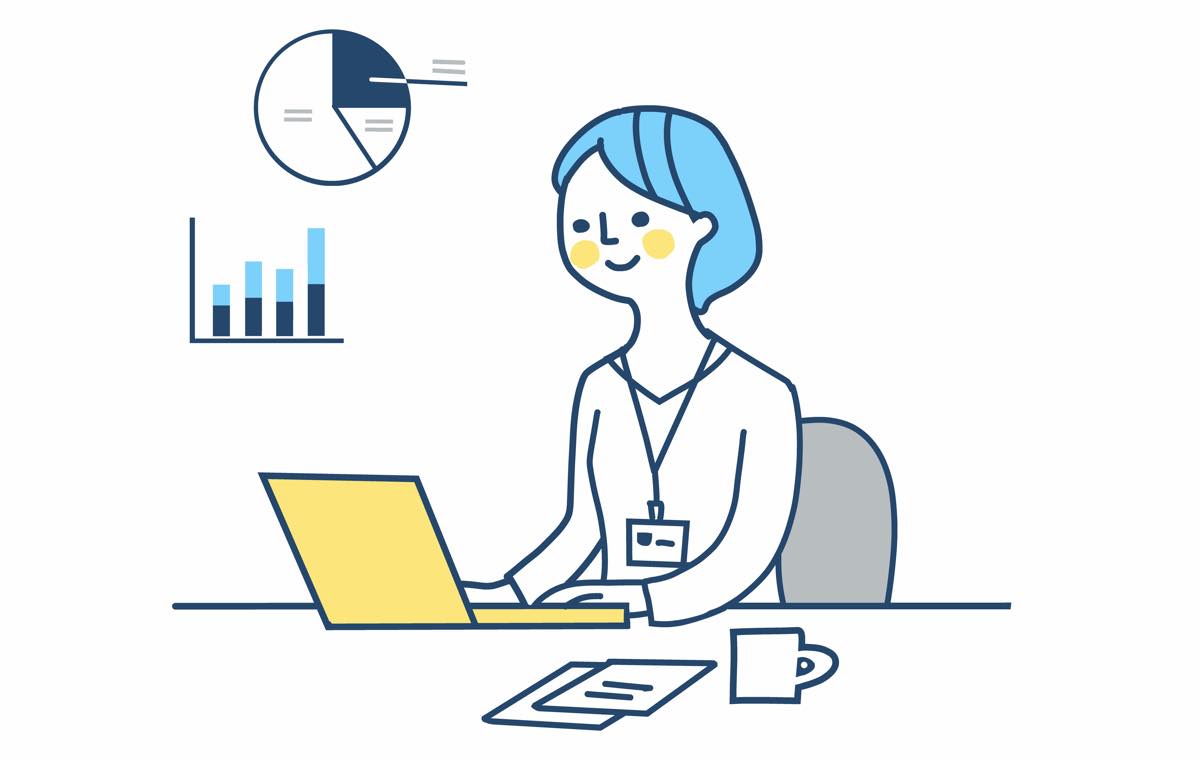
「釈迦に説法」をたしなめる際に使う場合は、状況を良く把握し、細心の注意を払う必要があります。
自分がへりくだる時に使う
自分がへりくだって相手に何か提案する場合にもよく使われます。
「こんなことを申し上げるのは釈迦に説法ですが」「釈迦に説法とは存じますが」のようなフレーズは覚えておくといざという時に使えるので便利です。前述の、相手をたしなめる使い方よりは、気軽に使いこなせるでしょう。相手が『釈迦に説法』の意味を理解していれば、謙遜の意も自然に伝わります。
誠意のある謝罪をする時に使う
その道のプロや知識人に、知ったように知識をひけらかしてしまうことは、相手に失礼になる場合があります。わざとでなくても、相手のことをよく知らないまま会話をしていれば、「釈迦に説法」なことをしてしまうかもしれません。
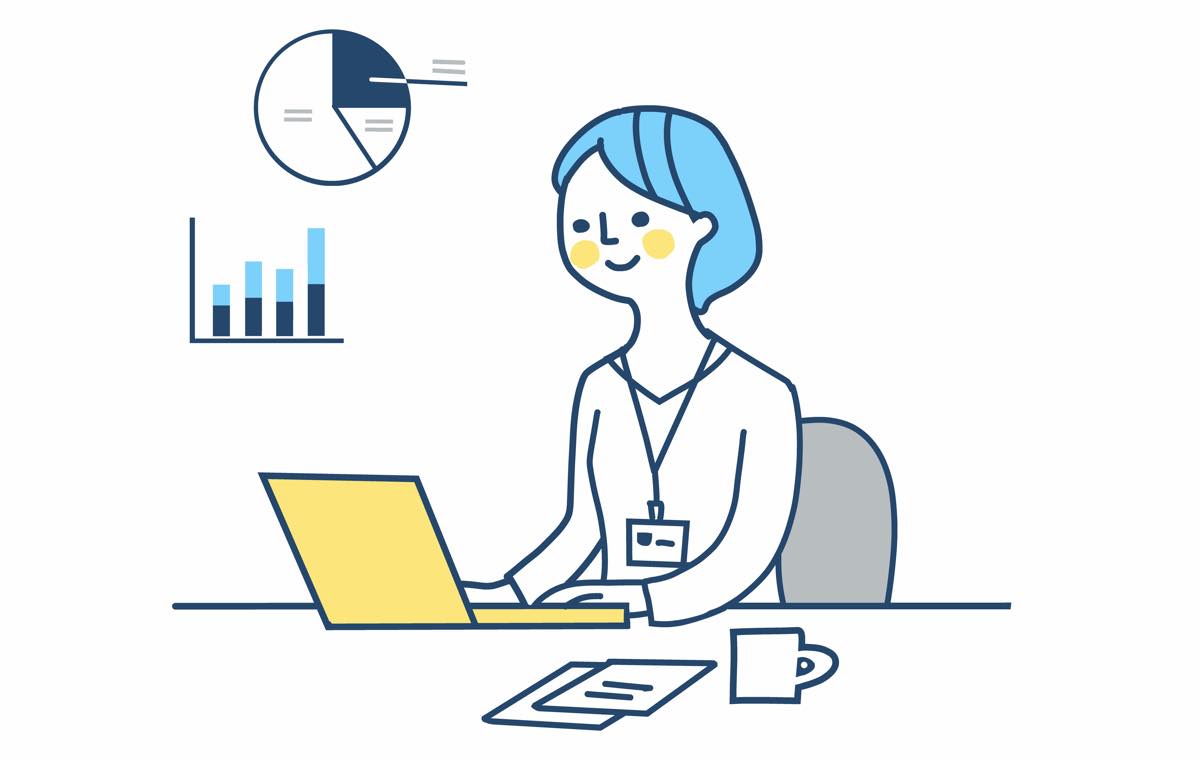
もし意図せずそんな状況に陥ってしまったら、「釈迦に説法」を上手く使いこなして謝罪してみましょう。







