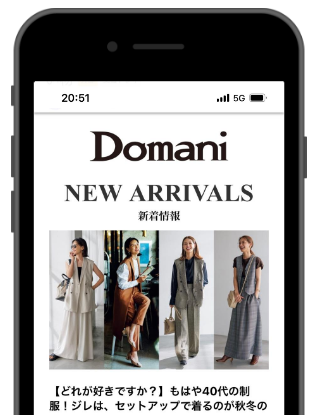「辞令」という言葉を、どこかで見聞きしたことはありませんか? 職場で、「転勤の辞令が出た」などと耳にする機会があるかもしれませんね。
ただ、詳しい意味や種類を聞かれると、よくわからないという方も多いキーワードではないでしょうか。また、「辞令と内示はどう違うの?」や「辞令には法的な効力がどこまであるの?」などの疑問をお持ちの方もいらっしゃることでしょう。
そこで、この記事では、辞令の意味や種類、内示との違いや法的効力について解説します。
辞令とは? 意味や役割を解説
まずは、辞令について、基本的な意味や役割を見ていきましょう。
辞令の定義と基本的な役割
辞令とは、仕事の役職などの任命のときに本人に渡す文書のこと。辞令には、新しい仕事についての認識を合わせ、異動をスムーズにするという役割があります。口頭だけだと、認識違いや「言った言わない論争」に発展しがちでしょう。そういった背景もあり、辞令は組織運営をスムーズにする上で、とても重要な書類といえます。

(c) Adobe Stock
内示との違いとその重要性
辞令とセットで覚えておくと便利なのが、「内示」です。内示は、辞令の発令前に、非公式に本人へ伝えることを指す言葉。それに対して、辞令は決定した内容を公式に伝える文書のことです。辞令を出す前に、まず口頭で本人に伝える内示をすることで、異動を円滑にするという役割がありますよ。
辞令交付の流れを徹底解説
辞令交付は、流れを知っておくことも大切です。ここからは「辞令交付」のステップもみていきましょう。
辞令交付の4ステップ:内示、発令、交付、着任
辞令交付は、一般的には次のような4つのステップで行われます。
ステップ1:内示(事前に本人へ、辞令の内容を非公式に伝える)
ステップ2:発令(正式な辞令を決定する)
ステップ3:交付(辞令の内容を通知する書面を本人へ渡す)
ステップ4:着任(辞令の内容にしたがい、新しい仕事をスタートさせる)
もちろん、会社によっては、一部を省略することもあるでしょう。基本的な流れとしてチェックしてみてくださいね。
辞令交付式の概要とマナー
会社によっては、「辞令交付式」というものを行うこともあります。例えば、全社員が集まり、社長が辞令を一人一人手渡すという会社も。
辞令交付式がある場合、マナーにも気をつけたいところです。基本的に、こういった式典は、オフィシャルな場面と考えておくのがいいでしょう。特に、式の最中は、必要のないおしゃべりを避けるなど、静粛な雰囲気を重んじるようにした方が無難です。
ただ、辞令交付式でのマナーは、会社によってかなり差があるので、悩ましいところ。どのような服装やマナーで出席するべきなのかというのは、事前に社歴の長い人に確認しておくとさらに安心ですよ。
辞令の種類とその具体例
辞令の種類にはどのようなものがあるのでしょうか? まず、一般的なのは、昇進や降格などの職位(ポジション)が変更される場合です。また、転勤、部署変更などの、いわゆる「配置転換」のときに辞令を出すというケースも多いでしょう。
さらに、別の会社に出向や転籍をする場合も、辞令を出すことが基本です。特に、出向や転籍の場合は、「どちらの会社に籍があるのか」などもはっきりさせておかないと、大きなトラブルに発展することも多いという点も気をつけましょう。

(c) Adobe Stock
また、会社によっては、社員の退職の際に「退職辞令」を出すことも。このように、辞令には、さまざまな種類がありますよ。
いずれにせよ、会社の人事に関わることについては、事実確認をしやすくするために、辞令を出すことが一般的です。
なお、辞令のテンプレートを使う場合、種類の間違いや、内容の更新忘れは特に気を付けたいところです。ある会社では、新卒社員の入社時に、「昇進辞令」を間違えて渡してしまい、「いきなり昇進ですか!?」とびっくりさせてしまったというエピソードもあったりします。タイトルや日付、内容は十分にチェックするようにしたいですね。
辞令の法的効力と対応方法
辞令には、法的な効力や拘束力があるのか、どの程度あるのかも気になるところですよね。ここからは、辞令がどこまで有効なのかを見ていきましょう。
辞令の法的拘束力|どこまで有効か
辞令の内容に法的拘束力があるかどうかは、ケースバイケースです。では、どのような判断要素があるのでしょうか? まず、就業規則や労働契約がどうなっているかという点です。また、その辞令に合理性や必要性があるものかというのは重要なポイント。例えば、転勤の辞令(転勤命令)で考えてみましょう。
大阪労働局のQ&Aによれば、会社の転勤命令については、労基法上の明確な定めはありません。そのため、一概に判断するのは難しいというのが実態です。
例えば、勤務地限定の労働契約ではなく、就業規則にも「転勤させる場合がある」などと書かれている場合はどうでしょうか? この場合、仕事上、その転勤の必要性も合理性もあるという場合は、原則その辞令を拒否するということは難しいといえるでしょう。