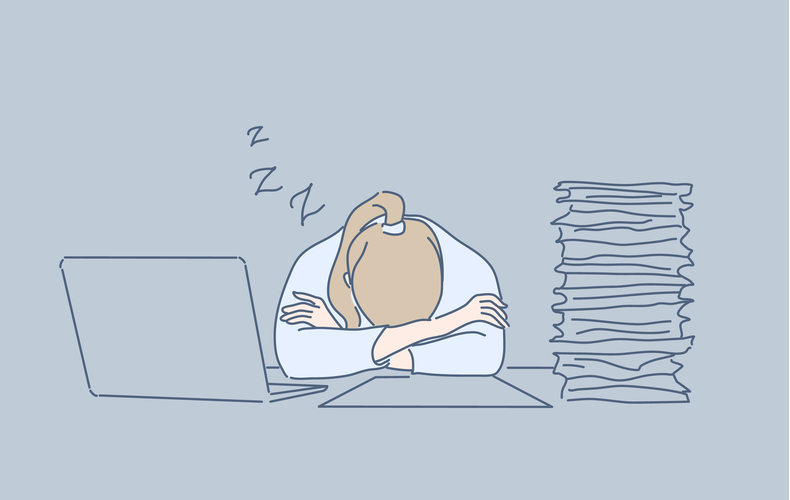「仕事しない人」は「仕事ができない人」ではない!?
同じ職場に仕事しない社員がいて、困っている方もいるでしょう。仕事をしない社員は仕事ができないのかと思われがちですが、「仕事しない人」と「仕事ができない人」はまったく異なります。

「仕事ができない人」とは、業務の能力が不足しているなど、自分の意思とは関係なく仕事ができない人です。仕事ができない原因はさまざまですが、仕事をする気持ちがないわけではありません。
一方、「仕事しない人」は仕事をする能力があり、できるにも関わらず仕事をしないのです。仕事ができるのにしないことに対し、苛立つ人も少なくないでしょう。
「仕事をしない人」は必ずいる?「働きアリの法則」とは
「仕事しない人」がそばにいると、「なぜ自分の周りにだけ」と思うかもしれません。しかし、働かない人はどの職場にも必ずいるという理論があります。「働きアリの法則」と呼ばれるもので、組織の中で真面目に働いているのは20%に過ぎないという法則です。
これは、「2:6:2の法則」とも呼ばれています。20%が働きアリのように一生懸命働いて60%が普通に働き、残りの20%がまったく働かないという理論です。この法則によれば、どの職場にも仕事しない人は一定の割合でいるということになるでしょう。
「仕事しない人」が職場に及ぼす影響
「仕事しない人」はただ働かないだけでなく、周りに悪い影響を与えます。他の社員は、自分が一生懸命働いているのに平気で仕事しない人がいれば、働く意欲をなくすでしょう。
また、働かない社員の業務は誰かにしわ寄せがいってしまいます。周囲の労働意欲が削がれることで、会社の業績にも影響が出るでしょう。仕事しない人が職場に及ぼす影響は、主に次の3つです。
周囲がイライラして働く意欲をなくす
自分が忙しく働いているのに仕事しない人が周りにいると、苛立って働くモチベーションが下がります。遊んでいても給与がもらえるのかと思い、真面目に働く気がなくなる人がいるかもしれません。
会社側が注意をするか、給与が下がるかのペナルティがあれば納得もできるでしょう。しかし、そのような動きもなければ周囲の不満は大きくなります。
誰かにしわ寄せがいく
「仕事しない人」がいれば業務が進まず、誰かにしわ寄せがいきます。代わりに業務をしなければならない人が出てきて、負担をかけることになるでしょう。
自分の業務であれば忙しくても仕方ありませんが、働かない人の仕事もするとなると理不尽に感じてしまいます。その結果、仕事ができる優秀な社員がやめてしまうことにもなりかねません。
会社が不利益を受ける
他の社員が仕事へのモチベーションや働く意欲をなくすことは、会社が不利益を受けることにもなります。労働意欲の減退は生産性の低下につながり、業績にも影響が出るでしょう。
優秀な人材が流出することで、採用のコストもかかります。働かない社員が一人いるだけで、会社が受ける不利益はかなり大きくなるといえるでしょう。
仕事しない人の5つの特徴
「仕事しない人」は、仕事ができないというわけではなく、あえて仕事をしようとしません。普通に働いている人からすると、そのような態度は不思議に思えるでしょう。

「仕事しない人」には、協調性がない、責任感がないなどいくつかの特徴があります。仕事をすればできるのに、自分は仕事ができないと思い込んでいる人もいるでしょう。ここでは、「仕事しない人」の特徴を5つ紹介します。
1.協調性に欠け、向上心がない
「仕事しない人」は、周囲との協調性に欠ける場合が少なくありません。周囲に気配りがなく、周りが一生懸命に働いているときに何もしなくても平気です。
自分が仕事しない場合、誰かがその仕事をすることになるといったことを考えません。気が向いたときに仕事をすることもあり、業務の進行に支障が出る場合もあるでしょう。
向上心もなく、仕事を頑張ってスキルを高めたい、高い評価を得たいという気持ちがありません。「頑張っても仕方がない」という、諦めのような気持ちもあります。
2.責任感がなくすべて他人任せ
「仕事しない人」は仕事への責任感がなく、最低限の仕事で給与をもらえばいいと考えています。少しでも責任を伴うことは避けたいと思い、自分から仕事をしようとしないのが特徴です。
仕事は与えられるものと考え、主体的に取り組みません。自分で判断せず、決めるのはすべて他人任せです。礼儀やマナーを守らないことも多く、挨拶も満足に返さない場合があるでしょう。
3.会社に貢献する気持ちがない
よく働く人は会社のビジョンを理解し、目標を共有して少しでも会社に貢献しようという意識があります。「仕事しない人」には、会社に貢献するという気持ちがありません。
どこで働いても同じだと考え、通勤するのは給与を得るためだけと考えています。自分の意に沿わないことがあればすぐに会社を辞めようと考えているため、積極的に仕事をこなそうという気持ちがありません。
4.仕事ができないと思っている
「仕事しない人」のなかには、自分に自信がなく、仕事ができないと思い込んでいる人もいます。過去にミスした経験があり、また失敗することを恐れて仕事をしようとしないのです。
自分は会社から期待されていないと思い、仕事をする気になれない場合もあります。重要な仕事を与えられていない場合、仕事内容に不満があるため仕事をしないということもあるでしょう。