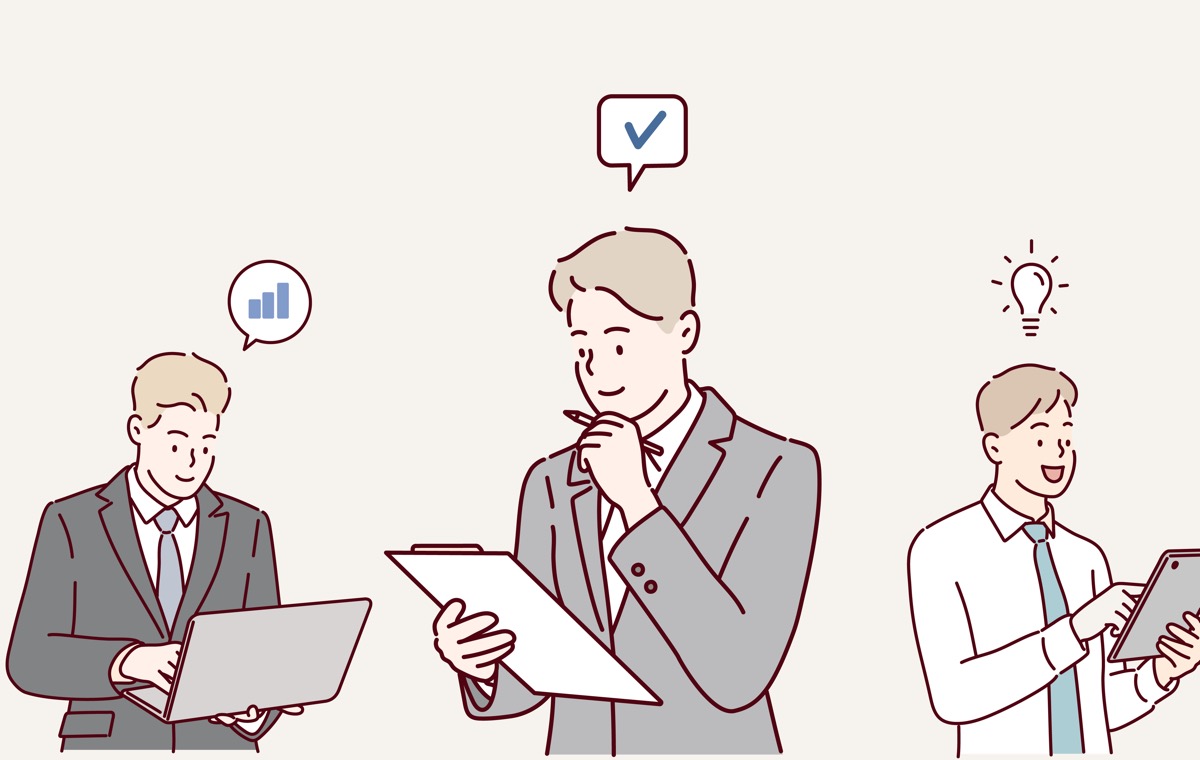Contents
ビジネスの最前線で成功を収める人々には、ある共通点があります。それは、ただ知識を詰め込むだけではなく、実際の現場で生まれたリアルな経験から深く学び、次のステップへと活かしていること。ケーススタディは、その道しるべとなるものです。日常のビジネスシーンで、どのようにこの「学びの宝箱」を開いていくのか…。この記事を通じて「ケーススタディ」を学びながら、一緒に探求してみませんか?
ケーススタディとは過去の事例から学ぶこと
ケーススタディとは具体的事例を分析し、問題解決のための原理を導き出す手法のこと。ビジネスでは新入社員の研修などで行われることが多く、医療や看護、教育の分野でも活用されています。
ケーススタディは、問題解決に向けた能力や洞察力が養えるなど、得られるメリットがいくつもあります。

(c) Adobe Stock
問題解決力を養える
ケーススタディでは、理論を学ぶだけでは得られない問題解決力を養うことができます。現場での経験を通じて問題解決力を培うこともできますが、その経験は環境によって異なり、すべての人が同じ機会を得られるわけではありません。
しかし、ケーススタディを活用すれば、自分自身では経験できない状況についても学ぶことができ、効率的にビジネススキルを向上させることができます。不測の事態が発生した際にも、適切に対応する力を身につけることができるでしょう。
また、ケーススタディは問題を解決する能力だけでなく、解決に至る過程で分析力や論理的思考力、洞察力なども学ぶことができます。
ケーススタディ3つの場面
ケーススタディは、ビジネス、医療、教育などさまざまな分野で活用され、いずれも事例を通じて問題解決能力や洞察力を養う方法です。それぞれの分野での具体的な取り組みを見てみましょう。
ビジネスにおけるケーススタディ
ビジネスにおけるケーススタディは、主に新人研修やリーダー・管理職の研修の場で行われます。実務経験の浅い新入社員は、実際の事例を学んで対応力を身につける必要がありますね。一方、新しくリーダーや管理職に就いた際は、ケーススタディにより、今後直面するかもしれない問題に対する解決能力を養うことができます。
リスクを回避し、解決を早めるためのアイデアを出す能力など、ビジネスにおいて必要とされる能力を養うことができるでしょう。
医療や看護におけるケーススタディ
医療や看護の現場では、医師や看護師などが集まり、実際の症例に対してケーススタディを行うことが少なくありません。目的は、患者のニーズを的確に把握し、ケアする能力を養うこと。同じ治療をした患者でも回復が異なるのはなぜかなど、複数の症例を比較するケーススタディが行われます。
実際の事例を学ぶことで、患者ごとに適切な対応ができる能力を養うことができるでしょう。また、看護の現場ではテーマごとに実際の症例に対する仮説を立て、検証をするケーススタディが行われます。
教育におけるケーススタディ
教育現場では、教職員と管理職に対するケーススタディが行われます。教職員に対して行うのは、授業や生徒への指導について実際の事例から学び、適切な対応力を身につける方法です。
管理職におけるケーススタディでは、学内で起きたトラブルや事故などへの対応や解決方法、再発防止に向けた対策などを具体的な事例を通して学びます。

(c) Adobe Stock
ケーススタディを用いるメリット
職場でケーススタディを用いると、どのようなメリットがあるのでしょうか? メリットを知って、実際の現場でも役立ててみてください。
問題解決力の強化
ケーススタディは実際の事例に基づいているため、理論だけでは学べないリアルな問題解決スキルを養えます。現実的な課題に対する具体的な対策や戦略を学ぶことで、実務に直結した能力が身につけることができるのは、大きなメリットです。
洞察力の向上
さまざまな視点から事例を分析することで、より深く理解でき、新しい発見も得られます。異なる要因や背景を考慮することで、複雑な状況をより正確に把握する洞察力が身につくでしょう。
論理的思考の育成
結論に至るまでのプロセスを詳しく分析することで、論理的な思考力が自然と育まれます。問題解決のために因果関係を考慮し、論理を組み立てる練習を通じて、説得力のある意見を構築する力が養われるでしょう。
ケーススタディ3つの方法
ケーススタディには、3つの方法があります。ケーススタディを行う際には、まず事例を決めて問題を明らかにし、解決策を導き出します。この手順を繰り返すことで、より深い理解が得られるでしょう。それでは、具体的な方法を以下に紹介していきます。
事例を決めて問題を作る
研修などでケーススタディを受ける場合は、すでに事例が用意されていることが多いでしょう。しかし自分で行う場合は、まず事例を決めることから始めます。
会社で実際に起こった事例や関連書籍、ネット検索などを利用して、事例を探してみましょう。偏りがないよう、さまざまな事例を収集することが、幅広い問題解決能力を養うコツです。集めた事例は内容ごとに整理しておくと、あとからでも探しやすくなりますよ。