「かしこまりました」は謙譲語、「承知しました」は丁寧語で、敬意の度合いが異なります。
Summary
- 「かしこまりました」は謙譲語、「承知しました」は丁寧語で、敬意の度合いが異なります。
- 上司や取引先には「かしこまりました」がよりフォーマルでおすすめです。
- 「承知しました」は事務的な返答や社内のやり取りで便利に使えます。
Contents
ビジネスシーンでよく耳にする「かしこまりました」と「承知しました」。どちらも丁寧な返答に感じられますが、実は、使用する状況や相手によって選び方に細やかな違いが求められます。
本記事では、それぞれの意味や背景を解説するとともに、シーン別の正しい使い分け方、注意すべき表記ルールまでを分かりやすく紹介します。大人の品格が伝わる「ワンランク上」の敬語を身につけましょう。
「かしこまりました」と「承知しました」の違いとは?
まずは、「かしこまりました」と「承知しました」、それぞれの意味と成り立ちを理解しましょう。ここが分かると、使い分けは驚くほど簡単になります。
「かしこまりました」の意味と語源
「かしこまりました」は、相手への深い敬意や、「謹んでお受けします」という気持ちを表現する謙譲語です。「かしこまる(恐れ敬う)」という言葉が語源で、もともと身分や立場の高い相手の前で、謹んで命令や指示を受け入れる態度を示す言葉です。古来、武家社会や宮中などで用いられてきた歴史があり、相手を立て、自分をへりくだるニュアンスが含まれます。
例えるなら、相手を主役にするスポットライトのような言葉です。お客様や社長、取引先の重役など、特に敬意を払うべき相手に使うことで、あなたの誠実な姿勢が伝わります。
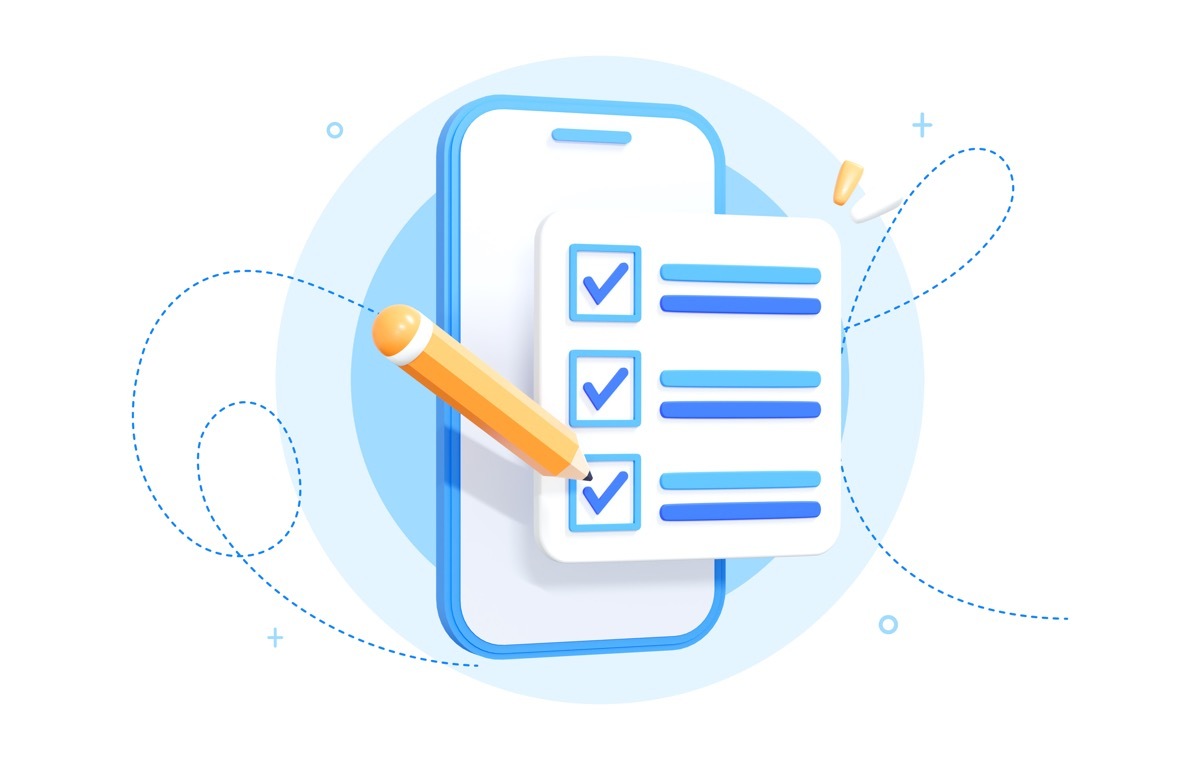
(c) Adobe Stock
「承知しました」の意味と成り立ち
「承知しました」は、「事情や依頼内容を理解し、受け入れました」という事実を伝える丁寧語です。「かしこまりました」ほどのへりくだったニュアンスはなく、指示や連絡を的確に受け止めたことを示す、実務的な響きがあります。
こちらは、タスクを確実に受け取ったことを示す「受領印」のようなイメージです。社内の上司や同僚とのやり取りで、内容を正確に伝えたい場面で使うと、スムーズな連携が生まれます。
二つの敬語が似て非なる理由
どちらも丁重な印象ですが、「かしこまりました」は相手への謙譲と、指示を謹んでお受けする姿勢をより強調する言い方です。一方で「承知しました」は、事務的な了解・認識を伝える返答としてやや中立的です。敬意の度合いや、上下関係の明確さに違いが出ます。TPOや相手との関係性を見極め、適切に使い分けることがビジネスパーソンには求められます。

シーン別に使い分ける|「この場面ではどちらを使うべき?」
上司との会話、社外とのメール、社内での口頭連絡など、状況ごとの適切な言い回しを知ることで、相手との関係性をより円滑に保つことができるようになります。
上司・目上の人への返答で迷ったときは?
職場で上司や取引先など、目上の方に対する返答の場合、「かしこまりました」はより敬意が伝わるため、初回のやりとりや重要な場面で特におすすめです。初対面やフォーマルな会議の場面でも、相手の立場を尊重する印象が残ります。
一方、「承知しました」も十分に丁寧ですが、場合によってはやや控えめで、無難な印象にとどまることも。相手やその場の空気感を読み、どちらを選ぶかを考えましょう。
ビジネスメールで適切な敬語を選ぶには?
ビジネスメールでは、内容や相手により使い分けが求められます。業務連絡や進捗報告など淡々とした事務連絡には「承知しました」が相性抜群です。一方、依頼や指示・確認事項への返信など、相手への敬意を示したいときは「かしこまりました」を使うと、より礼儀正しさが伝わります。

(c) Adobe Stock
社内・社外での使い分けのポイント
社内の同僚・部下への連絡には「承知しました」が簡潔で分かりやすい一方、社外の取引先や顧客に対しては「かしこまりました」といったワンランク上の敬語が推奨されます。

敬意が必要な場面では「かしこまりました」を選びましょう。
「いたしました」と「致しました」の違いも整理しよう
ここでは、「いたしました」と「致しました」の使い分けに迷わないための判断基準や、ビジネス文書における注意点を解説していきます。
「いたしました」と「致しました」、どちらが正しい?
「承知致しました」と漢字で書くべきか、それともひらがなにすべきか迷ったことはありませんか? 結論から言うと、「いたしました」とひらがなで書くのが一般的です。これは、「いたす」が「する」の謙譲語として動詞を補助する「補助動詞」として使われているためです。公用文では「補助動詞はひらがなで書く」というルールがあり、ビジネス文書でもそれに倣うのが通例です。
漢字の「致す」には「その事が原因で、ある結果を引き起こす」といった本来の意味があり、少し硬い印象を与えます。例えば「私の不徳の致すところです」のように使いますよ。「~してください」の「ください」と同じ感覚で、「~いたしました」もひらがな、と覚えておくと便利ですよ。ただし、漢字表記でも誤りとは言い切れません。







