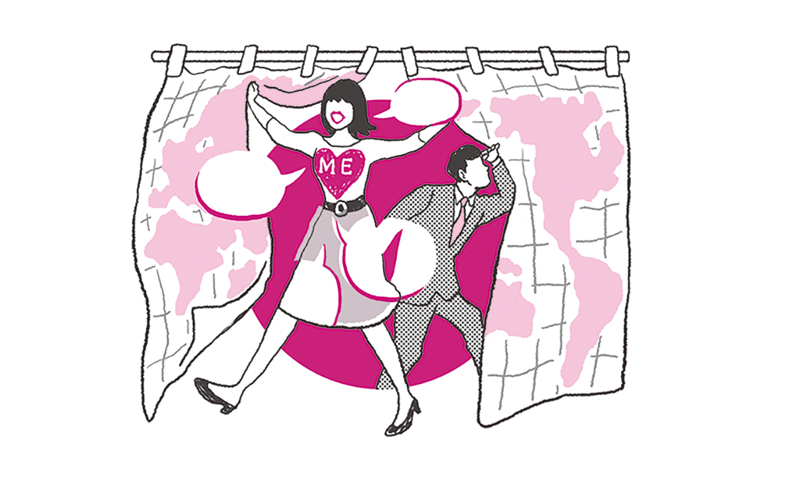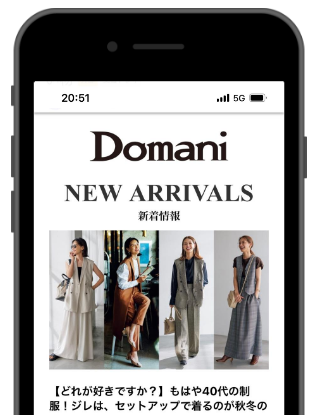女性の身体は、その人自身のもの。セクハラに声を上げ始めた世界。
アメリカの連邦最高裁判事候補に指名されたブレット・カバノー氏に対し、複数の告発があがりました。青年期のカバノー氏は日頃から女性をモノとして見る言動が多く、パーティーで酒やドラッグを用いて女性の意識を混濁させ、性暴力を行うなどの行為に加わっていたというのです。アメリカ政界は、共和党と民主党に分かれて判事任命の可否を激しく争い、メディアもこの話題でもちきりに。ただ、この一件が焙り出したのは、一判事の任命を超えた大きな問題だったと思っています。
余裕のある家庭の子たちが一軒の家でパーティーをする。アメリカではよくある風景で、ドラマのシーンでも描かれます。未成年なのにアルコールを飲んだり、違法ドラッグを試したり。本来、こうした集まりは出会いを求める同年代の若者が、男女ともに対等な立場で付き合うグループ交流だったはずです。しかし、そこでしばしば起きたのは、男子集団による計画的な女性への暴行でした。
カバノー氏が行ったとされる行為は、当時、訴えられもせず法で裁かれなかった犯罪です。共和党の男性たちはそれを「悪ふざけ」「若気の至り」として弁護し、あるいは「いわれなき濡れ衣」だと非難し返していました。明らかに犯罪行為であることを悪ふざけだとするのは、あまりに被害者の心情を無視した主張です。
問題は、そのようなことをする男性が連続殺人犯でもなく、ときに社会的に高い地位を有し、社会的な倫理観を打ち出したりしていることです。カバノー氏は中絶に反対する倫理主義者でした。政界、法曹界、経済界、メディアにもそうした男性が潜んでいます。さすがに、若いころと違い失うものが多い彼らは致命的な犯行には及ばないかもしれない。性欲や支配欲がほかのところで満たされていれば、弱い女性を標的にする必要もないかもしれない。けれども、地位ある成功者のなかに女性を軽く見る人間が一定数いるのです。
悔しいのは、被害に遭った女性たちが素敵な男の子と出会いたくておしゃれをしてうきうきと出かけたであろうこと。しかし、加害者にとってはそんな女性たちは自らの優位性を確認するためのモノでしかなかったわけです。そして、社会はパーティーにおめかしをして出かけていった被害者に対して、ときに残酷です。
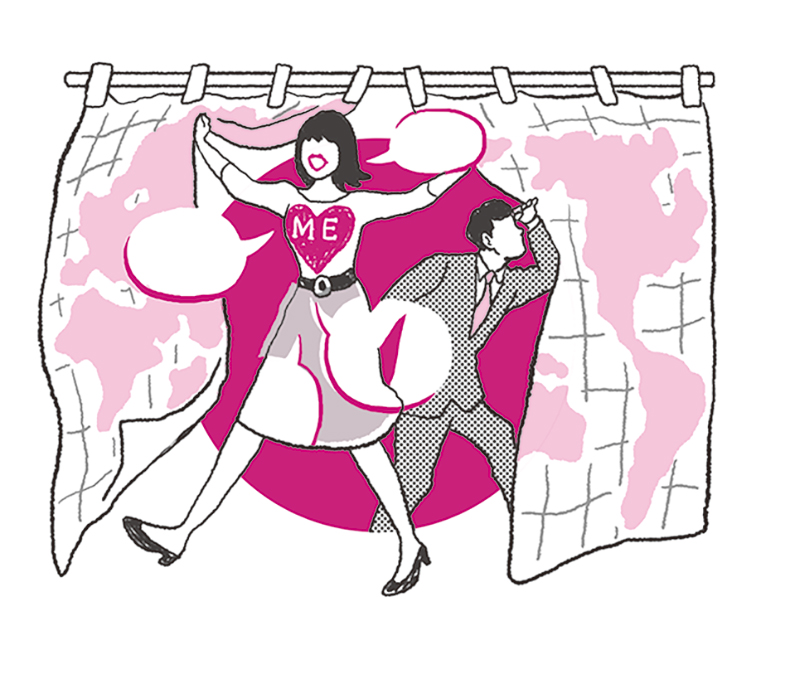
イラスト/本田佳世
世界各国の動きは?
現在、アメリカではふたつの大きな潮流がぶつかり合っています。ひとつは、#MeTooの波。女性の権利がかつてないほど注目されています。もうひとつは、それに抗う形で台頭してきた保守の波。その結果、ダブル・スタンダードが蔓延しています。何せ、トランプ大統領自身が数々のセクハラや暴行疑惑で告発されているほど。ただし、保守の揺り戻しがあるのは、少数者にも声が与えられる政治の世界だから。ビジネスの場では、大手であればあるほど訴訟リスクに敏感です。その結果、ポリティカル・コレクトネスから取り締まりや可罰性へと議論は進展してきています。日本がセクハラの明確な基準を定義できておらず、セクハラ問題が総じて権力バッシングの一環としてしか注目されないのと比べると対照的です。
日本と同様、アジアの諸国はたとえ民主主義でも、女性差別への対処に遅れが見られます。インドでは性暴力が多発し、韓国では、部下に対する性的暴行の罪に問われ、自らその過ちを認めた安熙正・前忠清南道知事に証拠不十分で無罪判決が出ました。思えば、私たちの社会は、女性がモノのように売られ、妻の不貞行為だけが処罰される時代、父親や夫の命令に従わなければならなかった時代からずいぶん遠くまで来ました。先進国では、数十年前の起訴されなかった暴行が政治上の論点になるほどにまで女性運動が躍進しています。しかし、周りを見渡せば、女性の主体性が確保されたとまでは言えない。
女性の身体はその人自身のものであり、何者にも従属する必要はない、ということ。権力を用いて性的な行為をすることは暴力であるということ。日本を含めた先進国は、こんな当たり前の認識の、ようやく入り口に立ったところなのです。

『あなたに伝えたい政治の話』/¥800 文藝春秋なぜ〝安倍一強〟時代は続くのか? グローバル化のなか、日本政治が直面する真の課題とは? 気鋭の国際政治学者・三浦さんが鮮やかに斬る最新刊。

国際政治学者
三浦瑠麗
1980年生まれ。国際政治学者。東京大学農学部卒業。東大公共政策大学院修了。東大大学院法学政治学研究科修了。法学博士。現在は、東京大学政策ビジョン研究センター講師、青山学院大学兼任講師を務める傍ら、メディア出演多数。気鋭の論客として注目される。
Domani2018年12月号『新・Domaniジャーナル 「優しさで読み解く国際政治」』より
本誌撮影時スタッフ: 撮影/五十嵐美弥 構成/佐藤久美子