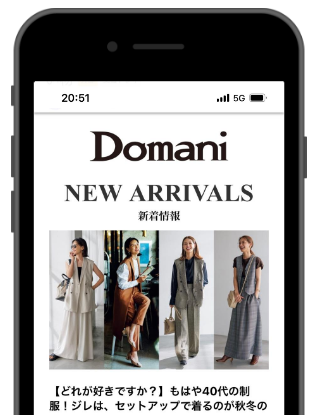手術前に1歳の長男の預け先探しに疲れ果て
10月下旬だというのに、連絡先を書き出したB5大の紙の上に、吉田さんの顔から脂汗がぽたぽたと滴り落ちた。丸テーブルが4つ置かれた病院の談話室。吉田さんは洗面台に腰を押しつけ、陣痛に近いような下腹の激痛をこらえながら、スマホを握りしめていた。2018年のことだ。
痛みの原因は、卵巣腫瘍の茎捻転(けいねんてん。卵巣が腫れて肥大したために、子宮との連結部がねじれて血流が停滞する疾患)。1歳の長男による、吉田さんの下腹への頭突きが原因だが、それまで痛みは少しもなかった。
茎捻転の痛みで受診したら、卵巣に悪性腫瘍の疑いがあるとわかり、手術が決まったその日から入院していた。卵巣腫瘍は症状が進行しないと自覚症状がないから、がんの早期発見という点では不幸中の幸いと言える。
吉田さんは9月に、キャリアカウンセラーとして独立開業した矢先だった。
入院後の彼女の最優先課題は、手術後から退院まで2週間の長男の預け先探し。夫はシフト勤務のバス運転手で、そう簡単には休みはとれない。
病院の冒頭の談話室から市役所に電話をすると、事務的な口調で言われた。
「まずは、自分で(関連部署を)探して、電話してみてください」
吉田さんはファミリーサポート制度や、里親制度の子ども一時預かりサービスなどを調べて、電話をかけ続けた。だが、何度もたらい回しされた挙句に成果はゼロ。彼女が暮らす神奈川県の市レベルでも、民間でさえ約2週間の、突発的な幼児預かりサービスは見当たらなかった。
翌日、彼女は市役所に再び電話してその結果を伝えると、「電話で話されてもわからないです。窓口まで来てください」と言われた。手術2日前の彼女はカッとなって「もういいです!」と電話を切ると、心が折れそうになった。
結局、夫が2週間休職して、長男の面倒を見ることになった。業務上、夫の同僚にも迷惑をかけることになり、心苦しかったという。
「迷惑をかける」という言葉をなくしたい
開腹手術で悪性腫瘍とわかり、吉田さんは再発リスクを下げるために、卵巣と子宮を全摘出。退院して自宅に戻ると夫は職場復帰した。彼女は3歳の長女を保育園に送り出し、長男をあやしながら家事を少しずつ再開した。

術後5カ月、保育園が決まったころの吉田さん(写真:吉田さん提供)
「本当は子どもがかわいくて仕方ない時期ですが、術後の痛みと体力のない状態での育児と家事は、本当につらかったです。元気な子どもに振り回された挙句に疲れ果てて、トイレに1人で閉じこもったりしていました」(吉田さん)
翌年2月、長男の保育園入りが決まる。術後の痛みも軽くなり、日中に自分1人の時間ができると、彼女には社会への強い違和感が膨らんだ。
「共働きの私ががんになっても、地域社会には支えてくれる仕組みがなかった。厳しい現実を思い知らされ、こんな社会は絶対に時代遅れだって……」
出産や病気、親の介護は、多くの社会人が経験するライフイベント。一方で、少子高齢化が進む日本は労働人口の減少に歯止めがかからない。病気や、老親の介護の度に社員が「迷惑をかける」と辞めていくと、会社も回らない。
「男女を問わず、仕事とライフイベントを普通に両立できる社会になる必要がありますよね。そのためには、『職場に迷惑をかける』という考え方自体を社会からなくしたい、そう強く思うようになりました」
同時に、彼女には苦い記憶がよみがえった。以前勤めていた会社の人事部時代に、がんを理由に退職を申し出た50代の男性社員のことだったという。
「当時の私は、『本人に非はなくても、がんになると会社にも迷惑をかけるし、自分から辞めることになるのか』と思いました。残念だけど、がんだから仕方ないのかもなぁ、と。でも、今振り返ると、あのときの私の考え方も、人事部としての対応も完全に間違っていました」
吉田さんは自身の経験をふまえ、企業を対象にがん教育を行う一方、各専門家と連携しながら、がんになった人と企業のニーズをつないで継続就労を支援する、一般社団法人「がんと働く応援団」の設立に向けて動き出した。
彼女がキャリアカウンセラーを目指した理由
そもそも、吉田さんはイベント会社や、自動車部品関連会社の人事畑を歩み、不動産ベンチャーで働きながら、国家資格2級のキャリアコンサルティング技能士を取得した。

「がんと働く応援団」の新年会の様子(写真:吉田さん提供)
「天真らんまんで、職場のムードメーカー。高齢のお客様に親身に接客できる彼女のおかげで、成約した事例もありました」(勤め先の不動産ベンチャーの元社長)
親身になれる力は、「がんと働く応援団」の副理事として、吉田さんを支える乳がん経験者の野北まどかさんも口をそろえる。
「彼女の趣味は人間観察で、相手の話を身を乗り出して聴ける人。そんな興味津々で話を聞いてもらえたら、誰だってうれしくなりますよ」
吉田さんがキャリアカウンセラーを志した理由は、彼女の両親の働き方にある。出版社勤務の厳格な父親は仕事中毒タイプ。一方の母親はポルトガル語が堪能で、同時通訳として活躍しつつ、育児も両立しようと懸命だった。
「2人とも一生懸命働いているせいで、家族だんらんの時間はとても少なかったと思います」(吉田さん)
両親の働き方への違和感が、幼い頃から彼女の心には積み重なっていった。
「ですから、『働く人と企業が<win—win>の関係になれる助けになりたい』という気持ちが、以前から漠然としてありました。結果、自分らしい働き方ができる手助けをするキャリアカウンセラーという仕事に、自然と憧れを抱くようになったんです」(吉田さん)
改めて、彼女が手術前に長男の預け先を見つけられなかったことを考える。彼女の母親の頃と比べて、女性の社会進出は飛躍的に進んだ。しかし、共働き女性の労働環境は、約30年前とどれほど変わったのか。
経験者が情報を発信して世の中を変えていく
「そうかぁ、よく頑張ってきたねぇ」
初参加の女性が、がん発症後の試行錯誤を話し終えると、吉田さんは穏やかな声でそうねぎらった。6月下旬にZoom上で行われた、がん経験者が集うオンラインサロンでのこと。「がんと働く応援団」主催の企画だ。
参加者は女性7人、男性3人。年齢やがんの種類はさまざまだ。がんは男女ともに60歳代から増加し、高齢になるほど死亡率は高い。病院での外来診療や、がんの部位ごとに集まる患者会に参加しても、20代から40代の人は少数派。同年代の患者に会える機会は少なく、孤独感に苦しむことが多い。

HP上で個別相談も受けている(写真提供:吉田さん)
当日も幼い頃に白血病を発症。その合併症として今もネフローゼ(排尿時に尿中に大量のタンパクが漏れ出て、血液中のタンパクが減少して体がむくむ)を患う女性が、同じ合併症を患った男性参加者の話を聞き、「自分と同じ病気になった方と話すのは初めてで、うれしい気持ちになりました」と語った。その「うれしい」は、今までの心細かった気持ちの裏返しだ。
オンライン上であっても、経験者同士がつながることで孤独感を和らげたり、有益な情報を共有したりすることが、明日を生きる力につながる。
Zoomに参加した別の男性が、抗がん剤の副作用で頭髪が抜けるようになると、当時の上司から、「しんどくても、しんどくないようにしとけよ」と言われたと語った。
ところが、吉田さんは彼には一転して、「がんについて知らない人が、何を言っても仕方がないと私は思います」と切り出し、こう続けた。
「むしろ、そんな心ないことを平気で言える人が時代遅れになるように、私たちが情報発信を根気強く続けて、世の中を変えていくしかないんですよ」
彼女は、発言した男性とは顔見知りで、彼の発言を否定する意図は少しもなかった。あえてデリカシーを欠いた言葉を肯定することで、当日が初参加の人にも、「血も涙もない発言に傷つけられる経験者」から「言うべきことは言う経験者」への発想転換を、暗に促していた。
そう言えば、前出の野北さんが、「外見は小柄でかわいらしいんですけど、吉田の辞書には『仕方ない』という文字がないんですよ」と、苦笑しながら話していたことを思い出した。
「自分の役割」を果たしたい
取材の終わりに、がんの経験を境に、不要なものを手放す力が強くなりました、と吉田さんは小さく笑いながら言った。もともと、物欲や出世欲はない。
がんの再発防止のために両方の卵巣を摘出したことで、彼女は更年期障害に似た体のダルさや、憂鬱に時々苦しめられる。そのときはサボることへの罪悪感を上手に手放そうと、今も練習中だ。
「そこで横になって、スマホでできる事務作業でもやろうと無理をすると、もっとひどい状態に落ち込むんです。自分の体が発する声にあらがえない側の人間になったんだなぁって、つくづく思い知らされますもん」
もう1つ実践したのは人間関係の断捨離。
「1年間に1度は会いたい人か。会うと、私も相手も楽しいかどうかと考えて、自分から出す年賀状を一気に減らしました。自分ができることを続けて、それを認めてくれる人が増えれば、新しい人間関係は自然とできてくるって」
すがすがしい表情で、自身にも言い聞かせるように吉田さんは断言した。自分の死をきちんと見据えると人生はシンプルになる、と気づいた。
取材後の撮影中、2歳の長男がようやくトイレで用を足せるようになったという。自分が力むとポトンと音がするのが、長男も楽しいらしい。トイレタイムになると、吉田さんにも近くでスタンバイするように要求してくる。
「すべての『ポトン』にうれしそうに反応するだけでなく、私にまでいちいち反応しろってせがむんですよぉ。それに毎回付き合わされて、ようやく終わったと思ったら、今度は4歳の長女が『私のほうがいい音が出せるっ!』と言い出して、2人別々にトイレの前へ連れて行かれるんですよねぇ」
その文字面とは裏腹に、吉田ゆりさんはほくほくした顔で言った。
ルポライター
荒川 龍(あらかわ りゅう)
1963年、大阪府生まれ。『PRESIDENT Online』『潮』『AERA』などで執筆中。著書『レンタルお姉さん』(東洋経済新報社)は2007年にNHKドラマ『スロースタート』の原案となった。ほかの著書に『自分を生きる働き方』(学芸出版社刊)『抱きしめて看取る理由』(ワニブックスPLUS新書)などがある。

東洋経済オンライン
東洋経済オンラインは、独自に取材した経済関連ニュースを中心とした情報配信プラットフォームです。