「覚束ない」とは頼りない様子のこと
「覚束ない(おぼつかない)」とはなんとなく頼りない様子のことを指す言葉です。はっきりとしないときや、ぼんやりとしているとき、また、確実には信用できないときなどに用いることがあります。
また、あまり相手と付き合いがないために様子がわからないときにも使うことがあるようです。そのほかにも、待ち遠しいけれども、自分からは行動を起こせないときも「覚束ない」と表現することができます。
おぼつかない【覚束無い】
形おぼつかな・しク
1. 物事の成り行きが疑わしい。うまくいきそうもない。「昨年並みの収穫は―・い」「今の成績では合格は―・い」
2. はっきりしない。あやふやである。「―・い記憶をたどる」
3. しっかりせず、頼りない。心もとない。「足もとが―・い」「―・い手つき」
4. はっきり見えないで、ぼんやりとしている。
「門上の楼に、―・い灯(ひ)がともって」〈芥川・偸盗〉
5. ようすがはっきりせず、不安である。気がかりだ。
「―・く思ひつめたること、少しはるかさむ」〈伊勢・九五〉
6. 不審である。おかしい。
「やや久しくものも言はでありければ、人ども―・く思ひけるほどに」〈宇治拾遺・一〉
7. 疎遠で相手のようすがわからない。
「かのわたりには、いと―・くて、秋暮れ果てぬ」〈源・末摘花〉
8. 待ち遠しい。もどかしい。
「返り事せずは―・かりなむ」〈堤・虫めづる姫君〉
(引用:小学館『デジタル大辞泉』より)
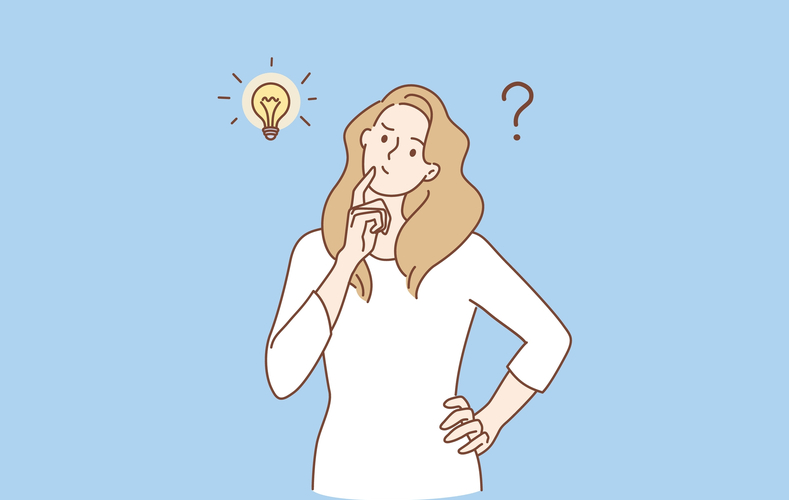
「覚束無い」は当て字!
「覚束無い」という漢字は当て字だといわれています。すべて平仮名で「おぼつかない」と表記されることのほうが多いでしょう。
また「おぼつかない」は形容詞であり、何かが無いことを意味しているのではありません。そのため、「おぼつかある」や「おぼつかだ」などの言葉は存在しません。
「覚束ない」の語源
「おぼつかない」の「おぼ」とは「おぼろげ」と同じで、漠然として明瞭ではない様子を示します。また、「つか」と「ない」はいずれも接尾語で、特に意味はありません。「ない」も打ち消しの意味ではなく、単に形容詞を作るために語尾に付けられた語なので、「おぼ」や「おぼつか」が「無い」わけではないので注意しましょう。
「覚束ない」を例文を使ってご紹介
「覚束ない」とははっきりとしていないときに用いることができる言葉です。感情がはっきりとしていないときや、行動や視線などが定まらないときに用いることができます。加えて、不安で気持ちが落ち着かないときや、言葉や動作などがスムーズに出てこないときなどに、もどかしい感情を表現することができます。
どのように使って良いか迷ったときは、例文からパターンを覚えると使いこなせるようになるでしょう。「覚束ない」を使ったよくあるパターンを4つ挙げ、それぞれの例文を紹介します。ぜひ参考にして使いこなしてください。
覚束ない足取り
「覚束ない足取り」とは、酔っ払ったようにまっすぐに歩けない様子を指す言葉です。必ずしも酔っているとは限りませんが、見ていて不安になるような歩き方をしているときに使うことができるでしょう。いくつか例文を紹介します。
例文
・私はあれから覚束ない足取りで家に帰った。彼に振られたショックで、どう歩いたのか覚えていない
・彼は大丈夫だというけれど、あまりにもお酒を飲んでいたので心配だ。覚束ない足取りで駅のほうに向かっているが、やはりついていったほうがよさそうだ。
覚束ない手つき
「覚束ない手つき」とは、手元がしっかりとしていない様子です。今までスムーズにできていたことができない様子、あるいは今まで一度も経験したことがないためスムーズにできない様子を指します。いくつかの例文から使い方を見ていきましょう。
例文
・祖母は覚束ない手つきで箸を持っている。こぼしそうで不安なのでスプーンを差し出した。
・ケーキのデコレーションは初めてなので、失敗しないか緊張している。覚束ない手つきでクリームの絞り袋を持ち上げた。
覚束ない記憶
まったく忘れているというわけではなくても、不明瞭な状態のときには「覚束ない記憶」と表現することがあります。時間が経って忘れていることや、あまりにも昔の話なので確実とはいえないときに使うことができる言葉です。いくつか例文を紹介します。
例文
・覚束ない記憶に頼って道を探してみた。駄菓子屋があったと思われるところには、それらしき建物は何もなかった。私の記憶違いなのだろうか。
・彼女は元々は兄の恋人だったと思う。覚束ない記憶だから正しいかどうかはわからないけれど。
~覚束ない
「覚束ない」という言葉を文章の最後につけることもできます。また、「覚束ない」を過去形にして「覚束なかった」と表現することもできるでしょう。いくつかの例文を紹介します。
例文
・このままでは就職どころか卒業すら覚束ない。まずは真面目に学校に行くようにして欲しい。
・明日のテストに行けるかどうか覚束ない。テスト範囲を勉強していないだけでなく、体調も思わしくない。
「覚束ない」の類語を例文でご紹介
「覚束ない」の類語としては、「茫々(ぼうぼう)」を挙げることができます。「茫々」とは、ぼんやりとかすんで判然としない様子を表す言葉です。
例文
・茫々とした記憶の中では、彼女はいつも元気に光り輝いている。
・どこまであるのだろうと思うほど広く、茫々たる草原だ。
また、「心許ない(こころもとない)」も「覚束ない」と似た意味の言葉です。なんとなく不安なときに使います。
例文
・彼に仕事を任せたけれども心許ない。大丈夫だろうか。
・娘が心許ない手つきで編み物をしている。
疑わしい気持ちがあるときに用いる「訝しい(いぶかしい)」も、はっきりとしない様子を指すので「覚束ない」と似た意味と考えられます。
例文
・彼は絶対にやり遂げるといったけれども、普段の行動を見ていると訝しく思える。
・彼女の目が泳いでいる.。きっと何か良くないことをしたのだろうが、言動すべてが訝しい。

「覚束ない」の対義語を例文でご紹介
「覚束ない」の反対の意味の言葉として「頼もしい」を挙げることができます。「頼もしい」とは、しっかりしている、信頼できるという意味の言葉です。いくつか例文を紹介します。
例文
・彼女の足取りは頼もしく、この人ならば信頼できると思えた。
・頼もしい発言を聞いて、安心感を覚えた。
まとめ
「覚束ない」という言葉は、日常生活だけでなくビジネスでも使える言葉です。はっきりと覚えていないことを話すときなどには「覚束ない記憶で申し訳ありません」というように一言添えることができるかもしれません。曖昧なことやしっかりとしていないことであれば使用できる便利な言葉なので、意味を正しく理解しておきましょう。

写真・イラスト/(C) Shutterstock.com
メイン・アイキャッチ画像/(C)Adobe Stock
▼あわせて読みたい








