「律儀」の意味や語源、正しい使い方
「あの人は律儀だよね」「彼は律儀な性格だから信用できる」のように、褒め言葉として使われることがある「律儀」。ビジネスシーンでも使われますが、この言葉の正しい意味を知らない人もいるでしょう。
本記事では「律儀」について、意味や使い方、注意点などを紹介します。一緒に見ていきましょう。
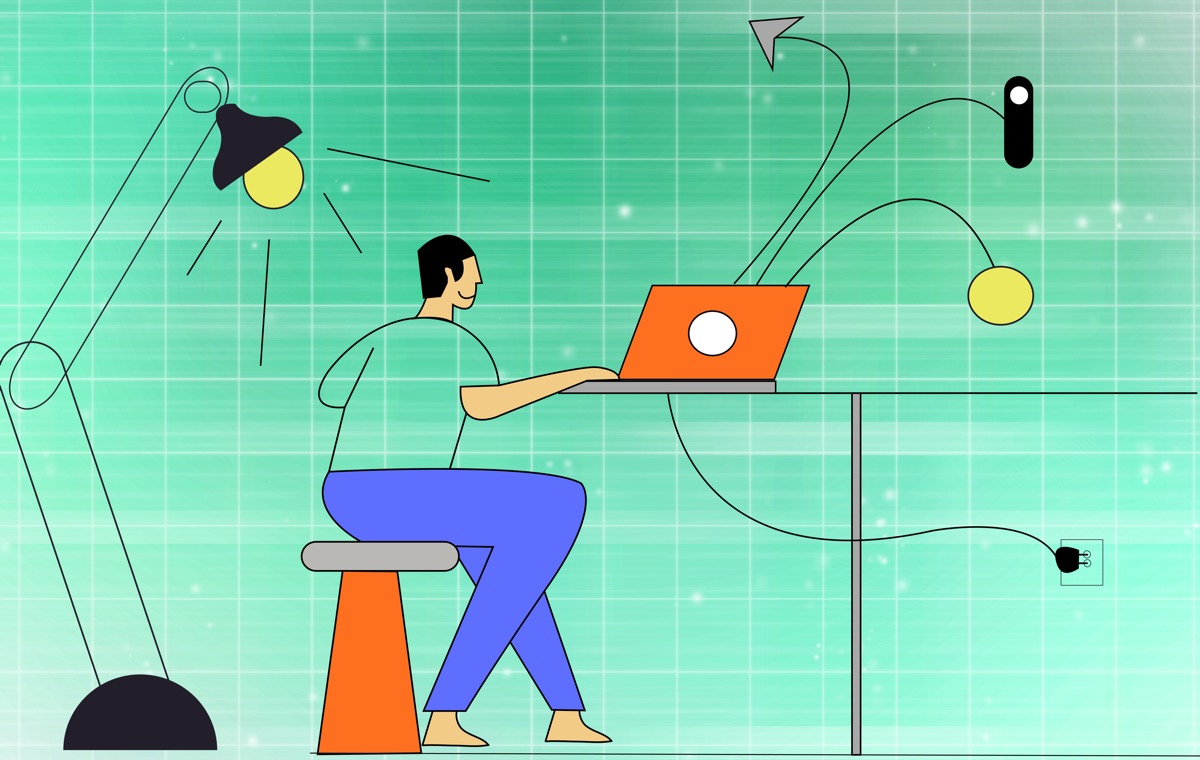
(c) Adobe Stock
「律儀」の意味は実直、義理堅い
「律儀」の意味は「実直、義理堅いこと」「健康であること」の2つ。よく使われるのは、「実直、義理堅いこと」のほうでしょう。
義理堅いとは、対人関係において誠実であることの意。具体的には、義務や規則を守る、挨拶を欠かさない、待ち合わせに遅れない、約束はどんなに小さなことでも忘れずに果たす、受けた恩には必ず報いる、などが挙げられます。
他人に対する礼儀を忘れず、基本的なルールを遵守する傾向がある人を指すといえるでしょう。
「律儀」の語源は仏法用語
「律儀」の語源は、仏法用語とする説があります。サンスクリット語の「samvara(サンバラ)」を意訳し、「悪や過失に陥ることを防ぐ働きのあるもの」「善行」を表すようになりました。また、善行を行うよう仏が定めた戒(かい:仏道を修める者が守るべき掟のこと)という意味も持ちます。
「律儀」は人を褒める時に使う言葉
「律儀」は、実直な人や義理堅い人を褒める際に用います。「律儀な人だ」は実直な性格の人、あるいは義理堅い性格の人を表す場合に使うことが多いでしょう。
よく使う言い回しには、「律儀に~をする」「律儀な〜」「律儀者」などがあります。
律儀すぎるは褒め言葉ではなくなるので注意!
「律儀」を使う際に注意したいことを見ていきましょう。
とても義理堅い人だと感じたら、「律儀すぎる人だ」と表現したくなるかもしれません。しかし、この使い方をすると、「相手の律儀さが過剰だ」という意味で受け取られることも。相手や状況によっては、注意が必要です。
また、「律儀者の子沢山」ということわざを使う際も、気をつけてください。「律儀な人は品行が正しく、家庭が円満であるため、子供がたくさん生まれる」という意味で、褒め言葉として用いられてきました。
しかし、現代において、出産や子供の話でこの言葉を使うと、相手によっては不快な思いをさせることになるかもしれません。時代とともに価値観は変わるもの。そのことを踏まえ、慎重に言葉を選びたいですね。
「律儀」の意味の使い分け
律儀の意味の使い分けを紹介します。ポジティブな意味とネガティブな意味があります。

(c) Adobe Stock
<ポジティブな意味の場合>
・理想の恋人の条件は、律儀な人だ。
・彼女は律儀な人なので、近くに寄った際は必ず挨拶に来てくれる。
・この前おごった缶コーヒーのお礼をわざわざするなんて、彼はなんて律儀な人だろう。
<ネガティブな意味の場合>
・あの人は律儀だけれど、律儀すぎるところがあって、こちらも気を使わなければいけないから疲れる。
・部長は律儀一点張りな性格だから、少しでもイレギュラーなことは認めないであろう。
「律儀」の漢字と読み方について
「律儀」の漢字と読み方について見ていきましょう。「律儀」と「律義」どちらが正しいのでしょうか?
「律儀」「律義」どちらでも意味合いは一緒
「律儀」の漢字表記には「律儀」と「律義」の2つがあります。「儀」とは、礼法にかなった行いという意味があり、「義」は人としての正しい行動や道を表します。「りちぎ」を漢字で書く場合、どちらを使ってもOK。間違いにはなりません。







