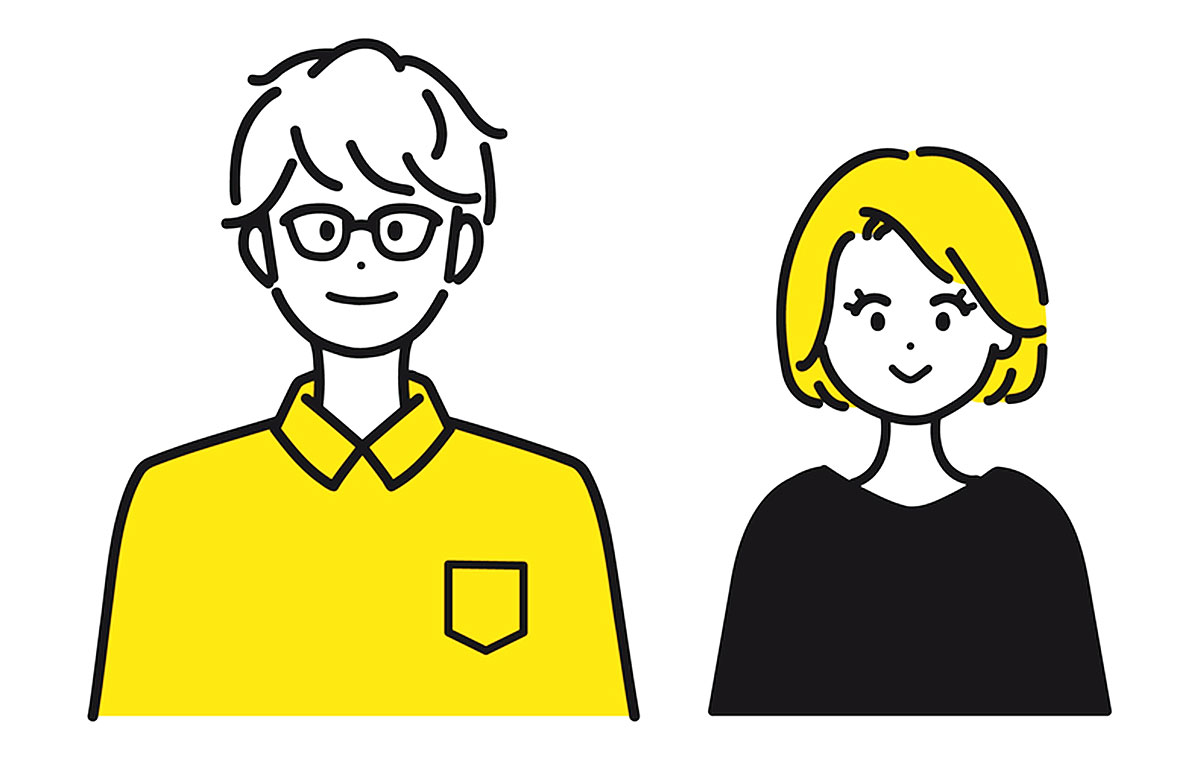「夫」はビジネスなど、どんな場面でも違和感なく使える呼び方です。
Summary
- 一般的に配偶者の呼び方は、「夫」「主人」「旦那」「亭主」の4種類
- ビジネスシーンでも使える「夫」が、どんな場面でも違和感なく使える呼び方といえる
- 「旦那」は妻の配偶者を指すくだけた表現で、「旦那さん」と呼ぶのは他人の夫に対してのみ適切
Contents
旦那?夫?配偶者の呼び方はシチュエーションによって異なる
配偶者の呼び方は、夫婦間で呼ぶ場合と、第三者がいる場合とでは異なるのが一般的です。夫婦間では、結婚しても付き合っている頃と同じようにニックネームで呼び合う家庭も多いのではないでしょうか。
その一方で、第三者がいる場合はニックネームで呼ぶ人の割合は減り、「夫」や「旦那」と呼ぶ人が多い傾向に。呼び方はどのように変化するのか、シチュエーションごとに比較してみましょう。

夫婦間での呼び方
夫婦間の場合は結婚前の呼び方をそのまま使用していることが多く、名前の後ろに「くん」や「さん」をつけて呼んだり、ニックネームやあだ名で呼ぶ人も少なくないでしょう。子どもがいる家庭では、「パパ」や「お父さん」と呼ぶ場合もよくあります。また、昔のドラマでよく使われていた「あなた」は、極少数派のようです。
第三者がいるときの呼び方
夫婦間での呼び方とは異なり、第三者がいる場合は「夫」がよく使われる呼び方です。人によって配偶者の呼び方に無頓着な場合はあるものの、夫婦間での呼び方とは使い分けることが多いといえるでしょう。「旦那」や「旦那さん」と呼ぶ人も多いですが、似たような表現である「主人」と呼ぶ人は、比較的少ないようです。
そのほか少数派の意見には、名字や名前、「パパ」「お父さん」「相方」「つれ」などがあります。近年、「夫さん」という呼び方も増えてきています。
呼び方の意味や使い分けのマナー
配偶者の呼び方で一般的なものは、夫・主人・旦那・亭主の4種類。それぞれニュアンスが異なるため、シチュエーションによって使い分ける必要があります。ここでは、呼び方の意味や使い分けの注意点を解説します。

「夫」とは配偶者である男性のこと
夫とは配偶者である男性、または成人した男性という意味を持つ言葉です。公的な文書では男性配偶者のことを「夫」と表記することから、配偶者を示す言葉としては最もメジャーであるといえるでしょう。また、近年は女性の社会進出をきっかけに、配偶者の呼び方にも変化が現れています。ジェンダー平等の観点からの見直しや、女性も家計を担うことで、「主人」という呼び名はふさわしくないと判断される機会が増えたのです。その流れもあり、配偶者のことを「夫」と呼ぶ女性が増加傾向であるといわれています。
使い分けのマナーとして、ビジネスシーンでは「夫」を使用するのが一般的です。いちばんスタンダードな呼び方であり、どんな場面でも違和感なく使える呼び方といえます。ほかにSNSなどで複数人とやり取りする場合にも、夫を使用するのが無難です。
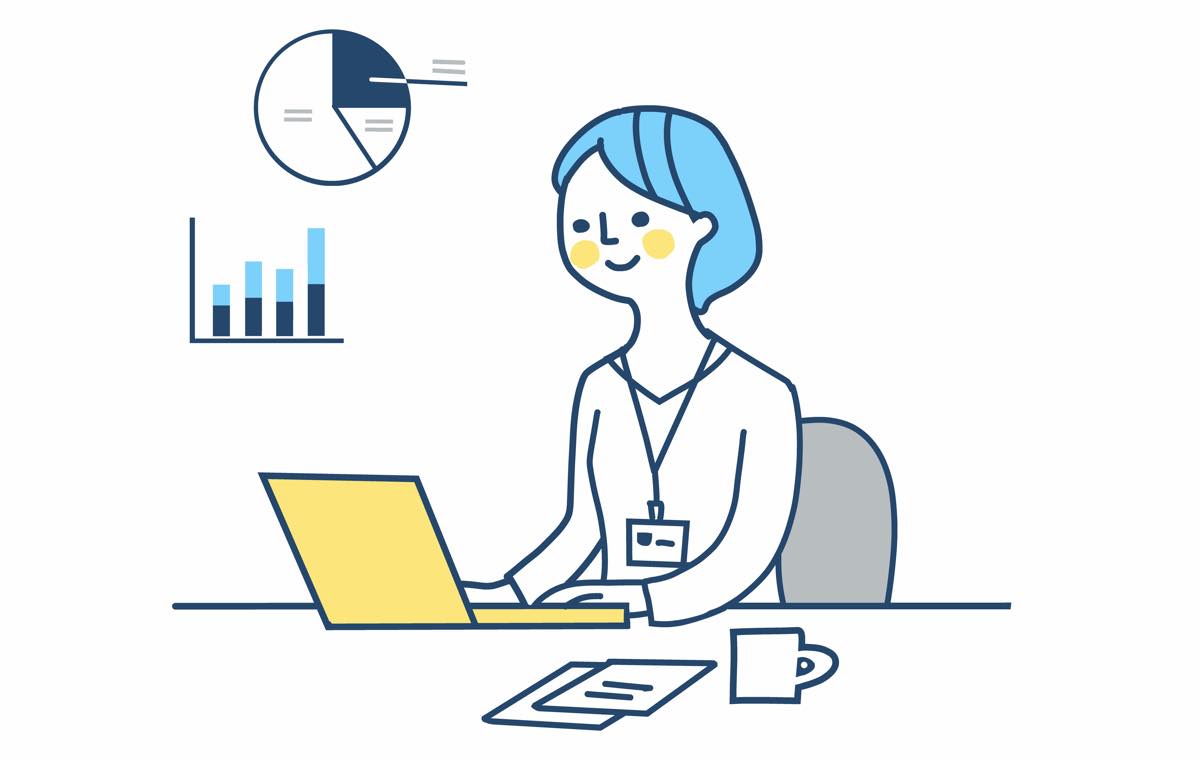
「主人」とは妻が自分の配偶者を指す言葉
主人とは一家の主、自分が仕える人といった意味を持ち、妻が自分の配偶者を呼ぶときに使用される言葉です。先に述べたように、現代では主従関係を表す「主人」という呼び名はふさわしくないとして、使用を避ける傾向にあります。
しかし、会社の上司や目上の人と話すときにはほかに代用できる言葉がないため、主従関係を示す言葉であってもそのまま使用し続けているというケースも珍しくありません。ちなみに他人の配偶者に対して使う場合は「主人」ではなく「ご主人」と表現するのが一般的です。また、主人と似ている言葉であるものの、基本的に「夫」は他人の配偶者には使用されません。
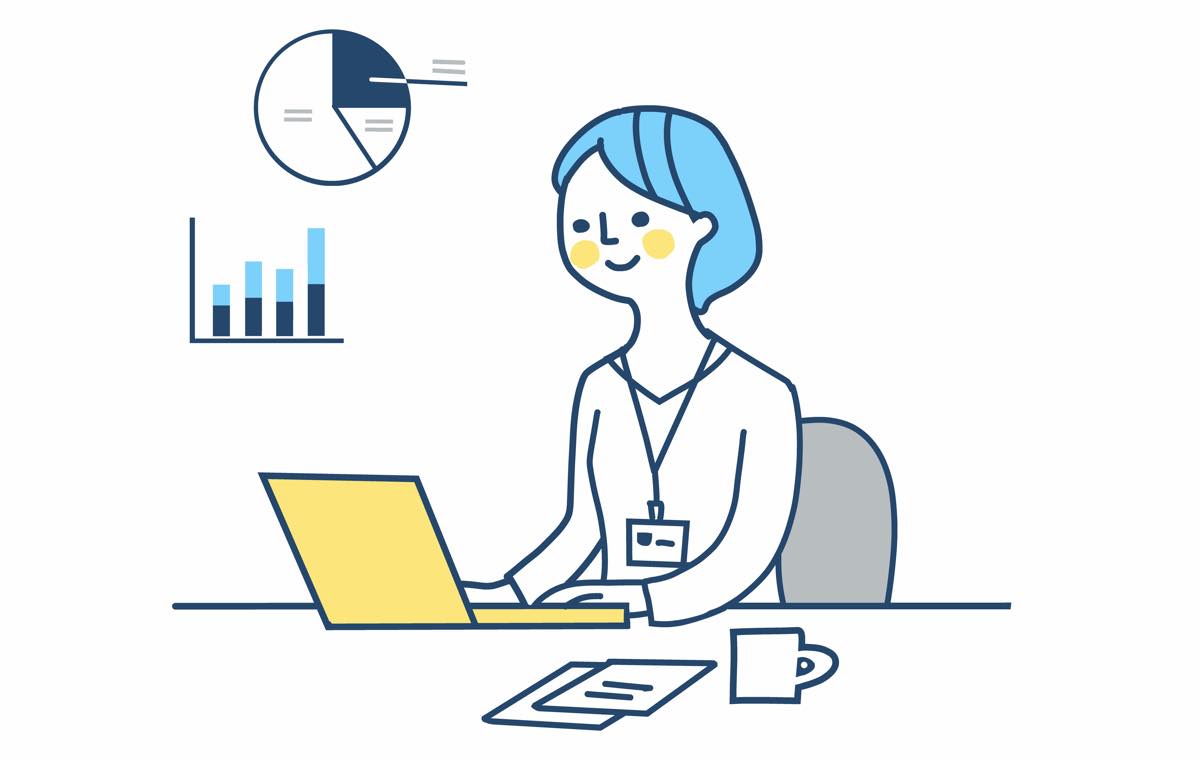
「主人」という呼び方は主従関係を表すため避ける傾向に。他人の配偶者に対して使う場合は「ご主人」表現しましょう。
「旦那」とは配偶者のくだけた表現
旦那とは妻の配偶者を指す言葉で、もともとはお布施をする人、檀家という意味を持つ言葉です。本来は敬意を込めた言葉として使用されていましたが、現在は妻の配偶者をくだけた表現で呼ぶ際に使用されます。そのためビジネスシーンや目上の人と話す場合は、旦那と呼ぶのは避けたほうがよいでしょう。そして「主人」と同様に主従関係を表す言葉であることから、使用を避ける場面も増えています。
また、旦那に「さん」をつけて呼ぶ女性は珍しくありませんが、本来旦那に「さん」をつけて呼ぶのは他人の夫に対して使うときのみです。自分の夫に「さん」をつけて呼ぶと身内に敬称を使用していることになるため、基本的には他人の夫に対して使うときのみ「さん」をつけます。
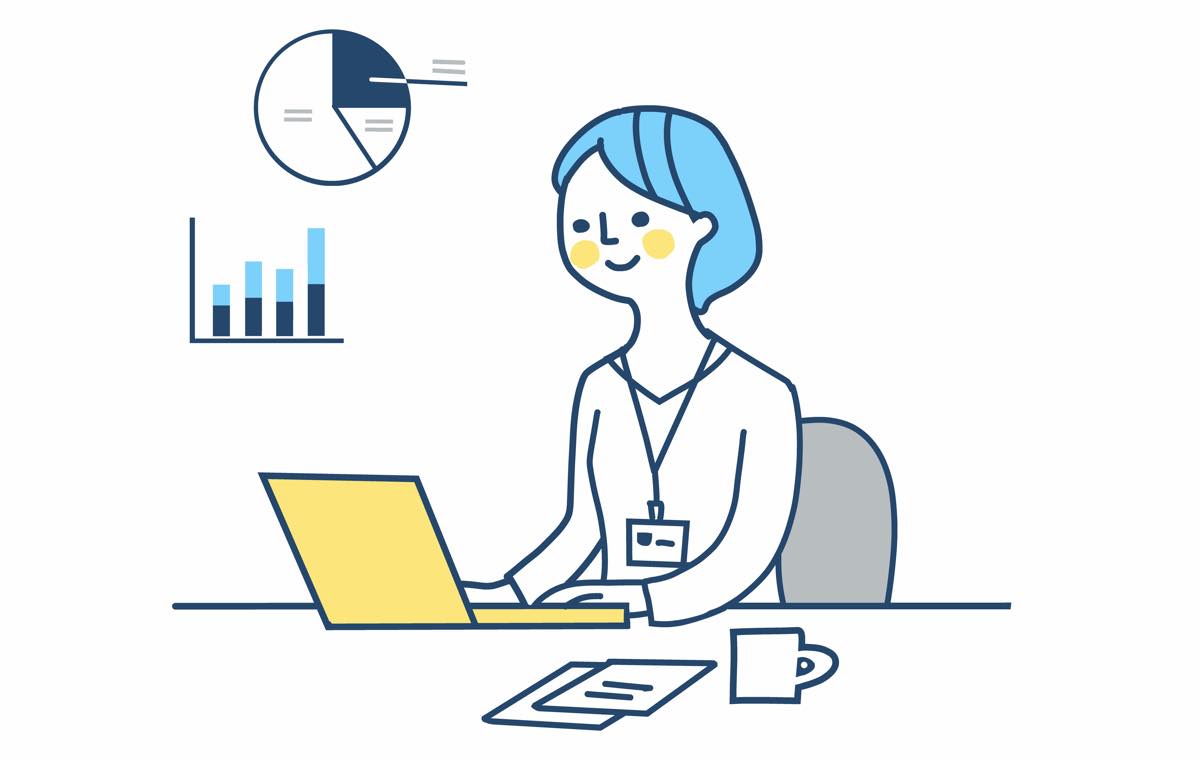
「旦那」は、くだけた表現の呼び方のため、ビジネスシーンや目上の人と話す場合に使うのは避けたほうがよいでしょう。