「砂上の楼閣」という言葉、実際にどう使うか知っていますか? 見た目は立派でも基盤が不安定なものを指し、実際には長続きしないことを意味します。ビジネスでは、実現不可能な計画などのたとえとして、使うことができるので覚えておきたいですね。この記事では、意味や使い方、由来、類語、対義語も解説します。
「砂上の楼閣」の2つの意味
「砂上の楼閣」には、「見かけ倒し」と「実現不可能」の2つの意味があります。ここでは、言葉の意味を詳しく見ていきましょう。
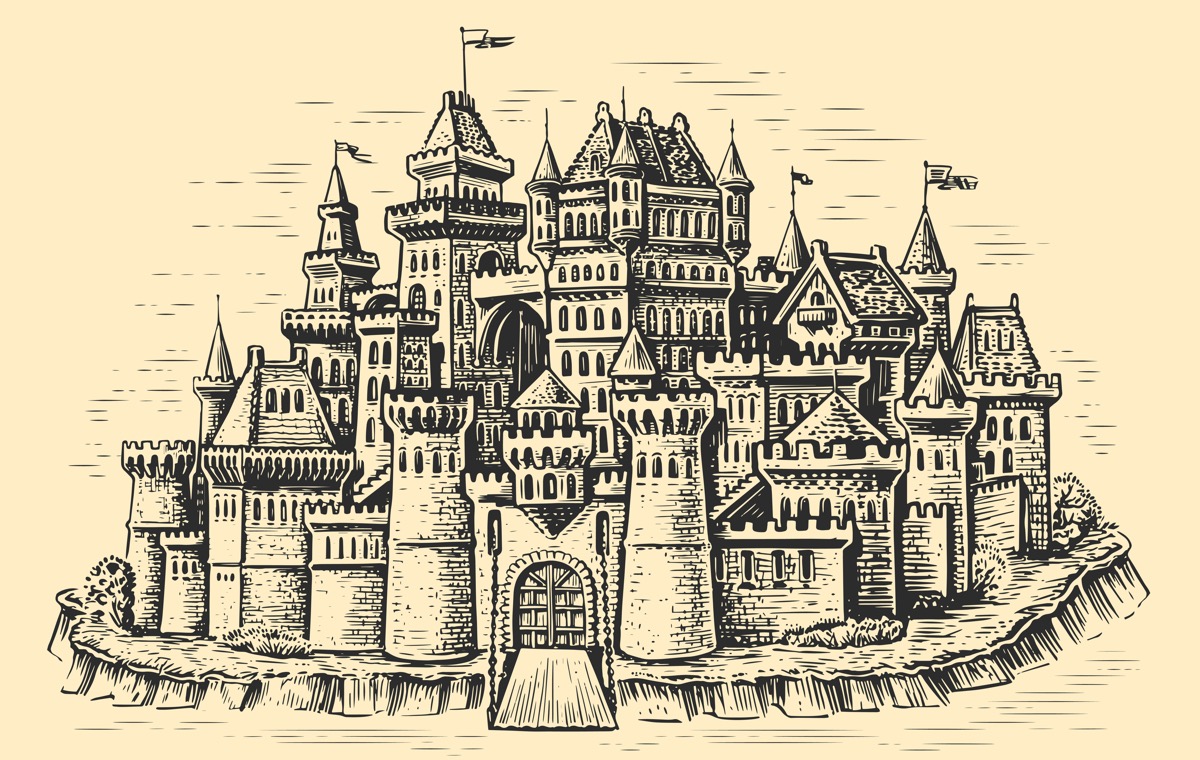
(c) Adobe Stock
見かけ倒しという意味
まずは、辞書で意味を確認しました。
砂上(さじょう)の楼閣(ろうかく)
見かけはりっぱであるが、基礎がしっかりしていないために長く維持できない物事のたとえ。また、実現不可能なことのたとえ。
[補説]「机上の空論」との混同で、「机上の楼閣」とするのは誤り。
『デジタル大辞泉』(小学館)より引用
「砂上の楼閣」は「さじょうのろうかく」と読み、不安定で移ろいやすいもののたとえとして用いられる言葉です。砂上とは文字通り「砂の上」を指し、楼閣とは「高層で立派な建造物」のことを表しています。
つまり「砂上の楼閣」とは、いくら高層で立派な建物であっても、砂の上のように不安定な場所に建てれば、たやすく倒壊してしまう、ということを表しています。
実現不可能という意味
「砂上の楼閣」は、「実現が不可能なこと」「現実味がないこと」といった意味も併せ持っています。そもそも砂の上に高層で立派な建築物を建てることは、現実的に考えて無理があるといえるでしょう。
そのため「砂上の楼閣」は、現実的に不可能な計画や、継続できないような事案に対しても使用できる言葉です。ビジネスや日常生活で無理な計画を避けて、堅実に進めるための教訓としても使えますね。
「砂上の楼閣」の由来は『新約聖書』
「砂上の楼閣」という言葉の由来は、『新約聖書―マタイ伝・七』にあるといわれています。イエス・キリストは、自分の教えに耳を傾けず実行しない人々を「砂の上に自分の家を建てた愚かな人」にたとえました。このたとえでは、雨が降り、洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると、その家は簡単に倒れてしまうという、もろく不安定な状態を象徴しています。
「砂上の楼閣」の使い方や例文
「砂上の楼閣」にはネガティブな意味が含まれていることから、使うシーンを間違えてしまうと、相手に不快な思いを与えてしまいます。
例えばビジネスシーンにおいて、進行中だったプロジェクトがうまくいかず、失敗に終わってしまった相手に対して「砂上の楼閣だったね」と声をかけるのは適切ではありません。「砂上の楼閣」には否定的な意味合いもあるため、使う際は注意が必要です。
例文
・資金の調達方法に無理があれば、そのプロジェクトは砂上の楼閣となるでしょう。
・計画通りに進むとは到底思えないほど、無理なスケジュールを組んだこの生産管理表は、砂上の楼閣と呼んで問題ないだろう。
「砂上の楼閣」の類義語
「砂上の楼閣」の主な類義語は、「羊頭を掲げて狗肉を売る」「机上の空論」「有名無実」の3つです。
ともに「砂上の楼閣」に似ている言葉ではありますが、多少意味合いに違いがあるため、正しい意味を理解しておくことが大切です。
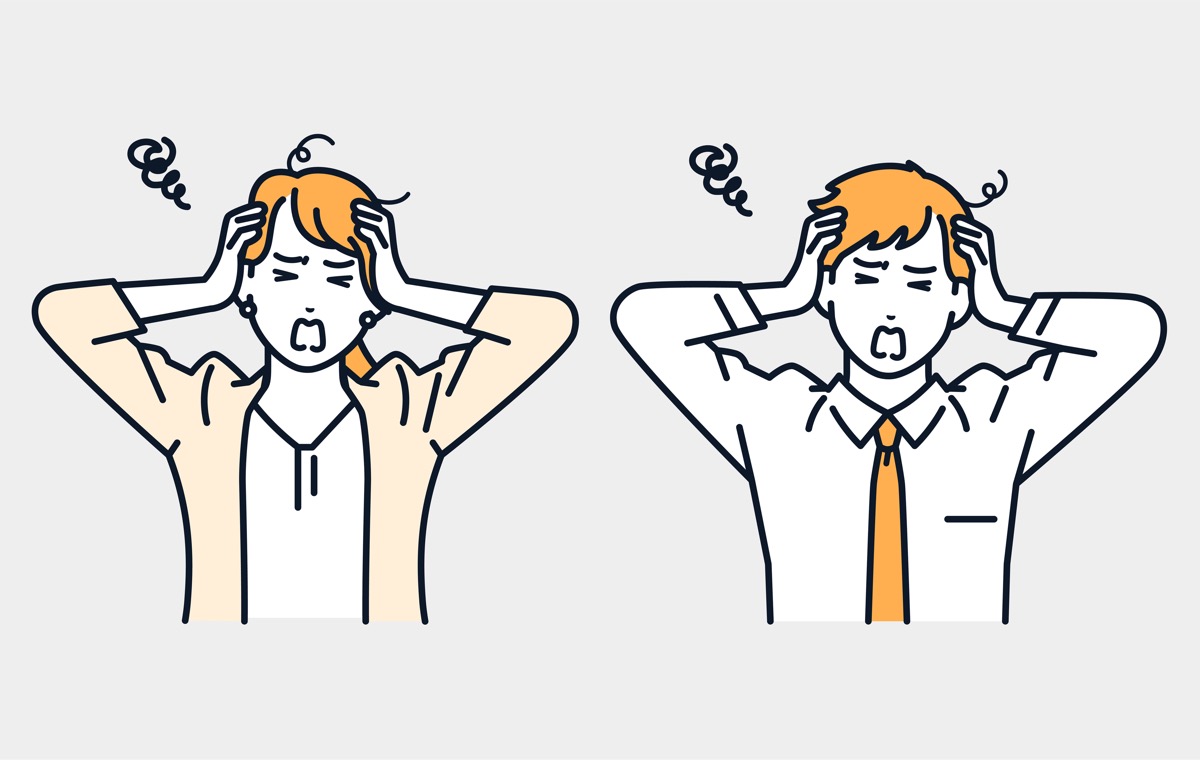
(c) Adobe Stock







