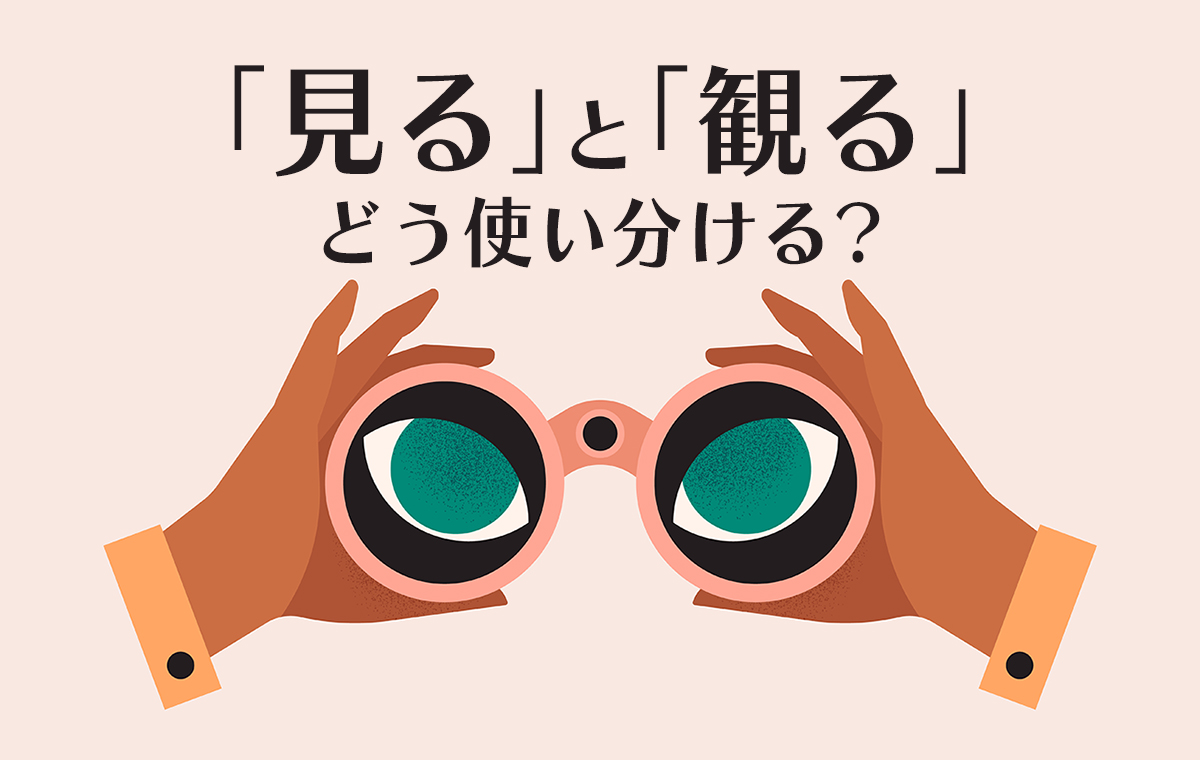見る・観るの違いは「意識しているかどうか」
日本語には同じ読み方の漢字がたくさんあります。例えば「見る」で辞書を引くと、以下のように説明されています。

【見る/▽視る/▽観る:みる】
[動マ上一][文][マ上一]
1.目で事物の存在などをとらえる。視覚に入れる。眺める。「みればみるほど良い服」「星空をみる」
2.見物・見学する。「映画をみる」
3.(「看る」とも書く)そのことに当たる。取り扱う。世話をする。「事務をみる」「子供のめんどうをみる」
4.調べる。たしかめる。「答案をみる」
5.(「試る」とも書く)こころみる。ためす。「切れ味をみる」
6.観察し、判断する。また、うらなう。評価する。「人をみる目がない」「運勢をみる」「しばらくようすをみる」
7.(「診る」とも書く)診断する。「脈をみる」
8.読んで知る。「新聞でみた」
9.身に受ける。経験する。「痛い目をみる」
10.(ふつう、前の内容を「と」でくくったものを受けて)見当をつける。そのように考える。理解する。「遭難したものとみられる」「一日の消費量を三千トンとみて」
11.夫婦になる。連れ添う。
「さやうならむ人をこそみめ」〈源・桐壺〉
12.(補助動詞)動詞の連用形に「て」を添えた形に付く。
(ア)「てみる」の形で、ためしに…する、とにかくそのことをする意を表す。「一口、味わってみる」
「男もすなる日記といふものを、女もしてみむとてするなり」〈土佐〉
(イ)「てみると」「てみたら」「てみれば」などの形で、その結果、ある事実に気づいたり、その条件・立場が認められたりすることを表す。「踏みこんでみるともぬけのからだった」「親としてみれば、そう言わざるをえない」
(引用〈小学館 デジタル大辞泉〉より)
「見る」と並んで「観る」も記載されているのがわかるでしょう。見ると観るはどちらも「みる」と読みますが、それぞれ異なるニュアンスをもっています。
見ると観るの違いを決定づけるポイントは、動作を行う人が意識を向けているかどうかです。それぞれを適切に使えるように、ニュアンスの違いを理解しておきましょう。ここでは、見ると観るの意味を詳しく解説します。
「見る」は受動的に視界に入ること
見るは、受動的に視界に入ることを表す言葉です。「見よう」という意図はなく、意識せずに存在を目でとらえるような状態を指します。ぼーっとしているときに景色や文字が視界に入る場面をイメージするとわかりやすいでしょう。
また、見るは視覚からの情報以外に、さまざまな感覚を通して物事をとらえる際にも使える表現です。例えば、味見は「味を見る」に由来するとされており、味の加減をとらえることを表します。「体の調子を見る」は、体の動きや感覚をもとに調子が良いか悪いかをとらえるというニュアンスです。
見るを他の漢字で表すと、「判断する」「経験する」「鑑定する」などが当てはまります。例えば、「雨が降っているか見てみよう」は、雨が降っているかを判断するために空を見る様子を表す文章です。この場合は無意識にとらえているわけではなく、意図的に動作を行うニュアンスを含みます。
「観る」は意識をして視線を向けること
観るは見ると同じように使えますが、見るよりも意識的に視線を向けるような状態を指します。「観察」や「観光」などに使われるとおり、本人の意思があって主体的にみようとするというニュアンスです。
例えば、ぼーっとしながらテレビをみる場合は見るを使いますが、しっかりと意識を向けてみる場合は観るが適切です。無意識で受動的に行う見るに対し、観るは能動的な動作であると覚えておきましょう。
見る・観るの正しい使い分け方
上述のとおり、見ると観るは同じように使える言葉ですが、細かなニュアンスに違いがあります。みようという意識がなく、受動的に視界に入る場面では見るを使うのが適切です。

一方、みようという意思があり、能動的に目でとらえる場面では観るが適しています。それぞれを正しく使えるように、使い分けの基準や迷ったときの対処法を知っておきましょう。
シーン別|見る・観るの使い分けの基準
見ると観るの使い分けの基準は、「どのようにみるか」です。例えば、テレビやアニメをみる際は見ると観るのどちらを使っても構いません。
ただし、集中してみていないときや、内容をあまり覚えていないときは、見るが用いられます。反対に、じっくりと意識を向けてみるようなときは観るを使って表します。
また、映画やスポーツをみる際は「観る」を使うケースが多いです。映画をみるために映画館に行ったり、スポーツ観戦のためにスタジアムに行ったりするのは、主体的な行動といえるでしょう。ただし、家で別のことをしながら映画をみているようなケースでは、見るを使うのが適しています。
見ると観るの具体的な使い方を例文で確認しておきましょう。
・帰宅後にテレビを見ていて、そのまま寝てしまっていました。
・バスの中で新製品の中吊り広告を見ていたら、つい欲しくなってしまった。
・正月の恒例行事は、家族そろって全国高校ラグビー大会を観ることです。
・自由研究のために、毎朝アサガオの成長を観る。