デジタル機器が溢れる今だからこそ、しっかりチェック!
「光や色に対して過度に〝いやがる〟〝疲れを訴える〟ことが多い場合は【視覚過敏】かもしれません」と話すのは、スクールカウンセラーとしても活動している、臨床心理士・吉田美智子さん。では、具体的にどのような症状が見られるのかお伺いしました。
不機嫌になったり、体調不良を訴える場合も
視覚過敏というのは、光や色などの視覚情報を、高い感度でキャッチする能力があるときに、結果として「つらさ」として感じられることを指します。どのようなものに反応を示すのか、よくあるパターンをご紹介します。
CASE1 光に敏感
ほかの人が感じない、気にならない蛍光灯のちらつきをキャッチし「チカチカ」する、白いノートが眩しく感じたり、太陽の光が眩しすぎて目を閉じずにはいられないなど、人よりも光に敏感。
CASE2 映像が苦手
TV、パソコン、ゲーム機など、視覚情報が多すぎる上に光が眩しく感じられて、気持ちが悪い・吐き気・頭痛が生じる。今は乗り物の中にも液晶画面がついていたり、正面を向いて歩くのが辛かったりします。
CASE3 ごちゃごちゃした場所が苦手
ショッピングモールや遊園地、お祭りなど人混みを嫌がる。街中には大型液晶ビジョンがいくつもあり、ごちゃごちゃ感がさらにアップしていますよね。
CASE4 色が苦手
強い色が目に刺さって感じられたり、色のコントラストが強いと眩しく感じられるなどという場合も。
室内ではカーテンや照明器具で光を調節したり、ごちゃごちゃした場所はサングラス、つばの広い帽子などで視覚情報を減らすことで対応してみてください。
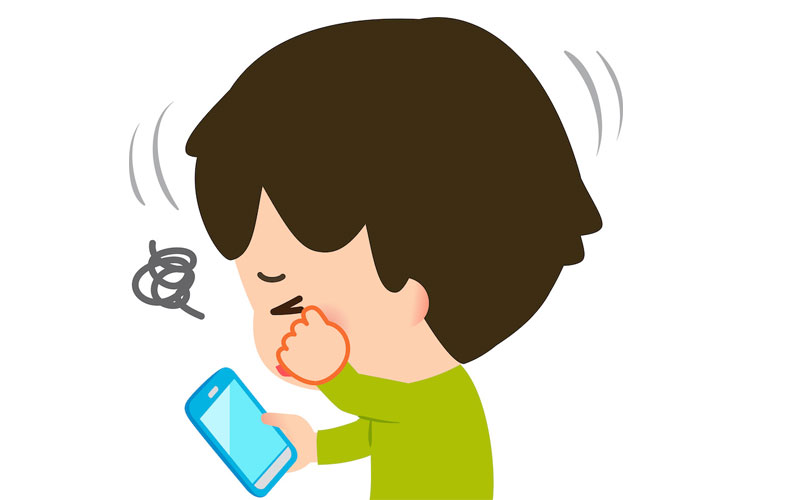
増えるデジタル機器との付き合い方
ゲームやYouTubeに加え、オンライン授業やタブレット授業など、今どきの子どもたちはただでさえ目を酷使しています。そこに視覚過敏が加わるとさらに状況は厳しいものになるでしょう。どうしても外せないオンライン授業であれば、ブルーライトカットフィルムや明るさ調整などできる限り光を抑える・読み上げ機能など画面を見なくて済む工夫をしてみてください。
また、学校でのタブレット授業は先生に相談をし、なるべく紙で対応できないか確認してみることも必要かもしれませんね。子どもが誤解を受けないよう、周りに協力を得るのも忘れずに。また、視覚過敏の中には片頭痛と関係しているものも見られます。光を嫌がり、頭痛や吐き気を訴えるときは、頭痛外来に相談してみることもおすすめです
取材・文/福島孝代
あわせて読みたい
▶︎コロナ禍に見る【子どものデジタル機器】との付き合い方|最低限守りたい3つとは?
▶︎かんしゃくを起こす子どもに〝同調〟は逆効果!?それよりも〝◯◯◯袋〟を育てて!

臨床心理士
吉田美智子
東京・青山のカウンセリングルーム「はこにわサロン東京」主宰。自分らしく生きる、働く、子育てするを応援中。オンラインや電話でのご相談も受け付けております。
HP
Twitter: @hakoniwasalon






