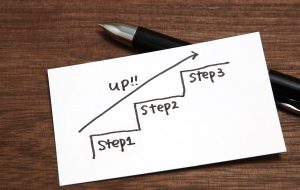昇格はキャリアの重要な転換点であり、責任と期待が変化する契機でもあります。しかし、昇進との違いや具体的な影響を理解している人は意外と少ないかもしれませんね。
そこで、この記事では、昇格の意義や背景、関連する実務的な知識を掘り下げ、管理職として押さえておくべき視点をお伝えします。
昇格とは? わかりやすく解説
昇格は、組織運営の中で何を意味するのでしょうか? ここでは、昇格の定義を確認しましょう。

(c) Adobe Stock
昇格の基本的な意味
まずは、「昇格」について辞書で調べました。
しょう‐かく【昇格】
[名](スル)格式や階級などが上がること。また、上げること。格上げ。「課から部に―する」⇔降格。
引用:『デジタル大辞泉』(小学館)
昇格とは、格式や階級が上がることを指します。しかし、単に階級が上がるだけでなく、新たな責任範囲や意思決定への影響力の拡大を伴うことが一般的でしょう。
なお、公務員の場合、昇格は同一俸給表(給料表)の上位の職務の級への変更を指します。
また、昇格の意義を理解する上で、企業内資格制度との関連にも触れておくべきでしょう。企業内資格制度とは、仕事上の地位とは別に、各企業が一定の基準によって設定した資格等級を当てはめ、処遇や配置などを結びつける制度のことです。この中で等級が上がることを「昇格」といいます。
昇格と昇進の違いは?
昇格と昇進の違いを正確に認識している人は多くないでしょう。ここでは違いを確認していきます。

(c) Adobe Stock
昇格と昇進の違い
「昇進」についても辞書で確認しておきましょう。
しょう‐しん【昇進/×陞進】
[名](スル)《古くは「しょうじん」とも》職務上の地位、官位などが上がること。「課長に―する」
引用:『デジタル大辞泉』(小学館)
「昇進」は、職場における地位がより上位に上がることだとわかりました。例えば、「主任」から「課長」に上がることなどが例として挙げられます。昇進に伴い、社外に向けた肩書きや名刺の表記も変わり、外部とのやり取りにおける影響力が増すことが一般的です。
一方で、昇格は企業内資格制度の中で、等級が上がることを意味します。昇格によって責任範囲や職務内容が広がることはありますが、対外的な肩書きや地位は変化しないケースも少なくありません。
興味深い点は、昇進と昇格が必ずしも同時に起こるわけではないということです。例えば、役職が「課長補佐」から「課長」に昇進しても、等級は据え置かれる場合があります。また反対に、昇格によって職務遂行能力が評価されながらも、組織内のポジションに空きがないため、昇進が見送られることもありますよ。
昇格による給与や待遇の変化
昇格は給与や待遇にどのような影響があるのでしょうか? ここでは、昇格による具体的な変化について紹介します。

(c) Adobe Stock
昇格で給料はどれくらい上がる?
昇格に伴う給与の増加幅は、業界や企業規模、さらには人事制度によって大きく異なります。例えば、ある企業では等級が1つ上がることで、基本給が平均5〜10%増加するそうです。これは、昇格によって職務の難易度や責任が高まるため、その評価として給与が調整されるためです。
一方、近年注目されているフラット組織などでは、昇格が必ずしも給与に直結しない場合もあるようです。階層が少ないため、等級の変化が責任範囲の拡大には影響するものの、報酬に反映される時期や程度が曖昧になることが特徴です。
昇格したのに給料が変わらないケースもある?
昇格後もすぐに給与が変わらないというケースは、一部の民間企業で見られます。
例えば、昇格により等級が上がったとしても、実際の給与変更は次の給与改定時期に反映される仕組みだからだそうです。この運用は、組織内の公平性を保つために設定されています。しかし、昇格後の責任増加と給与のタイムラグが生じる結果、「責任だけが先行する」と感じる人もいるようです。
また、昇格に際して給与が変わらないもう一つの要因として、「昇給」と「昇格」を別々に管理する企業の方針が挙げられます。こうした企業の場合、給与の改定は一定の評価期間を経て実施されるため、昇格直後には報酬面での変化を感じにくいかもしれません。
最後に
昇格は、キャリアの転換点となる重要なステップです。昇格の意義や影響を正しく理解することで、次の目標が明確になり、効果的なキャリア形成が可能になるでしょう。
TOP画像/(c) Adobe Stock
あわせて読みたい