ワーキングプアとは何を指す?
テレビやインターネットなどで「ワーキングプア」という言葉を見聞きしたことはあっても、意味をよく理解していないという人もいるのではないでしょうか? まずは、ワーキングプアの意味や判断するための目安などを紹介します。
「働く貧困層」を指す
ワーキングプアとは、「働いているにもかかわらず貧困状態にある人々」を指す言葉です。日本語では「働く貧困層」とも呼ばれており、正社員やフルタイムで働いていても、収入が生活保護水準以下など、貧しい生活を強いられている就労者の社会層を意味します。
ワーキング‐プアー【working poor】
フルタイムで働いているが、生活保護水準以下の収入しか得られない人々のこと。賃金が安く生活の維持が困難な就労者層のこと。統計を取るための正式な定義はまだない。働く貧困層。→ハウジングプアー
小学館『デジタル大辞泉』より引用
ワーキングプアの人々は、生活を安定させるため長時間労働に陥りやすく、体調を崩す人も少なくありません。働くのが困難となり、さらに状況を悪化させてしまうケースも見られます。
また、高学歴者や中高年層でも、就職難や低賃金によりワーキングプアに陥るケースがあるのです。ワーキングプアは、個人の生活困窮だけでなく、少子高齢化の加速など社会全体に深刻な影響を与えており、早急な対策が求められています。
ワーキングプアとなる年収の目安
ワーキングプアとされる年収の目安に明確な基準はありませんが、年収200万円以下とされることが多いといいます。これは、厚生労働省が公表している資料において、「一般的にワーキングプアへ含まれる人」の年収が192万円未満とされていたためです。
また、生活保護の受給対象が「国が定める生活に必要な最低限の収入」であることから、その対象となる収入を目安とする場合もあります。
ただし、最低限の生活費は世帯構成や地域によって異なるため、一概に年収だけでワーキングプアかどうか判断することは難しい点に注意が必要です。
参照:厚生労働省ホームページ(非正規労働者データ資料(修正)P. 41より)
ワーキングプアが増えているとされる理由

(c)Adobe Stock
ワーキングプアの増加には、複数の要因が絡み合っています。ここでは、主な理由を3つ紹介します。これらの要因を理解することで、ワーキングプア問題の本質が理解できるはずです。
物価の上昇と給与水準の低迷
ワーキングプアが増加している主な要因のひとつが、物価の上昇です。近年、日本では燃料費や原材料費の高騰を背景に、物価が上昇しています。企業は増加した生産コストや運送費、保管費などの負担を製品価格に反映せざるを得ない状況です。
一方で、給与水準は低迷しています。給与が上がらないにもかかわらず、生活必需品をはじめとするさまざまな商品の価格は上昇し続けており、ワーキングプアの増加に拍車をかけているのです。
働き方が多様化したため
働き方の多様化も、ワーキングプアの増加要因のひとつとして挙げられます。かつては終身雇用制度が主流でしたが、近年は人々の価値観が変化し、多様な働き方を選択する人が増えています。
たとえば、お金よりも自由な時間や自分の好きなことを重視し、労働時間や収入の少ない仕事を選ぶ人などです。自分の望むライフスタイルを維持するために、あえてワーキングプアに陥る状況を選択する人も存在します。
このように働き方の多様化は、人々に選択肢を与える一方で収入の不安定さや低さをもたらし、ワーキングプア増加の一因となっています。
非正規雇用の増加
非正規雇用の増加もまた、ワーキングプアの主要因のひとつといえるでしょう。1990年代以降、労働市場の規制緩和により、パートタイム・アルバイト・派遣社員・契約社員といった非正規雇用が急増しました。
企業は人件費削減のため、正規雇用よりも非正規雇用を好む傾向にあります。非正規雇用は、正規雇用と比べて賃金が低く雇用も不安定なため、労働者の収入が減少し、生活が苦しくなるケースが増えています。
また、非正規雇用では、スキルアップやキャリア形成の機会が限られやすいものです。これが長期的な収入の伸び悩みにつながり、ワーキングプア状態からの脱却を困難にしています。
ワーキングプアを脱却する方法
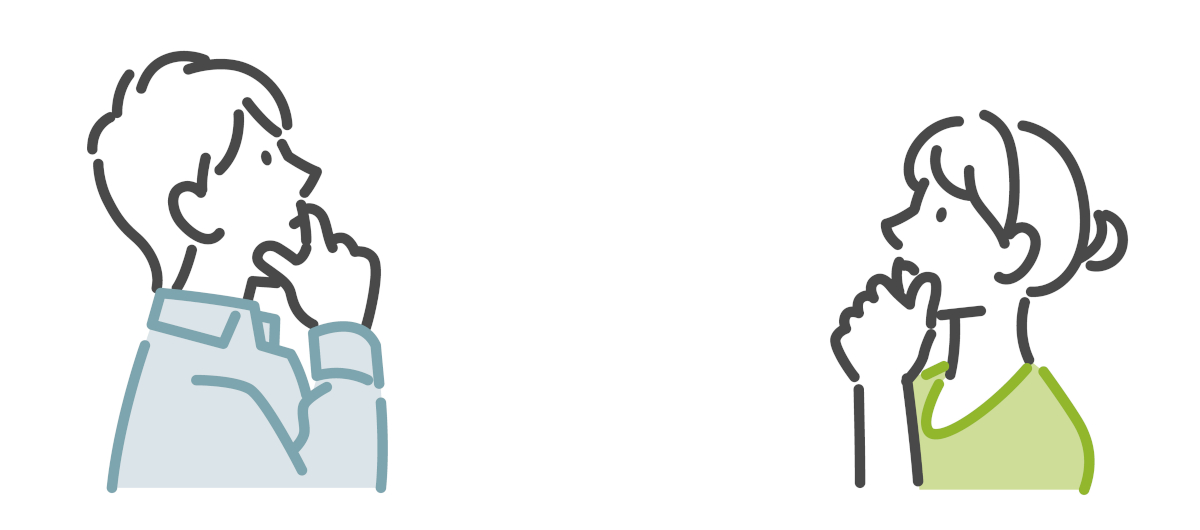
(c)Adobe Stock
ワーキングプアからの脱却は、決して不可能ではありません。状況を客観的に分析して適切な行動を取ることで、ワーキングプアの人々も収入を増やし、自身の生活の質向上を目指せます。
ここでは、ワーキングプアに陥ってしまった人が、その状況を脱却するための具体的な方法を紹介します。
転職を検討する
収入を増やすための方法として、転職があります。現在の職場で収入アップや成長の見込みが薄い場合、より待遇がよく、成長の機会を提供してくれる職場への転職を検討しましょう。
転職活動では、自己分析が重要です。自身のスキルや経験・強みを見極め、それを活かせる業界や職種を選ぶことが成功への鍵となります。また、転職市場で求められるスキルを習得すると、候補となる企業や職種の幅が広がります。
たとえば、パソコンスキルは多くの職種で必要とされる基本スキルのひとつです。さらに、キャリアアドバイザーの支援を受けることも有効な手段とされています。プロのサポートを受けることで、自分に合った職場を見つけやすくなる可能性があります。
資格取得・自身の価値を上げる
自身の市場価値を高める方法として、資格取得が挙げられます。これは、昇給や昇進の可能性を高めたり、より待遇のよい職場への転職機会を広げたりする手段となります。
具体的には、IT関連スキルや語学力、ビジネススキルなど、幅広い分野で活用可能な資格が推奨されています。オンライン講座などを活用すれば、働きながらでも効率的に学べるでしょう。自己投資にはコストが伴いますが、長期的なキャリア形成に寄与する可能性があります。
副業を始めてみる
副業も収入を増やす手段として注目されています。近年では副業を認める企業が増加しており、インターネットを利用した副業の種類も多様化しています。
具体例として、クラウドソーシングを利用したライティングやデータ入力、SNSを活用したマーケティングなどが挙げられます。これらは収入増加だけでなく、新しいスキルの習得やネットワークの拡大といった副次的な効果も期待されます。
ただし、副業を行う際は本業に支障をきたさないよう注意が必要です。
政府が行っているワーキングプアへの支援

(c)Adobe Stock
日本政府は、ワーキングプアの人々を支援するため、いくつかの制度を設けています。これらの支援策を活用することで、ワーキングプアの人々がより安定した生活基盤を築ける可能性があります。どのような支援制度があるのか見ていきましょう。
求職者支援制度
「求職者支援制度」は、主に雇用保険を受けられない人や、収入が一定額以下の在職者を対象とした国の支援制度です。この制度では無料で職業訓練を受けながら、生活を支えるための給付金の受給が可能です。
給付金の受給には、本人収入が月8万円以下、世帯全体の収入が月30万円以下などの条件があります。給付金には月額10万円の職業訓練手当に加え、条件に応じて通所手当や寄宿手当も支給されます。
職業訓練は、ビジネスパソコンなどの基礎・IT・営業・事務・介護福祉・デザインなどさまざまな分野から選択可能で、期間は2〜6カ月です。この制度を利用することで、新たなスキルを身につけながら、次の就職に向けた準備ができます。
参照:厚生労働省ホームページ(求職者支援制度のご案内 )
自立支援教育訓練給付金
「自立支援教育訓練給付金」は、ひとり親家庭の親の就労支援を目的とした制度です。職業能力の開発や資格取得を目指す際に、教育訓練の受講費用の一部が給付されます。対象となるのは、20歳未満の子どもを扶養する、ひとり親家庭の親です。講座は雇用保険の教育訓練給付金指定講座から選択できます。
給付額は入学金と受講料の60%相当で、上限は講座の種類により20万円から160万円です。専門実践教育訓練給付金の対象講座を受講し、1年以内に資格を取得して職に就いた場合、給付額が85%に拡大されます。
申請には事前に自治体での手続きが必要です。この制度を活用すれば、経済的負担を軽減しながらスキルアップを図り、よりよい就業機会を得ることができます。
参照:子ども家庭庁(母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業について)※参照 令和7年1月21日
各税金の減額申請もあり
ワーキングプアの人々が利用できる支援制度として、各種税金の減額申請があります。低所得者世帯向けに、申請によって税金を減額または猶予できる制度が設けられています。
たとえば、生活保護を受けている人や合計所得が設けられた基準よりも低い場合、住民税は非課税です。また、国民年金や国民健康保険の保険料についても、免除・納付猶予制度が用意されています。
さらに、所得税などの国税に関しては、病気療養や失業などで納税が困難な場合、税務署に申告することで1年間の納税猶予が認められる場合があります。
これらの制度を活用することで、経済的負担を軽減しつつ生活の立て直しが図れます。税金や保険料の滞納を避けるためにも、早めに担当窓口で相談し、減額や猶予の申請を行うことが重要です。
メイン・アイキャッチ画像/(c)Adobe Stock
あわせて読みたい












