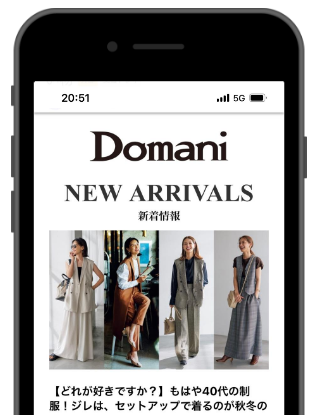おふくろの味としてよく挙がる「肉じゃが」。しかし、男が「あなたは肉じゃがが大好きですか?」と聞かれた場合、大多数はそうではないだろう。「嫌いじゃないけど別に“大好き”ってほどではない。ジャガイモが入った料理ではカレーは大好き」という答えになる。
なぜ肉じゃがは「おふくろの味」なのか?
しかし、何らかの流れで「あなたにとっておふくろの味は?」と聞かれた場合に「えーと、えーと、あれあれ、なんだったっけ、オレ、母ちゃんに作ってもらったのなんだったっけか? 本当にうちの母ちゃん、毎日昼メシは購買部でパンを買えなんて言って毎日200円くれるだけだったし、夜はレトルトカレーばっかだったよな。えーい、よくわからんが、『肉じゃが』ってことにしておくか!」ということで挙げられるのである。

この刷り込みはかなり強固であり、大衆居酒屋に行くと男も女も肉じゃがをけっこうな割合で頼む。ジャガイモを酒のツマミにしたいのであれば、ポテトフライやじゃがバターのイカの塩辛 or 酒盗(カツオの内臓の塩辛)乗せといったものが合う。
あるいは、「ジャーマンポテト」と呼ばれる、ゆでたジャガイモを輪切りなどに細かく切り、ベーコンとタマネギとともに塩こしょうで炒めたものにタバスコをかければ完全に「ビールの友」となる。
はたして本当に世界的に「ジャーマンポテト」という食べ物があるのかと、German potatoでグーグル検索してみた。「フレンチトースト」なんてもんが日本にはあるが、「本場フランスにはそんなもんない!(キリッ)」みたいな話があるので、これって日本独自の創作料理なのかな、と思ったらわれわれがイメージするGerman potatoはたくさん出てきた。
しかし、実際はGerman potato saladで、サラダの扱いになっていた。これは驚いた。それにしても「トルコライス」とか「イタリアン」とか「ナポリタン」とか本場の人からすれば「そんなもんはわが国にない!」と言いたくなるようなものをよくぞこうも開発できるものだ。
しかしそれはそれで構わない。何しろ海外にも怪しげな日本料理というものは多数存在するのだから。1980年代にアボカドにしょうゆをつけたらトロの味がする、とカリフォルニアの寿司店でカリフォルニアロールが誕生したが、今では日本でもアボカドは巻き寿司では人気の種となっている。外国で別の形で進化した日本食の逆輸入万歳である。
それはさておき、居酒屋で肉じゃがをオーダーするときは「おふくろの味って感じ?」という言葉がセットになる。そこで「家でお母さん、本当に肉じゃがをよく作ってくれていましたか?」と聞くと彼らは若干狼狽しながら「えっ、えっ……。そういえば、肉じゃがってむしろこうして居酒屋で食うものだよね。母は袋入りラーメンばっか作ってくれたような気がする……」なんてことを言う。まぁ、無粋な質問だ。
新刊『意識の低い自炊のすすめ』ではかくして「食はかくあるべし」的な通説に対して「無理するな」を言い続けるし、時に手抜きだったり、中食で済ませられるような「意識の低い自炊」を紹介していく。
だから、煮物が苦手な人は無理して肉じゃがづくりに取り組む必要はないし、彼氏ができたからといって肉じゃがづくりをマスターする必要もない。
ここで女性の皆さんに言いたいのは、「母親の料理とあなたの料理を比較してあなたのは口に合わない、的なことを言う男はその習慣をやめさせるか別れてしまえ」ということである。マザコン男ほど厄介な存在はない。
結婚でもしようものなら、何かと母とあなたを比較し、そして実家にやたらと帰りたがる。「おふくろの味は肉じゃが男」はそういった側面がある。なお、味覚というものは日々の生活で変わるもの。いつの間にか辛い物が得意になったり、薄味が好みになったりする。
「家庭料理は女のもの」の違和感
家庭料理は女のもの――そういった価値観は今の日本でも根強く残っており、定年退職をした夫がつねに食事のことばかり考えている、といった嘆きも聞こえてくる。
11時50分になると、食卓に座りテレビを見たり新聞を読んだりしている夫の姿。妻は「もぉ〜、勝手にお茶漬けでも作って食べてよ〜! パンだってあるんだから焼いてマーマレードでも塗っておいてよ!」なんて思うものの、夫は「今日のお昼はまだ? 何が出てくるのかな」なんて雨に濡れたチワワのような純粋な目でこちらを見てくる。
かくして妻は冷凍うどんを使って「簡単きつねうどん」を作ってあげるのだが、「おいしい?」と聞いても夫は「あぁ」と言うだけでテレビに熱中している。妻は「何よ、せっかく作ってあげたのに、プンプン」みたいな状態になってしまい、かくして定年後の夫婦関係というのは難しいのだった。

以前、実家に妻と一緒に帰ったときに母から感謝されたことがある。夕食は母親が作ってくれたカレイの煮つけや酢の物だったのだが、2人して「おいしいね!」と言いながら食べていたら、母はしみじみと言った。
母「あんたたちはエラいわねぇ〜」
筆者「えっ? なんで?」
母「やっちゃん(父のこと)なんてね、何を出しても『おいしい』なんて言わないでただ黙々と食べているだけなのよ。作っている側としては反応してもらえないとむなしいのよ、これが」
妻「だって本当においしいですよ!」
筆者「別に『おいしい』なんて言うのは簡単なことなので素直に思ったことを言ってるだけだけど」
母「それが年を取るとできなくなるのよね……」
現在74歳の父は多分料理はできないと思う。今までに彼の作った料理を一度も食べたことがない。料理に近いことをやったのは、出張先の岡山で大量にもらってきた蝦蛄(シャコ)を母親に塩ゆでしてもらい、それを父がハサミを使って身を次々と出してくれたことぐらいか。
あとは中高時代アメリカに住んでいたころ、庭にBBQのグリルがあったのだが、それに火をつけ、ステーキを焼いてくれたことはあった。だが、これはアメリカの男のマッチョ思考にも似ており、「BBQで肉を焼くのは男の仕事!」的メンタリティーがあったのでは。
妻が料理をしなくても「家庭円満」な理由
そして現在のわが家である。料理担当は私だ。妻は食器洗いをしてくれる。なぜこうなっているかといえば「私は料理が苦手だから中川さんやって」(妻)という状況にあるからだ。
一方、私は食器洗いは苦手なので、この役割分担が互いに心地よい。私も彼女も飲み会がない夜は、2人して18時頃からキッチンでちょっとした酒のさかなをツマミにビールを飲み始める。このとき、夕食用によく作るのは「作り置きできるもの」だ。

私は飲み会が多いため(コロナ禍の前のこと)、朝ごはんは毎日作れるものの、夜は作れない。しかし彼女は料理が苦手で本当はやりたくない。1人で外食するのも苦手なのでやりたくない。そんなときに、この“キッチン居酒屋”をしながら作った料理を活用するのだ。大量に作っておき、その晩食べる分以外はすべてタッパーに入れてしまい、それを彼女は翌日の夕食にする。
料理が完成すると「私の生命線。これで3食分になる。助かった」といつも彼女は言う。この大量作り置き料理で便利なのは、「カレー」「キーマカレー」「ミートソース」「マーボー豆腐・マーボー野菜」「豚肉しょうが焼き」「鶏肉そぼろ」「ブリ大根」「タコス」などだ。
カレーの場合は汎用性が高くライス、パスタ、うどんのいずれでも食べることができ、キーマカレーはライス以外にもスーパーで買ってきたナンで食べることができる。とにかく煮込むタイプの料理で汎用性が高いものを大量に作っておくと、料理の苦手な家人にとっては救いの神となる。
作る人は家族の誰でもいい。やりたい人、得意な人がやればいいし、もっというと料理をするのが楽しくて仕方がない人がやればいい。
『意識の低い自炊のすすめ 巣ごもり時代の命と家計を守るために』(講談社)
ネットニュース編集者
中川 淳一郎(なかがわ じゅんいちろう)
1973年生まれ。東京都立川市出身。一橋大学卒業後、博報堂で企業のPR業務を担当し、2001年に退社。CM・広告関連記事を担当する雑誌ライターとして活動後、「TVBros.」編集者などを経て現在に至る。著書に『ウェブはバカと暇人のもの』『ネットのバカ』『謝罪大国ニッポン』『バカざんまい』など多数。

東洋経済オンライン
東洋経済オンラインは、独自に取材した経済関連ニュースを中心とした情報配信プラットフォームです。
写真/Shutterstock.com