Summary
- エイプリルフールは毎年「4月1日」に「罪のない嘘」をついていい日
- 日本に入ってきたのは、大正時代で「四月馬鹿」と呼ばれていた
- 「エイプリルフール」の起源は諸説あり、はっきりわかっていない
エイプリルフールとは
長く日本に定着しているイベント「エイプリルフール」。毎年4月1日に訪れるエイプリルフールですが、由来については知らない人も多いのではないでしょうか。この機会にエイプリルフールについて詳しくなってみませんか?

4月1日は嘘をついてもいい日
エイプリルフールは毎年「4月1日」で、「罪のない嘘」をついていい日とされています。欧米発祥で、相手を傷つけないおかしな嘘で家族や友人と笑い合うのが習わしです。驚かせたい人に対していたずらをしかけて笑わせるような、場を和ませるイベントともいえます。
「嘘をついていい」といっても、相手を不幸にしたり、心配や不安をあおったりするような嘘は避けるのがマナーです。
日本に入ってきたのは大正時代
エイプリルフールが日本に入ってきたのは、大正時代といわれています。それ以前は、4月1日は「不義理の日」とする風習がみられました。これは中国伝来で、「義理を欠いている人へお詫びの気持ちを表す日」として、なかなか会えない人へ手紙を書いて失礼を詫びていたそうです。
そのため、大正時代にエイプリルフールが直訳された「四月馬鹿」として日本に伝えられても、すぐには「4月1日は嘘を楽しむ日」としては浸透しにくかったようです。しかし現在では個人的に楽しむだけでなく、企業が嘘の広告や情報を発信し、世間からの注目を浴びるための戦略として利用するなど、盛り上がりを見せています。
由来は諸説あり
「エイプリルフール」の起源には諸説あります。一般的に知られている、エイプリルフールの由来を見てみましょう。

インドが起源説
インドから生まれた風習がヨーロッパに伝わり、それがエイプリルフールになった、という説があります。始まりは「インドで厳しい悟りの修行期間を終えて、俗世に戻って来るのをからかった」ことにあるようです。
インドの仏教徒は、春分(3月20日前後)から3月31日まで、悟りの境地をめざして過酷な修行に励みます。ところが修行を終えて俗世に戻る4月1日には、一転して再び煩悩が生じてしまうため、そのことを周囲の人がからかった、というエピソードです。
これが「揶揄節(やゆせつ)」と呼ばれ、やがて西洋に広まったといわれています。
フランスが起源説
エイプリルフールの起源については、フランスで誕生したものだという説もあります。その誕生は1564年、当時の国王・シャルル9世が暦を変えたことに起因します。
1564年までは、ヨーロッパでは3月25日が新年とされ、4月1日まで春の祭りが行われていました。しかしシャルル9世が1月1日を新年とする暦を採用したことで、反発した国民が騒動をおこし、4月1日を「嘘の新年」とした、という説です。
イギリスが起源説
イギリスの王政復古を祝う5月29日の「オークアップルデー」が元になっているという説もあります。実はエイプリルフールには「嘘をついていいのは午前中だけ」というルールがあり、これはオークアップルデーから影響を受けているようです。
17世紀にイギリス国王によって設けられた王政復活を祝う日に、国民は国王への忠誠の証として、午前中にオーク(樫)の実を身に着ける義務がありました。このとき、着け忘れてしまうと周りからからかわれる、ということが由来といわれています。
今でもイギリスでは、4月1日の午前中に嘘をつき、午後には嘘の「ネタばらし」をして笑い合う、という風習が続いています。
嘘をつくときのマナー
「エイプリルフールだから何でもOK」と思って嘘をついていたら、周りとの関係が壊れてしまうかもしれません。 あくまで周囲の人を「楽しませる」ための風習として、覚えておきたいマナーをチェックしておきましょう。

相手を傷つける嘘はNG
「嘘をついていい」からといって、相手を傷つける内容は避けなければなりません。ジョークであっても絶対に言ってはならないことを発言すれば、信頼関係を失いかねません。
例えば、大好きな恋人の反応を見るために「別れよう」と伝えたり、「実は浮気しているの」と心配させたりといった嘘は要注意。たとえ「エイプリルフールだから」といっても、相手に不安を与えたという事実はなかなか消えないものです。
周囲からの関心を引きたいからといって、「身内に不幸があった」「実は大病にかかった」という嘘も、当然ついてはいけません。嘘といっても、あくまで「軽い内容」で「後で笑える」ものにするのがエイプリルフールを楽しむマナーです。
ネタばらしは早めにする
嘘をついた相手から期待以上の反応があると、しばらくその様子を楽しみたいと思うかもしれません。しかし嘘を本当だと思い込んでいる当人にとっては、心が落ち着かない状態が続いてしまい辛いもの。ネタばらしは早めにしましょう。
前述した通り、イギリスでは「午前中に嘘をつき、午後はそのネタで笑い合う」という風習があります。傷つかない、驚きがある嘘を「最後にみんなで笑い合う」というのが、エイプリルフールの面白さです。
長時間嘘をつき続けたり、笑えない内容だったりするようでは、相手との信頼関係が崩れてしまう可能性も。相手を不安にさせるようなことは避け、面白がってもらえるような「上質な嘘」を楽しみましょう。
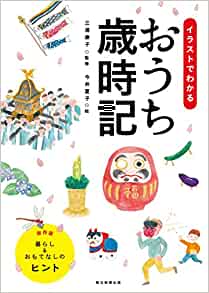
年中行事、ならわし、旬の食べ物、まつり…1年を通じて楽しいことがいっぱい! 二十四節気も暮らしに潤いをもたらします。季節とともに暮らすノウハウやちょっとしたアイデアが満載です。

監修/和文化研究家
三浦康子
古を紐解きながら今の暮らしを楽しむ方法をテレビ、ラジオ、新聞、雑誌、Web、講演などで提案しており、「行事育」提唱者としても注目されている。連載、レギュラー多数。All About「暮らしの歳時記」、私の根っこプロジェクト「暮らし歳時記」などを立ち上げ、大学で教鞭もとっている。著書『子どもに伝えたい 春夏秋冬 和の行事を楽しむ絵本』(永岡書店)ほか多数。
エイプリフールが禁止されている国は?
日本以外の多くの国でも定着しているエイプリフールですが、インドネシアやマレーシアなどイスラム教徒の多い国では、イスラム教の聖典であるコーランに「他人に嘘をついてはいけない」という一文があるためエイプリフールを楽しむ風習はありません。
エイプリルフールは相手を傷付けない嘘で笑い合うことを目的としたイベントですから、相手の宗教や価値観に配慮することも大切です。
▼あわせて読みたい








