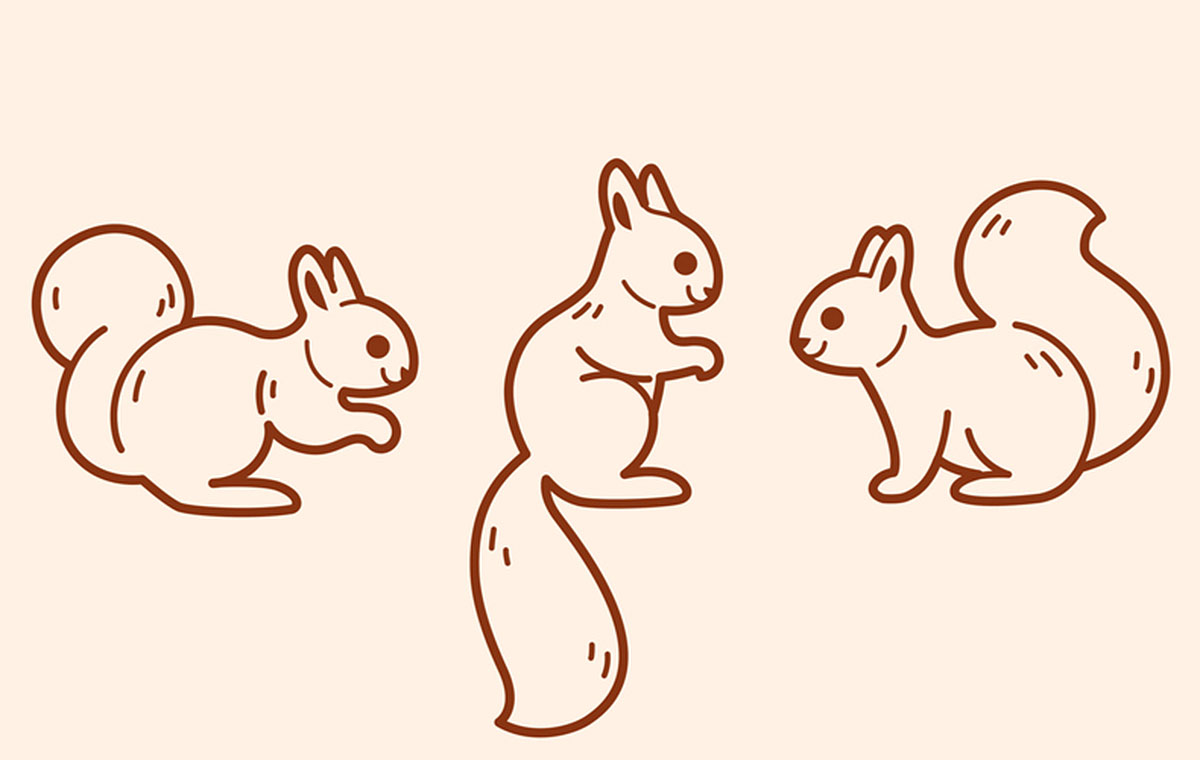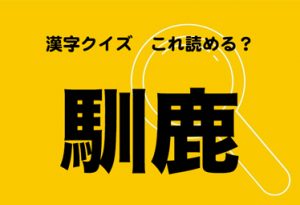「栗鼠」の正しい読み方や意味とは?
「栗鼠」の読み方をご存じでしょうか。動物園やペットショップでも見かけることの多い動物で、小さな体と長い尻尾が特徴です。また、動きが素早くて木登りが得意。
「栗鼠」の正しい読み方は、「リス」。または漢字のまま「クリネズミ」と読まれることもあります。
辞書で「栗鼠」の説明を見てみましょう。
【栗鼠:りす】
《「りっす(栗鼠)」の音変化》
1. リス科の哺乳類。体長15〜22センチ、尾長13〜17センチ。冬毛では背が暗褐色か黄褐色で夏毛では淡黒褐色になり、毛はふさふさしている。樹上生で、果実・種子・芽などを主食とし、巣も樹上に作る。本州・四国に分布。日本りす。本土りす。
2. 齧歯(げっし)目リス科の哺乳類のうち、樹上にすみ昼間活動するものの総称。日本にはニホンリスとエゾリスが生息し、タイワンリスが野生化している。尾は体長と同じくらい長くてふさふさし、動作はすばしこく、クリ・クルミなどの木の実を好む。広くは、リス科のうちムササビ類以外を総称し、シマリス、ジリスなども含まれる。きねずみ。くりねずみ。
(引用:小学館『デジタル大辞泉』より)
次項では、「栗鼠」の名前の由来について解説します。

リスと呼ばれるようになった理由
リスと呼ばれるようになった理由には漢語が関係しています。もともと栗鼠は漢語で「リッス・リッソ」と読まれており、日本では促音の「ッ」が脱落したリスという読み方が広まりました。
なお、「栗鼠」という漢字の成り立ちは、「栗鼠」の見た目や餌に由来します。「見た目がネズミに似ている」「栗などの木の実を食べる」という特徴から、栗と鼠という漢字が当てられました。
「栗鼠」には別名もいくつかあり、素早く木登りする様子から「木鼠」、針葉樹林に生息することから「松鼠」と呼ばれることもあります。
▼あわせて読みたい
「栗鼠」の生態について
栗鼠は種類によって体長や重さに差があったり、ほお袋を使って貯食(ちょしょく)したりと、興味深い特徴をたくさん持っている動物です。野生で暮らすイメージが強いですが、ペットとして飼育される種類もあります。
「栗鼠」の読み方や名前の由来とあわせて、その生態についても知っておきましょう。ここでは、栗鼠の基本的な特徴や飼育方法などをご紹介します。

「栗鼠」の体長や重さ、寿命
栗鼠の平均的な体長は15〜22cm、重さは240〜300gです。ただし、栗鼠の種類は250種以上もあり、個体によって体長や重さが大きく異なります。中でも小さいアフリカコビトリスと、特に大きなアルプスマーモットの体格の違いは以下のとおりです。
・アフリカコビトリス:体長7〜10cm、重さ10g
・アルプスマーモット:体長53〜73cm、重さ5〜8kg
寿命も個体によって幅がありますが、目安としては5〜10歳まで生きるとされています。寿命には生活環境も大きく影響しており、野生の栗鼠の場合は敵に襲われるリスクがあることから、寿命は3〜5年程度と考えられています。
「栗鼠」の食事の仕方
栗鼠の主食は木の実や種子、花などの植物性の餌です。昆虫などの動物性の餌を食べることもあります。ほお袋を使って貯食することが特徴的です。貯食とは、食べ物が豊富な時期に餌を蓄えておくことを指します。
栗鼠はほお袋に餌を詰め込み、地面の中や樹木の上などの保管場所まで運びます。餌を保管場所に置いたら、土をかけるなどして上手に隠し、餌が少ない時期でも食事ができるように備えるのです。
また、餌の運搬だけではなく、食べ切れなかった餌を一時的にほお袋に貯めておくこともあります。
「栗鼠」をペットとして飼育する方法
栗鼠は野生で暮らす動物として知られていますが、家庭でペットとして飼育が可能な種類もあります。栗鼠を飼育する際は、大きなケージを用意して野生と同じ環境に近づけましょう。ケージの底には牧草や広葉樹マットなどを敷きます。または、ちぎった新聞紙や綿などでも構いません。
ケージには寝ぐらとなる巣箱を置きます。そのほか、餌箱や給水器、運動するためのおもちゃなども必要です。
栗鼠の飼育には温度管理が重要なため、ケージは直射日光が当たらない場所に置きましょう。できれば温度計を設置して温度をこまめにチェックし、暑すぎず、寒すぎないように管理するのが理想です。飼育下の栗鼠を冬眠させると健康面でのリスクがあるため、室温を20℃以上に保って冬眠させないことが大切です。
栗鼠の飼育難易度は比較的易しいと言われていますが、飼育する際は押さえるべきポイントをきちんと理解しておくことが大切です。飼育書をしっかりと読んで、責任をもって世話をしましょう。
「栗鼠」以外にもある!動物の難読漢字3選
漢字の読み方が難しい動物は「栗鼠」だけではありません。例えば、動物の難読漢字として以下の3つが挙げられます。
ひらがなやカタカナではよく目にしていても、漢字になると読み方を推測するのは難しいもの。栗鼠とあわせて、その他の動物の難読漢字も読めるようになりましょう。ここでは、それぞれの読み方や特徴などをご紹介します。

海獺(らっこ)
【海獺:らっこ】
《アイヌ語から》イタチ科の哺乳類。海で生活し、体長約1.2メートル、尾長40センチ。全体に黒褐色から灰褐色で、四肢の指に水かきがある。海上であおむけに浮かび、腹の上に石をのせ、アワビ・ウニなどを打ちつけ殻を割って食べる。かつては北太平洋沿岸に広く分布したが、すぐれた毛皮のために乱獲されて激減、保護されている。
(引用:小学館『デジタル大辞泉』より)
「海獺」はイタチ科の哺乳類で、お腹の上に石を乗せている姿が特徴的です。「海獺」以外にも、「猟虎」・「海猟」・「獺猢」とさまざまな漢字表記があります。
「ラッコ」と呼ばれるようになった由来は、アイヌ語の「rakko」。中国語の「臘虎」が語源ともいわれますが、「臘虎」はアイヌ語の「rakko」または和名の「ラッコ」の音訳と思われるので、この説は可能性が低いでしょう。
膃肭臍(おっとせい)
【膃肭臍:おっとせい】
アシカ科の哺乳類。体長は雄が約2メートル、雌が約1メートル。頭は丸く、四肢はひれ状で、全身に刺毛と綿毛が密生。北太平洋に分布し、夏、小さな島に多数集まり、一夫多妻の集団をつくって繁殖する。毛皮は良質だが、国際条約によって保護されている。ウニウ。
〈補説〉アイヌ語「オンネップ」を中国で「膃肭」と音写、この臍(へそ)が薬用として膃肭臍または海狗腎(かいくじん)の名で日本に入った。
(引用〈小学館 デジタル大辞泉〉より)
「膃肭臍」はアシカ科の海生哺乳類に属する動物で、読み方は「オットセイ」です。野生の膃肭臍は海岸に近い場所に生息し、一夫多妻の集団を形成して繁殖します。
「膃肭臍」の名前の由来は、アイヌ語の「onnep(オンネプ・オンネップ)」です。この言葉が中国語で「オツドツ」と音訳され、オットセイの一部を使った薬が「膃肭臍(オツドツセイ)」と呼ばれたことから、のちに日本に伝わった際も「膃肭臍」表記が定着し、さらに「オットセイ」と読み方が変化したと言われています。
▼あわせて読みたい
羊駱駝(あるぱか)
【アルパカ(alpaca)】
1. ラクダ科の哺乳類。南米のアンデス山中で飼われ、毛をとる。
2. 1の毛を紡いだ糸。また、それで織った織物。
(引用:『小学館 デジタル大辞泉』より)
「羊」に「駱駝(ラクダ)」を合わせた動物の名前は「アルパカ」です。羊駱駝はラクダ科に属しており、主にアンデス山岳地帯で飼育されています。良質な体毛は衣類やカーペットなどに加工され、体毛を目的として品種改良・家畜化されてきた歴史があります。
ラクダ科に属すること、羊の代わりのような役割を担ってきたことがわかると、「羊駱駝」の漢字の読み方を簡単に覚えられるでしょう。
まとめ
「栗鼠」は野生動物としても、飼育できるペットとしても知られている動物で、正しい読み方は「リス」です。元々は漢語で「リッス・リッソ」と呼ばれていましたが、日本語では「ッ」が抜けてリスと発音されるようになりました。
「栗鼠」の特徴には、小さな体や長い尻尾を持つこと、ほお袋を使って貯食することなどが挙げられます。身近な動物である「栗鼠」の読み方や生態を覚えておきましょう。

写真・イラスト/(C) Shutterstock.com
▼あわせて読みたい