「お茶を濁す」とはその場しのぎでごまかすこと
「お茶を濁す」は「おちゃをにごす」と読み、本人にとって望ましくない状況を、その場しのぎの適当でいい加減なことをいうことでごまかし、取り繕うことを意味する慣用句です。「お」を除き「茶を濁す」ともいいます。

辞書には、次のような意味が記載されています。
【御茶を濁す:おちゃをにごす】
いいかげんに言ったりしたりしてその場をごまかす。「冗談を言って―・す」
(引用〈小学館デジタル大辞泉〉より)
「お茶を濁す」は、日常会話でもよく使われる言葉です。しかし、そもそもお茶を「濁す」とはどういうことなのか、それがなぜその場しのぎをしてごまかすことを意味するのか、説明できる人は多くないでしょう。
ここからは、「お茶を濁す」という言葉の由来を確認していきます。
茶道の作法が由来
「お茶を濁す」という言葉の由来は、茶道の作法にあるといわれています。茶道には、亭主(先生)に点ててもらった抹茶を飲む際、決められた作法があります。
しかし、よく知らない者があたかも知っているかのようにそれらしくかき混ぜ、抹茶を濁らせたことから、その場しのぎをしてごまかすという意味で使われるようになったようです。
出されたお茶の濁っているさまを話題にして、作法に関する話を逸らしたことを由来とする説もありますが、後からつくられた俗説である可能性も高いと言われています。
「濁す」は日本ならではの表現
「お茶を濁す」の「濁す」は、日本人の特性などを背景とした、日本ならではの表現といえます。日本では謙虚さや周囲との協調性が重視され、白黒はっきりさせずに濁すことで曖昧にし、波風をたてないことが求められる傾向にあります。
周りと良好な関係を維持するために「お茶を濁す」のは、日本独特の慣習であるといえるでしょう。
【例文付き】「お茶を濁す」の使い方
「お茶を濁す」は、望ましくない状況においていい加減なことを言ったり言い訳をしたりすることで、その場を取り繕うという意味で使われます。「お茶を濁す」を使用した例文を確認し、実際の使い方の参考にしてください。

・彼は肝心なことについてはいつも【お茶を濁し】、話そうとしてくれない
・年齢を聞かれたので【お茶を濁して】おいた
・答えたくない雰囲気を出していたにもかかわらず、相手からの質問があまりもしつこかったので【お茶を濁した】
「お茶を濁す」の類語・対義語
「お茶を濁す」には同じような意味をもつ類語、対象的な意味である対義語があります。「お茶を濁す」だけでなく、その類語や対義語も一緒に知ることでさらに理解が深まるでしょう。
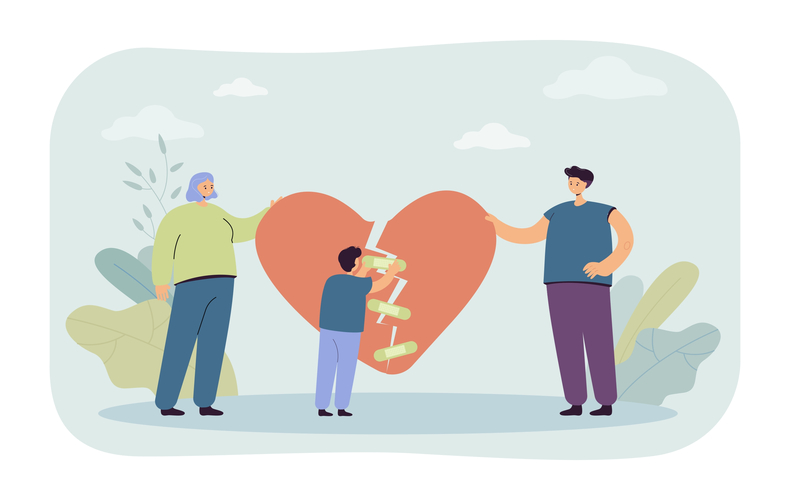
ここでは、類語として「その場しのぎ」「取り繕う」、対義語では「明るみに出る」「正々堂々」の、意味や例文を解説していきます。それぞれ確認していきましょう。
類語は「その場しのぎ」「取り繕う」
「その場しのぎ」とは後のことを考えずに、とりあえずその場を取り繕うこと、またそのような態度や口実を意味する言葉です。「その場しのぎの嘘をつく」というように使います。
「取り繕う」には、整えて見栄えをよくする、不都合を隠すためにうわべを飾るという意味があります。「取り」には取り敢えずと同じで、急場をしのぐという意味があり、繕うは修繕するという意味です。「その場を取り繕う」といったような使い方をします。







