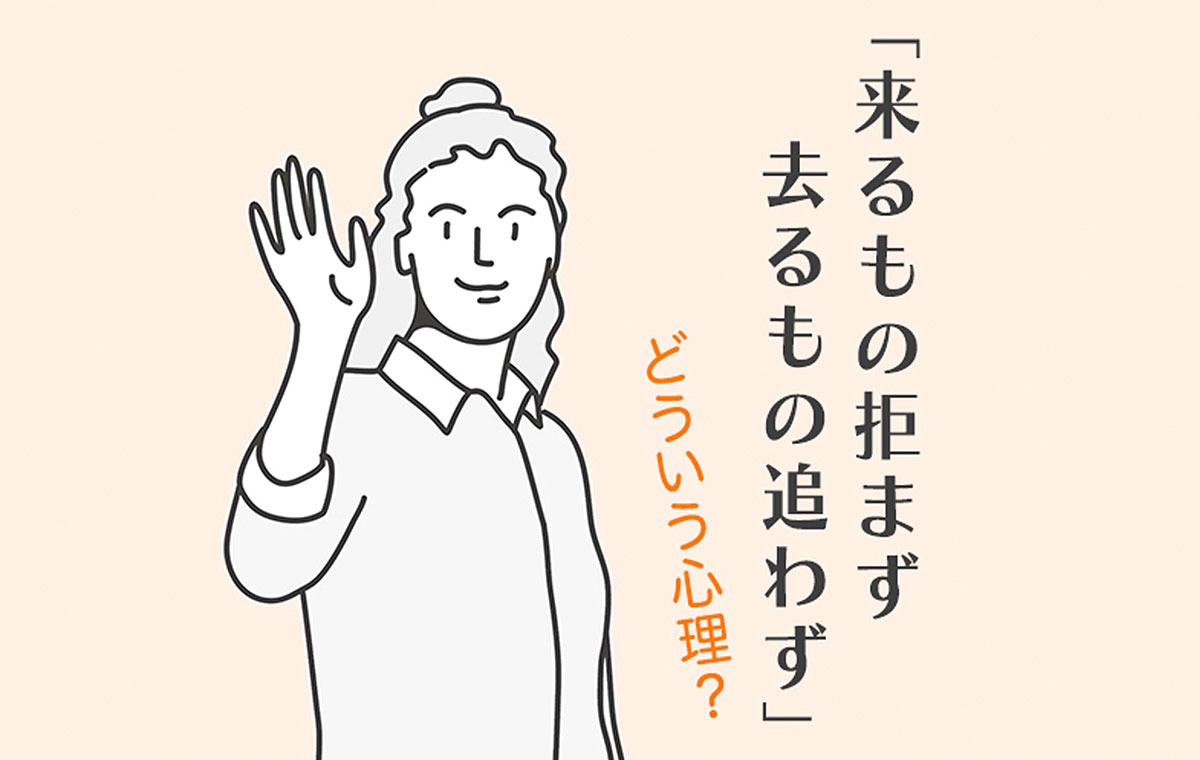Summary
- 「来るもの拒まず去るもの追わず」の意味は、離れていく相手を引き止めず、やって来る相手は受け入れる
- 懐が大きいという意味合いを持ち褒め言葉として使われるが、ドライな性格という意味で使われることもある
- 類義語には、「清濁併せ呑む」や「寛仁大度(かんじんたいど)」などがある
「来るもの拒まず去るもの追わず」の意味とは?
「来るもの拒まず去るもの追わず」とは、どんな意味を持つ言葉なのでしょうか。まずは言葉の意味と、その由来について説明します。

相手の考えを尊重するスタンスを意味する
「来るもの拒まず去るもの追わず」は、もともとは「去る者は追わず来る者は拒まず」といい、「離れていく相手を引き止めたりはせず、やって来る相手は誰であれ受け入れる」という意味のことわざです。
主に、人間関係における考え方を表した言葉といえます。
相手を選ばず付き合うというニュアンスも含まれているため、基本的には誰とでも分け隔てなく接するというスタンスです。自分より相手の思いを尊重する考え方ともいえるでしょう。
中国の「孟子」が由来の故事成語
「来るもの拒まず去るもの追わず」は、中国の思想家・孟子の逸話を集めた「孟子」に登場する言葉です。ここでは「往(さ)る者は追わず、来たる者は拒まず」と表現されました(「往(ゆ)く者は追わず」とする場合もあります)。
孟子には多くの弟子がいましたが、相手の気持ちが離れたら無理に引き止めはしないと宣言したのです。師匠として弟子に向き合う際の、価値観を示した言葉ともいえるでしょう。
また、北宋時代の文人・蘇軾(そしょく)の文章が由来という説もあります。いずれも、「自分を信じる者なら、どんな者でも受け入れる」という意思を表しています。
「来るもの拒まず去るもの追わず」の使い方
「来るもの拒まず去るもの追わず」は、人の性格に対する褒め言葉としても使われます。使える場面や、例文を見ていきましょう。
人の性格やスタンスを表す言葉
「来るもの拒まず去るもの追わず」は、人の考え方を表す言葉です。相手を選ばず受け入れる点で「懐が大きい」という意味合いを持っているため、褒め言葉としても使われます。
ただし、「来るもの拒まず」だけでなく、「去るもの追わず」の意味にも注意が必要です。場合によっては、「人に執着しないドライな性格」という意味で使われることもあります。
そのため、褒めたつもりでも、皮肉と取られてしまう可能性もあるかもしれません。誤解を避けたいときは、「来るもの拒まずな性格」と使うようにしてもよいでしょう。