お祈りメールとは、多くの人が就職活動や転職活動の中で一度は受信するものです。お祈りメールを受け取ることは決して喜ばしいことではありませんが、適切な対応や考え方を知ることで、次のチャンスを掴むきっかけにもなるでしょう。
本記事では、お祈りメールの基本的な意味から、返信方法やポジティブに捉えるためのヒント、さらにはよくある疑問への対処法まで、幅広く解説します。
お祈りメールとは? 意味と背景を紹介
まずは、お祈りメールの基本的な意味と背景について紹介します。就活や転職における位置づけを知り、今後の対応に役立てましょう。
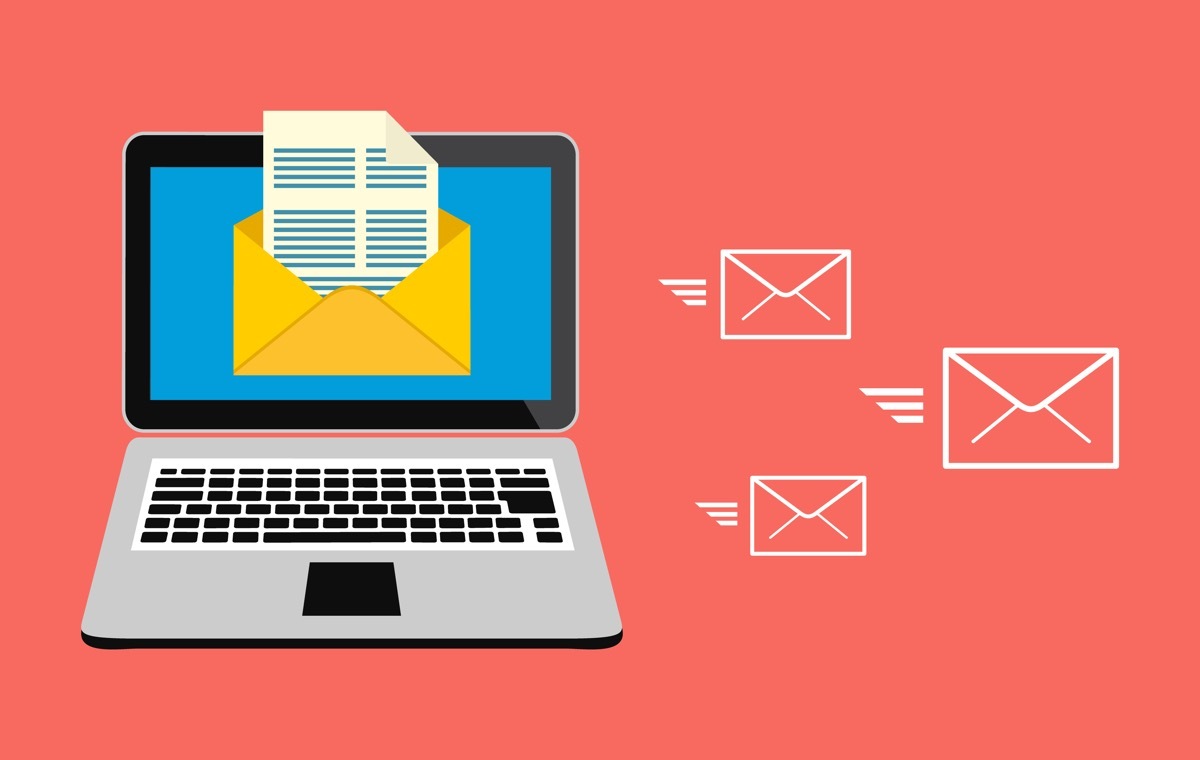
(c) Adobe Stock
お祈りメールの定義と由来
まずは「お祈りメール」の定義を辞書で確認しましょう。
おいのり‐メール【▽御祈りメール】
就職試験において、不採用であることを知らせる電子メール。就職活動中の学生などが使う俗語で、多く、文末に「今後のご健闘をお祈りいたします」といった文章が添えられていることから。
引用:『デジタル大辞泉』(小学館)
お祈りメールとは、就職試験を受けた会社からの不採用通知のメールのことです。主に就職活動中の学生などが使う俗語だということを理解しておきましょう。「今後のご健闘をお祈りいたします」や「ますますのご活躍をお祈り申し上げます」といった特徴的なフレーズに由来します。
「お祈りメール」に込められた企業側の意図
企業側がお祈りメールを送る理由は、候補者に対して敬意を持って選考結果を伝えるためです。
また、企業のイメージを保つためにも重要な手段とされています。一部の企業では、不採用の通知を丁寧に行うことで、将来的に別のポジションでの応募を促したり、候補者にいい印象を与えたりすることを意図する場合もあります。
お祈りメールに返信は必要?
お祈りメールを受け取った場合、返信は基本的に不要です。特に応募者が多数いる新卒採用では、返信が不要と見なされることが一般的でしょう。
ただし、返信が禁止されているわけではありません。例えば、感謝の気持ちを伝えたい場合には、簡潔にお礼を伝えるのもいいでしょう。以下は好印象を与える文例です。
「この度は選考の機会をいただき、誠にありがとうございました。残念な結果ではございましたが、貴社の選考を通じて業界への理解が深まり、大変貴重な経験となりました。今後とも貴社のご発展をお祈り申し上げます。」
嫌味や感情的な返信を避けるための注意点
お祈りメールを受けた後の返信で、感情的な内容や皮肉を言うのは避けましょう。不採用に対する不満や怒りをそのまま表現すると、結果的に自身の評価を下げてしまいます。また、ユーモアのつもりでも、文脈によっては失礼と捉えられることもあるため注意が必要です。
例えば、「今回の結果には失望しましたが、御社の判断は尊重します」というような表現は、一見丁寧に見えても、ネガティブな印象を与えかねません。返信する場合は、建設的で前向きなトーンを保ちながら、冷静に感謝を伝えることが最良の選択です。
お祈りメールをポジティブに捉える方法
お祈りメールを受けると落ち込むこともありますが、それを成長のきっかけに変えることもできます。ここでは、お祈りメールをポジティブな視点で捉え直し、次のステップに進むための考え方を提案します。

(c) Adobe Stock
お祈りメールを前向きに捉えるコツ
お祈りメールは、一見するとネガティブな出来事のように感じられますが、新たな成長のチャンスが潜んでいるともいえます。不採用の理由は、自分の能力そのものではなく、企業の求めるスキルや価値観とのマッチングによることがほとんどです。視点を変えることで、自分の適性に合った新たな道を探る契機となります。
また、「応募経験が自身の視野を広げた」という意識を持つことで、次の挑戦に対するエネルギーが湧いてくるでしょう。







