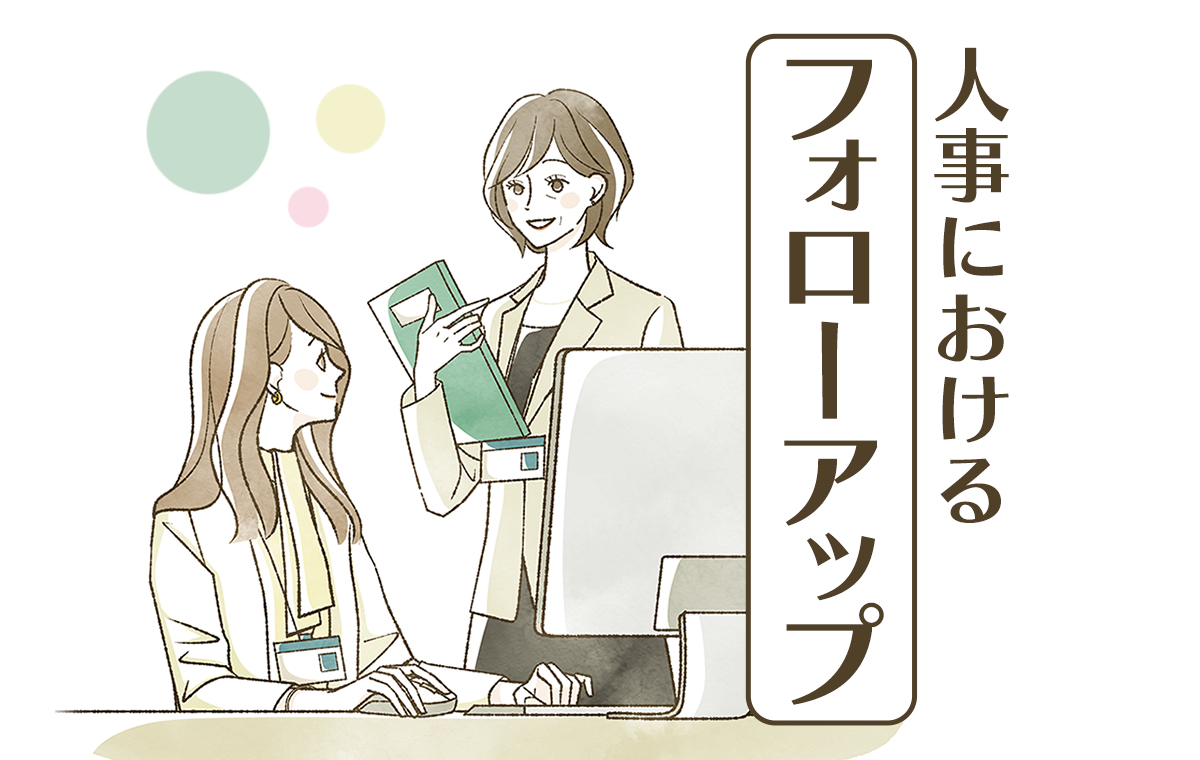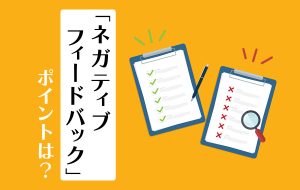フォローアップの意味とは?
フォローアップとは具体的にどのようなものか、言葉の基本的な意味を押さえます。「フォロー」「フィードバック」といった、取り違えやすい言葉との違いもチェックし理解を深めましょう。

(c)AdobeStock
人事とマーケテイングにおけるフォローアップ
フォローアップは「経過観察」「進捗確認」という意味の言葉です。物事を順調に進めるために、定期的に状況を確認したり面倒を見たりすることを指します。
ビジネスでは人事とマーケティングの分野でよく使われます。例えば、人事で研修を実施した後に、学んだことが身に付いているか受講者に確認したり、確認結果を受けて新たな研修を行ったりすることです。
シチュエーションによって多少表現が変わりますが、フォローアップの基本的な意味は、物事を「継続」「追跡」することです。
フォロー‐アップ【follow-up】の解説
[名](スル)ある事柄を徹底させるために、あとあとまでよく面倒をみたり、追跡調査をしたりすること。
引用:『デジタル大辞泉』(小学館)
フォローやフィードバックとの違い
フォローアップと似た言葉にフォローやフィードバックがあります。「フォロー」とは、相手のカバーできない部分を代わりに補うことです。
ビジネスにおけるフォローアップは、相手が十分なスキルなどを身に付けられるように伴走することなので、同じサポートでも相手に対する関わり方が違います。
「フィードバック」とは、結果が良くなるように評価やアドバイスを伝えることです。相手の成長や改善を目的とする点はフォローアップと共通します。ただし、フォローアップはフィードバックより長いスパンで寄り添う点が異なります。
人事におけるフォローアップの目的
人事が行うフォローアップにはさまざまな形態がありますが、主な目的は共通です。入社1~3年目の新入社員向けフォローアップや、何かの研修後に受講者を対象にしたフォローアップを例に、フォローアップの目的を見ていきます。

(c)AdobeStock
職場定着率を高める
すぐに辞めてしまう新入社員が多ければ、採用や教育コスト面はもちろん、職場全体のモチベーションにもマイナスの影響を与えます。
厚生労働省の「新規学卒者の離職状況」によれば、大学新卒者の3年目までの離職率は34.9%、高校新卒者の3年目までの離職率は38.4%(ともに2021年3月卒者分)で、約3~4割の新卒者が3年以内に離職しています。
また、内閣府の2020年版「子供・若者白書」では、若者の職場における悩みの1位は「職場になじめなかったから」、2位は「上司や同僚との関係が悪かったから」という結果です。このことから、人間関係の問題から辞める人が多いと分かります。
そのため、新入社員が職場になじみやすいように3年目までサポートすることは、職場の定着率を上げる効果があるでしょう。
出典:新規学卒者の離職状況 学歴別就職後3年以内離職率の推移 | 厚生労働省
出典:令和2年版子供・若者白書|内閣府
社員の実践力を育てる
フォローアップのもう一つの目的は、社員の実践力を育てることです。企業が望む成果を出すために、社員は一定のスキルや社会人としての心構えが求められます。
また、身に付けたスキルを現場で生かすには、基本的な知識だけでなく個々のケースに合わせた工夫や応用力が必要です。
フォローアップは、まだ社会経験に乏しい新卒者向けの訓練や、キャリアアップを念頭に置いた中長期的なスキルアップ、新しいビジネス知識の職場導入などを目的に行われます。
フォローアップを実施することは、社員が基礎力・応用力を身に付ける役に立ちます。
フォローアップの実施例
新入社員が業務の進め方に慣れるよう支援するなら、直接の上司が適任です。一方で、新入社員がその上司との関係性に悩んでいる場合、なかなか本人には相談できません。人事担当者との面談やメンター制度など、サポート内容でフォローアップの形態は変わります。

(c)AdobeStock
人事担当者との面談
人事担当者との面談は、しばしば行われるフォローアップ形態です。新入社員の場合は、直接の上司や同じ部署の先輩社員よりも、採用面接や新人研修で関わった人事担当者の方が本音を話しやすいことが多いのが理由です。
入社して1年以上たっていたとしても、利害関係の絡みやすい直接の上司や同じ部署の先輩よりも、人事担当者の方が悩みを素直に相談しやすいでしょう。
人事担当者との面談では、対象者が今何に困っているか、職場環境に何を望んでいるかを聞き、状況改善するための対策を話し合うのが一般的です。
上司との1on1ミーティング
上司は部下の日頃の様子や業務内容を把握しやすい立場なので、具体的なアドバイスをしやすいという利点があります。
普段の業務内ではゆっくり話しにくいので、1on1ミーティング形式のフォローアップを設定するとよいでしょう。
フォローアップの対象者が抱える日常業務での課題や、それに対するアドバイス、今後を見越したスキルアップや中長期目標について話し合うことは、上司と部下の信頼関係を築くチャンスです。
信頼関係が深まれば、コミュニケーションの円滑化や対象者のモチベーションアップも期待できます。
先輩社員によるメンター制度
メンター制度もフォローアップの一形態になります。社内の先輩社員が定期的に後輩の相談に乗って、職場になじめるようにサポートしていく仕組みです。
サポート役のメンターは、フォローアップ対象の後輩と年齢や経歴が近いほど、似たような悩みや目標を持つ相談相手として支えになりやすいでしょう。
また、同じ部署よりは他部署の先輩の方が、悩みを打ち明けやすく望ましいといわれています。相談者とメンターが性格的に話しやすい組み合わせかも考慮する必要があります。
フォローアップ研修
フォローアップ研修とは、新人研修などを実施した後で、研修の内容を復習し定着させる目的で行うものです。
ただ研修を受けるだけでは、その学びが業務にどう生かされているか、受けた対象者の理解度や定着度が把握できません。もし、うまく定着できていないなら、抜け落ちている部分について再度研修が必要です。
よく行われるフォローアップ研修のテーマには、キャリアデザインの作成やコミュニケーションのスキルアップなどが挙げられます。
以前の研修で学んだことを実際の業務にどう反映するか、受講者にプレゼンテーション形式で発表させると、知識が整理され身に付きやすくなります。
フォローアップに必要なポイント
繰り返しフォローアップを実施したとしても、的外れなやり方ではあまり成果は上がりません。フォローアップの目的を達成するためには必要なポイントがあります。適切なタイミングやアプローチ方法を理解しましょう。

(c)AdobeStock
適切なタイミングで実施する
フォローアップで重要なことは、まず適切なタイミングで実施することです。新入社員が職場になじむためのフォローアップは日常的に行われます。
入社したばかりは分からないことが多く、不安や疑問を小まめに解消する必要があるからです。例えば、入社してから1カ月の間は終業時刻間際に10分程度の面談を行うといった方法があるでしょう。
研修後のフォローアップは学びの定着が目的なので、3カ月後と1年後に行われるのが一般的です。何かトラブルや大きな変化があった直後、職務の節目も悩みを抱えやすいので、フォローアップ面談の実施が効果的です。
対象者に成長を実感してもらう
フォローアップは、対象者が成長を実感できるほど効果を見込めます。成長を実感させるには、フォローアップにPDCAサイクルを取り入れるのがポイントです。
ピーディーシーエー‐サイクル【PDCAサイクル】
《PDCA cycle PDCAは、plan-do-check-act(action)の略》生産・品質などの管理を円滑に進めるための業務管理手法の一。(1)業務の計画(plan)を立て、(2)計画に基づいて業務を実行(do)し、(3)実行した業務を評価(check)し、(4)改善活動(act)が必要な部分はないか検討し、次の計画策定に役立てる。
引用:『デジタル大辞泉』(小学館)
自分で成長目標や計画を立ててもらい、計画を行動に移してどうだったか、分析と対策を話し合いましょう。
また、業務の中で基礎力や実践力を身に付けていくことと、人事における評価や給料アップを連動させることも大切です。実力が評価に反映されると分かれば、対象者のモチベーションアップにつながります。
本音を話しやすい関係づくり
フォローアップでは、適切なタイミングを選ぶのと同じくらい、対象者がリラックスして話せる環境が重要です。
一方的に指導するような関係ではなく、対象者の意見に耳を傾け尊重しましょう。特に新入社員向けフォローアップは、対象者に悩みを打ち明けてもらい、それを解消することで職場になじみやすくすることが目的の一つです。
面談や研修でフォローアップを行うときには、対象者が話しやすい雰囲気をつくると同時に、普段から面談者との信頼関係を構築する努力が必要です。
効果的なフォローアップは職場定着率を向上させる
フォローアップとは、「経過観察」「進捗確認」という意味です。サポート内容によっていくつかのパターンがあり、新人研修の3カ月後と1年後に行われるフォローアップ研修が代表的です。
他にも、直接の上司が行う1on1ミーティングや先輩社員によるメンター制度といった形式が挙げられます。
また、実施の際はフォローアップの目的を忘れてはいけません。ポイントを押さえたフォローアップは、社員のモチベーションを高め職場定着率や貢献意欲を向上させる効果があります。それがひいては企業全体の成長にもつながるでしょう。
メイン画像・アイキャッチ/(c)AdobeStock
あわせて読みたい