Contents
首すわりとはどんな状態?
赤ちゃんの首がすわると、抱っこや日々のお世話がぐっとしやすくなります。では、首すわりとは具体的にどのような状態なのでしょうか?

首がしっかりと安定すること
大人が支えなくても「赤ちゃんの首が安定した状態」のことを首すわりといいます。首すわり前の赤ちゃんは頭部を自力で支えられず、首がグラグラして不安定です。首がすわると、赤ちゃんは自分で頭を動かせるようになります。興味のある方向へ首を動かすことも可能です。
運動機能は上から下へ、中心部から末端へと発達すると言われています。首すわりは頭に近い部分の運動機能です。しっかり首がすわることは、赤ちゃんの運動機能が発達するための第一歩といえます。
見分けるときの指標
首すわりの時期は赤ちゃんによってさまざまです。そのため、1人ずつ発達の段階を見て判断します。首すわりの基準は、自分で頭を持ち上げられるかどうかです。うつ伏せにしたときに、自分で持ち上げようとするなら、首がすわっていると考えられます。また、縦抱きにしたときに頭を支えていられるかどうかでも判断が可能です。体を傾けても赤ちゃんが自分で首を支えていられるようなら、首すわりしています。
赤ちゃんを仰向けに寝かせた状態から、両手を持って起こしたときの状態でも、首すわりしたかどうかをチェックできます。頭がついてくるようであれば首が安定しています。

いずれの場合も、無理には行わず優しくゆっくり行うようにしましょう。
専門家に判断してもらおう
自宅で簡単にチェックできそうな首すわりですが、意外と判断が難しいケースもあります。そんなときは、医師や保健師などの専門家に確認してもらいましょう。

首の状態は3~4カ月健診でも必ず確認する項目です。もし健診のときに首すわりがまだのようであれば、医師の指示に従って経過観察のための健診をすることがあります。
赤ちゃんの日常の様子を見ていて、首すわりについて疑問や不安がある場合には、かかりつけの医師に相談してみましょう。自己判断せず、専門家に見てもらうことが大切です。
首すわりが完成する時期は?
発達のスピードは赤ちゃんごとにそれぞれ違います。首すわりも同様で、早い赤ちゃんもいれば、遅い赤ちゃんもいるのが普通です。どのくらいの時期に完成することが多いのか、その時期について紹介します。

早い子だと生後2ヵ月頃から
頭から順に運動能力が発達する赤ちゃんは、数カ月で首がしっかりしてきます。
首すわりが早い赤ちゃんの場合、生後2カ月頃から頭を動かします。うつ伏せのまま頭を持ち上げたり、縦抱っこでも安定した姿勢を保てたりするようなら、首がすわり始めているサインです。自分の意思で見たい方向を向くこともできるようになります。
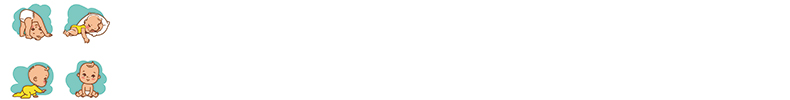
多くの子が5ヵ月頃には完成する
3~4カ月頃に完成することが多い首すわりですが、約90%の赤ちゃんは遅くても生後5カ月の終わり頃までに首すわりが完成しています。特に、発育がゆっくりの場合や、早産だった場合、頭が大きく重いといったケースでは、首すわりまで時間がかかりがちです。赤ちゃんそれぞれで状況が違うため、個々の体格や状態をよく観察します。
目安としては5カ月までに首すわりすることが多いですが、個人差があるため、平均的なタイミングで必ず首すわりするとは限りません。あくまでも目安として考えておくとよいでしょう。
参考:乳幼児身体発育調査:結果の概要 4 一般調査による乳幼児の運動・言語機能について|厚生労働省

遅いと感じたら専門家に相談を
首すわりできるようになる時期は、赤ちゃんによって全く違います。生後1カ月頃からしっかりしてきたというケースもあれば、生後6カ月までかかったというケースもあり、さまざまです。
もしも、首すわりが遅いと感じるなら、医師や保健師など専門家に相談しましょう。生後5カ月を過ぎても首すわりをする様子が見られない場合には、精密検査が必要なこともあるからです。
ただし、平均はあくまでも基準として覚えておき、個人差が大きいということも心に留めましょう。あせり過ぎず、ゆったりした気持ちで赤ちゃんの成長を見守る気持ちも大切です。
その上で専門家に相談できると、気持ちに余裕を持って対応しやすいでしょう。
練習方法と注意点

日常生活の中で少し工夫すると、首すわりのための練習ができます。注意すべきポイントを押さえて、安全に気をつけながら練習させてあげましょう。遊びや授乳をしながら、首の周りの筋肉を鍛えられます。
うつ伏せにしてあげる
赤ちゃんをうつ伏せにして、ひじを肩より下で立ててあげましょう。すると、自分で頭を持ち上げる練習ができます。興味のあるものが目の前にあると積極的に頭をあげやすくなるので、おもちゃを使ったり声掛けをしたりしながら遊び感覚で取り組むのがおすすめです。

最初は1回につき1~2分から始めて、慣れてきたら5~15分を目安にします。1日に4~5回程実施すれば、充分な練習になります。注意したいのは、授乳後すぐにやらないことです。うつ伏せはお腹が圧迫される姿勢なので、授乳後は吐いてしまう可能性があります。
縦抱きにしてみる
抱っこを縦抱きにするのも、首すわりの練習につながります。片手を赤ちゃんの膝下に入れ、反対の手で体を支えるように抱っこするだけです。慣れてきたら、少し前傾姿勢になるようにしてみてましょう。

縦抱きのまま授乳するのもおすすめの方法です。授乳中の赤ちゃんは、ママの顔を見上げようと頭を持ち上げます。そのため、自然と首すわりのための筋力が鍛えられます。授乳しながらであれば、わざわざ練習の時間を取らなくても、毎日の生活習慣の中で自然にできるのもポイントです。
必ず安全な場所で行おう
練習をするときには、安全を確認した上で行うことが大切です。必ず、大人の目がある状況で実施します。特に、うつ伏せは「乳幼児突然死症候群(SIDS)」の誘因ともいわれているので注意が必要です。

赤ちゃんのコンディションも確認します。きちんと起きているときで、空腹でも満腹でもない機嫌のよいタイミングを選ぶことが大切です。
周りに危険なものがないか、赤ちゃんが誤って落ちてしまうような段差はないか、といった点にも気を付けて、安全な場所を確保します。
無理し過ぎないことにも注意しましょう。たくさん練習したからといって、その分早く首すわりが完成するとは限りません。少しずつできる範囲で練習することが大切です。
首がすわる前の正しい抱っことは

まだ首が安定しない赤ちゃんを抱っこするときには、どこに注意して抱くとよいのでしょうか?安全に抱っこをするためのポイントを解説します。
必ず首と体をしっかり支える
ポイントになるのは、「常に首を支えておく」ことです。安定しない首筋は、手でしっかり支えてグラつかないようにします。また、抱っこの仕方は横抱きが基本です。首すわり前の縦抱きは赤ちゃんの負担になるだけでなく、お母さんも常に首回りを支えていなければなりません。
横抱きは、ひじの内側に赤ちゃんの頭を乗せ、体と首をしっかり支えて抱っこする方法です。このとき、赤ちゃんの体を自分に密着させると、しっかり支えやすくなります。

安定した状態で抱っこできれば、首すわり前でも安全にお世話が可能です。
赤ちゃんに合った抱っこ紐を使う
抱っこ紐を使って抱っこすることもありますが、必ず「赤ちゃんの発達に合ったものを選ぶ」ことが大切です。首すわり前の赤ちゃんであれば、横抱きをすることが多いため、横抱き用のものを使います。

首すわり前でも縦抱きができる抱っこ紐もあります。ただし、長時間の使用は赤ちゃんの負担になる可能性がありますし、ぐずってしまうこともあるでしょう。そのため、使用は短時間に抑え、たまに姿勢を変えてあげるのがポイントです。また、どの抱っこ紐を使う場合でも、必ず説明書通りに使うことが大切です。正しく使うことで、不意の事故を防ぐことができます。







