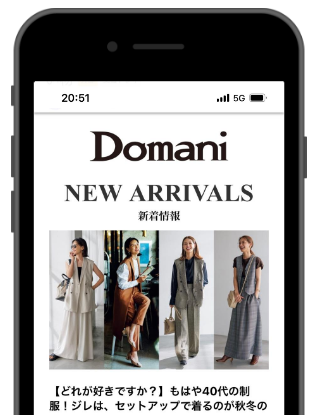まもなく初めての子どもが生まれるM氏は、ツイッターに流れてくる母親たちの夫への不満を眺めては「世の中には、こんなダメな父親がいるんだなぁ」と思っていた。M氏は「俺は、絶対にこんな父親にならないぞ。子どもは2人の子どもなんだから、妻だけに大変な思いをさせたりしないで2人で育てるんだ」と意気込んだ。
しかし、実際に子どもが生まれてみると、M氏は自営業という立場柄、取引先との付き合いを断つこともできない。それでも家に帰れば直ちに妻から育児をバトン・タッチし、子どもを寝かしつけ、朝まで頑張っていた。でも産後数カ月が過ぎたころ、さすがに疲れてきて、最近はついグッタリしてしまうこともある。
M氏は、そんな時、こんな妄想もしてしまうという――自分が見ていないところで、妻がスマホをつかみ取り、ツイッターへ自分のダメぶりを書き込んでいるという妄想だ。子どもはかわいい。だが、頑張っても、頑張っても、妻に満足してもらえないのではないかという不安に、M氏はさいなまれていた。
男性の育児ストレスがしばしば話題に

育児に時間を使う父親は増えてきたが、その影でM氏のような男性の育児ストレスも専門家の間でしばしば話題になる。これは一体なぜだろう。
父親の育児休暇取得率という数値は、強制的に取得させる制度ができれば増やせるだろう。でも肝心なのは、夫婦がどのように支え合って過ごせるかだ。
「育休をとってくれても、実際に育休をとった夫が家事・育児をした時間は1日わずか2時間以下が3割強」――こんな調査結果も話題を呼んだ(『パパ・ママの育児への向き合い方と負担感や孤立感についての調査』日本財団×「変えよう、ママリと」調べ 2019年10月実施)。
育児も男女平等が理想なのに、なぜか思うようにならないから女はいら立ち、男は肩身が狭い――令和の子育てにはそんなジレンマがあり、無視できない育児ストレスとなっている。
「ヒトも哺乳類である限り、育児の男女平等を実現することは生物学的に不可能なんです。そこに固執すると、思うようにいかないイライラがつのり、育児はもっとつらいものになってしまいます」
そう言うのは、動物行動学者・神経行動学の研究者でとくに動物の「コミュニケーション」「養育行動」に造詣の深い菊水健史氏(麻布大学獣医学部教授)である。この分野は人間もヒトという霊長類の一種として扱い、行動特性や脳内物質・神経システムの解明などを通じて、私たちが私たち自身を知るヒントを提供している。
自身も1児の父である菊水氏は、「僕も妻に『それは研究の世界の話でしょう』と言われますが」と苦笑しながら「どんな生物にも、子育てには明らかな『性差』があります。男性は、女性より苦手です」と言う。
「平等という言葉を、どうとらえるかが問題です。学業やビジネスでは、基本的に男女の差はないと思っていいでしょう。勉強や仕事は、大脳皮質を使うヒトに特有の作業だからです」
しかし、子育てで使われる脳は、そこではない、と菊水氏は指摘する。
「子孫を産み育てる行動は、ヒト以外の動物にもある非常に古い脳がつかさどる仕事です。そこにある視床下部という器官からオキシトシンというホルモンが分泌されて養育行動が起こりますが、実は、男性ホルモン(テストステロン)は、育児行動を起こすホルモン『オキシトシン』の分泌を阻害するのです」
男女は脳内物質に違いがあると踏まえて
オキシトシンは、子どもが巣から落ちたら拾いに行ったり、子どもを温めたり、なめたり、食事を与えたりする養育行動を起こさせる。菊水氏がすすめるのは、男女は脳内物質に違いがある生き物だということを踏まえたうえで、お互いの特性を生かした協力体制をつくることだ。
「近年、分子遺伝学的手法や、微量分子測定の技術革新によって、心や行動を左右するホルモンや神経伝達物質などがどんどんわかってきています。夫婦、親子の関わりもさまざまな分子が関与していることがわかってきたので、子育てを楽にするには、こうした知見も参照していくべきではないでしょうか」
「人間だけを見ているとわからないのですが、生物は、種によって、子育てで誰が何をするかが決まっています。そして、何かの理由でその環境が整わないと、親は強いストレスを感じます。動物実験では母親が消耗して痩せてしまったり、子どもをなめる回数が減ったりして、子どもの成長にも影響が出ます」(菊水氏)
哺乳類は、メスはすべて育児をするが、クマのように群れをつくらない種の中には、オスは交尾後どこかへ消えてしまうものが多い。メスは生まれてきた子どもをひとりで育てる。哺乳類の種の約半数は、このタイプだ。
家族を中心とした群れを作る種でも、もっぱら母親が子育てをする。オスは、少し大きくなった子どもと遊んだりはするが、母乳を飲んでいる間は基本的に関わらない。菊水氏によると、群れで生活する動物のオスが子育てをしないのは「子どもが自分の子どもである確証がないから」だそうだ。
例外はある。マウスは、オスも小さいうちから子どもを温めたりして、かいがいしく小さい子マウスの世話をするが、そこにはからくりがあった。
「マウスは妊娠中のつがいを同じケージに入れておくと、メスのフェロモンでオスのテストステロンが下がってしまうんですよ」
つがいを形成する動物では、父親が養育に携わることが多い。これは自分とずっと一緒にいるメスの子なら、わが子であることはある程度担保されるから。
でも、同じげっ歯類でも、ラットのオスはテストステロンが下がらず、子どもが生まれてきても何もしない。
「私たちも育児行動の実験を重ねていますが、育児をしない種のオスに育児をさせるのは、もう大変なんです。でも、マウスのオスも、テストステロンを作る器官である睾丸を切除したら、途端に育児を始めました」
マウスの世界でも、父親の育児はかくも厳しい。
では、ヒトの育児はどんな原型をもっているのか。
哺乳類のもうひとつのタイプは「共同養育」で、近年、生物学の世界ではこのスタイルが注目されている。ヒトは、このグループの代表だ。
まさに戦前の日本
「ヒトは、母親1人で子どもを育てる種ではありません。母親が中心ですが、祖母、姉妹と共に、集落の女性たちが協力して育てます。男性は、子どもがある程度大きくなってから子どもと遊ぶようになります」
まさに、戦前の日本だ。
「これはヒトや一部の動物にしか見られません。ラット、イヌ科の動物、あとはミーアキャットやプレーリードックなども、とても上手に共同養育をします。お祖母さん、お姉ちゃんに当たる3~4頭が母親と一緒に育児をすることが多いですが、血縁関係がないこともあります」
ヒトは共同養育の傾向が顕著で、子育てに関わる女性の人数がとても多く「集落に住む女性全体が育児に参加する種」とさえ言われている。
「私は、今、その形が崩れているのが、育児が大変になっている最大の原因だと思います。経済効率をよくするために若年人口を都市部に集中させ、転勤族を作った企業がそれを壊してしまいました。昔の長屋暮らしにあった深い懐から若者を引っ張り出し、ヒトという種が本来持つ、子どもを育むネットワークを分断してしまったのです。
今、地域コミュニティーを活性化しなくてはといろいろなプロジェクトが動き出しましたけれど、まだ、子どもを簡単に預けられるご家庭はほとんどないですよね。お母さんは、自分が体調を崩しても耐えてひとりで子どもをみるしかない。その矛先が、父親に向かっているのです」
菊水氏は、夫に不満な母親たちの姿をそう読み解き、育児そのものの危機を感じていた。
「では、大家族に戻ればいいのかというと、それも、生物学的に見て心配があります。生物には、自分が育てられたように子どもを育てるという『世代間連鎖』という現象があるからです。子育てには大家族がいいのですが、核家族で育った子どもは大家族の中で生きていく術を学んでいません。最近は、夫婦2人の暮らしも煩わしいという人が増えています。こうして、ヒトは、どんどん孤立の方向に向かっています」
そんな中で、現代においても母親が助けられながら子育てをするにはどうしたらいいのか。「保育園の保育士さんやベビーシッター、出産施設の助産師さんなどがもっと身近な存在になれば、共同養育に近い形かもしれません。
また、インターネットを利用し、親族がたくさんいる地元から引っ越さずに、リモートワークで東京の会社で働ける人も、もっといるはずなんです。働き方改革もそのあたりを真剣に知り組むべきで、こうしたことをおざなりにしたまま父親にだけ『やれ、やれ』と言ってもできないということです」。
父親も子どもと関わることでホルモンに変化

もちろん、父親は、母親のいちばんそばにいる存在だから活躍してほしい。
近年、ヒトの男性についての研究は増えてきており、それによると、子どもと関わる行為により、ヒトの父親もテストステロンが少しずつ減り、オキシトシン、プロラクチンといったホルモンが増えることが知られるようになった。
「スキンシップや見つめ合いは母親にも赤ちゃんにもオキシトシンを分泌させますが、これは父親と赤ちゃんでも同様なことが起きるんですよ」
ただ、女性はといえば、出産前からオキシトシンがどんどん増えていて、オキシトシンが陣痛を起こし、産後は子どもに母乳をあげるたびにオキシトシンが大量に出る。女性ホルモンはオキシトシンの効きをよくしたり、産生を促進したりもする。
「子どもが泣いても私はすぐに起きるのに夫は寝ている」「夫が指示待ちでイライラする」という不満を持つ母親は多いが、ホルモンの出方にハンディを持つ夫は、妻と同等にできなくても責められないところがある。そうであれば、夫は妻をいたわったり、妻が育児以外の事をやらずにすむように家事や片付けなどをサポートしたりするという作戦が有効ということになるだろう。そうしながらも子どもと触れ合っていれば、父親もオキシトシンが増えていく。
菊水氏は、育児の内容に、性による得意・不得意があることを示す研究も多いと言う。
「寝かしつけのように『子どもがじっとしている育児』は、テストステロンが多い男性がやると声が大きかったり、子どもにくわえる力が加減できなくて強すぎてしまったりすることがあります。すると、子どもが緊張して、かえって目が覚めてしまい、なかなか寝てくれません。反対に『高い、高い』のような、子どもが大きく動く育児は、一般的にいって、男性のほうが得意です」
「育児をしていると、男性ホルモンが減ってしまうのか」と、不安になる男性もいるかもしれないが、この点はどうだろう。
「そこは、トレード・オフです。諦めましょう」
では、やはり男性が育休をとったら男性社会の競争では不利になってしまうのか? これについては対策が打てる。
オン・オフの切り替えをしっかりやることが大事
「ひとりの人が「日昼は競争モード、夜は親和モード」といった使い分けをすることは可能ですよ。いわゆる『オンとオフの切り替え』をしっかりやることが大事です」
もちろん、1人ひとりを見ていけば個性があり、繊細な動作が得意な男性もいるだろう。女性も今は競争社会で活躍しているので、テストステロンの数値が高い女性が増えているという。夫婦の役割分担には、その夫婦にしかわからない機微があると思う。
ただ、私たちには遺伝子に書き込まれている、種の特性がある。子どもを迎えた夫婦がどうしても「これは、違う」と感じるものがあるなら、それは、人間がもともと集団で子育てをしていた時代の名残なのかもしれない。
父親がもっと育児をすることは、母親ひとりでやるよりはずっと楽になるだろうが、それでも、かつては経験豊かな大人数の集団でやっていたことを、たった2人で頑張ろうとしているわけだ。
お互いに多少の不満があっても「ふたりだけなのに、よく頑張っているよね」とお互いをねぎらう気持ちがあれば、現代の育児も、もっと楽になるのではないだろうか。そして、応援してくれるほかの人を少しずつ増やしていくことだ。
出産ジャーナリスト
河合 蘭(かわい らん)
1959年東京都生まれ。カメラマンとして活動後、1986年より出産に関する執筆活動を開始。東京医科歯科大学、聖路加国際大学大学院等の非常勤講師も務める。著書に『未妊―「産む」と決められない』(NHK出版)、『卵子老化の真実』(文春新書)など多数。2016年『出生前診断』(朝日新書)で科学ジャーナリスト賞受賞。

東洋経済オンライン
東洋経済オンラインは、独自に取材した経済関連ニュースを中心とした情報配信プラットフォームです。
写真/Shutterstock.com