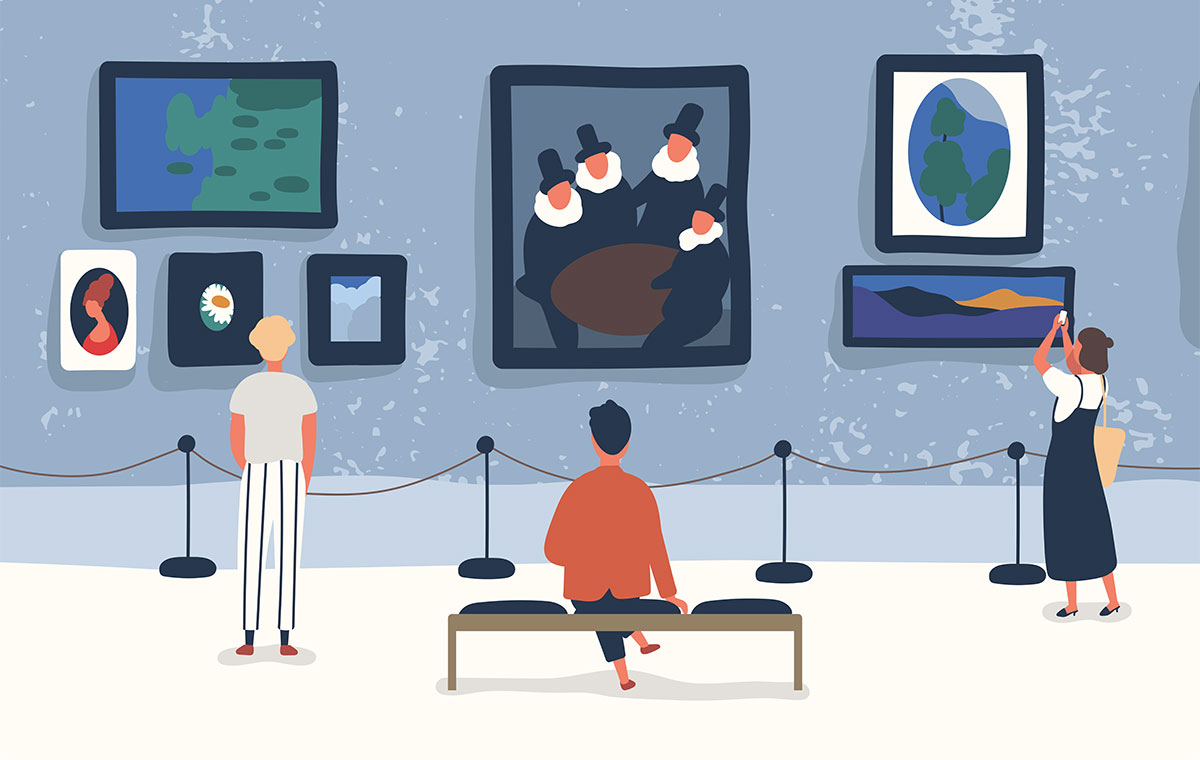Summary
- 文化の日は、毎年11月3日で、「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを願って作られた祝日
- もともとは明治天皇の誕生日で、終戦後は日本国憲法の公布日であることから文化の日と名付けられた
- 毎年同じ日が祝日になることや天候に恵まれる傾向が高いことから、結婚届の提出や結婚式を挙げるカップルが多い
Contents
文化の日とは
祝日にはそれぞれに意味が込められています。気になる祝日については、込められた願いや制定された背景などを知っておくことで、今までとは違った気持ちで祝日を過ごすことができるかもしれません。今回は、11月の祝日である「文化の日」について解説します。
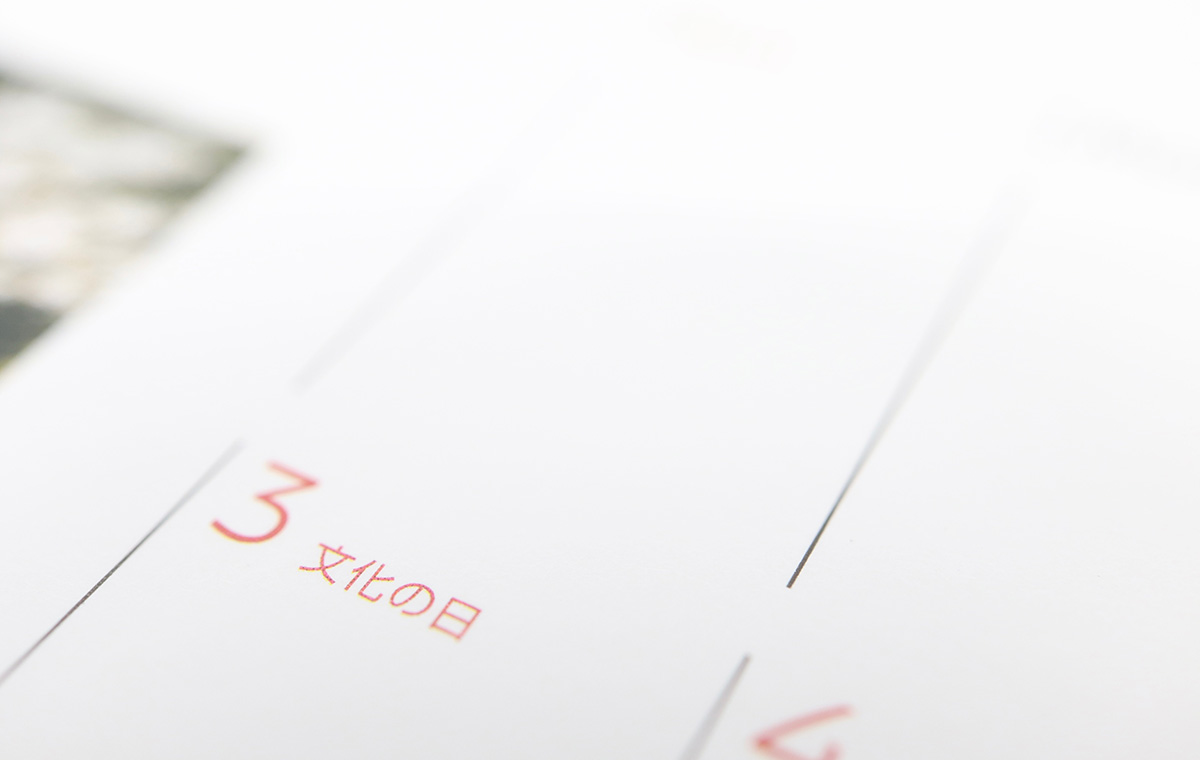
(c)AdobeStock
11月3日の国民の祝日
文化の日は、国によって定められた国民の祝日の一つであり、毎年11月3日と日付が決まっています。1946(昭和21)年11月3日に、「平和と文化を重視する日本国憲法が公布された」ことから、「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを願って作られた祝日として制定されました。
もともとは明治天皇の誕生日、明治節
11月3日は明治天皇の誕生日です。日本には天皇の誕生日を「天長節」と呼び、祝日とする習慣があります。明治天皇が崩御されると、天長節は次の大正天皇の誕生日となり、明治天皇の崩御日を「先帝祭」としました。しかし、大正天皇が崩御されたことにより、明治天皇にまつわる祝日はなくなってしまったのです。
明治天皇は文明開化の時代を治め、日本の近代化を進めた人物であり、国民の尊敬を集めていました。そのため、明治天皇を記念する祝日を形に残したいと希望が多かったことから、11月3日は「明治節」という祝日として残ることとなりました。終戦後は日本国憲法の公布日であることから「文化の日」と改めて名付けられて現在に至ります。これも、戦後の事情がありながらも当時の日本人が11月3日の祝日を残したいという思いを持っていたからだといわれています。
婚姻届を出すカップルが多い?
文化の日をはじめ毎年同じ日にある祝日は、婚姻届を提出する日に選ぶカップルも多くみられます。カレンダーに記載されているため忘れにくく、祝日のため仕事がある人も休みがとりやすいというメリットがあるのです。役所に婚姻届けを提出しに行くことはもちろん、その後も夫婦でゆっくり結婚記念日を祝うことができます。さらに、文化の日は天候に恵まれる傾向が高いことから「晴れの特異日」とも呼ばれています。婚姻届の提出だけでなく、結婚式の日程を文化の日に決めるカップルも多数見られるのもそのためです。
文化の日のイベント・行事
文化の日には、子どもも大人も楽しむことができるさまざまなイベントや行事が開催されています。把握しておくと毎年の文化の日の過ごし方が充実するはず。具体的にどのようなイベント・行事があるのかを見ていきましょう。

(C)Shutterstock.com