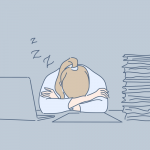職場など身の回りに、「この人は、周囲の人に頼りすぎだな…」と感じる人はいませんか? 特にそれが会社の部下や後輩だと面倒を見る機会が多く、負担にもなりますよね。そこで本記事では、「おんぶにだっこ」の意味や「おんぶにだっこ」に当てはまる人の心理、付き合い方などを解説します。
「おんぶにだっこ」の意味とは
辞書を見ていくと、「おんぶにだっこ」は以下のように説明されています。
何から何まで人の世話になること。他人の好意に甘えて頼り切ること。「親に―の状態」
『デジタル大辞泉』(小学館)より引用
「おんぶにだっこ」とは、おんぶをしたらそれだけでは満足できず、だっこを催促して甘えてくる子どもの様子から例えられた言葉です。子どもが親に対して際限なく甘えてしまうように、他人に頼りきって、何から何まで任せきりになってしまう状態のときに用いられます。類語は、「他人任せ」「人任せ」「他力本願」「任せきり」などです。

(c) Adobe Stock
おんぶにだっこを使った例文
「おんぶにだっこ」は聞いたことはあっても、実際に使ったことがない言葉かもしれませんね。ここでは、ビジネスシーンと日常の場面で使われる例文を紹介します。
いつまでもA社におんぶにだっこの状態では、我が社は成長しません。
取引先など、特定の会社に頼りきりになっている状態が予想できますね。あまりに他社に依存していると、その会社が潰れた際に共倒れになるリスクもあります。そのような状況に危機感を抱いて、社員が「おんぶにだっこではいけません」と改善を要求することもあるでしょう。
いつも、おんぶにだっこで申し訳ありません…。
いつもお世話になっている上司や先輩へ、謝る時にも使います。仕事を何度も教えてもらったり、ミスした仕事を手伝ってもらったりとお世話になりっぱなしで申し訳ないと感じた時に、このように伝えます。「おんぶにだっこ」を使うことで、自分が一方的に迷惑をかけているというニュアンスを伝えることができますね。
弟は社会人になっても両親の世話になっているので、「おんぶにだっこをやめなさい」と注意した。
日常生活で「おんぶにだっこ」を使う時には、大人としての責任感に欠けていることを揶揄する場面で使用します。社会人になっても、両親に甘えるなど自立していない様子を見かねて、例文のように注意をすることもあるでしょう。
おんぶにだっこな部下の特徴
何かと他人に頼ってばかりで、1人で判断したり行動したりできない部下の対応に困っていませんか。そのような「おんぶにだっこ」状態の部下には、いくつかの共通した特徴が見られます。

(c) Adobe Stock
自分に自信がない
このような人には、「自分に自信がない」特徴が共通する傾向にあります。一見すると、上手に他人を頼っているように思えますが、実際は自分に自信がなく、挑戦することに臆病になっているようです。
逃げ腰の姿勢が癖になっているため、「自分には問題を解決する能力がない」とやる前から決めつけていることも…。自分がやって失敗することが怖いため、常に消極的な姿勢で主体性がなく、指示がないと行動ができません。
▼あわせて読みたい
面倒くさがり
面倒くさがりな性格も特徴の一つです。「面倒だな」と感じると、他の人がいるから自分はやらなくても任せておけばよい、という思考に走りがちです。何かに関わるということに対して、消極的ともいえるでしょう。
「誰か他にできる人がいるなら、その人がやればよい」と考えているため、手伝うことからも免れようとします。判断することや責任を負うことに対しても面倒くささを感じ、自分の頭で考えられないという人も多く見られます。
▼あわせて読みたい
人任せにする心理
何事もおんぶにだっこ状態になってしまう人には、どのような心理が隠れているのでしょうか。改善を促す前に、まずは相手の心理状態をしっかりと理解しましょう。
自分がやるより人に任せた方がよい
「自分に自信がない」ことが理由で人任せになっている人は、「自分がやるより人に任せた方がよい」と考えている可能性も…。自分がやるよりも、最初から得意な人がやった方が効率的だと考えているのです。
例えば、PC操作・資料の作成・数字の計算・電話対応などを苦手とする人は多いものです。そして、おんぶにだっこの人は、自分が苦手なことには手を出そうとしないケースも多々みられます。できないからやらないという考えが根底にあるため、「苦手を克服しよう」「もっと成長しよう」などといった向上心を抱きにくいのでしょう。