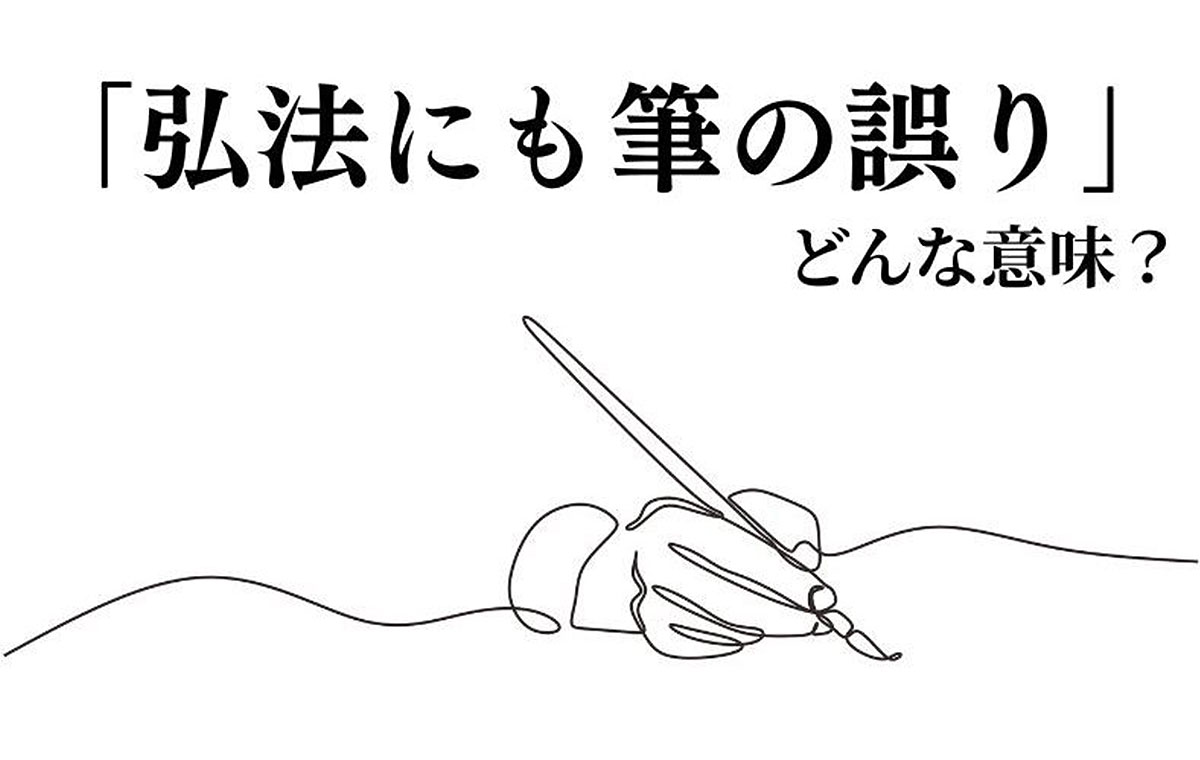「弘法にも筆の誤り」の意味や読み⽅とは?
そもそもこの「弘法」とは誰のことかはご存じですか? 弘法とは、平安時代初期の僧侶・空海のことです。空海は、真言密教を日本に広めた功績から「弘法大師」と呼ばれました。その弘法大師が筆を誤ったことによって、ことわざになったのはなぜでしょうか。その意味や語源、由来なども見ていきましょう。

意味や読み方
「弘法にも筆の誤り」は「こうぼうにもふでのあやまり」と読みます。実はこの「弘法」こと空海は、嵯峨天皇、橘逸勢(たちばなのはやなり)と並んで「三筆(さんぴつ)」と呼ばれた書の名人だったのです。書の名人であるにもかかわらず、筆に対するこだわりのない人でした。どんな安くてささくれているような筆でも、立派な書を書いていたそうです。
そのような立派な弘法大師でも、文字を書き損じることがあったのでしょう。そのことから「弘法にも筆の誤り」とは、「どんなに上手な人、名人であっても間違えたり、失敗したりする」という意味で使われます。
語源・由来
いったい弘法はどんな時に何を間違えたのでしょう。ことわざになるほどの大きな間違いをしたのでしょうか?その語源は『今昔物語』の巻十一の第九話におさめられています。
弘法は勅命を受けて、京都の大内裏にある応天門に掲げる額を書くことになりました。書き終えて額を掲げてみると、「応」の文字に上の点を打ち忘れていたのです。すでに高い位置に取り付けられた額をおろすわけにもいきません。みんなどうしたらいいものか困っていました。その時弘法は、その額めがけて筆を投げつけ、見事に点を打ったというお話です。
この逸話から「弘法にも筆の誤り」ということわざが生まれたそう。「すごい人は間違えてもその直し方がすごい。さすがである」という意味もこのことわざには含まれています。では、なぜ「弘法にも」という表現と、「弘法も」という2つの表現があるのでしょうか? これを普通の言葉に置き換えてみると、
・名人にも間違いはある
・名人も間違えることがある
となります。
表現の仕方が若干異なる程度でほとんど同じ意味です。さまざまな国語辞書を見ても明確な違いを指摘しているものはなく、現実的にはどちらでもよいということになるでしょう。
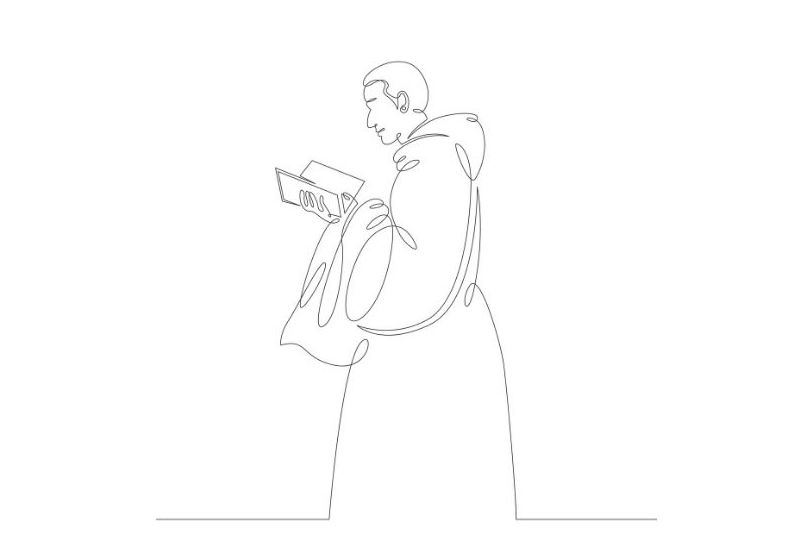
「弘法にも筆の誤り」使い⽅を例⽂でチェック
では、この「弘法にも筆の誤り」を例文でチェックしながら使い方を覚えましょう。