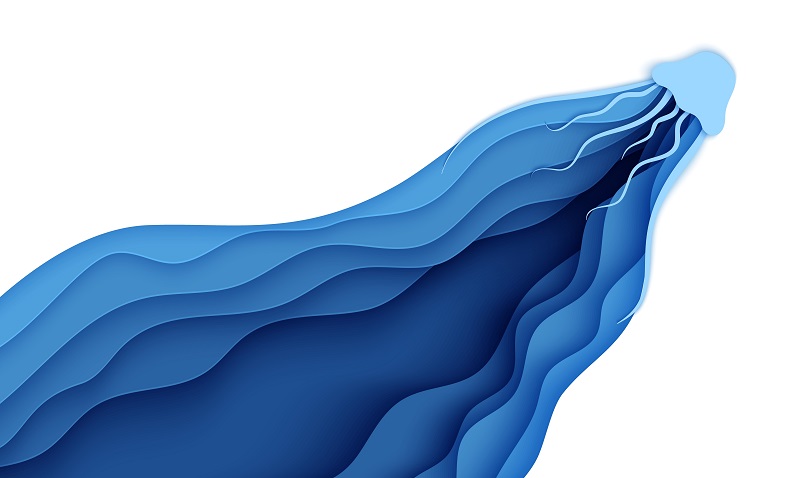「水母」とは?
「水母」は「すいぼ」と読み、辞書で調べてみると以下のようにあります。
腔腸動物の基本形のうち、浮遊生活を送るもの。ハチクラゲ類・ヒドロ虫類など。体は寒天質からなり、傘の形をしていて、これを伸縮させて泳ぐこともある。傘の中に消化循環系・生殖器があり、骨はない。傘の周縁に多数並ぶ触手には刺胞(しほう)があり、強い毒をもつものもある。
引用:小学館 デジタル大辞泉
「水母」はクラゲの漢名となります。
「水母」の由来とは?
何故クラゲを「水母」と表すのか? というと、それは定かではありません。しかし、中国、晋の時代の書物『博物志』の中に出てくるものが有力であるとされています。それは「水母」には目がないため(実際には目のような感覚器官があり光は感知します)、目のあるエビが道案内をしているかのように寄り添っていた。その姿を母と子に例えて「水母」という名称になった、という説が。
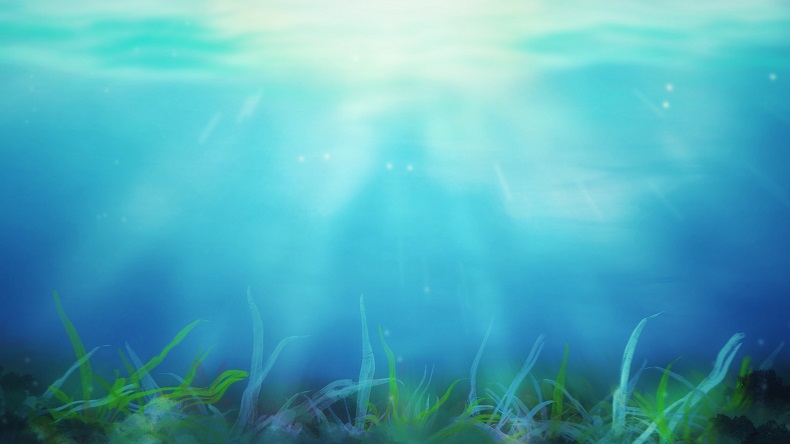
「水母」と「海月」、 どちらが正解
どちらも「くらげ」を表現します。クラゲを表す漢字で、多くの人が最初に思い浮かべるのは「海月」ではないでしょうか。「海月」は、クラゲが海中を漂う姿が、海の中に月があるかのようにみえたことから「海月」と表すようになったとされています。またクラゲは他に、「水月」「鏡虫」「久羅下」と表記されることもあります。
そもそも何故「クラゲ」といわれるようになったのか? その語源については諸説あります。目が見当たらなかったため、見えないだろうとされ「暗気」から由来したとされる説や、クラクラと回転しながら海中を浮かぶ姿から「クラゲ」といわれるようになったという説。「輪笥(くるげ)」という丸い入れ物に、形が似ていたことから由来するという説まで様々あります。
「水母」を英語で表すと?
「水母」は英語で「jellyfish」です。直訳すると「ゼリー状の魚」。「水母」はゼラチン質で、そのほとんどが水分でてきているそう。プルプルとした見た目がゼリーのようですよね。

「水母に刺された」を英語でいうと?
もし英語圏で「水母」に刺されたときは「stung by a jellyfish」といいましょう。「stung」は「刺す」ことを意味する「sting 」の過去分詞形。昆虫や生物の針や刺毛によって刺されるときに用います。
例文:My daughter was stung by a jellyfish.(私の娘は水母に刺された)
ちなみに「jellyfish」は「弱虫」や「意思の弱い人」、「意気地なし」を表す際に使われる言葉でもあります。
「水母」を使ったことわざとは?
ことわざの中には、「水母」が使われているものがいくつかあります。その意味や使い方をチェックしていきましょう。