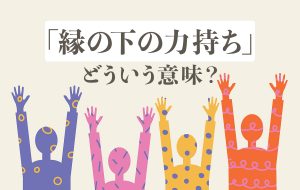内助の功とは身内の活動を援助するはたらきのこと
内助の功とは、身内の活動を陰から援助するはたらきを指す言葉です。「内助」には内部から支える助力、「功」には苦労して成し遂げた結果や手柄といった意味があります。
たとえば、表に立って仕事をする身内が出世するために、パートナーが生活面や精神面などで献身的にサポートしているケースが当てはまります。
■夫の活躍を支える“妻”のはたらきを指すことが多い

内助の功は、身内の活動を支えた功績を意味する言葉であり、援助や助力をする人物が限定されているわけではありません。
しかし、一般的には、夫の活躍を支える妻のはたらきをあらわす言葉として使われます。
■語源は戦国時代の武将「山内一豊」の妻
戦国時代から江戸時代にかけて活躍した、「山内一豊」の妻「千代」のはたらきが、内助の功の語源とされています。
千代は嫁入りの際に持参したお金で、一豊のために立派な馬を用意しました。そして、千代が用意した馬が「馬揃え」といわれる馬を集める行事で織田信長の目に留まります。
この馬揃えをきっかけに、一豊は順調に出世をしていったことから、内助の功という言葉が生まれたといわれています。
【例文付き】内助の功の使い方
内助の功は、身内のサポートによって活躍をした際に、「内助の功のおかげだ」あるいは「内助の功があってこそだ」などと使うことが多い言葉です。以下に、いくつかの例文をご紹介します。
・彼が出世できたのは、奥さんの内助の功があってこそだというのは、よく聞く話だ
・今回、無事に昇格できたのは、妻の内助の功のおかげだ
・あの野球選手の今季の活躍は、内助の功によるものだろう
内助の功の類似表現
内助の功には、同じような意味を持つ言葉として、以下の3つが挙げられます。

それぞれの意味と使い方をみていきましょう。
1.「縁の下の力持ち」
縁の下の力持ちは「えんのしたのちからもち」と読み、他人のために陰から努力や苦労をする人をたとえた言葉です。「縁の下」とは、家の床下部分のことです。
普段、床下の存在を意識することはほとんどありません。しかし、床下がしっかりと家を支えていなければ、家は崩れてしまうでしょう。
このように、目立たない場所から支えてくれる人のことを、縁の下の力持ちといいます。
2.「鶏鳴の助」
「鶏鳴の助」は、「けいめいのたすけ」または「けいめいのじょ」と読み、妻が陰から夫をサポートすることのたとえです。内助の功と同じような場面で使います。
「鶏鳴」には鶏が鳴き、夜明けの訪れを告げるという意味があります。妻が、鶏の鳴く声が聞こえたため夜明けだと思い、夫を起こそうとしたものの実は聞き間違いで、まだ夜中だったという故事から生まれた言葉です。
夫が仕事に遅れないように先に起きようとする、甲斐甲斐しい妻の姿をあらわしています。
3.「簀子の下の舞」
簀子の下の舞は「すのこのしたのまい」と読み、陰から援助をする人のことを指します。
劇場の舞台の天井である「簀子」の下で、縁者が無観客の中で舞の踊りの練習をしていたことから転じて、人知れず他人の助けになることをあらわす言葉として使われるようになりました。
「内助の功」に求められる要素
内助の功に求められる要素は、主に以下の3つです。それぞれ解説していきます。

・謙虚さ
内助の功といわれる妻には、謙虚さが求められることが一般的です。表舞台で活躍するのは夫であり、妻は決してスポットライトを浴びることはありませんが、夫のために尽くせるマインドが必要です。
たとえば、目立ちたがり屋の性格の妻が、賞賛を得るために人前でのみ夫のサポートをするのは、内助の功とは呼びません。誰からも褒められることがなくても、夫の成功のために動ける謙虚さは、内助の功とされる妻の1つの特徴といえるでしょう。
・相手への思いやり
内助の功に求められる要素として、相手への思いやりも挙げられます。思いやりとは、相手の気持ちを想像し、何を望んでいるのかを親身になって考え、接することです。
内助の功を果たすには、さりげなく相手の状況や気持ちを考え、仕事などで力を発揮できるように配慮できるように立ち回ることが大切です。
常に自分本位の考え方をしている人は、思いやりのある行動を取ることは難しいでしょう。内助の功といわれるには、ときには相手を優先することが必要です。
・見返りを求めない行動
内助の功には、見返りを求めない行動も必要とされます。内助の功と称えられる妻は、決して自分から、「私が尽力したことで、夫が出世しました」とアピールすることはありません。
人から賞賛を受けるために頑張るのではなく、純粋に夫の活躍を願う見返りを求めない行動が、内助の功につながると考えられます。
内助の功の意味や由来を知ろう
内助の功とは、身内が出世や活躍をするために、陰から支えるはたらきを意味する言葉です。

「内助」には内部から支える助力、「功」には苦労して成し遂げた結果や手柄といった意味があり、一般的には、夫の活躍を支える妻のはたらきをあらわす言葉として使われます。
内助の功の語源とされているのは、戦国時代から江戸時代にかけて活躍した、「山内一豊」の妻「千代」の逸話です。
千代が持参した嫁入りのお金で一豊のために用意した馬が、「馬揃え」という行事で織田信長の目にとまり、そこから一豊は出世の階段を駆け上がったといわれています。
内助の功の類似表現としては、「縁の下の力持ち」「馬揃え」「簀子の下の舞」などが挙げられます。内助の功とあわせて覚えておくと、語彙の幅が広がるでしょう。
また、内助の功に必要な要素は、主に謙虚さや相手への思いやり、見返りを求めない行動などです。内助の功の意味や言葉の由来を知り、適切に使えるようにしましょう。
▼あわせて読みたい