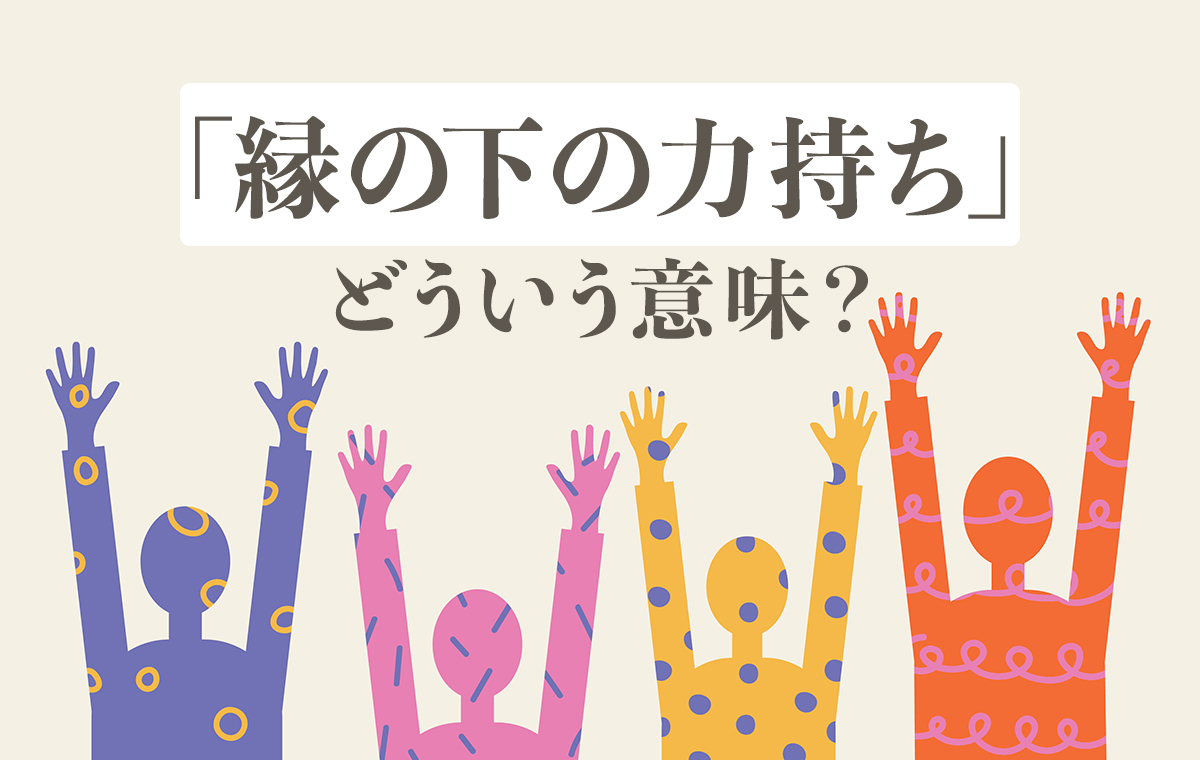縁の下の力持ちとは?
縁の下の力持ち(えんのしたのちからもち)とは、見えないところで人を支え、苦労する人を指す言葉です。目立たない部分で重要な役割をしていることを称賛する意味合いがあります。

ただし、縁の下の力持ちのもともとの意味は現代と異なり、ネガティブなニュアンスがありました。ここでは、縁の下の力持ちの変遷している意味や言葉の由来などを解説します。
■現代は意味や用法が大きく変わっている
縁の下の力持ちは、人のために陰で苦労している人を称賛する意味合いがあります。しかし、明治大正の時代までは、他人のために苦労して報われない行為や人を指す言葉で、そのような行為を否定する意味で使われていました。
当時は人前で演じる「力持ち」と呼ばれる芸があり、人に見えないところでやっても意味がないことから、「縁の下の力持ち」という言葉が生まれたのです。
「力持ち」の芸がなくなってからは、現代のような意味に変わってきました。また、現代は組織を成長させるため、裏方の仕事が評価されるようになってきています。そのような背景も、縁の下の力持ちが肯定的な意味に変わってきた理由といえるでしょう。
■言葉の由来
縁の下の力持ちは、大阪四天王寺の経供養で催された舞楽が由来とされています。経供養とは日本にお経が伝来したことを記念して行われた舞楽法要のことで、舞楽は舞台上ではなく、非公開で演じられていました。
そのため「椽(えん)の下の舞」と呼ばれ、人が見ていないところで虚しく苦労しているという意味で使われていたということです。
■リーダーにも求められている
縁の下の力持ちは組織の成長を支える存在ですが、近年はリーダーにも縁の下の力持ちの側面が求められています。そのようなリーダーは「サーバントリーダー」と呼ばれ、多くの企業で注目を集めています。
サーバントリーダーは、従来の強いリーダーシップでチームを先導するリーダーではなく、部下をサポートして集団に奉仕するリーダーのことです。
人材の多様化が進む現代、さまざまな価値観を持つメンバーが集まる職場では、支配型のリーダーシップではなくメンバーに寄り添うサーバントリーダーが必要とされています。
企業にサーバントリーダーを配置することで部下のモチベーションが上がり、生産性を高めるなどのメリットがあります。
縁の下の力持ちをアピールできる人とは?
縁の下の力持ちといわれるのは、人の見えない部分で重要な役割をしている人です。リーダーシップを発揮するなど目立った行動で称賛されることはないものの、誰かのために努力をしていたり裏方として補助していたり、隠れたところで力を尽くしています。

ここでは、縁の下の力持ちをアピールできる人について、さらに詳しく解説します。
■献身的な努力ができる
自分ではなく、誰かのために尽力できる人は、縁の下の力持ちをアピールできます。過去のエピソードとしては、「学生時代に部活のマネージャーとして選手たちの活躍を支えていた」といったことがあげられます。
また、営業部の内勤で営業に回るメンバーを補助する事務をしているといったことも、縁の下の力持ちといえるでしょう。
■裏方として貢献できる
自分が成果を出すことや地位・名声にこだわらず、「誰かの役に立ちたい」という気持ちで働ける人も縁の下の力持ちの特徴です。
いつも控えめで主張はしないものの、ほかの人が避けてしまうことでも率先して引き受けます。また、そのような人は周囲の状況をよく観察しており、自分が務める役割を的確に判断して行動できるのも特徴の一つです。
縁の下の力持ちの例文
ここでは、縁の下の力持ちを使った例文をいくつかご紹介します。文脈を通して、縁の下の力持ちの理解を深めましょう。
・プロジェクトが成功したのは、縁の下の力持ちとなったメンバーのおかげだ
・周りの社員が大変なとき、彼女はいつも縁の下の力持ちとなって手助けをしている
・自分は目立つのが苦手な性分で、縁の下の力持ちになるのが好きだ
縁の下の力持ちの類語・類似表現
縁の下の力持ちにはよく似た表現もあります。陰ながら人の支えとなる人を表す「簀子の下の舞」や、陰ながら援助する身内を表す「内助の功」などがあげられます。主役を引き立てる役割を演じる「名脇役」も類語といえるでしょう。一緒に覚えておけば、状況に応じて適切な表現ができます。

縁の下の力持ちの類語・類似表現を見ていきましょう。
「簀子の下の舞」
簀子の下の舞(すのこのしたのまい)とは、表に出ず陰ながら人の支えになるという意味です。語源は、縁の下の力持ちと同じです。大阪四天王寺の経供養で催されていた舞の演者が、人知れず簀子の下で練習をしていたことが言葉の由来とされています。
(例文)
・会社が成長できたのは、簀子の下の舞となるスタッフが頑張っているおかげだ
「内助の功」
内助の功(ないじょのこう)とは、陰ながら援助する身内の功績という意味です。特に、夫の活躍を支える妻の働きを指して使われます。「内助」は内側からの助けを表し、「功」は苦労して成し遂げた成果や手柄という意味があります。
(例文)
・彼が早く出世できたのは、陰ながら支えている妻の内助の功が大きな役割を果たしている
「名脇役」
名脇役(めいわきやく)とは、映画やドラマ、舞台などで主役を引き立てる役を演じながら、主役以上の存在感を感じさせる脇役を指す言葉です。ほかの場面でも、組織の円滑な運営になくてはならない人を指し、比喩的に使われます。
(例文)
・組織がここまで成長できたのは、社長を長年陰で支えてきた彼が名脇役としての役割を演じてきたからにほかならない
縁の下の力持ちを正しく理解しよう

縁の下の力持ちは、見えないところで重要な役割をしている人を指します。もともとは他人のために苦労しても報われないという、ネガティブな意味で使われていました。しかし、現在はそのような意味合いはなく、もっぱら称賛する意味で使われています。
縁の下の力持ちをアピールできるのは、自分の成果にこだわらず、人のために努力し貢献できる人です。近年は、リーダーにも縁の下の力持ちとしての役割が求められています。
あわせて読みたい