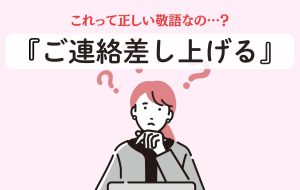Contents
「重ねてのご連絡失礼いたします」とは
取引先とのやりとりを始めて間もない頃は、メールの文面ひとつにも気を使うものです。「重ねてのご連絡失礼いたします」という表現に出会い、丁寧で印象のよい言い回しだと感じた人も多いのではないでしょうか。まずはこの表現のニュアンスや、使うときのポイントをわかりやすく解説します。
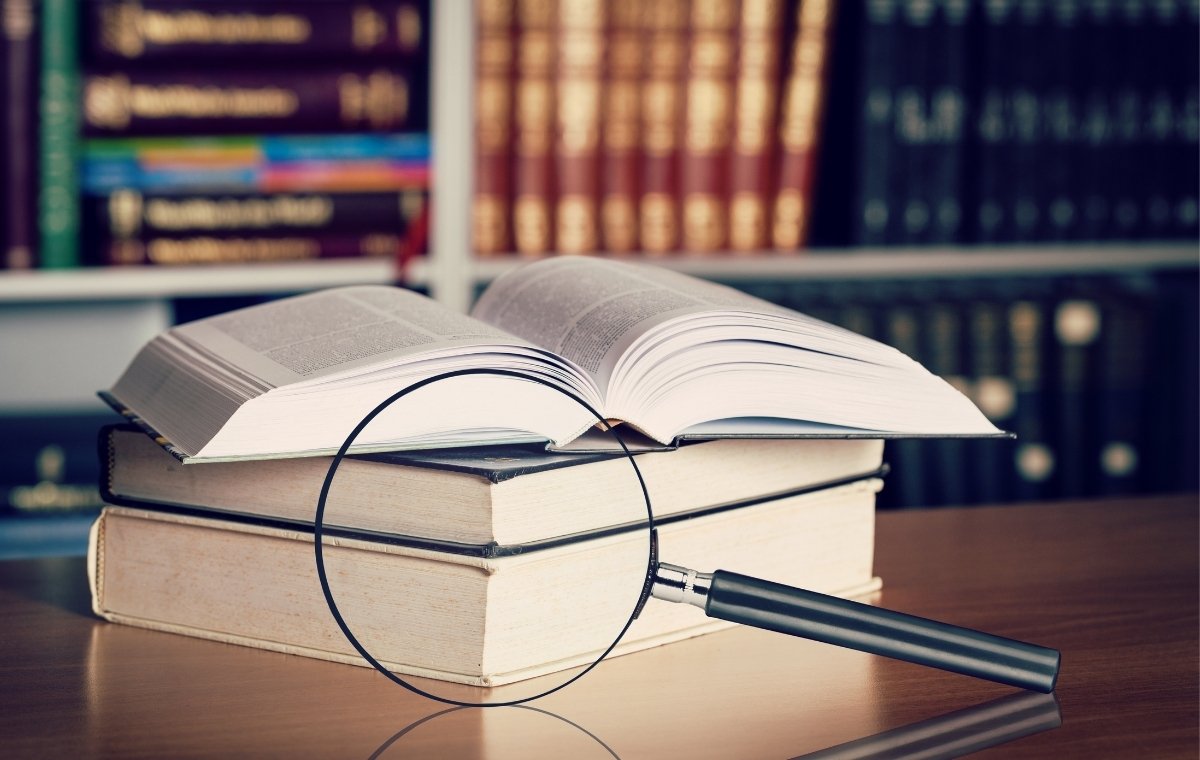
(c)Adobe Stock
度重なる連絡に対する気づかいの表現
「重ねてのご連絡失礼いたします」は、既に一度連絡をしている相手に対し、改めてメールを送る際に添える定型表現です。繰り返しの連絡となることへのお詫びや、もう一度メールを読む相手の負担を気づかう気持ちを表しています。
「重ねて」という言葉を辞書で引いてみると…
かさね‐て【重ねて】
[副]
1. 同じことを繰り返すさま。もう一度。再び。「重ねて注意する」
小学館『デジタル大辞泉』より一部引用
とされています。つまり「重ねてのご連絡失礼いたします」は、「再び連絡してしまってすみません」といったニュアンスを含む言葉です。
この表現は取引先や上司など、目上の人へのビジネスメールでよく使われます。特に相手の返答を待たずにこちらから連絡をする必要があるときなどに、メールの冒頭に添えると丁寧で配慮ある印象を与えられるでしょう。
要所要所で理由を添えて使う
「重ねてのご連絡失礼いたします」は丁寧な印象を与える表現ですが、使う頻度には注意が必要です。多用しすぎはかえってくどい印象になり、相手の負担が増えてしまう可能性もあります。
また、毎回この表現を使っていると、「1回のメールで必要事項を伝えきれない人(または会社)」という印象を与えかねません。相手も再び連絡が来ると想定している、と察せられる場合は「再度ご連絡いたします」といった、よりシンプルな言い回しで十分です。
再連絡となった理由を一言添えると、相手にも納得してもらいやすくなります。「○○の件につきまして、お返事がなかったので念のためご連絡申し上げます」などと具体的に書くことで、メールの意図も明確に伝わるでしょう。
「重ねてのご連絡失礼いたします」を使う場面と例文

(c)Adobe Stock
丁寧な印象を与える「重ねてのご連絡失礼いたします」は、ビジネスの現場で追加の報告や状況の変化・返答の催促など、さまざまな場面で活用できます。具体的にどのようなシーンで使えるのか、場面ごとの例文も参考にしながら、使い方をマスターしましょう。
追加の連絡事項が出てきたとき
1通目のメールを送った後に、伝え忘れていた情報や後から追加で伝えるべき内容が出てくることもあります。たとえば、メールでサービス資料を送った後の会議でサービス内容が追加されることになったため、連絡事項が増えたようなケースです。
このような場合は「重ねてのご連絡失礼いたします」を使って、改めて丁寧に補足しましょう。
【例文】
重ねてのご連絡失礼いたします。先ほどご案内した資料の件で、1点追記がございます。ご確認いただけますと幸いです。
「重ねてのご連絡失礼いたします」があるとないとでは、丁寧さがまったく違います。
最初の連絡から状況が変わったとき
一度送った連絡内容や依頼事項に変更が生じた場合にも「重ねてのご連絡失礼いたします」と一言添えることで、相手に気づかいが伝わり、再送の必要性に目を向けてもらいやすくなります。
例を挙げると、「月曜10時からの打ち合わせと連絡していたけれど、出席者の都合がどうしてもつかなくなり、11時に変更する」といったようなケースです。
【例文】
重ねてのご連絡失礼いたします。先ほどお送りした打ち合わせのご案内に関しまして、時間を変更させていただきたくメールいたしました。こちらの都合で大変恐縮ですが、出席予定の弊社担当者に急な予定が入ってしまったため、同日の11時からに変更できないかご検討いただけますと幸いです。
このケースでは相手に予定を変えてもらうお願いをすることになります。例文のように、変更をお願いする背景と、予定変更に対する申し訳なさを表す文面を心がけるといいでしょう。
返答をもらえずリマインドしたいとき
依頼や確認事項に対して返答がない場合、リマインドのメールを送ることになります。ただ、催促のメールは、相手に気を使って送るのをためらってしまう人もいるのではないでしょうか。
そんなときこそ、催促のトーンがやわらかくなる「重ねてのご連絡失礼いたします」を添えてみましょう。
【例文】
重ねてのご連絡失礼いたします。先日お送りしたご提案について、進捗などをご確認いただけますと幸いです。お忙しいところ恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。
最後にも「お忙しいところ恐縮ですが」と一言プラスすることで、「早く返事をしろ」といったニュアンスをほぼ感じさせずにリマインドできます。
「重ねてのご連絡失礼いたします」の類似表現や違い

(c)Adobe Stock
「重ねてのご連絡失礼いたします」は便利な表現ですが、場面や文の長さによっては別の言い回しの方が自然な場合も少なくありません。意味合いの近い類似表現とその違い、具体的な使用シーンを解説します。
締めくくりに使う「度々のご連絡失礼いたしました」
何度かメールのやりとりを重ねた後に、最後の締めくくりとしてお詫びの気持ちを込めて使われるのが「度々のご連絡失礼いたしました」です。メールの冒頭ではなく、終わりに添えることで丁寧な印象を与えます。
何度もやりとりしてくれた相手の負担を気づかう気持ち、やりとりを往復させてしまったことに対する申し訳なさを伝えられる表現です。
なお、同じメールの中で「重ねてのご連絡失礼いたします」と「度々のご連絡失礼いたしました」を両方使うのは避けましょう。くどい印象を与え、かえって相手の負担になってしまいます。
「重ねてのご連絡失礼いたします」は2回目のメール、「度々のご連絡失礼いたしました」は3回以上のやりとりの後に使うのが基本です。
短い文章で使う「重ねての(度々の)ご連絡で恐縮ですが」
再連絡の理由が明確で、本文が1〜2文で完結する場合には、「重ねてのご連絡で恐縮ですが」や「度々のご連絡で恐縮ですが」といった簡潔な表現もおすすめです。
たとえば「重ねてのご連絡失礼いたします」と文を改めると、少し仰々しくなりすぎる軽い要件のときには、このような言い回しがスマートに見えます。文全体のバランスを見ながら、場面に合った表現を選ぶようにしましょう。
例としては、「重ねてのご連絡で恐縮ですが、先ほどお送りいただいた資料は担当に連携しております。」といった使い方が挙げられます。
期間が空いたときに使う「ご無沙汰しております」
前回のメールから数カ月以上経っているようなケースでは、相手からの返信が来ていない状態で再びメールするとしても、「重ねてのご連絡〜」ではなく「ご無沙汰しております」が適しています。
「ご無沙汰しております」は相手との関係性を尊重しつつ、時間が空いたことへの配慮を表す丁寧なあいさつです。「先日はありがとうございました」などの言葉と一緒に添えておくと、より自然で礼儀正しい印象を与えられます。
再連絡の理由が明確なら、「ご無沙汰しております。○○の件でご連絡を差し上げました」と続ければスムーズな書き出しになります。
「ご無沙汰」を使う期間の目安は、一般に2〜3カ月以上、対面でもメール・電話でも連絡をとっていないときです。
「重ねてのご連絡失礼いたします」を適切に使いこなそう

(c)Adobe Stock
「重ねてのご連絡失礼いたします」は、ビジネスメールの中でも特に丁寧な印象を与える表現のひとつです。相手への気づかいや礼儀をきちんと伝えたいときに、適切なタイミングで使いましょう。
また、似たような場面でも状況に応じて「ご無沙汰しております」や「度々のご連絡失礼いたしました」といった表現を使い分けることで、やりとりの印象がぐっと洗練されます。
社外とやりとりした経験が浅くても、こうした言い回しを少しずつ覚えていけば、メール対応にも自信が持てるようになるはずです。
メイン・アイキャッチ画像/(c)Adobe Stock
TEXT
Domani編集部
Domaniは1997年に小学館から創刊された30代・40代キャリア女性に向けたファッション雑誌。タイトルはイタリア語で「明日」を意味し、同じくイタリア語で「今日」を表す姉妹誌『Oggi』とともに働く女性を応援するコンテンツを発信している。現在 Domaniはデジタルメディアに特化し、「働くママ」に向けたファッション&ビューティをWEBサイトとSNSで展開。働く自分、家族と過ごす自分、その境目がないほどに忙しい毎日を送るワーキングマザーたちが、効率良くおしゃれや美容を楽しみ、子供との時間をハッピーに過ごすための多様な情報を、発信力のある個性豊かな人気ママモデルや読者モデル、ファッション感度の高いエディターを通して発信中。
WEB Domani
あわせて読みたい