年収は1年間の収入金額の合計。所得は、年収から必要経費や各種控除を差し引いた後の金額のことです。
Summary
- 年収は、1年間の収入金額の合計額。所得は、年収から必要経費や各種控除を差し引いた後の金額。
- ふるさと納税をする場合は、所得控除後の課税所得が基準。
- 配偶者控除の適用条件は、合計所得金額が48万円以下であること。
「年収」と「所得」は同じ税金に関わる場面で使われるため、意味を混同しがちですが、明確な違いがあります。この違いを誤解していると、確定申告や控除の申請で損をしてしまう可能性も…。特に会社員と個人事業主では、年収・所得の計算方法が異なり、節税対策に大きな影響を及ぼします。
そこで本記事では、「年収」と「所得」の基本的な違いを明確にし、実際の計算例や税金への影響を詳しく解説します。知識を深め、自分の収入・所得を正しく把握して、税金対策に生かしましょう。
年収と所得の違いとは? 基本を押さえましょう
「年収」と「所得」は、全く別のものを指します。ここでは、それぞれの違いを確認していきましょう。

(c) Adobe Stock
年収とは?
年収とは、1年間の収入金額の合計を指します。会社員であれば、毎月の基本給だけでなく、賞与や各種手当、残業代などが含まれます。転職情報の「年収500万円」など、世間一般で「年収」というとこの総収入の合計を指すことが多いです。
所得とは?
所得は、年収から必要経費や各種控除を差し引いた後の金額を指します。会社員の場合、「給与所得控除」という制度により、収入から一定額が差し引かれます。給与所得控除は給与所得者の概算経費として認められているもので、差し引かれる金額(控除額)は収入に応じて段階的に決まる仕組みです。
一方、個人事業主や自営業者の場合は、売上から事業に必要な経費を差し引くことで所得が算出されます。経費として認められるものは所得税法等で決められており、事務用品費や家賃、光熱費など、事業の維持にかかる支出は原則として経費として認められることが多いです。
税金はこの「所得」に基づき計算されるため、控除や経費で税金の金額は大きく変動します。

年収と所得の違いを具体例で比較
実際の例を用いて、年収と所得の違いを確認してみましょう。年収500万円の会社員の場合、給与所得控除が適用されると、課税対象となる所得は約360万円弱となる計算になります。国税庁のホームページには簡易的に計算できるツールもありますよ。
一方、個人事業主が年間売上500万円を得ていた場合、そこから必要経費を差し引いて所得が決まります。具体例を示すと、事業にかかる経費が200万円であれば、所得は300万円という計算になります。ただし、経費として計上できるものは所得税法等で定められており、私的な支出は除外されるので注意が必要です。
このように、同じ500万円の収入であっても、職業や経費の内容によって課税対象となる所得は大きく変わります。
個人事業主・自営業者が知っておくべき「年収」と「所得」の違い
個人事業主やフリーランスは、事業経費の扱いや税金の計算で「年収」と「所得」の違いを理解することは欠かせません。確定申告を行う際には、この違いを理解していないと、税金の計算を誤る場合があります。

(c) Adobe Stock
個人事業主の年収と所得の違い
個人事業主における年収は、1年間の売上総額を意味します。商品の販売額やサービス提供による収入など、事業活動から得たすべての金額が対象です。ここで注意したいのは、事業に関係ない収入(アルバイトなどの副業や株を売って得た臨時収入など)は、個人事業主としての事業所得を計算する際には含まない点です。
一方、所得は、この年収から事業運営に必要な経費を差し引いた金額を指します。具体的には、店舗の家賃や光熱費、消耗品費、広告宣伝費など、事業を続けるために必要な支出が経費として認められます。経費が多ければ、その分所得は減少し、結果的にその所得を基に計算する税金も抑えられます。ただし、経費として認められるかどうかは、所得税法等や国税庁のガイドラインに基づく必要があります。個人的な支出は含まれません。経費になるかどうか不安な場合は、税金のプロである税理士に相談しましょう。
所得48万円以下のポイントと税金の関係
所得が48万円以下の場合、所得税が課税されないケースがあります。これは基礎控除が適用されるためです。会社員にとっても個人事業主にとっても把握しておきたい控除です。
また、配偶者控除を受ける場合にも、この所得48万円の基準が関わります。配偶者の所得が48万円以下であれば、配偶者控除の対象となるからです。配偶者が個人事業主の場合、事業収入と経費の計算結果により、控除の対象となるかならないかが決まるため、慎重な計算が求められます。
年収と所得が関わる税金や控除の基本
続いては、税金や控除の基本について見ていきましょう。
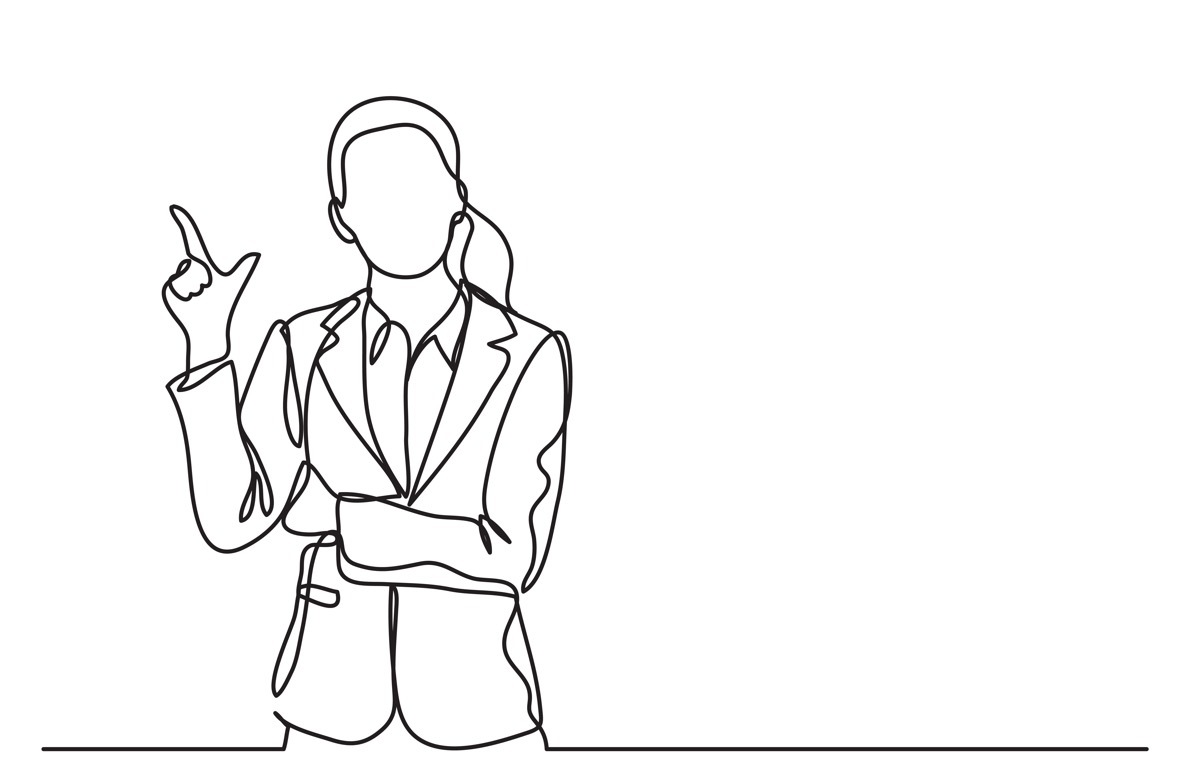
(c) Adobe Stock
ふるさと納税で重要な「年収」と「所得」の基準
ふるさと納税では、全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安を把握しておくことが重要です。この控除額の計算には「所得控除後の課税所得」が基準として用いられます。つまり、この金額が高ければふるさと納税額の上限額も高くなります。上限額を超えてふるさと納税をすると、自己負担が発生してしまう可能性もあるため、注意しましょう。
ふるさと納税を活用する際には、事前に各種サイトで控除上限額をシミュレーションしておくことが重要です。各種ツールを活用し、自身の所得に応じた適切な寄付額を検討しましょう。
配偶者控除・扶養控除における年収と所得の違い
配偶者控除や扶養控除の判定においても、年収と所得の違いが関わります。配偶者控除の適用条件は、配偶者の合計所得金額が48万円以下であることが基準となります。年収ではなく、所得で判断されるため、注意が必要です。
具体例として、配偶者の年収が100万円であっても、その全額が給与で、給与所得控除が適用されれば、所得は48万円以下になる場合があります。この場合は配偶者控除の対象となります。ただし、合計所得金額が48万円を超えると配偶者控除は適用されません。一定の金額までは配偶者特別控除が適用されますが、控除金額が減る可能性があるため、年末時点での所得額の把握が必要です。
扶養控除も同様に、扶養される人の所得が基準となります。アルバイトなどで給与収入を得ている場合、その所得が一定額を超えると扶養控除の適用外となる場合があるため、収入の状況を定期的に確認することが大切です。
最後に
- 年収は1年間の収入金額の合計額、所得は年収から必要経費や各種控除を差し引いた後の金額を指します。
- ふるさと納税をする場合は、所得控除後の課税所得が基準として用いられます。
- 配偶者控除の適用条件は、合計所得金額が48万円以下であることです。
「年収」と「所得」の違いを理解することは、税金対策や賢い資産管理の第一歩です。特に、経費や控除の適用条件、全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の計算を誤ると、想定外の負担が発生する可能性があります。会社員も個人事業主も、適切な計算方法を把握し、正しい税申告が行えるようにしましょう。この記事を参考に、ぜひご自身の収入・所得を正しく把握し、賢く税金と向き合っていきましょう。
※この記事は、2025年4月1日時点の情報をもとにしています。
TOP画像/(c) Adobe Stock

監修
わく社会保険労務士事務所代表 和久 明(わく・めい)さん
社員12万人超の会社で社会保険、給与計算、社内研修講師を15年以上経験した後、社会保険労務士開業。 常に忙しく手が足りない中小企業の、就業規則作成や法改正フォロー、業務の見える化による社員の働きやすさ実現に取り組んでいる。褒め言葉インストラクター。趣味はサウナ。
事務所ホームページ:https://waku-sr.com
ライター所属:京都メディアライン
あわせて読みたい










