「一気呵成」とは一気に文章を書き上げること
「一気呵成」とは、一気に文章を書き上げる様を表現した言葉です。物事を始めたら、最後までやり遂げることを意味します。
【一気呵成(いっきかせい)】
《「呵」は息を吹きかける意》ひといきに文章を書き上げること。また、ひといきに仕事を成し遂げること。「脚本を―に書き上げる」
(引用〈小学館 デジタル大辞泉〉より)
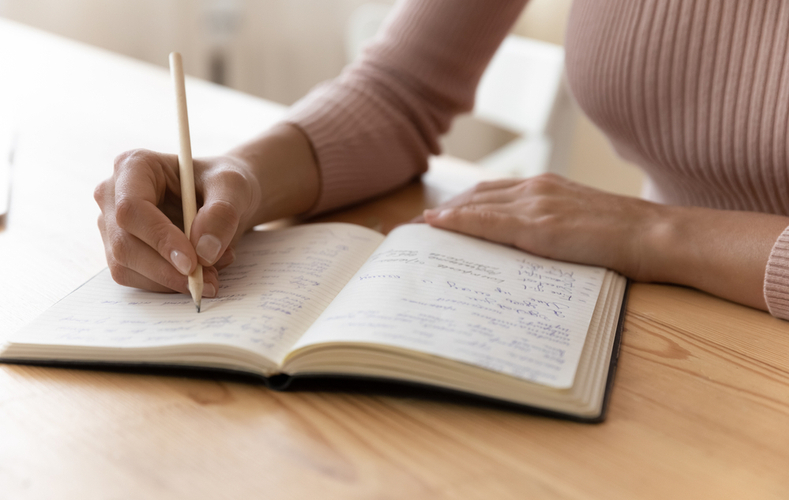
「一気呵成」は、「一気」と「呵成」の2つに分けられます。一気は「一呼吸のうちに」という意味です。「呵成」の呵には「息を吹きかける」、成には「完成する」という意味が込められています。つまり、「呵成」は息を吹きかけて完成させる様を表現した言葉といえるでしょう。
したがって、「一気呵成」は、休憩や休息を取らずに一気に作業を終わらせる効率の良さを表現した言葉といえます。
「一気呵成」の使い方
「一気呵成」の使い方は、以下のとおりです。

・私の父は真面目な性格なため、何事も【一気呵成】に仕上げないと気が済まないようです。
・我が家は共働きのため、週末を利用して一週間の献立を【一気呵成】に仕上げるのが決まりです。
・【一気呵成】の人は、せっかちに思われやすいかもしれません。
・明日提出する予定のレポートを、今晩【一気呵成】に仕上げる予定です。
「一気呵成」を使用する場合は、通常よりも早く仕上げるという意味合いが強いです。そのため、「一気呵成に仕上げる」「一気呵成に終わらせる」といった表現が多いでしょう。
「一気呵成」の類義語5つ
「一気呵成」の類義語は、以下の5つです。
・一網打尽
・破竹の勢い
・一瀉千里
・懸河之弁
・一足飛び

「一網打尽」とは、1回にすべてを捕まえるという意味の言葉です。「破竹の勢い」は、物事が勢いよく進む様を表現しています。「一瀉千里」とは、川が勢いよく流れる様からできた言葉です。
「懸河之弁」は、つまらずに流暢に話す様子を表したいときに使用します。「一足飛び」とは、一気に移動するという意味を持つ言葉です。ここでは、「一気呵成」の類義語をご紹介します。
一網打尽(いちもうだじん)
【一網打尽(いちもうだじん)】
《「宋史」范純仁伝から》一度打った網でそこにいる魚を全部捕らえること。転じて、一味の者を一度に全部捕らえること。「密輸グループを―にする」
(引用〈小学館 デジタル大辞泉〉より)
「一網打尽」とは、1回ですべてを捕らえるという意味をもつ言葉です。「一網打尽」の「一網」には「網を一度に打つ」、「打尽」には「すべてを捕らえる」という意味が込められています。
もともと「一網打尽」は、魚やほかの生物を一度で捕まえるという意味で使用されていましたが、意味合いが派生して、犯人を一度に捕まえる、複雑な事柄を一度に片付けるとの意味でも使われています。
【例文】
・警察が犯罪組織に潜入した結果、【一網打尽】に成功しました。
・優秀なスタッフが、システム上で発生したトラブルを【一網打尽】に解決しました。
破竹の勢い(はちくのいきおい)
【破竹の勢い(はちくのいきおい)】
《「晋書」杜預伝から》竹が最初の一節を割るとあとは一気に割れるように、勢いが激しくてとどめがたいこと。「―で連戦連勝する」
(引用〈小学館 デジタル大辞泉〉より)
「破竹の勢い」とは、物事が勢いよく進んでいく様を表した言葉です。竹は節があるため簡単に割れないものの、節さえ割れればスムーズに割れる様子からできた言葉といわれています。
【例文】
・【破竹の勢い】で、全国制覇を目指していこうと思います。
・【破竹の勢い】で物事を進めたからこそ、このような罠にかかってしまったのかもしれない。
・【破竹の勢い】で、勝利を次々に掴んでいきました。
一瀉千里(いっしゃせんり)
【一瀉千里(いっしゃせんり)】
《川の水が一度流れだすと、またたく間に千里も流れる意から》
1.物事が速やかにはかどり進むこと。「仕事を―に片付ける」
2.文章や弁舌のよどみないことのたとえ。「―に物語る」
(引用〈小学館 デジタル大辞泉〉より)
「一瀉千里」とは、物事がスムーズに進む様を表現した言葉のことです。川が勢いよく流れる様子からできた言葉だといわれています。そのため、文章を一気に書き上げるという意味を持つ「一気呵成」と似た言葉だといえるでしょう。
【例文】
・長年続いた親族間での争いは、敏腕弁護士の登場で【一瀉千里】に解決しました。
・【一瀉千里】で書き上げた電子書籍の売れ行きが、好評のようで安心しました。







